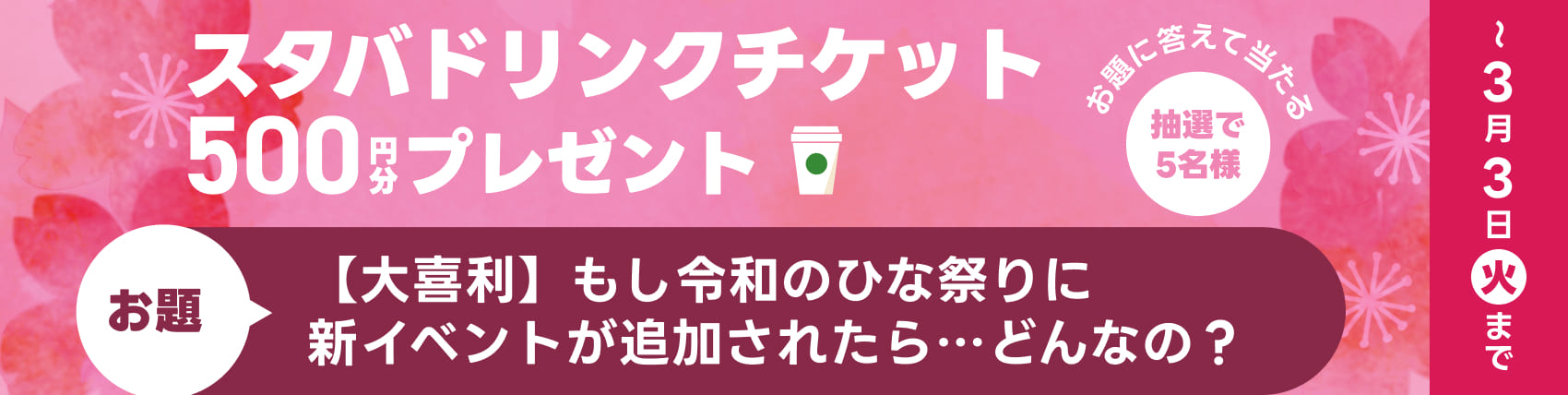小学生の友達関係に悩む保護者必見!子どもの成長を支えるコツとは?
子どもたちの友達関係で不安になることはありませんか?親として今できることとは?
学校

小学生の友達関係に悩む保護者必見!子どもの成長を支えるコツとは?
こんにちは、多様な教育ナビゲーター・あずみのこです。
15年以上、子どもや保護者の居場所づくりや子育て支援に携わり、これまで100人以上の保護者と向き合ってきました。そして今は、小学生と中学生を育てる、現役バタバタ共働きママでもあります。
今回のコラムのテーマは小学生の友達関係の悩みです。
小学生の友達関係は、学年や発達段階によって姿を変えていくもの。ちょっとしたケンカから、グループの仲間外れや価値観の違いまで、悩みのかたちはさまざまです。
「親としてどう関わればいいのかな?」「友達関係でつまずいていないか心配…」そんな声には、思わず「わかるわ〜...」とうなずいてしまいます。私も、子どもが友達との関係で悩んだときにどう寄り添えばいいのか迷い、あれこれ試行錯誤してきました。このコラムでは、学年別の特徴や保護者が抱えやすい不安、そして家庭でできるサポートの工夫をまとめました。読んでくださる方が「うちも同じだな」と少し安心できたり、「これならできそう」と感じてもらえたら嬉しいです。
学年別に見る小学生の友達関係の特徴

低学年:まだお互いを思いやる余裕がなく、感情がぶつかりやすい
低学年のうちは、「席が近いから」「家が近所だから」といったシンプルなきっかけで友達になることが多いんですよね。とっても可愛らしい反面、相手の気持ちを想像する余裕はまだ小さくて、ちょっとした物の貸し借りや遊びのルールでケンカに発展しやすい時期でもあります。
でも、こうしたぶつかり合いも大切な学びのプロセス。家庭で「どうしたら仲直りできるかな?」と一緒に考えてみたり、気持ちを言葉にする練習をしたりすることが、のちの人間関係の土台になっていきます。
中学年:グループ形成が進み、仲間外れが起こりやすい時期
3〜4年生になると、友達同士でよく集まるグループができてきます。楽しい反面、「誰を入れる・入れない」という問題が出てきやすいんですよね。ちょっと目立つ子や、少し違う行動をとる子が仲間外れにされてしまうことも…。
この時期は、親だけで抱え込まずに先生や地域のサポートを頼ることがとても大切です。「お友達のいいところに気づけるといいね」と、家庭でもさりげなく声をかけてあげられると安心につながります。
高学年:価値観や共通の趣味でつながる友達を重視するようになる
高学年になると、「自分と合うかどうか」を意識して友達を選ぶようになります。共通の趣味や目標を持つ仲間と深く関わったり、逆に価値観の違いから距離をとったり。人間関係が一気に複雑になってくる時期です。
てつなぎの掲示板でも、こんな声がありました。
「うちの小学生の息子はこの春から中学受験対策で塾に通い始めた。塾ではA君とB君と仲が良いらしいけど、最近なんとA君がB君を無視していると息子がぼやいていた。原因はB君の方が模試の算数の偏差値が高かっただけ…。揉め事は御免だ、塾の友達なんかいらないのかも」
(🔗てつなぎ掲示板|“揉め事はごめんだぜ”)
学力や成果が絡むことで友達関係が揺れるのも、この時期ならではの現実です。
でもこれは、自分らしさを模索している成長の表れ。親としては「この子が安心して過ごせる居場所はあるかな?」と見守る視点を持つのがポイントです。たとえ仲間と合わなくても、家庭に“自分をそのまま受け止めてくれる場所”があることが、子どもの大きな支えになります。
保護者が抱えがちな悩みと不安
小学生になると、保護者の目が届かない時間が一気に増えます。「友達とちゃんとやれているのかな?」と心配になるのは自然なことです。
「小学生になって学校での様子や友達との関係、何をしてるのか見えなくなり、ちょっと寂しい。幼稚園とは違うよね。学校のこともあまり喋ってくれないし。楽しく通えてるのかな…?とりあえず休まず行ってくれてるので、安心して良いのでしょうか🥹」
(🔗てつなぎ掲示板|“小学生になったけど見えない学校での様子”)
こうした「見えないことへの不安」は、多くの保護者に共通する悩みです。

子どもが友達と遊びたがらない、または誘われないケース
「うちの子、最近ひとりで過ごすことが多いかも…」と気になる瞬間、ありますよね。親としてはどうしても心配になります。でも大事なのは、それが「一人の時間を楽しんでいる」のか「本当は寂しい」のかを見極めること。
本を読んだりゲームに夢中になったり、本人が心地よく過ごせているなら、それも立派な“自分らしい時間”です。無理に遊ばせようとするより、「どんな時間を過ごしたい?」と気持ちを聞いてみるだけで、子どもは安心します。
私も、下の子が「今日は誰とも遊ばない」と言ったときに不安になったことがあります。でも後で聞いたら「一人で工作したかったから」だったんです。親の心配と、子どもの気持ちってずれることも多いんですよね。
トラブル・いじめなど具体的に心配すべきサイン
一方で、見過ごしてはいけないサインもあります。表情が急に暗くなったり、学校の話を避けたり、登校を嫌がるようになったときは要注意。「お腹が痛い」と繰り返し訴えるのも、実は心のSOSのことがあります。
深刻化すると対応が難しくなるので、普段から小さな変化を見逃さないことが大切です。「最近元気ないね、大丈夫?」と声をかけるだけでも安心材料になりますし、気になるときは学校や信頼できる保護者仲間と情報を共有するのも心強いです。
子どもの苦しみを理解するためのサインの見極め方
「最近ちょっと元気がないな…」と思うとき、そこには友達関係のストレスが隠れていることもあります。
●朝起きるのを嫌がる、体調不良を訴える
●言葉数が減り、表情が暗い
●SNSやゲームなど、今まで楽しんでいたことを急にやめる
こうした変化は、子どもからの「しんどいよ」というSOSかもしれません。大切なのは問い詰めることではなく、「最近元気ないね、どうした?」とやさしく声をかけること。たとえすぐに答えてくれなくても、「見てくれている人がいる」と感じられるだけで安心につながります。
学校に行きたがらない、不登校・登校拒否の兆候
朝の準備を強く嫌がったり、突然「お腹が痛い」と訴える場合、友達関係のストレスが背景にあることも少なくありません。深刻化する前に、家庭での会話時間を意識的に増やしたり、一緒に気持ちを整理できる場をつくることが大切です。
必要に応じてスクールカウンセラーや専門機関に相談するのもためらわなくて大丈夫。「早めに動いてよかった」と感じられるケースは本当に多いんです。
表情や言葉数の減少など子どもの行動面の変化
いつもは友達と遊んでいた子が急に一人で過ごすようになったり、楽しんでいたSNSやゲームをぱったりやめてしまうことも、心の負担を示すサインかもしれません。子どもは気持ちをうまく言葉にできないとき、行動で示すことがあります。
だからこそ、日常のちょっとした変化に敏感になり、「前と違うな」と思ったら軽く声をかけてみる。その積み重ねが、子どもが安心して本音を話せるきっかけになります。
親ができる具体的なサポート方法

コミュニケーションを深めるための質問の仕方
子どもに「学校どうだった?」と聞いても「別に」「ふつう」と返されて会話が続かない…そんな経験、ありませんか? 私もよくあります(笑)。
大事なのは、Yes/Noで終わらない問いかけです。「どんなことが楽しかった?」「一番びっくりしたことは?」と、具体的に聞くと子どもも自分の言葉で話しやすくなります。うまく答えられなくても、「そう思ったんだね」と受け止めてあげることが次の会話につながります。
子どもが本音を話しやすい雰囲気づくり
叱ったり、ほかの子と比べたりすると、子どもは心を閉ざしてしまいますよね。大切なのは「安心して話せる場所」を家庭に用意すること。
例えば、夕飯のあとにちょっとお茶を飲みながら話す時間をつくるのもいいですし、寝る前に「今日はどんな日だった?」と一言だけ聞いてあげるのでも十分です。親の意見はあえて少なめにして、子どもの気持ちを受け止めることが、自己肯定感を育てる第一歩になります。
第三者への相談や支援を積極的に活用する
「親子だけで解決しなくちゃ」と思い込む必要はありません。担任の先生やスクールカウンセラー、地域の子育て支援機関に相談するのも立派な選択肢です。
実際に、私の周りでも「先生に相談してみたら思った以上に気持ちが軽くなった」という声はたくさんあります。客観的な視点が入ることで、子ども自身も「一人じゃない」と感じやすくなり、保護者にとっても安心材料になるはずです。
親が気をつけたい接し方と声かけ

無理に介入しすぎず、子どもの意志を尊重する
子どもが友達とのトラブルを抱えたとき、「親がなんとかしてあげなくちゃ」と思うのは自然なこと。でも、時にはぐっとこらえて“見守る”ことも大切です。
自分で考えて解決する経験は、子どもにとって大きな力になります。もちろん本当に困ったときには支えてあげる姿勢を示しつつ、普段は「あなたを信じて見ているよ」というスタンスを持てると安心感につながります。
失敗やトラブルも成長の糧であることを伝える
ケンカや仲間外れ、ちょっとした失敗…。親としては「そんな思いをさせたくない」と胸が痛くなりますよね。けれども、子どもにとっては“人との関わりを学ぶチャンス”でもあります。
「失敗=ダメ」ではなく、「次にどうしたらいいか一緒に考えてみよう」と声をかけてみてください。小さな失敗を振り返りながら乗り越えることで、自己肯定感や解決力が少しずつ育っていきます。
まとめ:子どもの気持ちに寄り添いつつ、安心して成長を見守ろう
小学生の友達関係は、低学年のころはケンカや小さなトラブルが多く、高学年になると価値観や趣味の違いから関係が複雑になっていきます。そうした変化は、子どもが成長している証でもあります。
親にできる一番のことは、「子どもが安心して相談できる存在」でいること。完璧に守ることはできなくても、「見守ってくれる人がいる」という安心感があるだけで、子どもの心は強くなります。
家庭や学校、地域の人たちと力を合わせながら、子どもが自分らしく過ごせる居場所を整えていきましょう。そして「友達との関係に悩むのは成長の一部なんだ」と、親自身も肩の力を抜いて見守れたらいいですね。
そして、どうしてもつらい夜があったら…ひとりで抱え込まなくても大丈夫です。「てつなぎ」の掲示板に、気持ちをそのまま書き込んでみてください。 同じように悩んだ親御さんたちが、きっと温かく受けとめてくれます。
あずみのこも、掲示板を読んでいますよ。ここでのつながりが、少しでも心の支えになったらうれしいです。
多様な教育ナビゲーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね