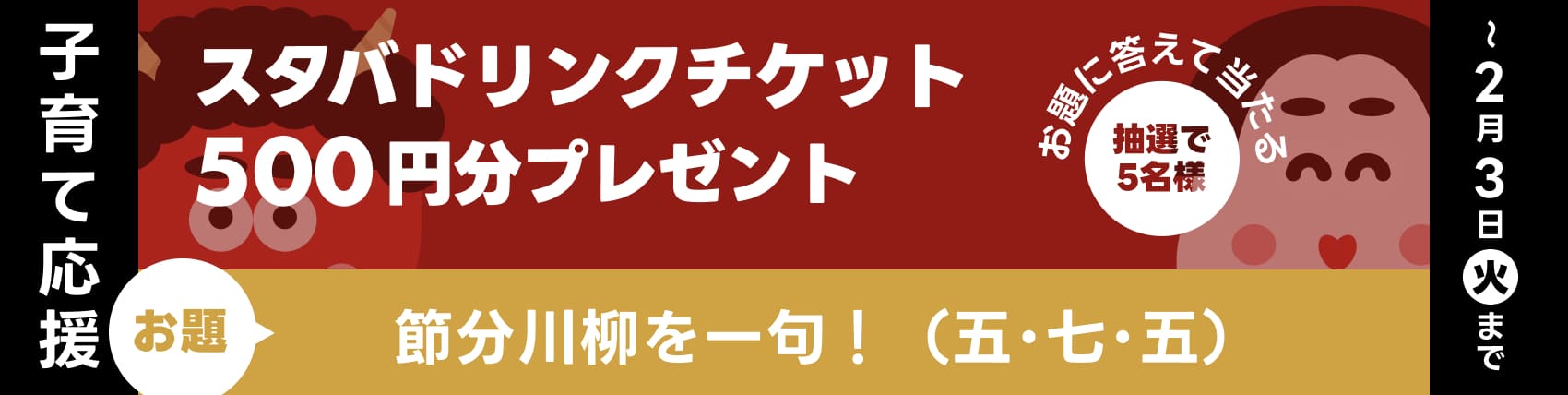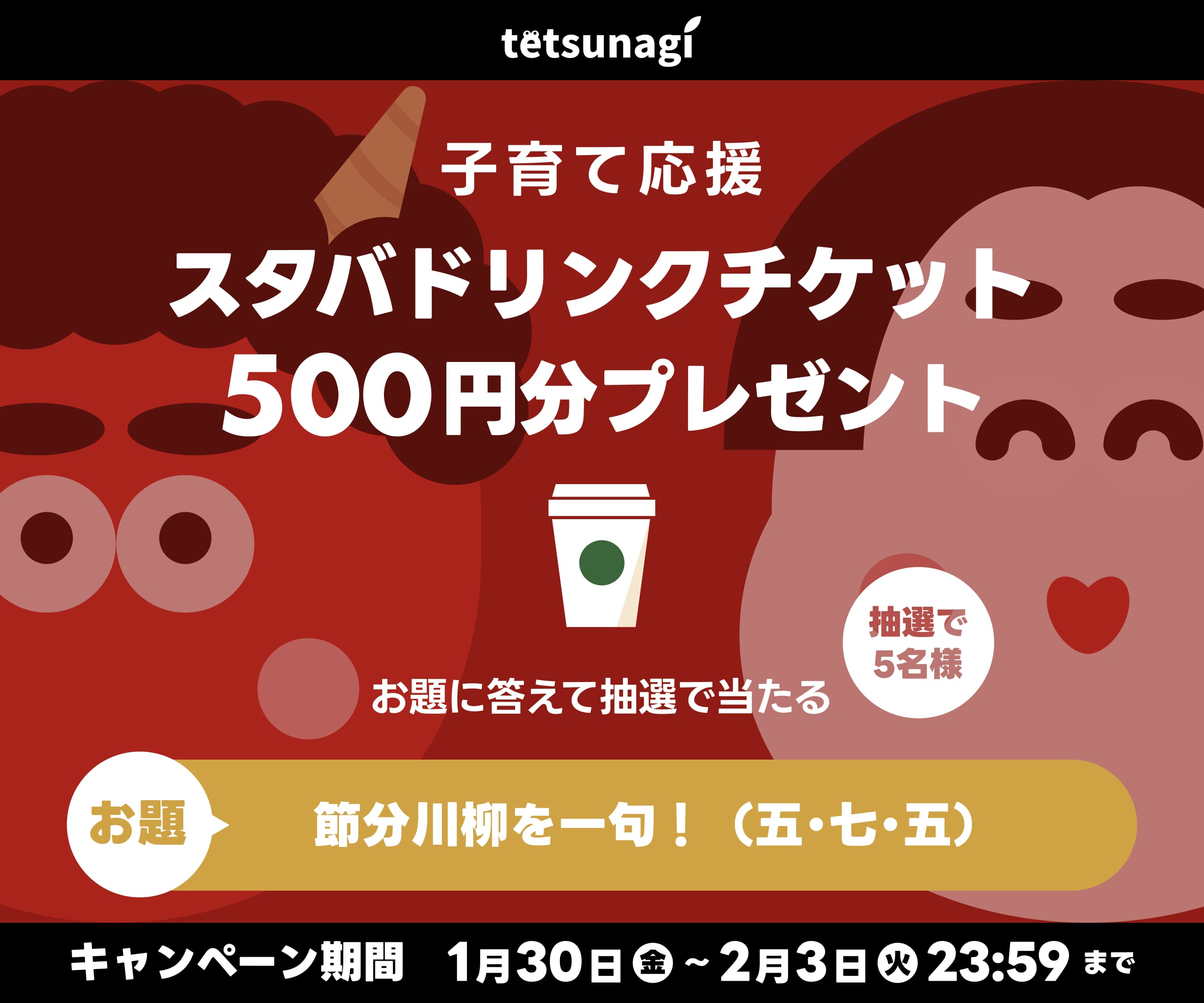中学生が勉強のやる気を出せない原因と具体的な対策方法(第2回)
やる気を出させる7つの方法と学習習慣作りのポイント
教育
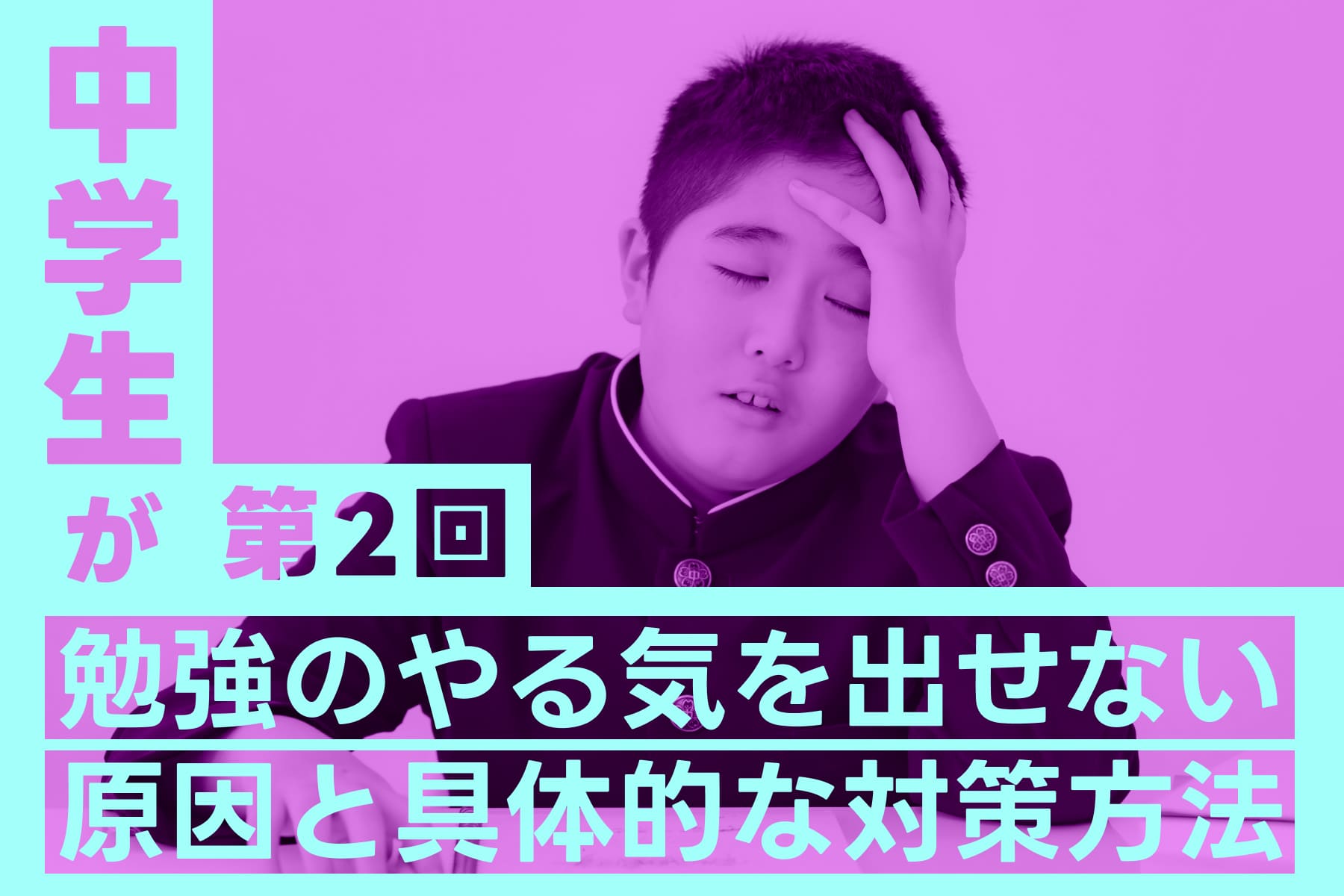
中学生が勉強のやる気を出せない原因と具体的な対策方法(第2回)
こんにちは、多様な教育ナビゲーター・あずみのこです。
15年以上子育て支援に携わり、2人の小中学生を育てる現役共働きママの視点から、コラムをお届けしています。
本コラムは「中学生が勉強のやる気を出せない原因と具体的な対策方法(第1回)」の続きとなります。第1回では、勉強のやる気が出ない原因やタイプ別にみたやる気の出ない中学生への対策を中心に説明をしました。本コラムでは、やる気を引き出す方法や学習習慣作りを中心に説明していきます。
中学生のやる気を引き出す7つの方法
子どものやる気を引き出す方法って、本当に人それぞれです。ある子は「ちょっとしたご褒美」がきっかけになるし、別の子は「机の周りを片づけただけ」で集中しやすくなることもあります。
「これさえやれば絶対大丈夫!」という魔法はないけれど、いくつかの工夫を少しずつ重ねていくうちに、その子なりの勉強スタイルが見えてくるもの。
大事なのは、小さな成功を積み重ねて「できた!」という感覚を持てること。その実感こそが、やる気を育てる一番の原動力になります。
ここでは、家庭で無理なく取り入れられる7つの方法をご紹介します。お子さんのタイプやその日の調子に合わせて、「これならできそう」と思えるものから、気楽に試してみてくださいね。
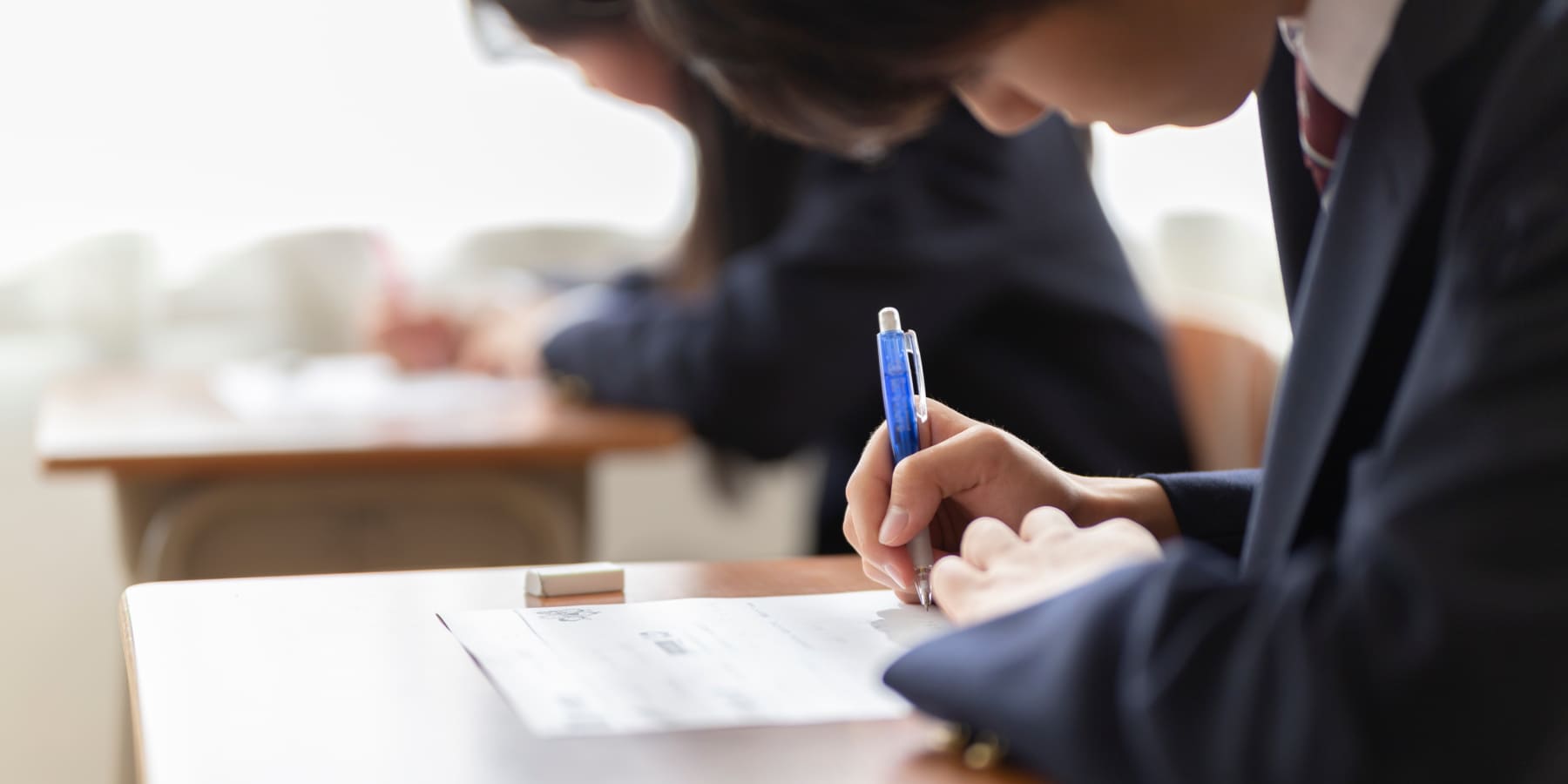
方法1:小さな成功経験を積ませる
「この問題、できた!」という実感が、子どものやる気を動かす大きなきっかけになります。つい「もっと頑張ってほしい」と大きな目標を掲げたくなりますが、最初は短い英単語テストや簡単な計算問題など、“すぐに達成できる課題”から始めるのがコツ。
小さな成功体験を積み重ねるうちに、「あれ、自分にもできるんだ」と少しずつ自信が芽生えていきます。その積み重ねが勉強への抵抗感をやわらげ、「じゃあ次もやってみようかな」という前向きな気持ちにつながります。
たとえば「今日はここまでできたね」「この問題、前より早く解けたね」と一言ほめるだけでも十分。ちょっとした声かけが、子どもの小さな達成感をさらに大きなやる気につなげてくれますよ。
方法2:勉強環境を整えて誘惑をコントロール
スマホやゲームが近くにあると、つい手が伸びてしまう…これは大人でも同じですよね。「ちょっとだけ」のつもりが、気づけばあっという間に時間が過ぎていた、なんてこともあります。
勉強のときだけでも見えない場所に置いたり、使う時間を決めたりするだけで、集中しやすくなります。また、机の上を片づけて「ここに座ったら勉強する」と決めるのも意外と効果的。
小さな工夫でも“勉強スイッチ”が入りやすい環境をつくれると、子どもの集中力は高まりやすくなります。「ここなら落ち着いて取り組める」という安心感があるだけで、子どもも自然と机に向かいやすくなるんですよね。
方法3:親子で目標を設定し進捗をチェックする
「一週間でここまでやろう」と一緒に小さな目標を立てて、週末に振り返る。たったこれだけでも、子どもの勉強に対する意識は大きく変わってきます。
大切なのは、“監視”ではなく“伴走”。親が「どこまでできた?」と聞くのは責めるためではなく、「一緒に見てるよ」というサインなんですよね。
小さなゴールを確認して「ここまでやれたね」と声をかけるだけで、子どもは「次も頑張ろうかな」と前向きになりやすくなります。親子で一緒に小さな達成感を共有できると、勉強が「やらされること」から「一緒に進むこと」に変わっていくのだと思います。
方法4:ご褒美や記録を活用してモチベーションを保つ
スタンプカードやポイント制など、がんばりを「見える化」すると、子どもは自分の進み具合を実感しやすくなります。カレンダーにシールを貼るだけでも、達成感って大きいんですよね。
「ここまでやったら推しグッズ!」なんてユルいご褒美も(笑)、子どもにとっては立派なモチベーション。“がんばりが形になる”ことで自信が芽生えて、自然と次のステップにも進みやすくなります。
方法5:子どもの「できた」を積極的に認める言葉かけ
「ここまでよく頑張ったね」「昨日より早く終わったね」などのほんの一言でも、子どもにとっては大きな励みになります。
つい「まだここができてないでしょ」と注意に目がいきがちですが、まずは“できたこと”に目を向けて声をかけることが大切です。親のそのひと声が、「もっとやってみようかな」という前向きな気持ちを引き出してくれるはず。
小さな変化でも一緒に喜べると、勉強が「叱られる時間」ではなく「認めてもらえる時間」になっていきます。
方法6:ルーティーンを作り、決まった時間に学習する
この時間になったら机に座る」と決めておくと、不思議と勉強へのハードルが下がることがあります。たとえば「部活のあとに30分だけ問題を解く」「朝ごはんの前に英単語を5個覚える」など、ほんの小さなルールで十分です。
毎日同じ時間に続けることで、“勉強するのが当たり前”という感覚が少しずつ育っていきます。親としても「今はこの時間だから勉強してるんだね」と見守れるので、声かけの回数が減り、お互いのストレスも少なくなります。
もちろん、できない日があっても大丈夫。「今日は無理だったけど、また明日やろうか」でOKです。続けようとする姿勢そのものが、子どもの自信を育てていくのだと思います。
方法7:部活や休息のバランスを見直す
部活や友達との時間は、中学生にとって大切な成長の一部。でも、疲れて帰ってきて「もう今日はクタクタ!」という様子のときに「勉強は?」と声をかけても、余力は残っていないものです。
そんなときは「もっと時間を作らなきゃ」と詰め込むよりも、思い切って休むことも大事。たとえば「今日は練習がハードだったから10分だけやろう」「休日は午前はゆっくり休んで、午後にまとめてやろう」と調整するだけで、ぐっと気持ちが楽になります。
親が「今日は疲れてるから、このくらいでOKだね」と認めてあげると、子どももホッとした表情になることがあります。無理なく続けられるペースを一緒に探すことこそ、勉強を長く習慣にしていく近道になるのだと思います。
てつなぎ掲示板:勉強に関する投稿 同じような悩みを持つママがいるかも!?
親が気をつけたいNG行動と上手な接し方
やる気を削がないためには、子どもへの声かけや態度にちょっと注意が必要です。思春期の中学生って、こちらが何気なく言ったひとことや顔の表情に、びっくりするくらい敏感なんですよね。「自分はダメなんだ」と思い込んでしまうこともあるかもしれません。
親の態度は、子どもの勉強への気持ちに直結することがあります。だからといって、いつも完璧に優しく接するのは難しいもの。そこでここでは、「ついやってしまいがちなNG行動」と、その代わりにできる声かけの工夫をご紹介します。ちょっと言い方を変えるだけでも、子どもの受け止め方は大きく変わってくるはずです。
”みんなの声”アンケート:過去に子どもの自主性をつぶしてしまったあなたの言動は?(一言NG)

NG行動1:怒鳴って無理やり勉強させる
「早くやりなさい!」と強い口調で言えば、その場は動くかもしれません。でも、子どもの気持ちはどんどん離れてしまうことがあります。実際、多くの親御さんが「つい声を荒げてしまって、あとで逆効果だったかも…」と振り返ることがあるのではないでしょうか。
無理やり進めた勉強は、その場しのぎになりがちです。それよりも「どこでつまずいてる?」と聞いてみたり、「今日はここまででいいよ」と小さく区切ってあげたり。そんな寄り添う声かけの方が、長い目で見て子どもの力になっていきます。
NG行動2:他の子どもとの比較を繰り返す
「○○ちゃんはもっとできてるよ」「お兄ちゃんのときは…」。つい口から出てしまいそうになる言葉ですが、言われた子どもにとっては「自分はダメなんだ」と感じやすいものです。励ましのつもりでも、比べられると自尊心を傷つけてしまうことがあります。
比べるなら“昨日の自分”。
「昨日より漢字がスラスラ書けたね」「前より集中できたね」といった声かけの方が、「少しずつ成長してる」と実感しやすくなります。
子どもの小さな変化を一緒に喜べると、「またやってみようかな」という気持ちにつながっていきます。親子でそんな積み重ねをしていけたら、きっと勉強の時間も少しずつ前向きなものになっていくはずです。
NG行動3:感情的に責め立ててやる気を失わせる
疲れているときや余裕がないときに、子どもに感情的な言葉をついぶつけてしまうこと…そんな時は誰にでもあると思います。後になって「あぁ、また言いすぎちゃった」と自己嫌悪になることもありますよね。
でも、責められると子どもは「どうせ何やっても怒られる」と感じてしまい、やる気をなくしがちです。そんなときは、ちょっと深呼吸して冷静に「ここがまだ終わってないね」「次はどうしたらうまくいくかな?」と、一緒に事実を確認するだけにしてみるのもひとつの方法です。
親だって人間ですから、いつも完璧に優しく接するのは難しいもの。でも、“責め合う関係”ではなく“考え合う関係”になれたら、子どもも「またやってみようかな」と気持ちを取り戻しやすくなると思います。
「勉強しなさい」と言えば言うほどお互い疲れてしまうこともありますよね。そんなときは、やり方やタイミングを一緒に考えてみるだけでも十分です。親子で少しずつ試行錯誤していけば大丈夫。同じように悩みながら歩んでいるご家庭もたくさんありますから、「うちだけじゃない」と思えるだけでも、少し気持ちが軽くなるのではないでしょうか。
勉強のやる気向上に役立つ塾・家庭教師の活用法
「家で声をかけても、なかなか進まない…」そんなときに頼りになるのが、塾や家庭教師といった専門家のサポートです。
学校以外の場所だからこそ質問しやすかったり、勉強のコツを効率的に教えてもらえたりするのは大きなメリット。特に苦手分野の克服には、個別でじっくり取り組める指導が効果を発揮します。
一方で、集団指導では仲間と一緒に学ぶことで刺激を受け、「自分も頑張ろう」と思える子もいます。子どものタイプや性格に合わせて選べるのが良いところですよね。
中学生は部活や習い事で忙しくなりやすい時期なので、スケジュールや体力も考えながら、無理なく続けられる形を選ぶことが大切です。最近はオンラインのサービスも増えていて、移動時間がかからないぶん取り入れやすいという家庭も多いです。
ただ、相性が合わないまま続けてしまうと逆効果になることも…。カリキュラムや先生との相性をしっかり確認して、子どもに合ったサポートを選ぶことが大事なポイントです。

塾の特徴:集団指導と個別指導の違い
塾は、大きく分けると「集団指導」と「個別指導」があります。
集団指導は、クラスのみんなと同じ内容を学んでいくスタイル。友達と一緒に取り組むことで刺激を受けたり、「自分も負けずにやろう」とやる気が出たりする子にはぴったりです。仲間と一緒に学ぶことで、勉強が「孤独なもの」ではなく「共有できるもの」と感じやすいのも魅力です。
一方で、個別指導は「ここだけわからない」をピンポイントで解消できるのが強み。たとえば「英語の文法は得意だけどリスニングが苦手」「数学の図形だけがどうしても…」といった部分的な悩みにも柔軟に対応してくれます。
家庭教師のメリット:柔軟な指導とモチベーションサポート
家庭教師の大きな魅力は、子どもの生活リズムに合わせて柔軟に対応できることです。たとえば「部活で帰りが遅い日は夜に少しだけ」「テスト前の週だけ回数を増やす」といった調整ができるのは安心ですよね。
自宅で学べるので移動の負担もなく、その場で分からないことをすぐ質問できるのもメリットです。さらに、ただ教えるだけでなく「ここはできてるよ、大丈夫」と気持ちを支えてくれるのも家庭教師ならでは。
勉強へのやる気が落ちているときでも、隣に寄り添って伴走してくれる人がいるだけで「またやってみようかな」と思いやすくなります。親だけでは補いきれない部分をそっと支えてくれる存在がいると、本当に心強いですよね。
学習塾やオンラインサービスの選び方
塾やオンラインサービスを選ぶときに大切なのは、「うちの子に合っているか?」という視点です。集団で競い合う方がやる気が出る子もいれば、マンツーマンでじっくり取り組んだ方が伸びる子もいますよね。
そのためには、まず体験授業に参加して「ここなら気楽に続けられそう」と子ども自身が感じられるかどうかを確認するのがおすすめ。親が良さそうと思っても、本人が「無理…」と感じたら続けにくいものです。
目的や学び方が子どもにフィットすると、「ここで頑張ってみようかな」という気持ちが自然に出てきます。塾やオンラインサービスは“魔法の特効薬”ではありませんが、相性が合えば長く学びを支えてくれる心強い味方になってくれるはずです。
やる気を継続させる学習習慣づくり
一時的に「よし、やるぞ!」と気合いが入っても、それが続かなければ成果につながりにくいんですよね。大切なのは「習慣として自然にできるかどうか」。
これは子どもだけじゃなく、大人も同じです。ダイエットや運動、家計簿なども、最初は気合いで頑張っても三日坊主で終わってしまうことってありますよね。勉強も同じで、最初から完璧を目指すより「今日は10分だけやろう」とハードルを下げた方が続きやすいんです。
中学生は部活や友達との時間も多く、生活が不規則になりやすい時期。だからこそ「毎日きちんと」でなくても大丈夫。無理のないペースで少しずつ習慣を整えていくことが、長く続けるコツになります。
完璧さよりも「続けられるリズム」を一緒に見つけてあげられると、子どもにとって勉強はぐっと身近で安心できるものになっていくはずです。

生活リズムの整え方:睡眠・食事・運動
夜更かしや食事の乱れって、思った以上に集中力や記憶力に響きますよね。私も「ちょっとだけ動画を…」と夜更かしして、次の日まったく頭に入らなかったことが何度も(笑)。やっぱり「7~8時間の睡眠」と「朝ごはん」は勉強の土台になるんだなぁと実感します。
理化学研究所の研究でも「眠っている間に脳の神経回路が整理されて、学んだことが記憶に残りやすくなる」と報告されているんです【※3】。こうした話を聞くと、「やっぱり寝るのも勉強のうち」と思えますよね。
それから、部活や散歩みたいなちょっとした運動も大事。体力づくりになるだけじゃなくて、気分が切り替わって「よし、ちょっとやってみようかな」と自然に背中を押してくれる感じがします。
モチベーション低下時のリセット方法
「全然進まない…」「もうイヤ!」そんなときって、誰にでもありますよね。私も子どもの勉強を見ていて、「あ、もう今日は限界だな」って顔に出ているときがあります。そんなときは、無理に続けさせるより、いったん区切ってリセット。
私も、家事や仕事で煮詰まったときにお茶を飲んだり、ちょっと音楽を流したりすると気持ちが軽くなることがありますから。子どもにとっても同じで、ストレッチをしたり、数分ぼーっとしたりするだけで、また気持ちを立て直しやすくなるんですよね。
「これをやればちょっと元気が戻る」というリフレッシュ方法を、親子で一緒に見つけておくのもおすすめです。
まとめ・総括
中学生が勉強に前向きになれない理由は、本当に人それぞれです。「なんで勉強しなきゃいけないのか分からない」「授業についていけなくてつらい」「部活やスマホで毎日くたくた」
きっと子どもたちは、そんな思いをたくさん抱えているのだと思います。
まずは、「どうしてやる気が出ないんだろう?」と、一緒に考えてみることから始めてみませんか。理由が見えるだけでも、子どもが安心して前に進む一歩になることがあります。
そのうえで、お子さんの性格や今の状態に合った工夫を試したり、必要であれば塾や家庭教師といった外の力に頼ってみるのもいいと思います。「ここなら安心して勉強できる」と感じられる場所が一つあるだけで、子どもの心はきっとラクになります。
親として「早くなんとかしなきゃ」と焦る気持ちは自然なこと。でも、勉強への気持ちは一気に変わるものではなく、少しずつ変わっていくものなんですよね。小さな「できた!」「わかった!」を重ねていくうちに、「自分にもできるかも」という前向きな気持ちが芽生えてきます。
焦らずに、無理をせずに。ときには立ち止まりながら、子どもと一緒にのんびり歩いていけたら十分。その姿勢こそが、お子さんの力を引き出す一番の応援になるんだと思います。
そして、どうしてもモヤモヤしてしまうときは、ひとりで抱え込まなくても大丈夫です。「てつなぎの掲示板」に、気持ちをそのまま書き込んでみてください。同じように悩んできた親御さんたちが、きっとあたたかく受けとめてくれるはずです。
てつなぎ掲示板:勉強に関する投稿 同じような悩みを持つママがいるかも!?
あずみのこも、掲示板をのぞいています。ここでのつながりが、あなたの心の支えのひとつになれたら…とても嬉しいです。
多様な教育ナビゲーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね