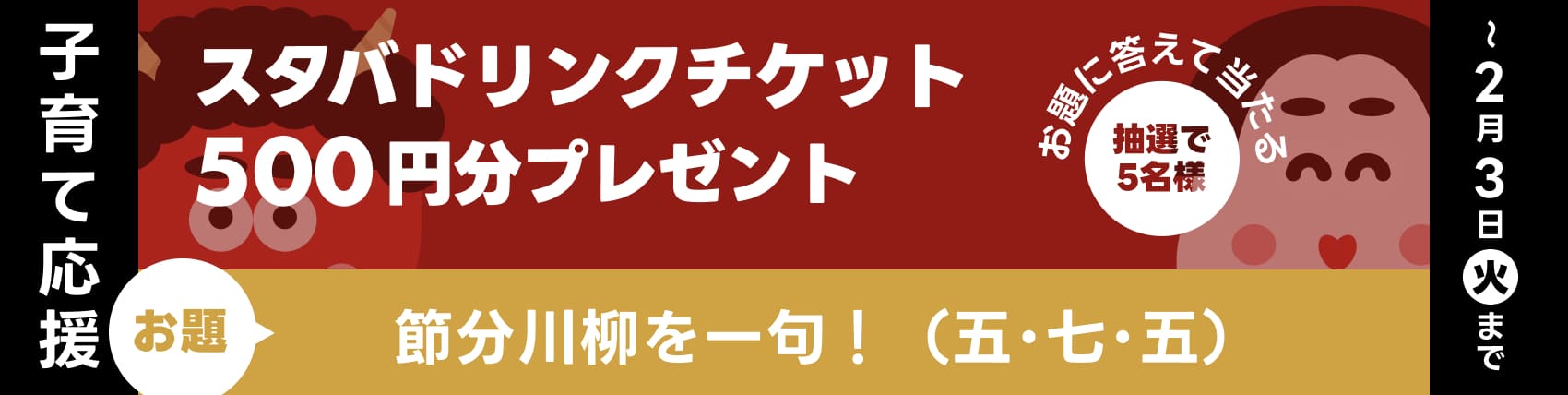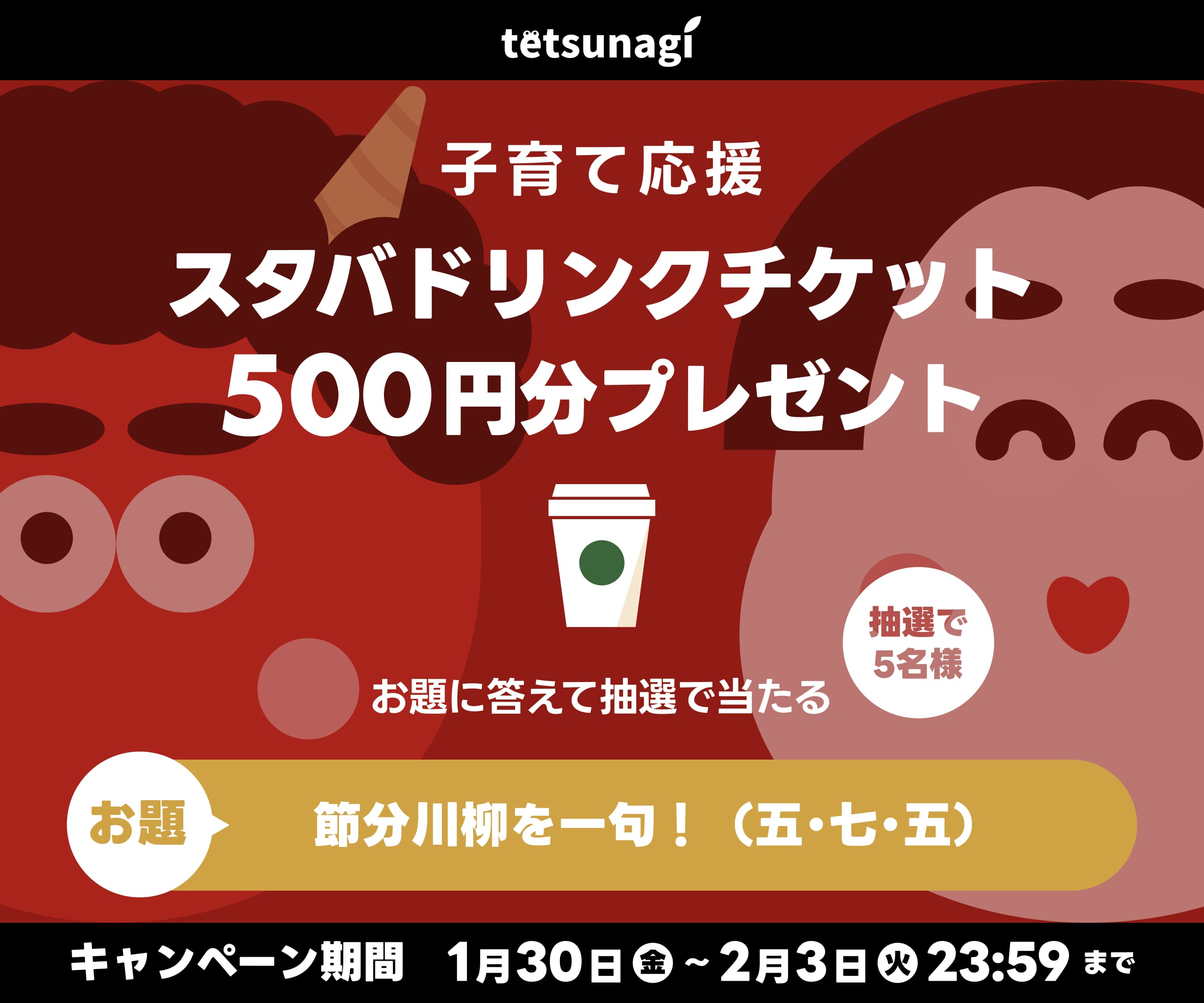中学生が勉強のやる気を出せない原因と具体的な対策方法(第1回)
タイプ別に見る『やる気が出ない中学生』への対策をまとめました
教育
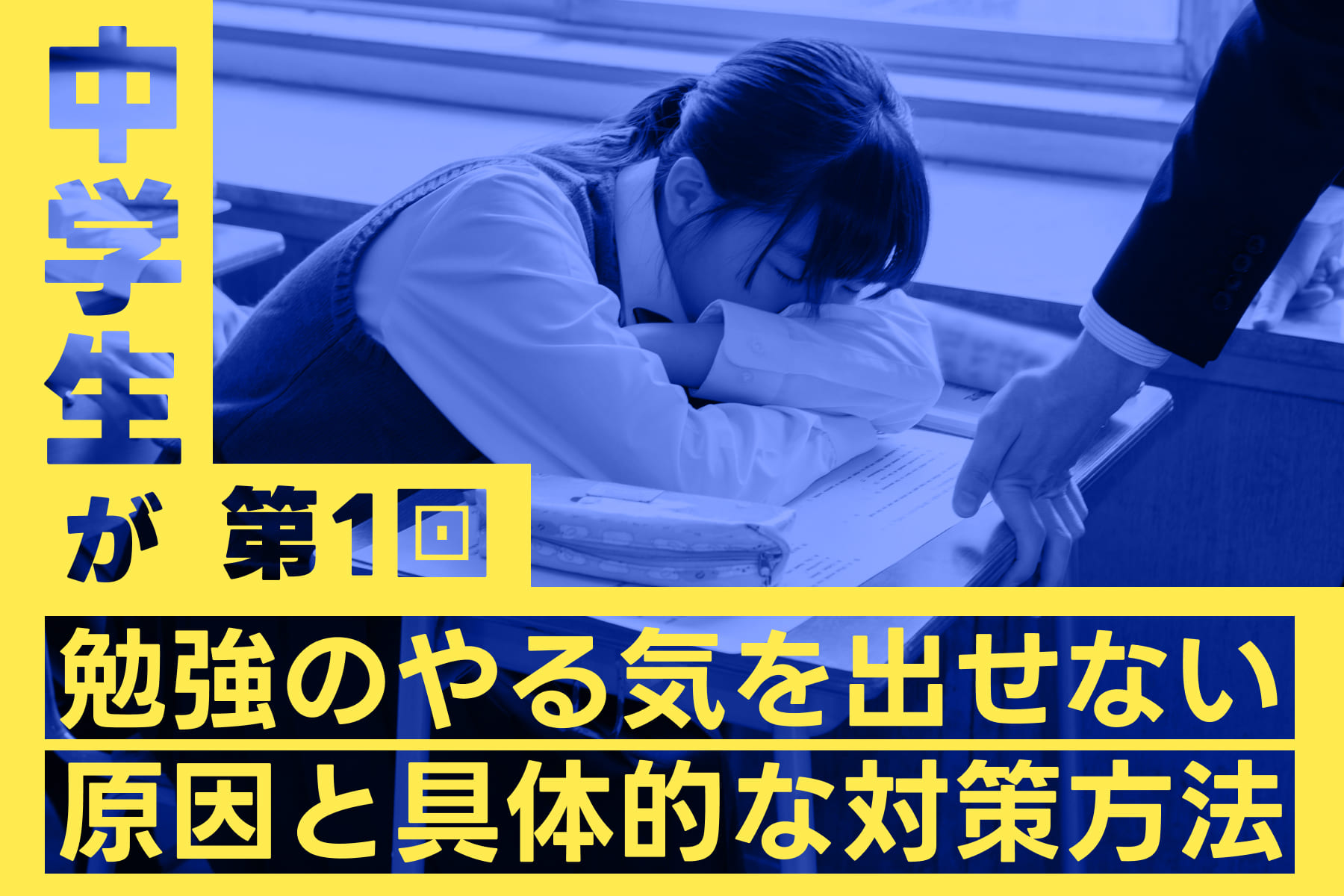
中学生が勉強のやる気を出せない原因と具体的な対策方法(第1回)
こんにちは、多様な教育ナビゲーター・あずみのこです。
15年以上子育て支援に携わり、2人の小中学生を育てる現役共働きママの視点から、コラムをお届けしています。
これまで多くのご家庭と関わる中で、特に中学生になると「勉強にやる気が出なくて心配」という声をよく耳にしてきました。
思春期は心も体も大きく変化する時期。「やればできるのに」と思う一方で、その言葉が逆効果になることもありますよね。応援したい気持ちと空回りしてしまう現実。その間で揺れるのは、多くの親に共通する姿だと思います。
このコラムでは、中学生が勉強のやる気をなくしてしまう理由や背景を整理しながら、親ができるちょっとしたサポートの工夫をご紹介します。「そうそう、うちも同じ!」と共感しつつ、「これなら試せそう」と思えるヒントを持ち帰っていただけたらうれしいです。
勉強のやる気が出ない中学生によくある5つの原因
「最近、全然勉強のやる気が見えない…」「部活から帰ってくると疲れて寝ちゃって、勉強してる気配がない…」きっと同じように感じているご家庭も多いのではないでしょうか。思春期の中学生は、心も体も大きく変化する時期。将来への漠然とした不安や「授業が難しい」という気持ちも重なって、やる気を保つのは簡単じゃないんですよね。
ただ、この状態を放っておくと、「勉強は自分には向いていないんだ」と思い込み、成績や進路、自己肯定感に影響してしまうこともあります。
まずは「どうしてやる気が出ないのか?」と親子で一緒に考えてみることが大切。理由が見えるだけでも、子どもの気持ちは少し安心できるはずです。
ここからは、中学生がつまずきやすい5つの原因を挙げながら、それぞれに合わせた対策のヒントを探っていきましょう。

原因1:勉強する意義が分からない・目標がない
「なんで勉強しなきゃいけないの?」
そう聞かれると、親の方がドキッとしてしまうこと、ありますよね。「将来のためでしょ」と当たり障りなく答えてしまい、子どもにとってはピンとこないまま会話が終わってしまうことも…。
中学生は、将来やりたいことがまだぼんやりしている子も多いので、「勉強がどこにつながるのか」をイメージするのは難しいのが自然です。親も無理に立派な答えを用意する必要はなくて、「ほんとだよね、意味わからないよね」と共感するだけでも子どもはきっと安心します。
さらに効果的なのは、子どもの“好きなこと”に結びつけてみること。たとえば「洋楽が好きだから英語に興味を持った」「推しのセリフを理解したくて韓国語を調べてみた」「ゲームのスコア計算から算数に興味を持った」など、きっかけは身近なところにたくさんあります。
子ども自身の関心と勉強がつながると、“自分ごと”として受け止めやすくなり、やる気の芽も育ちやすいんです。
”みんなの声”アンケート結果:子どもに「何で勉強しなくてはいけないの?」と聞かれたら何て答える?
原因2:授業内容が難しく理解できない
中学の勉強って、本当に一気にレベルが上がりますよね。小学校の頃まではなんとなくついていけていたのに、「急にわからなくなった」と感じる子は少なくありません。特に数学や英語は積み重ねが大事なので、前の内容でつまずくと「もう無理」と気持ちが折れてしまいやすいんですよね。
つい「ちゃんと授業聞いてればわかるでしょ」と言いたくなってしまうのですが、実際は“わからないまま授業が進む”という悪循環に入っていることが多いのかもしれません。
そんな時は、思い切って基礎に戻るのも有効です。小学校のドリルなど簡単な内容からやり直すことで「ここならできる」という感覚を取り戻しやすくなります。
「できるところからやり直す」ことは後退ではなく、前に進むための大切なステップ。小さな「わかった!」「できた!」を積み重ねることが、次のやる気へとつながっていきます。
原因3:勉強方法のやり方がわからない
「机には向かってるのに、全然進まない…」そんな姿を見たことはありませんか?とりあえず教科書を眺めたり、宿題だけは終わらせたり。でも、本人も「勉強してるのに成績が上がらない」と感じて、ますますやる気をなくしてしまうことがあります。
実は“勉強のやり方”って、誰もが自然に身につけられるものじゃないんですよね。計画の立て方、問題を解く順番、わからないところを質問するコツ…。大人からすると当たり前のことでも、中学生にはまだ難しかったりします。
そんなときに「もっと集中して!」と責めるのは逆効果。 「今日はどこから始める?」「まずは宿題、それから復習にしようか」と一緒に方法を探してあげるだけで、子どもは動きやすくなります。
小さな工夫でも「やればできるかも」と感じられると、次のやる気につながりやすいものです。
原因4:部活や遊びで疲れてしまい集中力が続かない
中学生になると、本当に毎日が忙しくなりますよね。部活でヘトヘトになって帰ってきたり、友達と遊んで帰りが遅くなったり…。家に着くころには、ご飯を食べてお風呂に入ったらもう電池切れ、なんてこともよくあります。
親からすると「時間はあるのに、なんでやらないの?」と思ってしまいがちですが、実際は“気持ちはあるのに体がついていかない”だけのことも多いんですよね。
そんなときは「根性でやりなさい!」ではなく、生活リズムをちょっと工夫してあげるのがカギ。夜に疲れてしまうなら、朝のスッキリした時間をほんの20〜30分だけ勉強にあててみる。週末に少し予習や復習をしておけば、平日の負担も減らせます。
「休むときはしっかり休む」「やるときは短時間でも集中する」。このメリハリがつくと、子どもも無理なく続けやすくなります。
もちろん、実際は朝もバタバタで「そんな余裕ない!」という日が多いと思います(笑)。でも、できるときに少しずつ工夫するだけでも十分なんですよね。
原因5:スマホやゲームに気を取られてしまう
スマホやゲームの誘惑は、とにかく強力です(笑)。「宿題やろう」と思って机に向かったのに、ついSNSを開いてしまったり、友達からのオンラインゲームの誘いに乗ってしまったり…。気づけばあっという間に時間が過ぎてしまいます。
親としては「スマホ禁止!」と言いたくなることもあるかもですが、完全に取り上げるのは現実的じゃないし、かえって反発を招いてしまうこともありますよね。
大事なのは“メリハリをつけること”。
「1時間はリビングで一緒に勉強しよう」
「宿題が終わったらゲームしてOK」
こんなふうに親子でルールを決めておくと、子どもも納得しやすくなります。やることを終えたあとで思いきり楽しめる時間があると、勉強にも自然と区切りがついて「またちょっと頑張ろうかな」という気持ちにもつながっていくんですよね。
てつなぎ掲示板:勉強に関する投稿 同じような悩みを持つママがいるかも!?
タイプ別に見る『やる気が出ない中学生』への対策
「やる気が出ない」とひとことで言っても、その理由は子どもによって本当にさまざま。授業が難しくて自信をなくしている子もいれば、「やらなきゃ」と思いながら手が動かない子もいます。性格や生活リズム、苦手科目によっても状況は違うので、同じ“やる気が出ない”でも背景は一人ひとり違うんですよね。
親としては「どうしたらやる気になるんだろう」と悩んでしまいますが、子どものタイプに合わせて関わり方をちょっと工夫するだけで、「あれ?今日は自分から机に向かってる!」なんて嬉しい瞬間が訪れることがあるかもしれません。
「うちの子はどのタイプに近いかな?」と重ね合わせながら読んでみてください。普段の声かけや勉強環境づくりのヒントが見つかると思います。ここからは、代表的な5つのタイプをご紹介しますね。

タイプ1:授業についていけず勉強に自信をなくしている
授業が分からないままどんどん進んでしまうと、「どうせ自分には無理だ」と気持ちがしぼんでしまうことがあります。テスト前になると「もう間に合わないし…」と、やる前から投げやりになってしまう姿に、親としても見ていて胸が痛くなること、ありますよね。
こんなときは、一気に全部を取り戻そうとしなくて大丈夫。まずは基礎をもう一度見直して、「ここだけはわかる!」という小さな安心を積み重ねていくことが大切です。
実際に「漢字ドリルを少し前の学年に戻って、1日1ページからやり直したら、少しずつやる気が戻ってきた」という保護者の声もあります。「昨日より少し進んだね」と小さな成功を一緒に喜ぶことで、自信は少しずつ回復していきます。
必要に応じて、塾や家庭教師など外の力を取り入れるのも一つの手。誰かが隣で寄り添ってくれるだけで、「もう少しやってみようかな」と思える子も多いんです。
タイプ2:何から勉強を始めればいいか分からず空回りしてしまう
「勉強しなきゃ…」と机に座ったのに、気づいたらノートを開いただけで時間が過ぎていた、なんてことありませんか。実はこういう子、とても多いんです。
このタイプの子には、やることを順番通りに並べてあげるだけで動きやすくなることがあります。たとえば「まず宿題 → 次に今日の復習 → 最後に明日の予習」みたいに小さく区切ると、迷わず始めやすいんですよね。ポイントは、“とりあえずの一歩”を軽くしてあげること。
学習心理学の研究でも「やることを小さく分けて、時間をどう配分するか意識すること」が学習効果を高めるとされています【※1】。
家庭ではもっとシンプルで大丈夫。付箋に「①宿題、②復習、③予習」と書いて机に貼っておくだけでもOK。「まずはこれだけ」と見える形にすると、迷う時間が減って「とりあえずやってみようかな」と思いやすくなりますよ。
タイプ3:勉強が嫌いで意味を感じられない
「勉強なんてつまらない」「やる意味あるの?」と、真正面からそう言われると、親としてはつい「いいからやるの!」と返したくなってしまいますよね。でも、このタイプの子にはその言葉が逆効果になってしまうことも少なくありません。
大事なのは、テストの点や成績だけを目的にしないこと。むしろ「ちょっと面白そう」と思えるきっかけをつくってあげる方が効果的です。
たとえば歴史好きなら「歴史を深めた人ってどんな仕事をしているんだろう?」と調べてみる。科学に興味があるなら「この分野を学ぶとどんな未来の研究につながるのかな?」と想像を広げてみる。実際、「ゲーム好きな子に統計やデータの話をしたら急にやる気が出てきた」という保護者のエピソードもあります。
子どもの“好き”と勉強を少し結びつけるだけで、拒否感がやわらぎ「じゃあ少しやってみようかな」と自然に気持ちが動きやすくなるんですよね。
タイプ4:集中力が続かず疲れてしまう
やる気はあっても、いざ始めてもすぐに気が散ってしまう子も多いですよね。部活や生活の疲れがたまっていることも多いので、「根性が足りない」のではなく“体力切れ”に近いのかもしれません。
このタイプには、短時間集中+休憩のサイクルが効果的です。たとえばポモドーロ・テクニック(25分勉強+5分休憩など)を取り入れると、「ちょっとなら頑張れる」と取り組みやすくなります。実際に、電気通信大学の研究では、学習中に適切なタイミングで休憩をはさむことで、後半の学習効果の低下を防げる可能性があることが示唆されています【※2】。
家庭学習でも「25分やったら5分休憩しよう」と声をかけたり、疲れのサインが見えたときにいったん区切ってあげたりするだけで、勉強が続けやすくなるかも。
そして、忘れがちなのが生活の土台。睡眠や食事のリズムが乱れていると、どんな工夫も長続きしにくいんですよね。「集中できないのは怠けじゃなくて、体が疲れてるからなんだ」と受け止めてあげるだけでも、子どもにとってはホッとできるサポートになると思います。
タイプ5:将来の目標がまだ見えずやる気を持ちにくい
「別にやりたいこともないし…」と、そもそもやる理由が見つからない子もいます。 親からすると「せめてテストくらいは頑張ってほしい」と思ってしまいますが、目の前のテストだけをゴールにしても「だから何?」と感じてしまうこともあるんですよね。
こういうときは、大きな夢をいきなり描かせる必要はなくて“ちょっと先の未来”を一緒に探すことから始めてみるのもおすすめ。たとえば進路相談やオープンキャンパスに足を運んでみたり、先輩や大人の体験談を聞く機会をつくってみたりすると、「へぇ、こんな道もあるんだ」と、子どもの中に小さな気づきが芽生えることがあります。
未来の姿がほんの少しでも具体的にイメージできるようになると、「じゃあ今やってる勉強も無駄じゃないのかも」と思いやすくなります。今は無気力に見えても、“きっかけ”さえあれば一歩踏み出せることもある。その小さな一歩を、親が隣でそっと支えてあげられると安心ですよね。
多様な教育ナビゲーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね