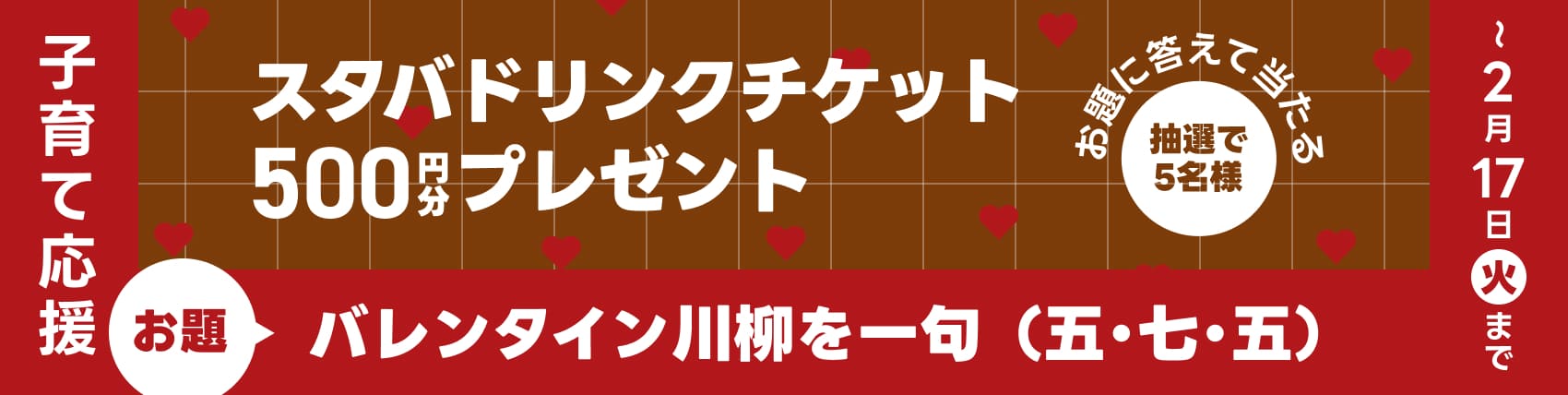【第2回】小学生の不登校とは?増加する背景とその実情
焦らず、比べず、「いま、この子にとって何が大切なんだろう?」と、一緒に考えていくこと。
学校
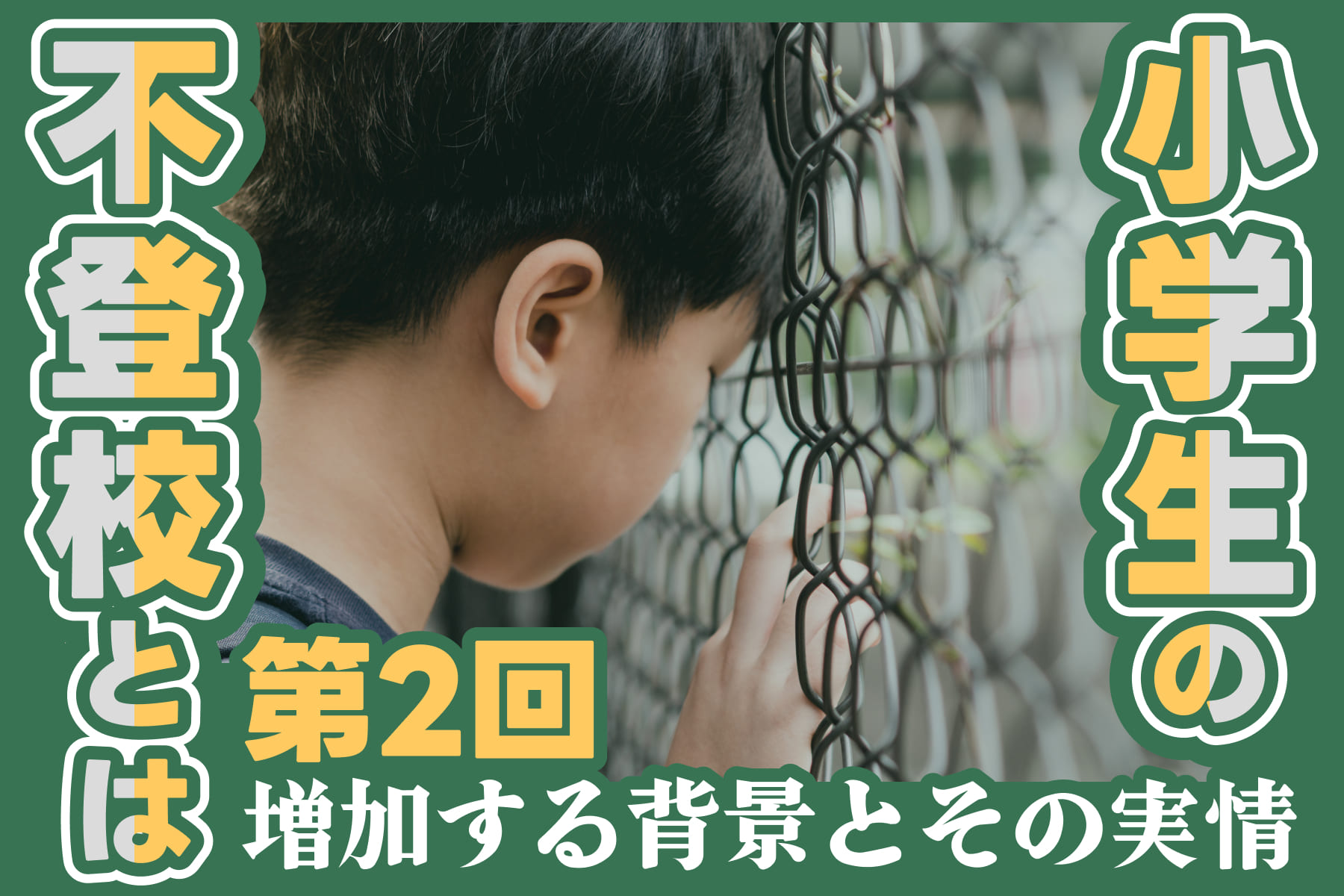
【第2回】小学生の不登校とは?増加する背景とその実情
2023年度の不登校の児童生徒数は全国でなんと41万5,844人。小・中・高校を合わせて、過去最多となりました。なかでも、小学生の不登校は13万人を超え、11年連続で増加。小学生の不登校とは?増加する背景とその実情とは?(全2回の第2回)
不登校の裏側にある小学生の心理的特徴
不登校という“行動”の奥には、「不安」「戸惑い」「がんばっても認められないつらさ」——。 そんな、言葉にならない感情がぎゅっと詰まっていることが少なくありません。
とくに小学1〜2年生ごろの子どもたちは、「自分の気持ちをどう説明すればいいのかわからない」まま、「なんでこんなに泣いちゃうの?」「どうして行きたくないのかわからない…」と、自分自身でも戸惑っていることがあります。
朝の支度をするころになると、強い不安や緊張がこみあげてきて、体が動かなくなってしまう。そんな状態を経験する子どもは、実は少なくありません。頭痛や腹痛などの身体の症状としてあらわれることも多く、その背景には、友達関係や勉強のつまずきだけでなく、家庭でのストレスが影響していることもあります。
大人から見ると、「どうしてそんなに不安なの?」と不思議に思うかもしれません。でも、子どもにとっては、それが本当に“いま、いちばんつらいこと”だったりするんですよね。
私自身、「学校行きたくない」と涙を流す子どもに、どう応えたらいいのかわからず、戸惑ったことがありました。でもある日、「今日はママと映画デートでもしようか!」と声をかけて、ふたりで出かけてみたんです。特別なことをしたわけではなかったけれど、帰り道、息子が「明日は行こうかな」って。“心がちゃんと休めたからこそ、また前に進もうとする気持ちが生まれたのかな”と感じた、あたたかい記憶として残っています。
まずは「つらいよね」「ここにいていいよ」と、そっと伝えること。その一言が、子どもにとって「ここなら大丈夫」と、次に進むための安心の入り口になるのだと思います。
周囲に気付かれたくないプライドや葛藤
小学校の高学年くらいになると、「できないところは見せたくない」「親に心配をかけたくない」と、あえて何も言わずにがんばろうとする子も増えてきます。でも実は、その沈黙の奥には、「本当はつらい」「でもうまく言えない」と、そんな“見せられない気持ち”との葛藤があることも、少なくありません。
「友だちに弱みを見せたくない」「親をがっかりさせたくない」と、そんな思いをぎゅっと抱えたまま、限界までがんばって、不登校というかたちでしか「つらい」を伝えられなくなることもあるのです。
J-STAGEに掲載された中学生への聞き取り調査では、「感覚の過敏さ」や「人前での緊張」が、学校での適応を難しくし、強い内面の葛藤につながることが報告されています(出典:日本作業療法士協会「通常学級に在籍する学校適応に困難のある中学生の語り」)。こうした傾向は、中学生に限らず、小学校高学年の子どもたちにも少しずつ見られるようになるものだと感じています。
だからこそ、「何も言わない=大丈夫」と決めつけずに、「もしかして、何か抱えているのかな?」と想像してみることが、大人にできるやさしい関わりなのだと思います。たとえば、笑顔の裏にふっとよぎる無表情や、ポツリと口数が減った瞬間など。
そんなささやかな変化に気づいて、「大丈夫だよ」「話したくなったら、いつでも聞くからね」と伝えられること。それだけでも、子どもにとっては「ここなら話せるかも」と思える、あたたかな環境づくりにつながっていくはずです。
「原因がわからない」と悩む子どもの本音
「理由はわからないけど、学校に行けない」。そんなふうに感じている子どもは、実はたくさんいます。 私がこれまでお話を聞いてきたご家庭でも、「何が原因かははっきりしないけれど、ある日を境に行けなくなった」という声は少なくありませんでした。たとえば、「朝になると涙が出てしまう」「学校に行こうとするとお腹が痛くなる」など、気持ちのつらさが身体にあらわれることもあります。でもそれは、子どもが「言葉にならない苦しさ」とたたかっているサインなのかもしれません。
J-STAGEに掲載された質的調査「不登校発生の背景要因に関する研究」でも、登校の子どもたちの多くが「自分の気持ちがうまく説明できない」「どこにも居場所がないと感じた」と語っていたことが報告されています(出典:日本家族心理学会『不登校発生の背景要因に関する研究』2023年)。
だからこそ、「わからない」という状態そのものが、とてもしんどいことなのだと思います。そんなときは、「そっか、うまく言えないくらい、気持ちがごちゃごちゃなんだね」「今は言えなくても大丈夫だよ」と、そっと寄り添うこと。その受けとめが、子どもにとっては「ここなら安心していられる」と感じられる、最初の一歩になるのだと思います。
低学年・中学年・高学年で異なる不登校の傾向
子どもが「学校に行きたくない」と感じる理由は、本当にさまざまです。その背景を考えるうえで大切なのが、「この子はいま、どんな時期を生きているのか」という視点です。小学校の6年間は、心も体もぐんぐん育っていく時期。1年生と6年生では、見えている世界も、感じていることも、まったく違うと言ってもいいかもしれません。
低学年では、まだ親とのつながりを強く必要としていたり、中学年になると、友だちとの関係や「自分はできるかどうか」が気になってきたり。高学年になると、自分なりの考えや違和感をもつようになり、それをうまく言葉にできずに抱え込んでしまうこともあります。
だからこそ、「この子はいま、どんなことでつまずいているのかな?」「どんなふうに受けとめてあげたらいいかな?」と、その子の“今”に寄り添うことが、周りの大人にできる大切なまなざしなのだと思います。

低学年(1~2年生)の不登校事情
小学校に入学したばかりの低学年の子どもたちは、まだ生活リズムも整いきらず、教室という集団の場に適応するだけでも、大きなエネルギーを使っています。とくに1年生は、園生活からガラッと環境が変わることもあって、「ママと離れるのがさみしい…」「学校ってなんだかこわい場所かも…」と感じるのも、自然な反応なのかもしれません。
朝の支度をするたびに涙が出たり、「お腹が痛い」と体にサインが出てきたり。そんな姿に、戸惑う保護者の方も多いと思います。でも、そんな時こそ、「この子はいま、どんな気持ちなんだろう?」と、少し立ち止まってみてほしいのです。「朝の表情がこわばってないかな?」「学校の話をすると顔が曇るかな?」など、そうやって、ほんの小さな変化に気づこうとするまなざしが、子どもにとっての安心につながります。
「まだ小さいから、きっとそのうち慣れるよね」と思いたくなることもありますが、安心できる場所があること、「そのままでいいよ」と受けとめてもらえた経験は、その子にとっての回復の土台になります。ときには、ほんの1日おやすみしただけで、「また行ってみようかな」と自分から言い出すことだってあるんです。 “ちょっと立ち止まること”も、子どもにとっては立派な前進のひとつ。焦らず、見守っていけたらいいですね。
中学年(3~4年生)の変化とふり幅
3〜4年生になると、友だちとの関わり方や勉強の難しさなど、学校生活の中で向き合うテーマが少しずつ複雑になっていきます。「グループの中でうまくやれてるかな」「自分だけ仲間はずれかも…」そんなふうに、“友だちとの距離感”を気にしはじめるのも、この時期の特徴です。また、勉強や運動の場面でも、「なんで自分だけできないんだろう」と、まわりとの違いに戸惑う子も出てきます。
それでも多くの子は、自分の気持ちをうまく言葉にできず、ただ黙ってがまんしてしまいがち。「行きたくない」と言えないまま、「とにかく行かなきゃ」と、自分を奮い立たせている子も、きっと少なくありません。この時期は、自立心も少しずつ芽生えてくる一方で、心の中ではまだまだ「受けとめてほしい」「わかってほしい」と思っていることが多いんですよね。
だからこそ、「なにがあったの?」と詰めるのではなく、「最近、ちょっとしんどい?」「学校、大変なことあった?」と、気持ちを受けとめる前提の声かけが、とても大きな安心につながります。子ども自身が「言葉にできない気持ち」を抱えていることに、私たち大人が気づけるかどうか。そのまなざしが、子どもの心をふっとゆるめるきっかけになるのだと思います。
高学年(5~6年生)の思春期と長期化リスク
5〜6年生になると、心も体も少しずつ思春期に向かっていく時期に入ります。「このままでいいのかな」「なんで学校に合わせなきゃいけないんだろう」と、そんなふうに、学校という枠組みに対して、“なんとなくの違和感”を抱き始める子も出てきます。
でも、その気持ちをうまく言葉にできないまま、「がんばらなきゃ」「迷惑をかけちゃいけない」と、自分を奮い立たせて無理を重ねてしまう。そしてある日、心の糸がぷつんと切れてしまったように、急に学校に行けなくなってしまうこともあります。
不登校が長期化するケースが少なくないのも、この時期の特徴かもしれません。だからこそ、「学校に行けるかどうか」だけをゴールにせず、「話せる場所があるよ」「他の学び方もあるよ」と、早いうちから伝えておくことがとても大切なんだと思います。その一言が、子どもにとっての“逃げ道”ではなく、「ここにいていいんだ」という安心の土台になるのだと思います。
家での過ごし方と生活習慣づくり
不登校の子どもにとって、家は「安心して自分でいられる」大切な場所。でもその安心感の中で、気づいたら昼夜逆転の生活になっていたり、「何もしたくない」が長引いてしまうこともあります。気づかないうちに、心と体のエネルギーがじわじわと削られていくこともあるんですよね。
「早く元気になってほしい」「また学校に行けるようになったら…」そんなふうに願うのは、親としてごく自然なこと。でも、だからこそつい「何かさせなきゃ」「少しでも前に進ませたい」と力が入ってしまうことも、あると思います。
でもまず大切なのは、子どもが“自分のペースを取り戻せる環境”を、いっしょに「整えていく」ことなんじゃないかなと、私は思います。

まずは心と体を休めること
「行けない」には、きっとその子なりの理由や背景があります。言葉にできていなくても、体が教えてくれていることもあるんですよね。学校がプレッシャーになっているなら、今いちばん必要なのは“安心して休める場所”。私はこれまで、たくさんの子どもたちや保護者の方々と関わってきて、そのことを何度も感じてきました。
心にエネルギーがたまってくると、子どもって不思議と、自分から動き出していくことがあるんです。「今日はちょっと外に出てみようかな」とか、「これ、やってみたいな」とか。
焦らなくて大丈夫。「今は止まっているように見えても、内側では次に向かう力がちゃんと育っている」。そう思えるだけで、子どもを見る目も、親としてのかかわり方も、少しだけ優しくなれる気がします。
好きなこと・できることがエネルギーになる
「学校には行けないけれど、好きなことには集中できる」。そんな時間が、子ども自身のエネルギーを回復させてくれることがあります。たとえば、料理に夢中になったり、ゲームで笑い合ったり、絵を描いたり。
周りから見たら何気ないように見える時間が、子どもにとっては「自分にもできることがある」と思える、大事な一歩になることもあります。「これなら、ちょっと楽しいかも」「ぼく、これ得意かも」。そんな感覚が少しずつ戻ってきたとき、子どもは自然と次のステップへ進む準備を始めるのだと思います。
毎日のリズムを整える工夫
「朝起きる」「顔を洗う」「ごはんを食べる」。そんな“あたりまえのこと”が、不登校の子にとっては大きなハードルに感じられることもあります。でも、それでいいんです。完璧じゃなくて大丈夫。今日は少し早く起きられた、昨日よりちょっとごはんが食べられた。そんな小さな“できた”を一緒に喜ぶことが、心のエネルギーを少しずつ蓄えていく支えになります。
毎日のリズムは、心のリズムでもあります。無理のない範囲で、子どもが「ちょうどいい」と感じられる過ごし方を見つけていけたら、きっとまた、自分らしいペースが戻ってくるはずです。
保護者ができる支援と具体的アクション
「どうして行けないの?」「早く学校に戻ってくれたらいいのに…」と、そんな気持ちが頭をよぎること、きっと誰にでもあると思います。私自身、わが子が登校できなくなったときは、不安と焦りでいっぱいで、「どうすれば元に戻るの?」と毎日のように悩んでいました。
でも、あとから気づいたんです。子どもが学校に行けないとき、いちばん必要なのは「行かせること」ではなく、「気持ちをわかろうとしてくれる存在」なんじゃないかって。その気づきが、わたし自身の気持ちを少しやわらかくしてくれて、子どもとの向き合い方もすこしずつ変わっていったように思います。

「無理に行かせない」スタンスが、大きな安心に
「今日はお休みでもいいよ」「話してくれてありがとう」。そんなシンプルな言葉が、子どもにとってどれほど安心につながるか、実感として感じています。“行けないこと”を責めるのではなく、“いまここにいるあなた”を受けとめること。それだけで、子どもの心の奥に「大丈夫なんだ」というあたたかい灯がともるんですよね。
先日、てつなぎの掲示板で、こんな投稿を目にしました。
「私も中学生の頃に2週間ほど学校に行かないときがあったな、と思い出した。 一度もなんで?と聞いてこなかった母親。今思えば、すごいなー。でも当人として、とてもありがたかったな。と思う。」
(出典:てつなぎ「#不登校の子をもつ親として」)
きっとそのお母さんも、内心は心配でたまらなかったと思うんです。それでも、「問い詰める」より「見守る」を選んだ。その姿勢が、子どもにとっては何よりの安心につながった。その話に、私も背中をそっと押されるような気持ちになりました。
学校や専門機関とつながることも選択肢のひとつ
不登校のサポートは、家庭の中だけで抱え込まなくていいんです。担任の先生やスクールカウンセラー、教育相談センター、フリースクールなど、頼れる人や場所は、実は思っている以上にたくさんあります。
私も以前、市の教育相談センターに電話をかけたことがありました。「こんなことで相談していいのかな」「ちゃんと話せるかな」と不安だったのですが、職員の方がとても丁寧に耳を傾けてくださって。支援の選択肢を一つひとつ教えてもらったとき、「自分たちにも選べる道があるんだ」と思えたんです。その感覚は、親の私だけでなく、子どもにとっても、見えない安心感につながっていた気がします。
外の支援につながることは、「特別なこと」ではありません。「ちょっと今より楽になれるかもしれない道を探してみよう」くらいの気持ちで、できるところから踏み出してみてください。
親自身も相談先を活用し、ストレスを軽減
子どもを思う気持ちが強いからこそ、親はつい自分を追い込んでしまうことがありますよね。私自身も、子どもが学校に行けなくなった当初、「私のせいかも…」と自分を責めてしまう日々がありました。
東京学芸大学の研究でも、不登校の子どもをもつ母親が「地域や学校から孤立している」と感じやすい傾向があると報告されています(出典:東京学芸大学 紀要〈教育実践研究〉第19号「不登校児童生徒の母親の支援方法の検討」)。
だからこそ、親が「自分を支えてもらえる場所」を持つことはとても大切なんです。「話を聞いてもらっただけで、気持ちがふっと軽くなった」「うちはうちでいいって思えた」と、そんな体験が、私にも何度もありました。
こんな声にも、思わず胸がきゅっとなりました。
「子どもの将来のことを考えたら、不安しか生まれない。『たくさん褒めて』『前向きに』なんて、正直もう無理ゲーだって思う。」(出典:てつなぎ「不登校を解決するのは親次第という偉い人多いけど」)
きっと、この声に「それ、すごくわかる」と感じる方も多いのではないでしょうか。
完璧じゃなくていい。うまくいかない日があっても大丈夫。「いま目の前にいるこの子と、どう向き合うか」それを一緒に考えていけたら、きっと十分なんだと思います。
まとめ:小学生の不登校と向き合うために
不登校は、いまや決して“特別なこと”ではありません。それはもしかしたら、子どもが「自分の心を守るために出した精いっぱいのサイン」なのかもしれないと、そう思えるだけで、見える景色が少し変わってくるように感じます。
だからこそ、そばにいる私たちにできることは、焦らず、比べず、「いま、この子にとって何が大切なんだろう?」と、一緒に考えていくこと。
大丈夫。子どもは、ちゃんと前に進んでいます。歩幅はゆっくりかもしれないけれど、確かに、少しずつでも前に向かっています。
🌱もっと知りたい方へ
「うちの子に合う学び方って、何だろう?」そんなヒントを探している方には、不登校専門のオンラインプロ家庭教師・植木先生へのインタビューもおすすめです。
家庭での関わり方、学習の進め方、親の心の整え方まで、迷いや不安に寄り添いながら、やさしく背中を押してくれるアドバイスが詰まっています。
てつなぎ編集部
※当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね