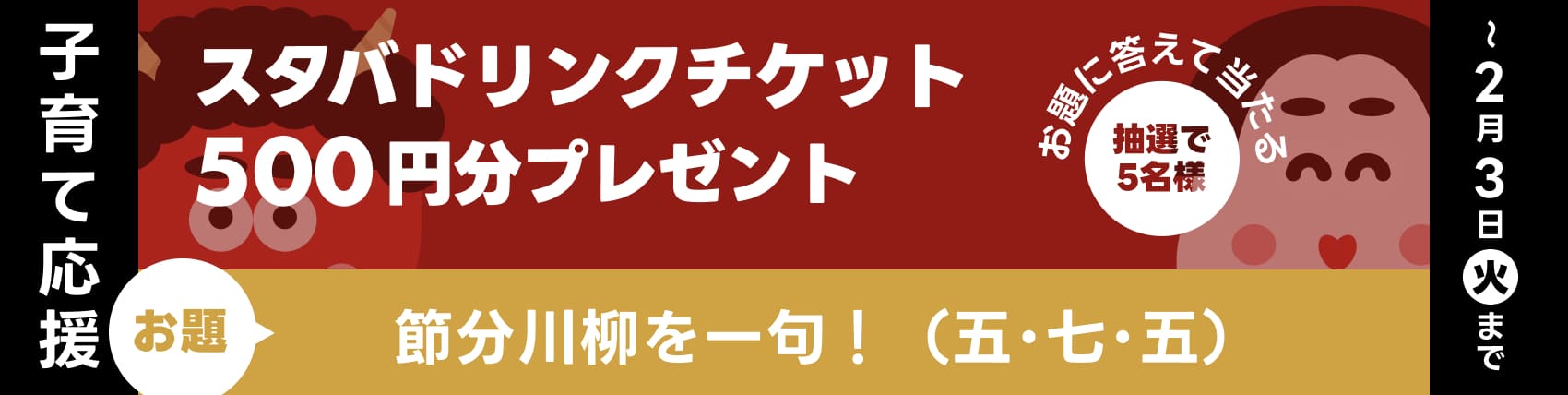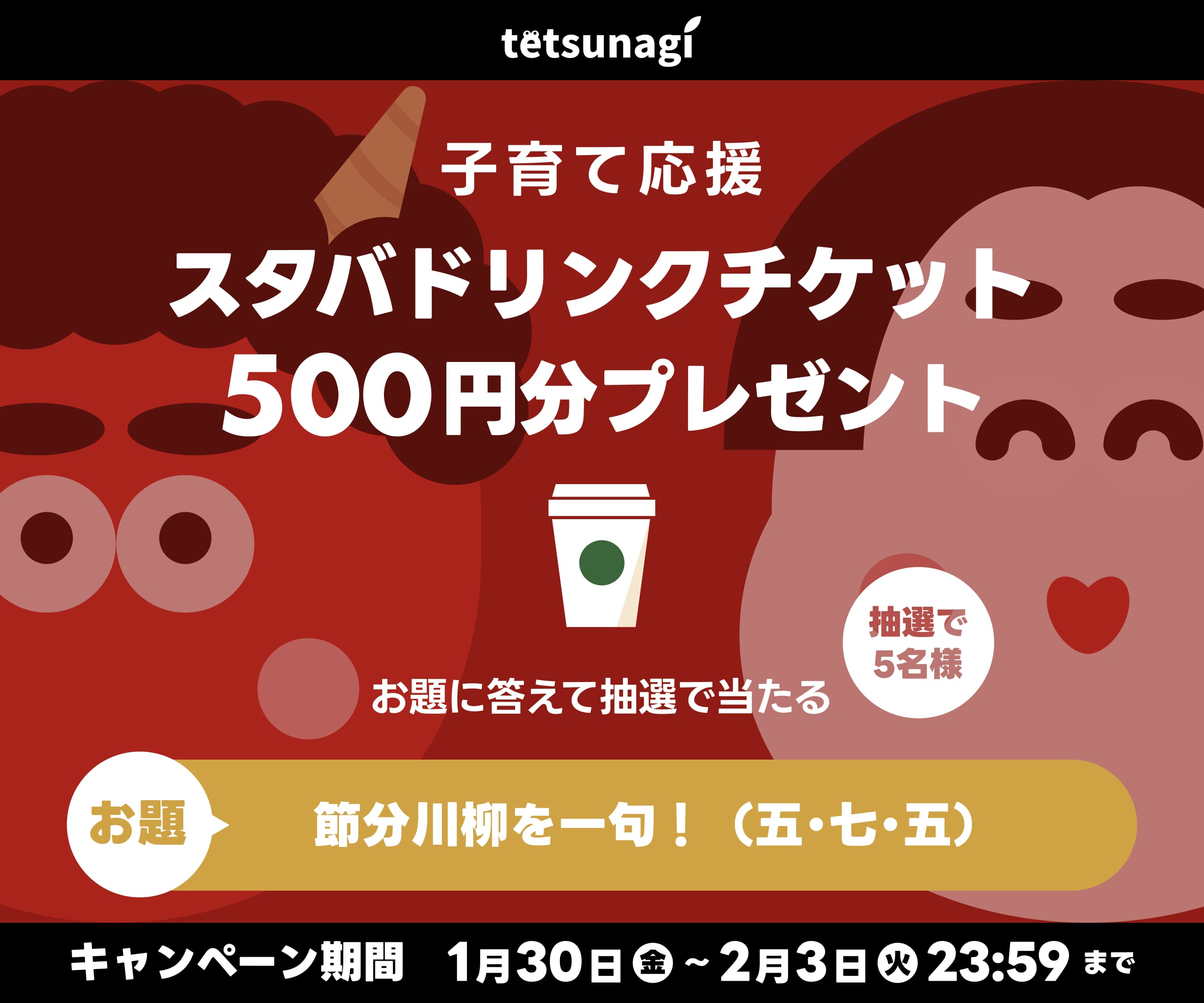「イヤイヤ期がつらい…」原因と乗り切り方を徹底解説|いつからいつまで?対処法・対応のコツ(第1回)
子どもが「イヤ」という理由と心理とは?イヤイヤ期との向き合い方
しつけ/育児

「イヤイヤ期がつらい…」原因と乗り切り方を徹底解説|いつからいつまで?対処法・対応のコツ(第1回)
こんにちは、多様な教育ナビゲーター・あずみのこです。15年以上子育て支援に携わり、2人の小中学生を育てる現役共働きママの視点から、コラムをお届けしています。
私自身「今日もまたイライラしちゃった…」なんて落ち込むことはしょっちゅうで、 特に子どもが小さかったころのイヤイヤ期は本当に大変でした。スーパーで泣き止まなくて、しまいには店内で地べたに座り込んで大泣き。通りがかりの人には迷惑そうに見られて、舌打ちされたことも...(涙)。
イヤイヤ期は、子育て経験者なら誰もが通る道と言われるほど、多くの家庭で悩みの種になるもの。子どもがちょっとしたことで「イヤ!」と泣き叫ぶ姿に、どう対応したらいいのか戸惑うのは自然なことだと思います。
でも、実はイヤイヤ期は子どもにとって自我の成長を示す大切なステップ。親にとってはつらい時期でも、正しい理解と対処法を知れば、肩の荷がだいぶ軽くなるはずです。
今回のコラムでは2回に分けて、そんなイヤイヤ期の時期や心理的背景、やりがちなNG対応とラクになるOK対応、日常のシーン別工夫や周囲とのかかわり方まで、専門的なデータや保護者の声も交えながら幅広くまとめました。家庭や状況に合わせて取り入れながら、子どもの成長を見守り、一緒にこの時期をのりこえていきましょう。
そして最後に…私も同じように悩んできた仲間のひとりです。このコラムが「ちょっと気持ちがラクになったかも」と思えるきっかけになればうれしいです。
イヤイヤ期とは?いつからいつまで?年齢と特徴をまず知ろう
イヤイヤ期は、一般的に1歳半〜3歳ごろに多く見られる行動の特徴を指します。特に2歳前後はピークになりやすく、「魔の2歳児」と呼ばれることもありますよね。
発達心理学者エリクソンの発達段階理論では、この時期は「自律性 vs 恥・疑惑」というステージにあたるとされています【※1】。つまり「自分でやりたい!」という気持ちが芽生える一方で、まだうまくできずに不安や恥ずかしさを感じやすい時期なんです。
たとえば、靴を履かせようとしたときに「イヤ!」と大泣きで拒否されるシーン。親としては「急いでるのに〜」と焦りますが、これも「自分でやりたかったのに、できなくて悔しい」という気持ちの表れなんですね。
毎日のように「イヤ!」が続くと親にとっては本当に大変ですが、この自己主張こそが子どもが健全に成長している証。「うちだけ?...」と思ってしまうかもしれませんが、同じように悩んでいる家庭はとても多いんです。
講談社コクリコラボのアンケート(2025年)では、8割以上のパパ・ママが「イヤイヤ期で悩んだり困ったりした」と回答しています【※2】。数字で見ても「みんな同じように悩んでいるんだな」と分かると、少しホッとしませんか?(てつなぎ掲示板 | イヤイヤ期の関連投稿を読む)

子どもが「イヤ!」と言う理由と心理
イヤイヤ期に直面すると、「どうしてこんなに反抗ばかり...?」と不安で仕方なくなる時もありますよね。
でも実は、この「イヤ!」には子どもなりの「深い理由」があるんです。心理学や発達の視点から見ていくと、その行動の意味が少しずつ見えてきます。

自我の芽生えと自己主張
一番大きな理由は、自我の芽生えです。これまで親に委ねていたことも「自分でやりたい」という気持ちが生まれ、その強い欲求を言葉や態度で表すのが「イヤ!」という反応なんですね。
たとえば、ズボンをはかせようとしたときに大泣きして拒否するのは、「自分でやりたかったのに!」という思いの裏返し。うまくいかないことも多いですが、この試行錯誤こそが成長の大事な土台になります。
言葉の表現力不足によるフラストレーション
イヤイヤ期の子どもは、自分の気持ちをまだうまく言葉にできません。大人なら「それは嫌だ」「これが欲しい」とはっきり伝えられることも、2歳前後の子には難しいんですよね。
「違う色がよかったのに」とか「まだ遊びたいのに」といった複雑な気持ちを、言葉で伝えられずに爆発させてしまう。それが「イヤ!」のひと言に込められています。
親としては「また始まった…」とため息をつきたくなる瞬間ですが、その背景には“伝えられないもどかしさ”が隠れているんだと思うと、少しだけ受け止めやすくなるかもしれません。
そんなときは、こちらが代わりにこうしたかったんだよね」と気持ちを言葉にしてあげたり、「赤と青、どっちにする?」と選択肢を用意してあげるのが効果的です。ちょっとした工夫で子どもも気持ちを整理しやすくなり、イヤイヤの嵐が少し和らぐこともありますので、ぜひ試してみてくださいね。
脳の未発達からくる感情コントロールの難しさ
イヤイヤ期の大きな特徴のひとつは、「感情の爆発を自分で止められない」ということ。
脳の中でも気持ちをコントロールする役割をもつ前頭前野は、まだ小さな子どもには十分に発達していません。そのため、ほんのちょっとした不満や不安が、大泣きや癇癪として一気にあふれ出てしまうんです【※3】。
「どうしてこんなに泣くの?」と戸惑うかもしれませんが、それは決してワガママではなく“脳の成長途中の姿”。「まだうまく抑えられないんだな」と少し見方を変えるだけで、子どもの姿が違って見えて、親の気持ちも少しラクになるかもしれません。
子どもの気質による違い
また、同じイヤイヤ期でも、「全然手がかからなかった子」もいれば「とにかく手がかかる毎日だった」という子もいますよね。心理学の研究(トーマスとチェス, 1977)では、子どもの気質を「扱いやすい子」「難しい子」「ゆっくり適応する子」に分けて説明しています【※4】。つまり、イヤイヤの強さや出方には“その子ならではの特徴”が大きく関わっているのです。
だから、「あの子は平気なのに、うちの子は…」と比べなくても大丈夫。子どもによって違って当たり前。親もその子に合ったかかわり方を少しずつ見つけていけばいいんです。
やりがちなNG対処法とそのリスク
イヤイヤ期に向き合っていると、「いいかげんにして!」とつい感情的に叱ってしまうこともありますよね。私もあとで「言いすぎたな…」と落ち込んだことが何度もあります。
でも、大声で押さえつけるような対応が続くと、子どもは「気持ちを分かってもらえない」と感じて、反発が強まったり、萎縮して自己表現しにくくなるリスクがあります。
一方で、泣かれるのがつらくて何でも要求を聞き入れてしまうのも要注意。「泣けば思い通りになる」と覚えてしまうと、さらに要求が強まることがあります。
また、突き放すように無関心でいると、子どもは「大事にされていないのかな」と不安を抱いてしまうことも。
結局のところ大切なのは、叱りすぎない・甘やかしすぎない・突き放さないというバランス。それが難しくて、みんな悩んでるんですけどね...(苦笑)。完璧じゃなくても大丈夫なので、少し意識しながらぼちぼちやっていきましょう。
つらい気持ちを軽減するOK対処法
イヤイヤ期に向き合っていると、「どうしたらいいの?」と親のほうが参ってしまうこともありますよね。そんなときに助けになるのが、子どもの気持ちを受け止めながら、親も少しラクになれる工夫です。
大切なのは、子どもの感情を頭ごなしに否定せず、「そっか、嫌なんだね」とまずは気持ちに寄り添うこと。そして、親自身もストレスを抱え込みすぎないように工夫することです。
パートナーや祖父母、保育園など外の力を頼るのも全然OK。むしろそうやって息抜きができたほうが、親の心に余裕が生まれて、不思議と子どもの「イヤ!」にもあたたかく対応できるようになるんですよね。
ここからは、イヤイヤ期に特に効果的とされる対処法を2つご紹介します。

まずは共感し、気持ちを受け止める
子どもが泣き叫んで止まらないときは、本当にしんどくなりますよね。思わず「いい加減にして!」と怒鳴りたくなる気持ちもわかります…。でも、そこでまずひと呼吸。
「そうだね、嫌なんだよね」「まだ遊びたいんだよね」と、気持ちを言葉にしてあげるだけで、子どもは「わかってもらえた」と安心します。
要求をそのまま叶えられなくても、「共感のひと言」があるだけで子どもの気持ちは少し和らぎやすくなります。私も「ひとこと共感してから伝える」と意識するようになってから、子どもが落ち着くのが早くなった気がします。
忙しいときほど難しいけれど、ちょっと意識するだけで、「わかってもらえた」と子どもが安心して、次の行動に移りやすくなることもあります。できそうなときに、ぜひ試してみてくださいね。
状況を変える・切り替えのコツを身につける
イヤイヤが長引いてしまうときは、その場の空気をちょっと変えてみるのも有効です。 「ちょっと散歩いこっか」「深呼吸してからもう一回ね」といった小さな工夫で、気持ちの切り替えがしやすくなったりします。
また、選択肢を与えるのも効果的です。 「赤と青、どっちの靴にする?」 「お風呂に入るのと歯みがき、どっちを先にする?」
こんなふうに2択で聞くと、子どもは「自分で選べた」と満足感を得られて、イヤイヤがやわらぐことも多いんです。
多様な教育ナビゲーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね