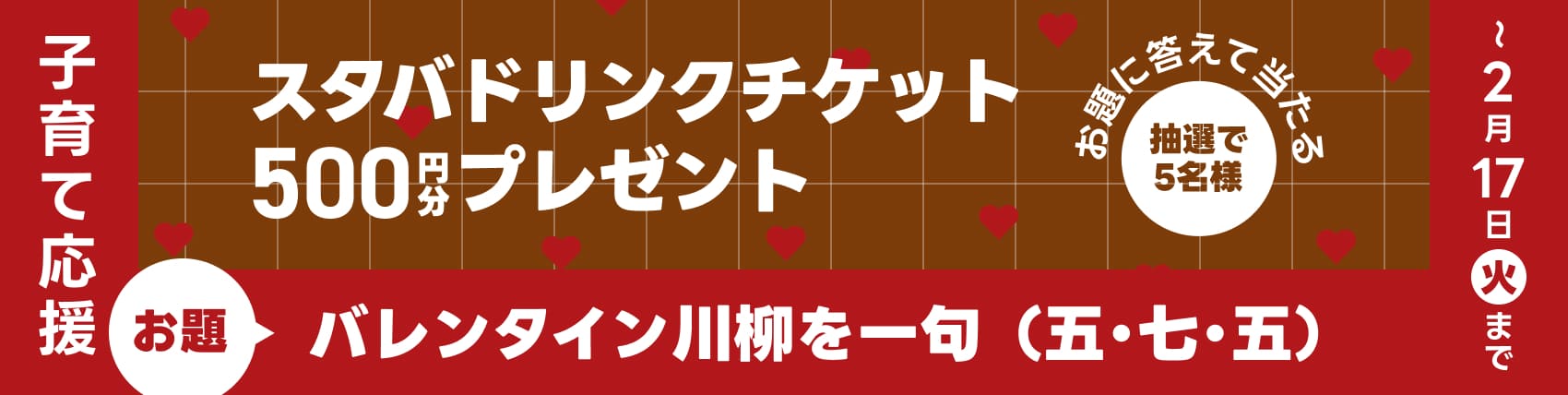【第1回】小学生の不登校とは?増加する背景とその実情
焦らず、比べず、「いま、この子にとって何が大切なんだろう?」と、一緒に考えていくこと。
学校
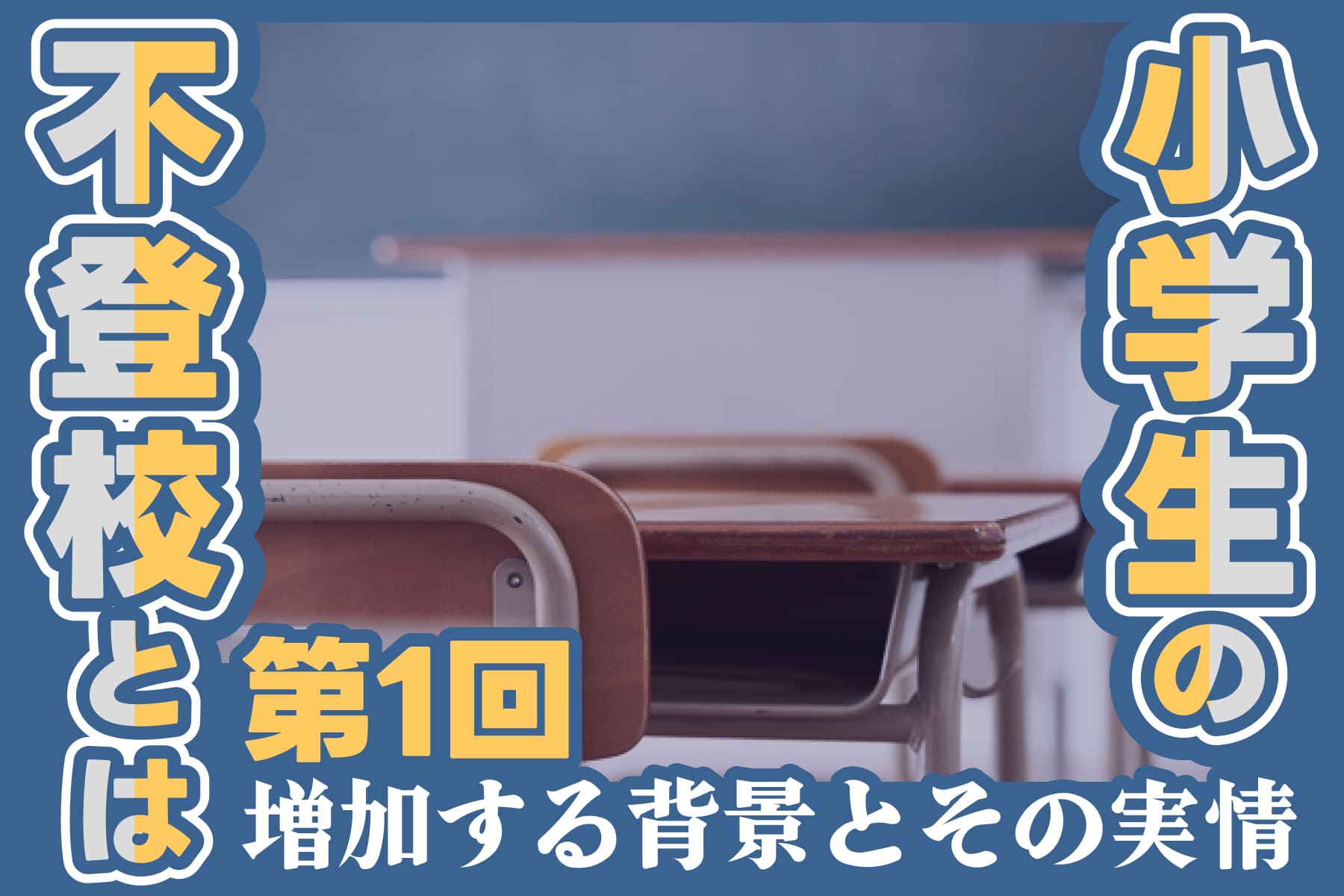
【第1回】小学生の不登校とは?増加する背景とその実情
こんにちは、あずみのこです。
ある日突然、子どもに「学校、行きたくない」と言われたらどうしよう? そんなふうに思ったこと、ありませんか?
実は私の息子も、小1のときに学校に行きしぶった時期がありました。最初は「ここで休ませたら、ずっと行けなくなるんじゃないか」と焦り、無理に登校させようとしてしまったことも。でも、そんな私に向けて息子が放ったひとこと。
「もうママには、何も話さない」
あのときの言葉が、今でもずっと心に残っています。
本コラムでは「小学生の不登校」を取り上げました。年々増加する不登校の背景とは?不登校の実情とは?(全2回の第1回)。
「不登校」という言葉でひとくくりにされがちですが、 実際には、保健室登校や別室登校、行ける日と行けない日が混在している行き渋りの子、理由が自分でもうまく言えない子など、一人ひとりにまったく違う背景や思いがあります。そして、そうした子どもたちの姿は、ようやく少しずつ“数字”にも表れはじめています。
私はこれまで、100人以上の保護者と向き合うなかで、不登校の子どもたちやその家庭の声をたくさん聞いてきました。その中で強く感じたのは、「学校に戻ること」をゴールにするのではなく、「安心して休める場所があること」「その子なりのペースで、自己肯定感や社会性を育んでいけること」。そのほうが、ずっと大切な支えになるという実感でした。
このコラムでは、不登校の小学生をめぐる現状や背景、学年別の傾向、そして家庭でできることについて、私自身の経験も交えながらお話ししていきます。もし今、「このままで大丈夫かな」と不安な気持ちを抱えていたとしたら、それは、ちゃんと子どものことを見つめている証です。
どうかここに綴ったことが、あなたの気持ちをすこしだけでもやわらかくしてくれますように。そして、「きっと大丈夫」って思える、小さなきっかけになれたら、それだけで何よりうれしいです。
不登校の小学生の人数・最新データ
文部科学省が2024年10月に公表した最新の調査(出典:「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」文部科学省)によると、2023年度の不登校の児童生徒数は全国でなんと41万5,844人。小・中・高校を合わせて、過去最多となりました。なかでも、小学生の不登校は13万人を超え、11年連続で増加。この現実に、胸がギュッと締めつけられるような思いがします。決して特別な家庭だけの問題ではなく、誰にとっても起こりうる、身近な課題なのだと感じています。
「こんなにたくさんいるの!?」と驚かれた方もいるかもしれません。でもこれは、これまで見えづらかった子どもたちの声が、ようやく届きはじめている証でもあるのかな、と私は感じています。
そして、こうした“数字に表れる子どもたち”だけでなく、行き渋りの子、保健室登校や別室登校をしている子もいます。毎日しんどさを抱えながら、なんとか学校に足を運んでいる子どもたちもたくさんいるんですよね。
「完全に不登校」ではないけれど、「毎日がつらい」。そんな子どもたちの存在にも、私たちはもっと耳を澄ませていく必要があると思っています。

文部科学省の調査からわかる増加傾向
ちなみに、小学生の不登校がここ数年でどれくらい増えているかご存じでしょうか?
文部科学省のデータによると、2013年度には約2万5千人だった不登校児童が、2023年度には13万人超(130,370人)にまで増えているんです。この10年で約5倍です。それだけ、たくさんの子どもたちが「学校に行くのがつらい」と感じているということなんですよね。
背景には、友達関係や勉強のつまずきだけじゃなく、日々の小さな不安やプレッシャー、そして「学校がしんどいな」と感じる気持ちが積み重なっていることが多いようです。
とくにここ数年は、コロナ禍による長期休校やオンライン授業の影響もあり、「学校って毎日行かなきゃいけないの?」と、子どもたち自身が“立ち止まって考える”機会が増えたようにも感じます。
わたしたち大人も、「行くことが当たり前」だった時代から少しずつ価値観を見直していく必要があるのかもしれません。「行けない」ことの背景に、どんな思いがあるのか。まずはそこに、そっと耳を澄ませていきたいですね。
不登校の定義と意外に幅広い基準
「じゃあ、不登校って具体的にどういう状態を指すの?」そんなふうに思われた方もいるかもしれません。ここで少しだけ、文部科学省の定義についても触れておきたいと思います。
文部科学省では、不登校を「病気や経済的な理由を除いて、年間30日以上学校を欠席している児童生徒」と定義しています(出典:文部科学省「不登校の現状に関する認識」)。ただ、実際の子どもたちの様子を見ていると、この「30日」という数字だけでは見えてこない現実がたくさんあるな、と感じます。
教室に入るのがつらくて保健室や別室で過ごしている子。週に1〜2回だけ登校する子、毎日連続登校が難しい子。中には、フリースクールやオンライン学習を利用して、在籍校で「出席扱い」となっている子もいます(出典:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日)。このように、制度上は「登校」とカウントされていて30日未満の欠席でも、すでに学校への不安が強くなっていたり、登校しぶりが続いていたりすることもあるんですね。だからこそ、「あと何日休んだら不登校?」ではなくて、「この子はいま、どんな思いで学校と向き合っているのか」に目を向けることも、とても大事なんじゃないかなと思います。
このように、制度上は「登校」とカウントされていて30日未満の欠席でも、すでに学校への不安が強くなっていたり、登校しぶりが続いていたりすることもあるんですね。だからこそ、「あと何日休んだら不登校?」ではなくて、「この子はいま、どんな思いで学校と向き合っているのか」に目を向けることも、とても大事なんじゃないかなと思います。
不登校を招く小学生の主な原因
ここまで、不登校の定義や増加傾向について見てきました。では実際に、子どもが「学校に行きたくない」と感じるとき、その背景にはどんな思いや理由があるのでしょうか?
もちろん、理由は一人ひとり違います。いじめや友だち関係の悩み、勉強への不安、家庭の変化やストレス…。ひとつの原因だけではなく、いくつもの小さな“しんどさ”が積み重なっていることも少なくありません。中には、自分でもうまく理由がわからないまま、「とにかくしんどい」「うまくいかない」と感じている子もいます。
だからこそ、「これは不登校になるほどのことじゃない」と決めつけるのではなく、「そう感じてるんだね」と、まずはまるごと受け止めてみること。それが、子どもにとっての“安心のはじまり”になるのだと思います。
ここからは、不登校の原因としてよく見られるいくつかのケースを、ご紹介していきますね。

いじめ・人間関係のつまずきや、先生との相性
小学生の不登校では、いじめや友達とのトラブル、先生との相性など、人間関係の悩みがきっかけになることも少なくありません。文部科学省がまとめた報告書でも、不登校の主な要因として「友人関係」や「教職員との関係」が挙げられています(出典:文部科学省『不登校に関する調査研究協力者会議 報告書』令和4年6月)。
てつなぎが運営するコラムにも、こんなエピソードがありました。「4月から小学生になった息子ですが、学校には数日しか行ってません。幼稚園の年少組のときまでは毎日楽しく登園していたけど、年中になって急に登園しぶりをし始めました。理由を聞くと、友達がイヤではなくて担任の先生がイヤだと言います。」(出典:てつなぎ公式note『子どもが不登校になった時』)
私の息子も、小学1年生のころ、「Aちゃんにイヤなこと言われる。だから学校行きたくない」と、泣き出したことがありました。でもそのとき、私はつい「そんなのよくあることだよ」「自分も何か言っちゃったんじゃないの?」なんて、軽く返してしまったんです。あとになって「あれは、勇気を出して話してくれた“心のSOS”だったんだ」と気づいたとき、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
大人から見ると「そんなことで?」と思えるような出来事でも、子どもにとっては、とても大きなストレスになっていることがあります。だからこそ、そんなときこそ、正論よりもまず、「つらかったね」「話してくれてありがとう」と声をかけること。そのひとことが、子どもにとって「ここにいても大丈夫なんだ」と思える、安心の土台になるのだと、私自身の体験からも強く感じています。
学習面のつまずきや学習障害
「授業についていけない」「漢字がどうしても覚えられない」「算数の時間が近づくと、お腹が痛くなる」──。そんな“できない”の積み重ねが、子どもにとって学校を「つらい場所」にしてしまうこともあります。
文部科学省の調査でも、不登校の背景には「学業不振」や「学習意欲の欠如」といった要因があるとされています(出典:「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」文部科学省)。また、日本小児精神神経学会の学術誌でも、「学習面での困難」や「認知特性の違い」が、不登校と関係しているケースがあると報告されています(出典:一般社団法人日本小児精神神経学会『小児の精神と神経』)。
とくに、「学習障害(LD)」と呼ばれる状態については、まだあまり知られていないかもしれません。これは、知的な発達に大きな遅れはないにもかかわらず、「読む・書く・計算する」などの特定の分野にだけ、著しい困難があらわれる状態を指します。
たとえば、「音読になると急に口ごもる」「何度書いても漢字が覚えられない」「簡単な計算でも数字がぐちゃぐちゃになってしまう」といったことが、日常の中で起きてきます。そうした姿だけを見ていると、「努力が足りないんじゃない?」「やる気の問題かも」と思ってしまうこともあるかもしれません。
でも本当は、“がんばっていない”わけじゃないんですよね。むしろ、誰よりもがんばっていて、それでもうまくいかなくて、悔しくて、恥ずかしくて…。そんな気持ちを、誰にも言えずに、ひとりで抱えている子も、きっとたくさんいます。
文部科学省の調査では、通常学級に在籍する児童生徒のうち約4.5%が学習障害(LD)の可能性があるとされています(出典:文部科学省「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒に関する実態調査(平成24年)」)。つまり、クラスに1〜2人は、目に見えない学びづらさを抱えているかもしれないということです。
そして「学習障害(LD)」は、脳の情報処理のしかたにその子なりの特性があることによって起こるものであり、文部科学省の報告でも「家庭環境や本人の努力が直接の原因ではない」ことも明記されています(出典:文部科学省「学習障害児に対する指導について(報告)」1999年)。
だからこそ、「この子は、どこで、なにに困っているのかな?」と、“できない”の奥にある苦しさや、助けを求める小さなサインに目を向けていくこと。それが、子どもにとっての「わかってくれる大人がいる」という安心につながり、子どもがまた一歩、前に進もうとする力になるのだと思います。
家庭環境と母子分離不安 ――「行きたくない」に隠れたサイン
「ママと離れるのが不安」「学校がこわい」——。そんなふうに感じる子は、けっして珍しくありません。とくに低学年や幼児期の子どもたちは、親とのつながりを“安心のよりどころ”にしていることが多く、ほんのちょっとした変化にも敏感に反応します。
でもそれは、「甘えすぎ」でも「過保護」でもありません。それだけ、子どもが親とのつながりを大切にしながら育ってきた証でもあるのだと思います。
たとえば、生活リズムが少し変わったり、保護者の仕事が忙しくなったり。どの家庭にも起こりうる“ちょっとした変化”が、子どもにとっては「なんとなく落ち着かない」「これまでと違う」という不安につながっていることもあるんですよね。
「もうそろそろ大丈夫でしょ?」つい、そんなふうに言いたくなってしまうこともあるかもしれません。私も、何度もありました。でも、そんなときこそ「まだ不安があるんだね」「大丈夫だよ、ここにいていいよ」と伝えてあげること。そのひとことが、子どもにとっての「安心のよりどころ」になります。“そのままの自分でいられる場所”があること。それは、子どもが自分のペースで、また一歩ふみ出していくための、大切な土台になるのだと思います。
発達障害や病気の可能性
「朝になると体調が悪くなる」「教室にいるのがつらい」——。そんな子どもの言葉に、最初は戸惑ってしまうかもしれませんよね。私も、わが子の「なんかムリ…」という小さなつぶやきを、最初はどう受け止めていいかわからなかったことがあります。でも、あとから振り返ってみると、その背景には“感覚のつらさ”や“身体のしんどさ”が隠れていたのかもしれない、と感じるようになりました。
たとえば、自閉スペクトラム症(ASD)などの発達特性がある子どもは、音や光、人の気配などにとても敏感に反応することがあります。実際に、発達特性のある子どもの60〜90%が感覚過敏を抱えているとも言われていて、にぎやかな教室のざわめきがどうしても耐えられないという声も聞きます(出典:国立障害者リハビリテーションセンター研究所「発達障害者の感覚の問題 」)。
また、「朝起きられない」「学校に行こうとすると頭が痛くなる」といった症状が続く場合には、「起立性調節障害(OD)」という身体の不調が関係していることもあります。これは自律神経の働きの乱れによって、朝に体が動きづらくなったり、立ちくらみや倦怠感が出る医学的な状態で、不登校の子どもの30〜40%が併発しているという調査もあります(出典:日本小児心身医学会「起立性調節障害」)。
「ただの甘えじゃないの?」「サボりたいだけなんじゃ…」と感じてしまうこともあるかもしれません。でも、もしそう思ったときは、すこしだけ視点を変えて、「もしかしたら、体や感覚がつらいのかもしれない」と考えてみる。それが、子どもにとっての「わかってもらえた」という安心につながる第一歩になるのだと思います。小さな声にならないSOSに、そっと耳を澄ませていけたらいいですね。
学校に行く意味を感じられない
「学校って行く意味あるの?」「行っても楽しくない」——。そんなふうに子どもに言われると、親としてはドキッとしてしまいますよね。わざわざ説明するのも面倒で、「そんなこと言わないで」「学校は行くものなの!」と、つい返してしまいそうになる。私にも、そんな瞬間がありました。
でも、よくよく考えてみると、「なんのために学校に行くの?」「勉強って意味あるの?」という問いは、実はとても自然なものなんですよね。子どもたちが、自分なりに感じて、考えているからこそ、そんな疑問が生まれてくるのかもしれません。
とくに、日々の学校生活のなかで、「なんだか居場所がないな」「わたし、いてもいなくてもいいのかな」と、そんなふうに感じる経験が重なっていくと、「行く意味がわからない」と思うのも、当然なのかもしれません。
私自身も、以前子どもに「なんで学校に行かなきゃいけないの?」と真顔で聞かれたことがありました。頭のなかでは、「社会で生きていくために必要だから」とか「義務教育だから」といった言葉がいくつか浮かんできたけれど、そのとき、うまく言葉にできなくて。
今思えば、正論を並べるよりも、「そう思うくらい、いましんどいんだね」と、そんなふうに気持ちを受けとめてあげることが、いちばん大切だったんじゃないかなと思います。「行く意味がわからない」と感じている子どもの声に、「でも行くべきだよ」と返すのではなく、「どんなふうに感じてるの?」と、ゆっくり耳を傾けてみること。
それだけで、子どもは「ちゃんと見てくれる人がいる」「わかろうとしてくれる人がいる」と感じられて、心の中にぽっと明かりが灯るような安心を得られるのだと思います。「わかってもらえた」「ひとりじゃない」——。そんな感覚が、子どもにとっての“安心の土台”になり、「もう一度やってみようかな」という小さな気持ちにつながっていくのだと思います。
てつなぎ編集部
※当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね