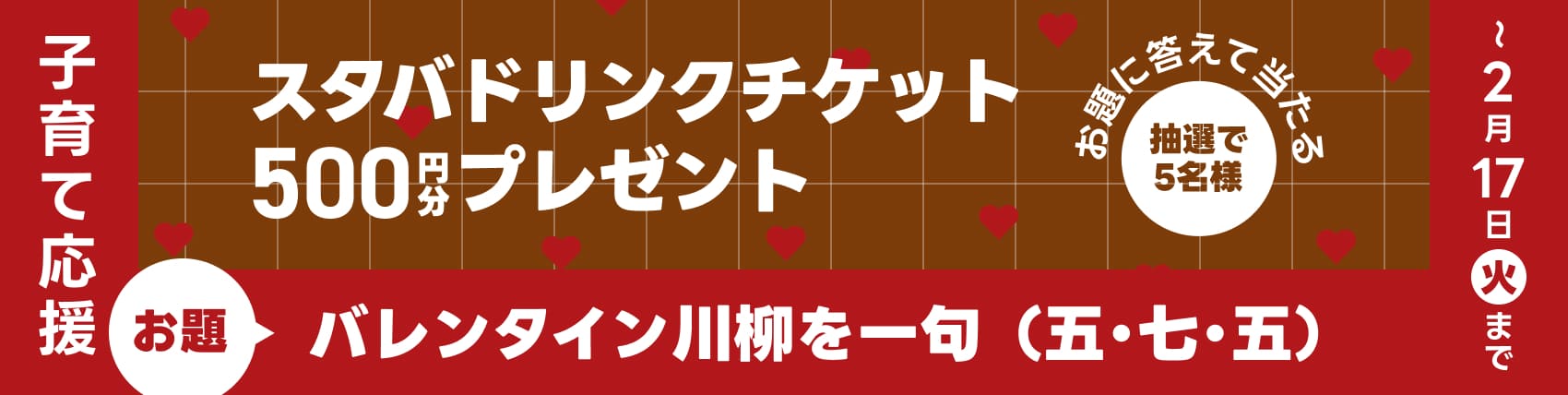【インタビュー】思春期の不登校に悩める親御さんへ伝えたいこと
思春期の不登校専門家、野々はなこ先生へインタビュー!思春期の不登校の子の親御さんへ伝えたいこと。
インタビュー
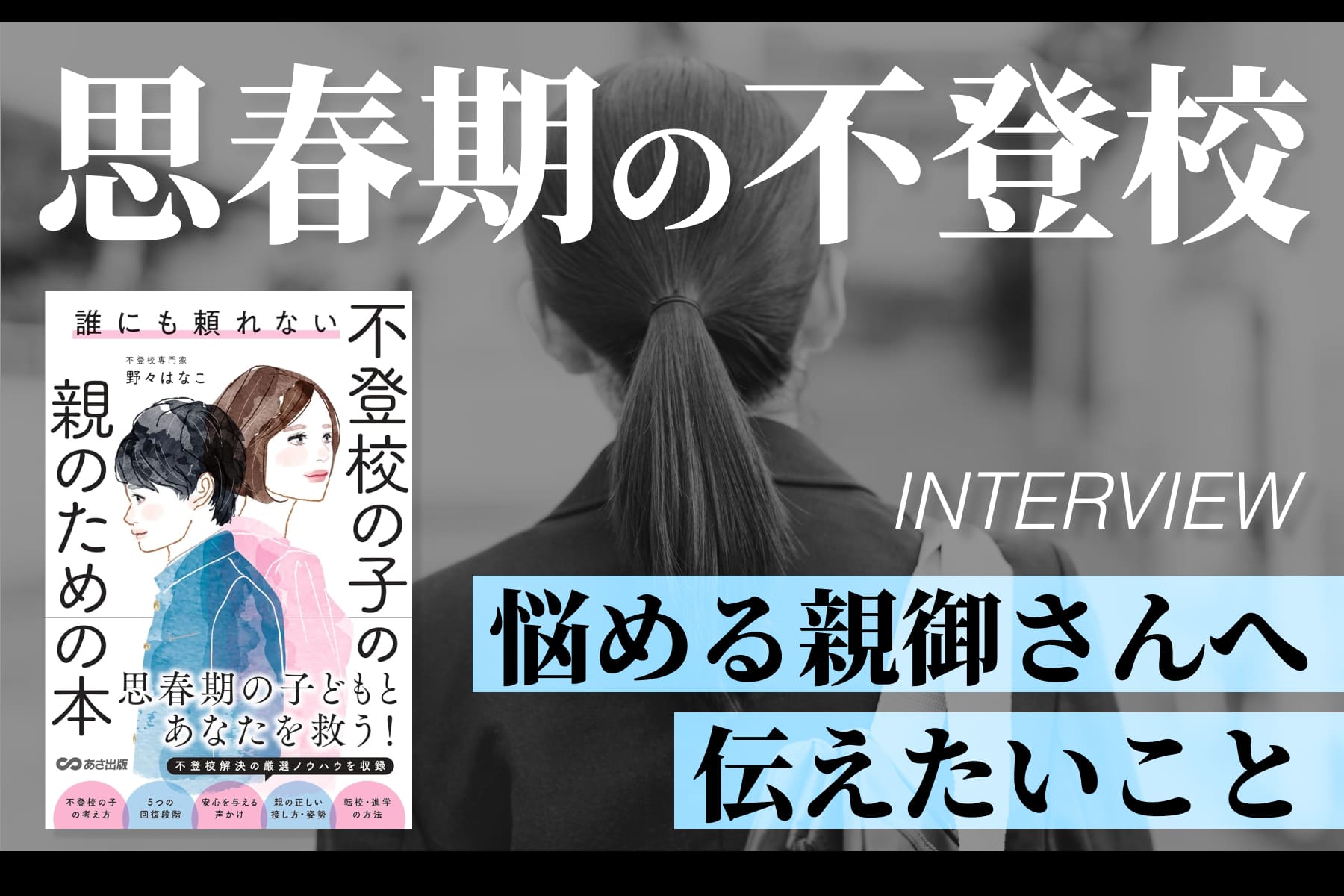
【インタビュー】思春期の不登校に悩める親御さんへ伝えたいこと
てつなぎ編集部
本日は思春期の不登校専門家 野々はなこ 先生にお越しいただきました。野々先生は大学を卒業後、高校教師を務めて30年以上。担任、保健室担当、特別支援教育コーディネーターとして不登校、発達障害やメンタル不全の生徒たちと長年関わってこられたご経歴があります。今回のインタビューでは2025年2月に出版された『誰にも頼れない 不登校の子の親のための本』(あさ出版)についてお話をお聞かせいただこうと思います。
まず最初にですが、『誰にも頼れない 不登校の子の親のための本』を執筆された背景をお聞きしてもよろしいでしょうか。
まず最初にですが、『誰にも頼れない 不登校の子の親のための本』を執筆された背景をお聞きしてもよろしいでしょうか。
リンク
野々先生
改めましてよろしくお願いいたします。
本書執筆のきっかけですね。まず最初に、10年以上前の話になりますが、私の子どもが不登校になりました。当時は「まさか自分の子どもが不登校になるなんて...」と正直思いました。とにかく何かしらの解決策を見つけたくてインターネットで情報を探したり、関連書籍を探しに書店に足を運んだりとありとあらゆる手を尽くしましたが、出てくる情報のほとんどが「不登校小学生のお母さんの体験談」みたいなものばかりで、不登校を解決するための手だてのようなものではありませんでした。
どう解決すればいいのか途方に暮れましたし、子どもが不登校になったときにどうすればいいのかを解決できる情報が欲しいと純粋に思いました。
今でも当時の私のように不登校で悩んだ親御さんは多くいると思います。そんな親御さんがちょっと困ったときに読んでみると安心できる“家庭の医学”のような本があれば良いのでは....?と思ったことが本書執筆のきっかけになります。
本書執筆のきっかけですね。まず最初に、10年以上前の話になりますが、私の子どもが不登校になりました。当時は「まさか自分の子どもが不登校になるなんて...」と正直思いました。とにかく何かしらの解決策を見つけたくてインターネットで情報を探したり、関連書籍を探しに書店に足を運んだりとありとあらゆる手を尽くしましたが、出てくる情報のほとんどが「不登校小学生のお母さんの体験談」みたいなものばかりで、不登校を解決するための手だてのようなものではありませんでした。
どう解決すればいいのか途方に暮れましたし、子どもが不登校になったときにどうすればいいのかを解決できる情報が欲しいと純粋に思いました。
今でも当時の私のように不登校で悩んだ親御さんは多くいると思います。そんな親御さんがちょっと困ったときに読んでみると安心できる“家庭の医学”のような本があれば良いのでは....?と思ったことが本書執筆のきっかけになります。

てつなぎ編集部
野々先生の実体験から執筆に至っている本なんですね。
実際に先生のお子さんが不登校になったときに感じたことは何でしたか?
野々先生
最初は中学生の息子が不登校になりました。
まったく予備知識がない状態だったので、とりあえず登校させようと“泣き落とし”“力技”、“怒鳴る”など手段を選ばず接しました。その結果、どんどん関係が悪くなり、息子が家のモノを壊すなど暴れてしまい、私も泣き叫ぶといった修羅場のような状況になりました。
次は娘が高校生のときに不登校になったんですが息子のこともあったので寄り添う姿勢、娘の気持ちを尊重することを意識したものの、彼女は口を閉ざし、痩せていき、人の目が怖くなり外にも出れなくなってしまいました。何をどうしていいか全くわからない、まさに“見えない奈落に突き落とされた”そんな感覚でした。
まったく予備知識がない状態だったので、とりあえず登校させようと“泣き落とし”“力技”、“怒鳴る”など手段を選ばず接しました。その結果、どんどん関係が悪くなり、息子が家のモノを壊すなど暴れてしまい、私も泣き叫ぶといった修羅場のような状況になりました。
次は娘が高校生のときに不登校になったんですが息子のこともあったので寄り添う姿勢、娘の気持ちを尊重することを意識したものの、彼女は口を閉ざし、痩せていき、人の目が怖くなり外にも出れなくなってしまいました。何をどうしていいか全くわからない、まさに“見えない奈落に突き落とされた”そんな感覚でした。
てつなぎ編集部
壮絶な状況ですが、今まさにそのような状況で困っている親御さんもいらっしゃると思いますが、先生はどのようにして乗り越えたのでしょうか。
野々先生
子どもが不登校になってから心理学、脳科学や栄養学など色々なことを学びました。その中でウェルビーイング(Well-being)という考え方に出会い、親子ともに“自分を大切にする”“完璧でなくていい”と意識しながら実践することで徐々に良い方向へ変わって行きました。
【注釈】ウェルビーイングとは
・身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。
・多様な個人がそれぞれ幸せや生きがいを感じるとともに、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあることも含む包括的な概念。
出典:文部科学省【ウェルビーイングの向上について(次期教育振興基本計画における方向性)】
てつなぎ編集部
親子で「完璧でなくていい」と思えるようになったことで、心が少し軽くなりますね。
一方で、社会全体としてはまだ課題も多いように感じます。先生は、日本の不登校の現状をどのように思いますか?
一方で、社会全体としてはまだ課題も多いように感じます。先生は、日本の不登校の現状をどのように思いますか?

野々先生
昭和の時代は、根性論や精神論がまかり通り、『不登校』も“しゃあない”という雰囲気があった気がします。
今は子どもたちのメンタルが弱くなっている一方で、親も“みんなに合わせなければ”というプレッシャーが強くなっています。さらに、早期教育や競争、そしてスマートフォン普及による情報の過多に親子ともに翻弄され、「こんな自分じゃダメだ」と自分を否定する気持ちが強くなってしまっています。またコロナ禍の影響も非常に大きく感じます。対面でのコミュニケーションや接触経験が激減し、表情や温かさを感じる機会が極端に減ってしまった。こういった環境で育った子たちへのアプローチも課題だと思います。不登校増加の一因として、こうした社会構造や時代の影響を強く感じます。
今は子どもたちのメンタルが弱くなっている一方で、親も“みんなに合わせなければ”というプレッシャーが強くなっています。さらに、早期教育や競争、そしてスマートフォン普及による情報の過多に親子ともに翻弄され、「こんな自分じゃダメだ」と自分を否定する気持ちが強くなってしまっています。またコロナ禍の影響も非常に大きく感じます。対面でのコミュニケーションや接触経験が激減し、表情や温かさを感じる機会が極端に減ってしまった。こういった環境で育った子たちへのアプローチも課題だと思います。不登校増加の一因として、こうした社会構造や時代の影響を強く感じます。
てつなぎ編集部
コロナ禍を機に大きな変化があり、色々な課題が生まれたと思います。そうした時代背景と社会構造の変化の中で野々先生が今、力を入れている活動はありますか?
野々先生
私が今、力を入れているのは、“心を育てる教育”、ウェルビーイング教育を教育現場に導入することです。
日本は学力は高いですが、幸福度は残念なことにOECDで下位となっていて非認知能力や自己肯定感を育む機会が不足しています。勉強や点数も大事ですがそれだけじゃありません。人のことを大切にするとか、優しさ、例えばお花が大好きとか、色々な非認知能力があります。そういったアイデンティティや自己肯定感と言ったウェルビーイングに関することですが、“心の健康”、“体の健康”それから“社会との繋がり”友達がいるっていいことだね。でもみんなじゃなくていいんだよ。一人でもいいんだよ。そういった話を小学校のうちから教育として導入したいと思っています。
日本は学力は高いですが、幸福度は残念なことにOECDで下位となっていて非認知能力や自己肯定感を育む機会が不足しています。勉強や点数も大事ですがそれだけじゃありません。人のことを大切にするとか、優しさ、例えばお花が大好きとか、色々な非認知能力があります。そういったアイデンティティや自己肯定感と言ったウェルビーイングに関することですが、“心の健康”、“体の健康”それから“社会との繋がり”友達がいるっていいことだね。でもみんなじゃなくていいんだよ。一人でもいいんだよ。そういった話を小学校のうちから教育として導入したいと思っています。
てつなぎ編集部
先生の活動が広がりウェルビーイングの導入が実現することで、日本の幸福度も上げていきたいですね。今後、野々先生が特に力を入れていきたいことや目標とされていることなどお聞かせくださいませ。
野々先生
ゆくゆくはウェルビーイング教育を導入した通信制高校を運営したいと思っています。
色々な理由で通信高校を選んでいると思いますが、通信高校を選んだ理由が“人生で苦しい思いをした”とかの理由であれば、勉強のし直しではなく、人生の立て直しや人間力を磨く場にし自分を大切にすることを学べる場にしたいと思っています。
色々な理由で通信高校を選んでいると思いますが、通信高校を選んだ理由が“人生で苦しい思いをした”とかの理由であれば、勉強のし直しではなく、人生の立て直しや人間力を磨く場にし自分を大切にすることを学べる場にしたいと思っています。

てつなぎ編集部
自分を大切にすることを学べる場というのはとても素晴らしいですね。
最後にですが、読者の方、思春期のお子さんの不登校で悩まれている親御さんへのメッセージをお願いします。
最後にですが、読者の方、思春期のお子さんの不登校で悩まれている親御さんへのメッセージをお願いします。
野々先生
私自身もそうでしたが、子どもが不登校になると子どもの言動による喜びや不安、絶望で心が激しく揺れます。そんな日々を送っていると親自身のメンタルが危険な状態となってしまいます。それこそ、鬱のような症状がでてしまう人がいるくらいに。
だけど、お子さんは絶対によくなるんです。絶対に花を咲かせる時期が来ます。どんな花が咲くかは分かりませんが、どんな花だっていいんです。
バラの花もあればスミレの花もある、大きいものもあれば小さいものも、葉っぱみたいな子もいるかもしれません。色々なんです。でも種は絶対に芽を出します。だから信じて、どんな花を咲かすのかお子さんをゆっくり見て、未来を信じてほしいなと思います。
だけど、お子さんは絶対によくなるんです。絶対に花を咲かせる時期が来ます。どんな花が咲くかは分かりませんが、どんな花だっていいんです。
バラの花もあればスミレの花もある、大きいものもあれば小さいものも、葉っぱみたいな子もいるかもしれません。色々なんです。でも種は絶対に芽を出します。だから信じて、どんな花を咲かすのかお子さんをゆっくり見て、未来を信じてほしいなと思います。
てつなぎ編集部
それぞれの「花」が咲く瞬間を、親子でゆっくりと見守っていく時間を大切にしてほしいと心から思います。先生の言葉が、多くのご家族の支えになると思います。
本日はありがとうございました。
本日はありがとうございました。
リンク
PROFILE
不登校専門家/ウェルビーイング教育コーチ
大阪府生まれ。大学を卒業後、高校教師を務めて30年以上。担任、保健室担当、特別支援教育コーディネーターとして不登校、発達障害やメンタル不全の生徒たちと長年関わってきた経験を持つ。プライベートでは子ども2人が不登校になったが、心理学や脳科学、栄養学などを学び、それらを子どもの教育に取り入れたことで2人とも大学進学するまで回復させることに成功。不登校で悩む保護者を応援するために改善の秘訣を発信しているブロガーであるほか、ウェルビーイング教育の普及活動も行っている。本書が初の著作。
※当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね