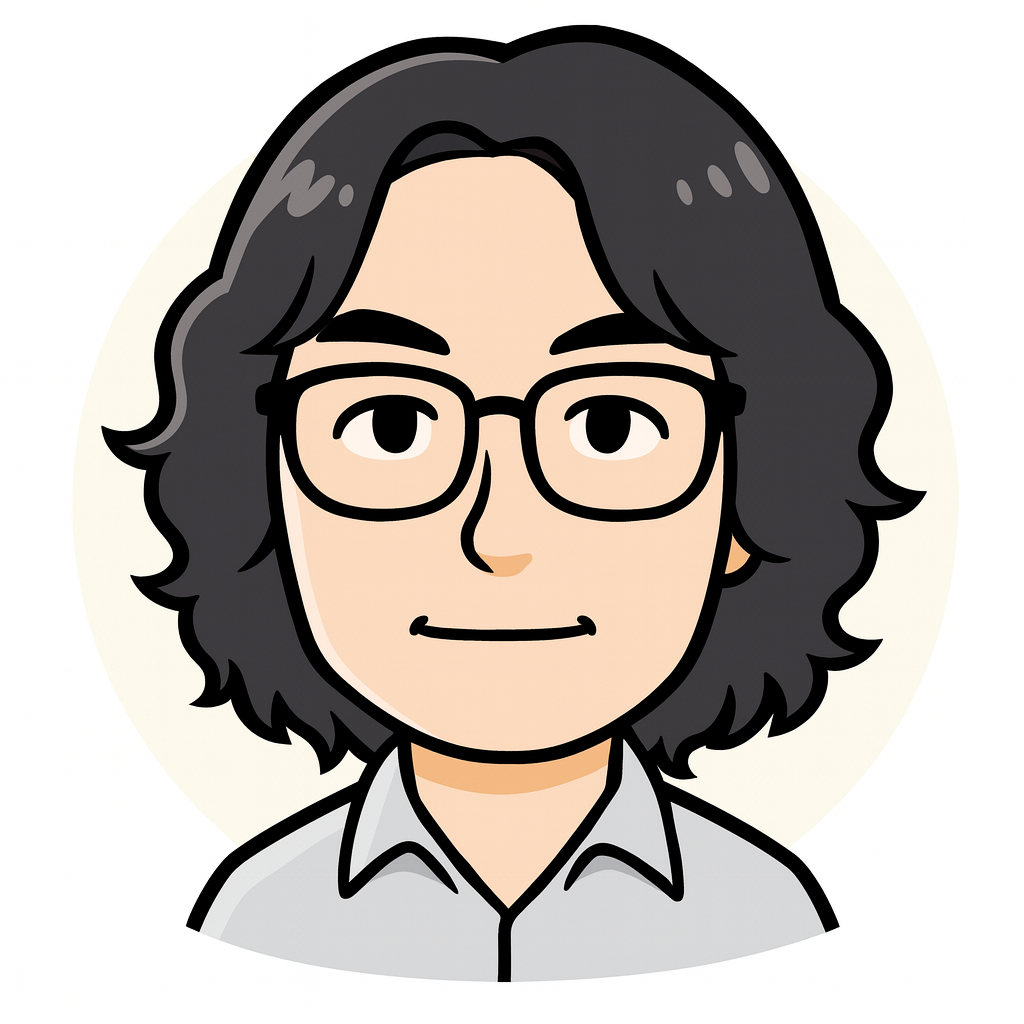【掲示板の声×公認心理師】子どもに『学校に行きたくない』と言われたとき(第1回)
不登校の時代に改めて考える、「学校に行く意味」と親の関わり方
インタビュー
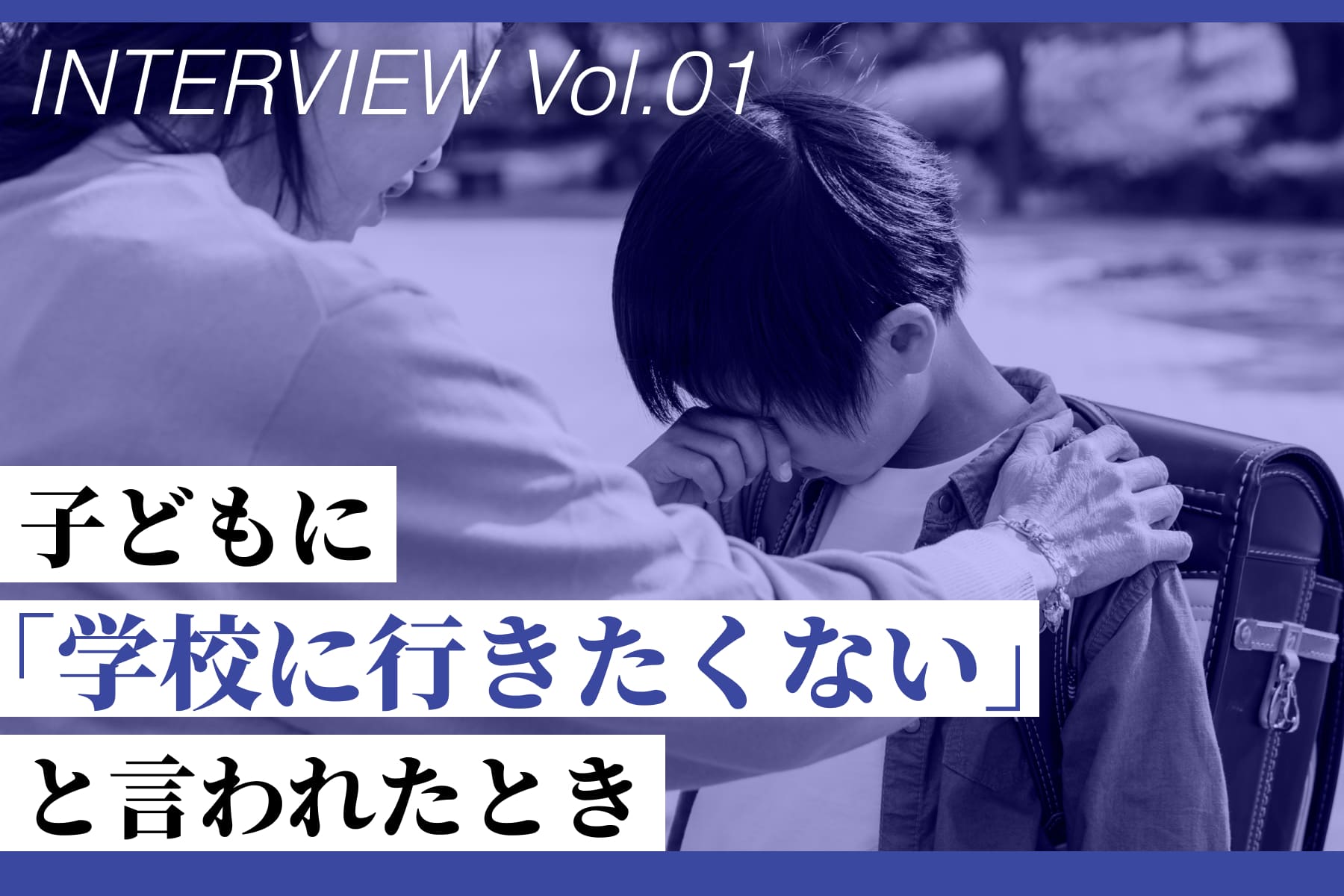
【掲示板の声×公認心理師】子どもに『学校に行きたくない』と言われたとき(第1回)
―不登校の時代に改めて考える、「学校に行く意味」と親の関わり方
「学校に行きたくない」と言われた朝、どう声をかけたらいいのかわからない。無理に行かせるべきか、それとも休ませるべきか...。そんな保護者の戸惑いが、夏休み明けの9月から10月にかけて特に増える時期と言われています。
文部科学省の令和6年度調査【※1】によると小中学生の不登校児童生徒は過去最多の35万3,970人、高校生を含めると42万人を超える規模と報告されています。
てつなぎ掲示板にも、「子どもが学校に行きたくない」「どう接したらいいかわからない」といった投稿が多く寄せられています。
そんな中、てつなぎ編集部では「公認心理師さんに聞いてみた!」連載コラムをスタート。教育・福祉・メンタルヘルスの現場で約20年間支援を続ける、公認心理師・カウンセラーの田村俊作先生に、“不登校の今と親子の支え方”について伺いました(全3回の第1回)。
不登校の増加と低年齢化をどう見るか? ― 公認心理師が語る今の現場

低年齢化する不登校 ― 低学年・未就学から広がる相談の実情
いま紹介したように“先生との関係”がきっかけになる場合もありますが、特に、最近増えている低年齢のお子さんたちが「行きたくない」と感じるとき、その背景にはどんな傾向や変化があると感じますか?
親の関わり方と時代の変化 ― 尊重と見守りのあいだで揺れる家庭
社会の変化と家庭の孤立 ― “誰か一人の責任にしない”視点を
それに、見方を変えれば、今の時代の子どもたちは“自分の気持ちを大切にできるようになってきた”とも言えます。昔のように「我慢して行く」のではなく、「しんどい」ときに自分の気持ちを言葉にできるようになった。親御さんも「子どもの気持ちを尊重しよう」と考える方が増えたのは、社会全体として大きな進歩だと思います。
不登校の時代に改めて考える、「学校に行く意味」とは?

「学校に行く意味」は“社会経験”と“関係づくり”
“学びの場”は学校だけじゃない ― フリースクールや地域のつながり
でも、それを学ぶ場所は“学校”に限らなくてもいい。たとえば適応指導教室やフリースクールなどでも、いろんな大人やいろんな年代の子達がいて、そういう中で関わり方を学ぶことができる。だから、どこで学ぶかは人それぞれでいいと思います。
「行かない」=終わりじゃない ― 子どもが輝く“タイミング”を信じて
たとえば海外なんかではホームスクーリングとかもありますし、今、日本でもだいぶ進んできてますよね。学校に行かなくても、自分に合ったいろんな方法で「学習」ってものが身につけばいいんじゃないかなと思うんです。
たまたま今は、学校とか、そういう“社会の場”に関わるタイミングじゃなかっただけじゃなかっただけ。いずれ、どんな形でもまた人や社会とつながっていく機会はあると思います。
やっぱり「適材適所」というか、その子が輝けるタイミングっていうのもあるから、不登校に対してネガティブには思わないですね。
不登校でも、人との関わりは育つ ― リアルでもオンラインでも広がる“つながり”の形

特に発達特性などからもともと人との関わりが苦手な子や、いじめなどの辛い経験から外に出ることに不安を抱えている子も少なくありません。
そうした子どもたちにとって、オンラインは“人と関わる”うえでハードルを下げるきっかけにもなりそうです。こうした“オンラインのつながり”の中でも、「人と関わる力」は育っていくとお考えですか?
オンラインでも育つ“人と関わる力” ― 安心できる関係から始めよう
やっぱりどこに行っても“人との関わり”はゼロにはならないと思うんです。結局、仕事をするときも誰かとやりとりをすることはあるし。AIで全くできないってこともないだろうけど、AIで仕事取ってくるって言っても、交渉したりやりとりしたりっていうのは“人”だから。
大切なのは「リアルかオンラインか」ではなくて、“安心できる関係”の中から少しずつ広げていくことだと思います。
“好きなこと”が関係を育てる ― 推し活や趣味から始まるコミュニケーション
要は、「雑談する」というのがとても難しいんですよね。「なんとなくふわっとした会話をする」って、実は一番難しい。でも、何か“共通の話題”があると、話ってすごくしやすいじゃないですか。
たとえば、「好きなキャラクター」とか、「推し活」とか。そういう“好きなもの”をきっかけに話すのも立派なコミュニケーションです。そういったところで関わりを育んでいくのも、十分いいと思います。それは、学校だけじゃなく、いろんな場所で、いろんな形で育っていくものだと思います。
リアルでもオンラインでも ― 子どもが“安心して関われる場”を見つけよう
安心して“人と関わる楽しさ”を感じることが、その後も「社会や人とつながる」きっかけになっていくのだと改めて感じました。
そして今の社会では、その“つながり方”そのものが多様化してきている一方で、「不登校」や「学校に行かない」という選択に対しては、まだ偏見や誤解が根強く残っているようにも感じます。
公認心理師
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね