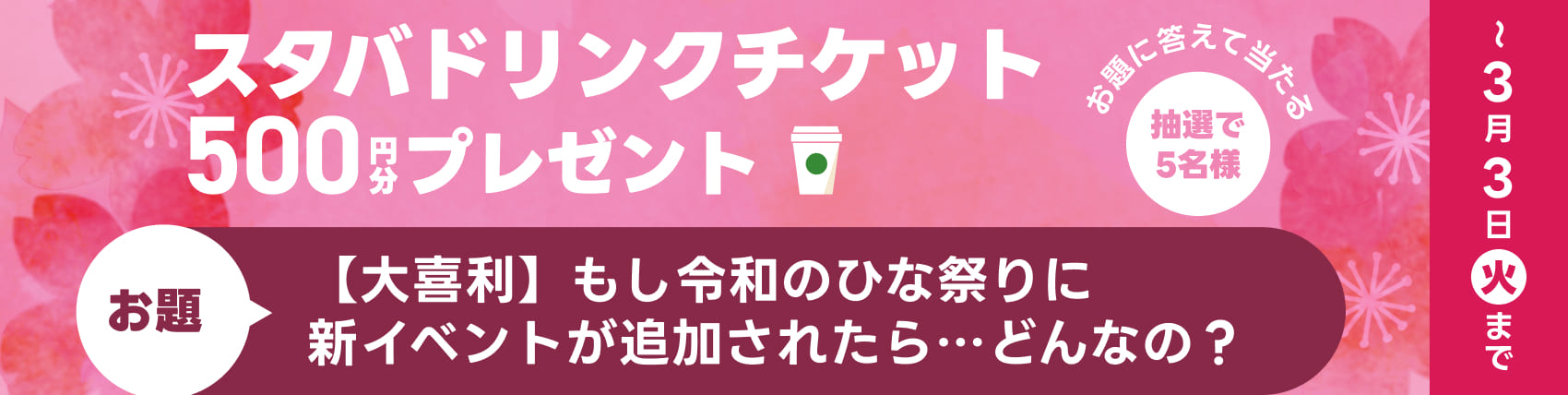子どもが小学校に進学したら読んでもらいたい「小1の壁」の理解とその乗り越え方
仕事と子育ての両立が難しくなる社会的な問題「小1の壁」。その乗り越え方とは?
学校

子どもが小学校に進学したら読んでもらいたい「小1の壁」の理解とその乗り越え方
小学校進学は子どもにとって大きな成長の一歩ですが、働く保護者にとっては保育園時代とは異なる生活リズムやサポート体制の変化に戸惑いを感じる時期でもあります。
特に共働き家庭や一人親家庭で直面する仕事と子育ての両立が難しくなる「小1の壁」は社会的な課題にもなっています。
今回のコラムでは「小1の壁」を取り上げます。「小1の壁」の課題を正しく理解し、事前に対策を取ることで、子どもの成長を支えながら仕事との両立を図ることが可能になります。実際に学童保育の利用や保護者の勤務体系の見直しなど、社会や家庭が連携して取り組むことで、子どもも保護者もより安心して新生活を始められるでしょう。

小1の壁とは何か?保護者が直面する変化と戸惑い
まずは小1の壁の概要と、保護者がどのような変化に戸惑いや不安を感じるのかを整理してみましょう。
小学校に入学すると、登校時間が早まり、学童保育の終了時間も保育園と比べて早いことが多くなります。これに伴って、保護者の勤務時間や通勤時間をうまく調整しなければならず、仕事との両立が難しくなるケースが増えます。
さらに、小学校は保育園のように連絡帳や細かなサポート体制が整っていない こともあり、保護者にとって情報共有の面で戸惑いが生じることもあります。
子ども自身にとっても、急にクラスや授業、宿題といった新しい要素が増え、生活リズムが大きく変化します。こうした変化は成長の証でもありますが、子どもの負担や保護者が子どもをサポートする時間が増えることで、家庭全体のスケジュールが乱れてストレスが溜まりやすくなる のが小1の壁の特徴といえます。
保育園・幼稚園との違い
保育園や幼稚園では夕方まで子どもを預けられる体制が整っている場合が多い一方、小学校では授業が終わると子どもがすぐに帰宅する ケースが一般的です。
学童保育の利用できる時間も限られているため、長時間働く保護者にとっては大きなスケジュール調整が必要になります。加えて、保育園時代ほどこまめな連絡ツールが存在しないため、子どもの様子や学習状況について把握しづらい面もあるでしょう。
放課後と長期休暇の負担
放課後の学童保育が定員オーバーになりやすい地域では、申し込んでもなかなか入れないケースがあり、民間の学童サービスを探すなど追加の労力がかかることが多くあります。また、夏休みや冬休みなどの長期休暇中は子どもが家で過ごす時間が増えるため、その間の見守り、子どもとの過ごし方を考える時間や給食が提供されないため昼食の準備など時間と労力がいつもより多くかかることになります。これらの負担が重なると、保護者の就業時間やスケジュールにさらなる制約が生じるのが実情です。

小1の壁が起こる主要な原因
小1の壁につまずく要因を理解することが、効果的な対策を立てる第一歩です。
保護者がここで強く感じる不自由さの背景には、学童保育の時間や定員の問題だけでなく、学校行事の多さや保護者会への参加 なども挙げられます。保育園時代でも行事はありますが、小学校に進学すると時間帯や頻度が変わるため、勤務先とのスケジュール調整が難しくなるのです。
また、子どもの学習面においても新たな負担が生まれます。宿題の内容によっては保護者がつきっきりでフォローすることも珍しくありません。結果として家庭と仕事の両面に大きな影響をもたらします。
学童保育の不足や待機
学童保育は働く保護者にとって重要なサポートですが、地域によっては供給が需要に追い付いていないという課題もあります。定員がすぐに埋まってしまい、待機状態となるケースも多々あります。
そうなると民間サービスの利用を検討せざるを得ず、費用負担や送迎の手間が増える ので保護者にとって大きな悩みの種になります。2025年5月時点で学童保育を希望しても利用できない待機児童は1万8462人となり、過去最多を記録しています。
保護者のスケジュール調整の難しさ
通勤時間が長く、帰宅時間が学童保育の終了時刻や子どもの下校時刻と合わない場合は、早退や時短勤務などを検討しなくてはなりません。特に単身赴任中や共働き家庭では夫婦間でお互いの勤務時間をすり合わせる必要がありますが、仕事や家事の忙しさ、初めての小学校生活からくるストレスで会話が減り、コミュニケーション不足になる家庭も多く見受けられます。
このコミュニケーション不足は夫婦間におけるスケジュール調整をより難しくさせます。家庭内での役割分担や夫婦間での協力体制は小1の壁を乗り越えるためには重要な要素になってきます。
学校行事や宿題への対応
小学校では入学式や運動会、保護者会、授業参観など多岐にわたる行事があり、頻繁に参加を求められることが少なくありません。 その中でも平日に行われるケースが多いPTAの活動が負担になっている保護者は多くいます。役員や委員になると定期的な会議だけでなく、突発的な会議が発生する場合もあります。また、子どもたちの登校の際の旗当番や登校班の見守り当番になると時間的負担がより増えることになります。
さらに、子どもが学習に慣れるまでは宿題のフォローも必要になります。 共働き家庭では、帰宅後の時間も限られていることもありフォロー時間の確保や日々の学習ペースをサポートするのは容易でありません。こうした行事や宿題対応が積み重なることで、保護者の負担が大きくなるのです。
小1の壁が及ぼす影響
小1の壁は家族だけでなく社会全体にも影響を及ぼします。
仕事と子育てを両立しにくい環境は、特に働く保護者のキャリア形成に影響を与えます。思うように勤務時間を確保できないため、職場での評価や昇進の機会を逃してしまうこともありますし、キャリアの継続自体が困難になるケースもあります。
子どもにとっても、生活リズムの変化、授業や宿題だけではなくクラスメイトや先生との新しい人間関係など、今まで経験したことのない活動や環境からくる精神的ストレスも増えます。さらに、社会全体としても保護者が時短勤務や退職、転職などを余儀なくされるケースも増えて、労働力の確保が難しくなっています。結果として、社会全体の生産性や経済活動にも大きな影響を与えています。
「仕事と家庭の両立」の難しさ
小1の壁に対応するために、勤務時間を短縮せざるを得ない場合や、フルタイムからパートタイムへの切り替え、場合によっては転職や退職を選択する保護者も少なくありません。 これにより、家計収入が減ったり、将来的なキャリア形成に不安を抱える家庭も出てきます。また継続して働く場合でも上司や同僚など周囲からの理解を得られないと、保護者自身の心理的負担も増えていきます。
子どもが感じる「ストレス」と「不安」
新しい生活リズムや人間関係にストレスを感じる子どもも多くいます。また、突然自宅や学童で過ごす時間が増えたり、忙しそうにしている保護者の姿を見て、不安を感じる子どももいます。特に、小学校への進学当初は宿題や持ち物の管理など、保育園時代には経験したことないことだらけで、十分なサポートが得られないと、自信の低下や学習モチベーションの喪失につながる場合があります。これらのストレスや不安の積み重ねは学校生活への意欲の低下につながります。 中には学校に行きたくなくなり、不登校になるケースも報告されています。

スケジュール管理と必要な情報収集
小1の壁を乗り越えるために、保護者が事前に準備しておける対策について紹介します。備えあれば憂いなしです。まず一番重要なのは、スケジュール管理を早めに検討し、家族全員の予定を共有、把握しておくことです。 最近ではスケジュール管理に特化したアプリも多数あるため、それらを有効活用することも一つの手段になります。
また、学童保育の情報や地域のサポート制度 については、入学前から積極的に調べることが大切になります。施設やサービスによっては申し込み時期が限られていることもあるため、早めのリサーチが後の安心感につながります。小1の壁を乗り越えるための必要な情報収集は欠かせません。
さらには、夫婦や家族間だけでなく、同じ学校の保護者や地域の人との情報交換を行えば、より鮮度の高い情報を得ることができますし、一人で抱え込む負担も減らせます。複数の家庭と協力しあうことで、場合によっては、交代で子どもの面倒を見るなどの工夫ができる場合もあります。そうなると、お互いに時間的なゆとりを作り出すことも可能になります。
地域子育て支援サービスの利用
小1の壁を乗り越えるために地域の子育て支援サービスを利用する ことも手段の一つになります。多くの自治体やNPOが地域で子どもの送迎や一時預かりなどの相互援助活動をするファミリーサポートや放課後の子ども教室などを提供しています。
その他にも習い事と預かりを組み合わせている民間のアフタースクールもあります。中には送迎付きや、学校まで迎えに来てくれるサービスもあります。民間のサポートの有効活用も選択肢の一つとして考えておくと、家庭だけで対処できない部分や保護者の負担など大きく軽減できるでしょう。

企業における働き方改革と職場環境の整備
小1の壁を乗り越えるためには企業による「職場環境」の整備は欠かすことができません。
近年は多様な働き方を推進する企業が増えています。在宅勤務や時短勤務の導入など数年前と比べ、大きく働き方も変わってきました。保護者の就労環境を整えることで、モチベーションやスキル維持にもプラスに作用します。企業側にとっても昨今の人材不足を考えたとき、働き続けてくれることは大きなメリットになります。
また、職場内で育児状況を共有する機会があると、子育て中の社員同士、管理職からの理解が深まりやすくなり、結果として働きやすい会社になり企業としての生産性も上がることになります。保護者の早退や休暇を取りやすい雰囲気が広がれば、離職率の低下や企業のイメージアップにもつながるでしょう。
柔軟な勤務制度と有給取得の促進
短時間勤務や時差出勤などを積極的に導入すれば、子どもの送迎と仕事を両立させやすくなります。また、有給休暇を取りやすい風土も欠かせません。事実、有給休暇を取りづらいと思っている保護者も多数います。 学校行事や子どもの体調不良による休暇に対しての企業側の理解も大切になります。こうした制度面のバックアップがあることで、保護者は安心して日々の業務に取り組むことができるのです。
管理職や同僚社員からの理解は必要不可欠
制度が整っていても、実際の運用において管理職や同僚の理解が得られなければ本末転倒です。SNSなどでも職場からの理解が得られないといった内容の投稿が多く見受けられます。
まずは、上司や同僚社員と日常的にコミュニケーションを図り、子どもの行事や急用時のサポート体制を共有しておくことも大切なフローになります。 職場全体でフォローし合う環境があれば、小1の壁に直面している保護者も働きやすさを実感しやすくなるでしょう。
国や自治体の制度の有効活用
小1の壁を乗り越えるには、国や地方自治体の制度を知り、有効活用することも欠かせません。
各自治体では放課後児童クラブの増設や補助金の充実など、保護者を支援するための施策を進めています。地域によって利用できる支援策が異なるため、役所や住んでいる自治体の公式ウェブサイトなどで最新情報をこまめにチェック することが大切です。繰り返しになりますが、小1の壁において情報収集は欠かせません。
また、具体的な助成金や補助制度は年ごとに内容が更新 される場合があるため、気になる場合は直接問い合わせるなどして確実な情報を得ることが有効です。こうした公的サポートを組み合わせれば、家族が安心して子育てと仕事を両立できる環境づくりに役立ちます。
放課後児童クラブの利用
放課後児童クラブは市区町村が運営し、保護者が仕事で日中家にいない子どもたちが放課後を安全に過ごすための場所を提供しています。待機児童問題を軽減するため、施設数や定員を増やす取り組みが進んでいる一方、地域格差もあるのが現状です。早い段階で見学や申し込みを行う など、保護者の積極的なアクションが求められています。
子ども・子育て支援新制度
内閣府が中心となって進める子ども・子育て支援新制度は、保育の質の向上や放課後児童クラブの拡張など、多方面から保護者と子どもを支援する仕組みを目指しています。具体的には、保育料負担の軽減や事業者の参入促進などが挙げられます。こうした制度を把握することで、保護者は自分のライフスタイルに合ったサービスを選びやすくなるでしょう。

子どもの気持ちと成長を支えるポイント
ここまで小1の壁の対策を説明してきましたが、何より大切なことは子どもが楽しく小学校生活を送り、スムーズに成長できること です。この章では、子どもの学校生活や成長において保護者が気をつけたいことを整理します。
大人の都合に振り回される子どもは、戸惑いや不安を感じがち です。入学直後は特に生活リズムが変わります。子どもが安心できるよう話を丁寧に聞いたり、学校での出来事、登校前の準備や宿題など子どもに小さな成功体験を積ませる仕組や環境作りも大切になります。
子どものペースを尊重しながら、無理をしすぎない環境づくりを心掛ける ことで、学校への適応や学習意欲の向上につながります。小1の壁は保護者にとっても試練ですが、子どもと良好なコミュニケーションを保つことが乗り越えるカギとなるでしょう。
子どもをポジティブな気持ちにする声かけのコツ
子どもが自分で準備をしたり、宿題を終えたりといった些細な行動を褒めてあげると、自信ややる気が育ちやすくなります。具体的には「あいさつができてすごいね」「自分でランドセルを片付けられてすごいね」など、行動に対して肯定的なフィードバック を与えることが効果的です。こうした積み重ねは、学習面だけでなく生活全般にもポジティブな影響を及ぼします。
友達や先生とのコミュニケーションを育む
小学校生活に早く慣れるためには、クラスメイトや先生との交流を円滑に進めることも大切です。保護者が子どもの話をしっかりと聞きながら、コミュニケーションがうまくいかないときの解決策を一緒に考えてあげる と、子どもは安心感を得られます。相手を尊重し、お互いの気持ちを理解し合う姿勢を示すことで、より豊かな学習環境を作ることができます。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね