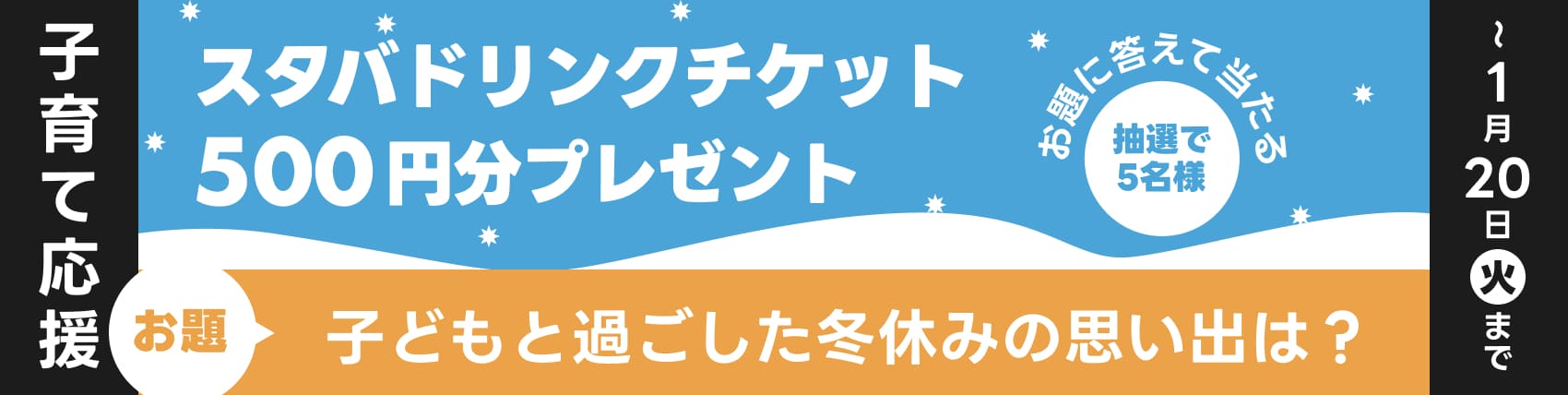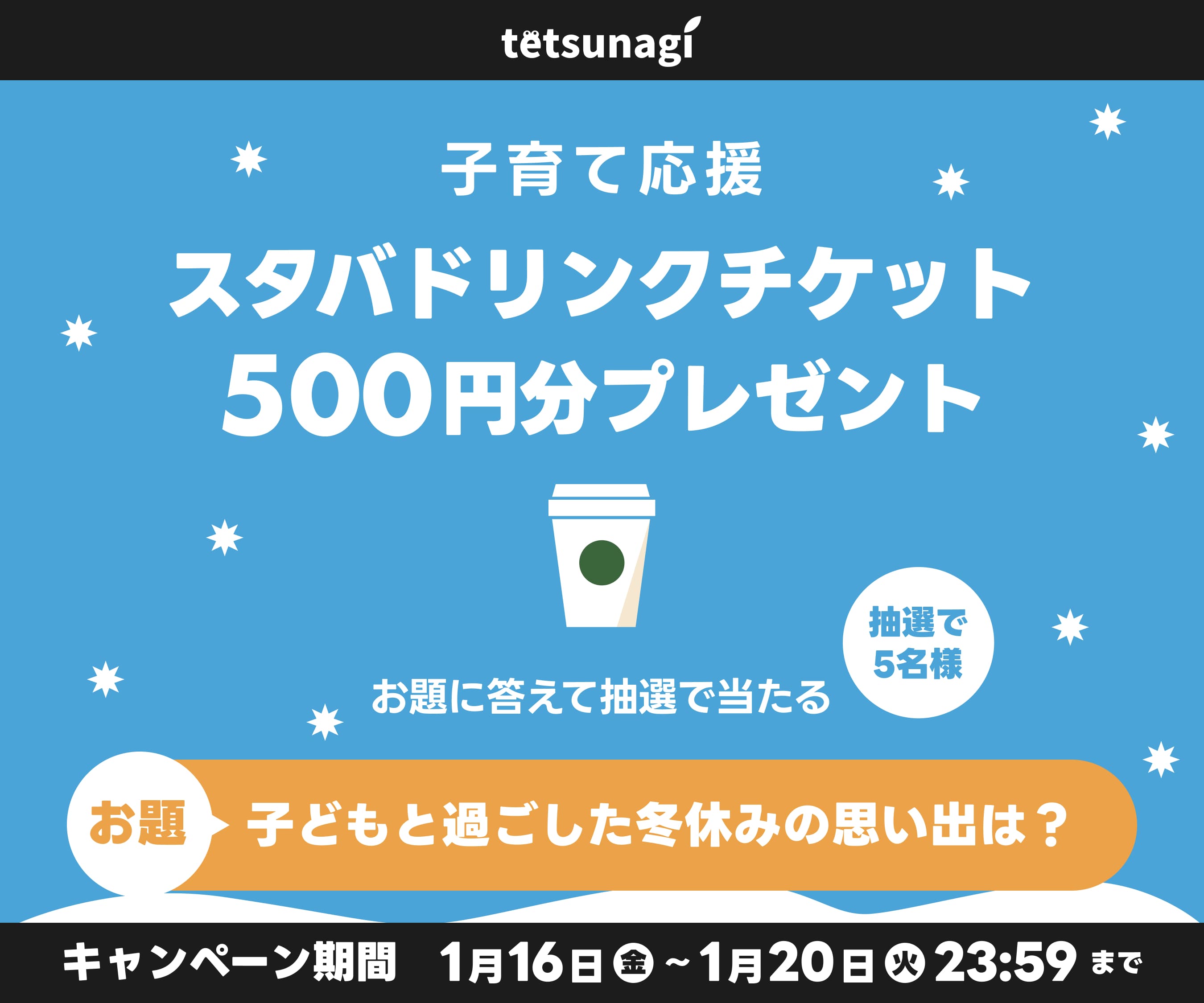【小学生】朝起きられない原因と対策を徹底解説|起立性調節障害の可能性も(第1回)
決して怠けているワケではない。小学生が朝起きられない背景と代表的な要因とは?
健康/病気

【小学生】朝起きられない原因と対策を徹底解説|起立性調節障害の可能性も(第1回)
こんにちは、多様な教育ナビゲーター・あずみのこです。15年以上子育て支援に携わり、2人の小中学生を育てる現役共働きママの視点から、コラムをお届けしています。
子育ての現場に立ちながら、同じ母親として「理想どおりにいかないなぁ」「どうしたらいいんだろう」と悩むこともしょっちゅう。だからこそ、このコラムでは専門的な視点と、等身大の母親目線の両方を交えて、“親も子も少しラクになれるヒント”をお届けできたらと思っています。
さて、今回のテーマは「小学生の朝が起きられない問題」。「何度声をかけても布団から出てこない」 「やっと起きても不機嫌で、着替えも朝ごはんも進まない」
長期休み明けや新学期など、特にこの“朝のバトル”にぐったりしてしまうご家庭は少なくないのではないでしょうか。
全2回に分けて、朝起きられない原因と対策を徹底解説していきます。
小学生が朝なかなか起きられない背景には、実はいろいろな要因が重なっていることがあります。「起立性調節障害(OD)」といった体の病気や、自律神経のバランスの変化、そして思春期に向けた体の成長…。さらに、宿題や習い事で夜が遅くなったり、スマホやゲームが長引いて睡眠不足になったり...。
でも、ここで気をつけたいのは「怠けているだけ」「夜更かしのせい」と決めつけてしまわないこと。実際には体の病気が隠れていることもありますし、生活リズムの乱れであっても、少しずつ無理のない工夫を続けることで、改善していくことも多いんですよね。
この記事では、朝起きられない小学生の原因や家庭でできる工夫、そして「そろそろ専門医に相談した方がいいかも?」というサインや目安についても触れていきます。母親としての体験や教育・福祉の現場で見てきたことに加えて、厚労省などの公的なデータや専門家の意見も参考にしながら、できるだけわかりやすくまとめてみました。
一緒に「どうしたらいいかな?」を考えながら、子どもの健やかな毎日を支えるヒントを探していきましょう。
小学生が朝起きられない主な原因とは?
小学生が朝なかなか起きられない背景には、いくつかの代表的な原因があります。
まずよく耳にするのが「起立性調節障害(OD)」と呼ばれる自律神経の不調です。思春期前後の子どもに多く見られ、朝になると強いだるさや立ちくらみで体が動かなくなることがあります。親としては「甘えなのでは?」「サボっているのでは?」と感じてしまうこともありますよね。でも実際には、子ども自身も「起きたいのに起きられない」と苦しんでいることが少なくありません。
また、夜更かしやスマホ・ゲームの長時間利用も大きな要因のひとつと言われています。ブルーライトの刺激で脳がさえて眠れず、気づけば深夜…という経験は大人にもありますよね。子どもが自分でコントロールするのはさらに難しく、その結果、体内時計が後ろにずれて「朝起きられない」状態になってしまいがちに。
さらに、学校や家庭でのストレス、運動不足、寝室の環境なども眠りの質を下げる原因になることがあります。こうしたさまざまな要素が重なり合うことで、自律神経の乱れなどによって体が思うように動かない状態になってしまうことがあるようです。
親としては「どうしたらいいのか...」と途方に暮れることもあると思います。でも、まずは「うちの子だけじゃないんだ」「いろんな理由があるのかもしれない」と知っておくだけでも、気持ちが少しラクになるはず。「そういうこともあるんだよね」と受け止めることから、少しずつ一緒に工夫していけたらいいのではないかと思います。

起立性調節障害(OD)とは
「朝どうしても体が動かない」「午前中はだるいけれど、午後になると元気になる」などの特徴が見られるときに考えられるのが、起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation:OD)です。
これは自律神経の働きがうまくいかず、血圧や脈拍の調整が乱れることで、朝起床時に強いだるさ、頭痛、立ちくらみなどが出る病気です。特に思春期の子どもに多く、小学生でも高学年になるにつれて症状が目立ってくる場合があります。
日本小児心身医学会によれば、起立性調節障害(OD)は中学生の約10%が経験し、不登校の約30〜40%に併存していると報告されています【※1】。また、小学生でも約5%が罹患するとされており【※8】、決して珍しい病気ではありません。けれども、周囲からは「怠けているだけ」と誤解されてしまうことも少なくありません。実際には“気持ちの問題”ではなく“身体の病気”であり、正しい理解と対応が欠かせないのです。
症状は午前中に強く出ることが多く、学校生活や家庭生活に支障をきたすこともあります。「どうして起きられないの?」と責めるのではなく、「体の仕組みが原因かもしれない」と知っておくだけでも、親の受け止め方はずいぶん変わるかもしれません。
もし「毎朝のだるさが数週間以上続く」「立ち上がると気分が悪くなる」といった状態が見られる場合は、無理をさせず、早めに小児科や専門医に相談するのが安心です。
睡眠リズムの乱れ(睡眠相後退症候群)
夜型の生活が続き、深夜にならないと眠れず、朝どうしても起きられないなどの状態は「睡眠相後退(前進)症候群(すいみんそうこうたい(ぜんしん)しょうこうぐん)」と呼ばれることがあります。
厚生労働省の資料によると、睡眠相後退症候群は「社会的に望ましい時刻に入眠・覚醒することが慢性的に困難になる状態」で、午前3〜6時ごろになってようやく眠れるため、午前中は強い眠気や頭痛、疲労感が出やすいと報告されています【※2 】。思春期から青年期に多いとされていますが、小学生でも夜更かしの習慣が続くと体内時計の乱れが固定化してしまうことがあるそうです。
生活習慣やストレスの影響
子どもが朝なかなか起きられない背景には、ストレスや不安が深く関わっていることもあります。家庭や学校でのプレッシャーが強いと、夜になっても頭の中が休まらず、眠りが浅くなったり、途中で何度も目が覚めてしまったり…。
渋谷駅前心療内科ハロクリニック(監修:草薙威史医師)によると、強いストレスを受けると交感神経が優位になり、体が「戦うか逃げるか」の緊張状態に切り替わってしまうため、寝つきが悪くなったり熟睡できなくなるのだそうです【※3】。その結果、夜に眠れないまま朝を迎え、さらに目覚めがつらくなる…そんな悪循環に陥りやすいといわれています。
スマホ・ゲームの長時間利用
また、小学生が朝起きられない大きな原因のひとつに、スマートフォンやゲームの長時間利用が専門家の間でも多く指摘されています。就寝前に画面を見続けると、夜間のブルーライトが睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、体内時計を乱して“朝起きられない”状態を引き起こす可能性があるそうです【※4】。
さらに、ベネッセの調査によると、小学生のゲーム利用時間は「平日1時間・休日2時間」が最多で、動画視聴は「平日1時間・休日3時間」が最も多いとのこと【※5】。特に休日になると、5時間以上も使ってしまう子も少なくないそうです。こうした長時間利用が積み重なると、ただ睡眠時間が削られるだけでなく、翌朝の目覚めの悪さやだるさにつながりやすいとも言われています。
大人でも「ちょっとだけ」と思いながらついスマホを見続けてしまうこと、ありますよね。子どもにとってはなおさら自分でコントロールするのが難しく、その習慣が積み重なることで生活リズムが乱れ、朝なかなか起きられない状態につながってしまうのかもしれません。
朝起きられない子どものセルフチェック
「うちの子はただの夜更かし?それとも病気?」と迷うときは、セルフチェックをしてみるのも一つの方法です。
朝起きられない状態が続いているときには、
● 午前中の授業に集中できず眠気が強い
● 起床直後にめまいや吐き気を感じる
● 日中の活動や生活に支障が出ている
といったポイントをチェックしてみましょう。保護者や先生だけでなく、子ども自身の「しんどい」という感覚にも耳を傾けることが大切です。
例えば、大正製薬「起立性調節障害セルフチェック」では、立ちくらみやめまい、午前中の強い倦怠感や頭痛など、11項目でセルフチェックできるシートが公開されています(監修:OD低血圧クリニック田中英高先生)【※6】。
声かけや就寝ルーティーンを工夫しても改善が見られない場合は、単なる夜更かしではなく疾患の可能性も考えられます。こうしたチェックを参考にしながら、数週間以上症状が続くようなら、自己判断せずに小児科や専門外来に相談してみることをおすすめします。
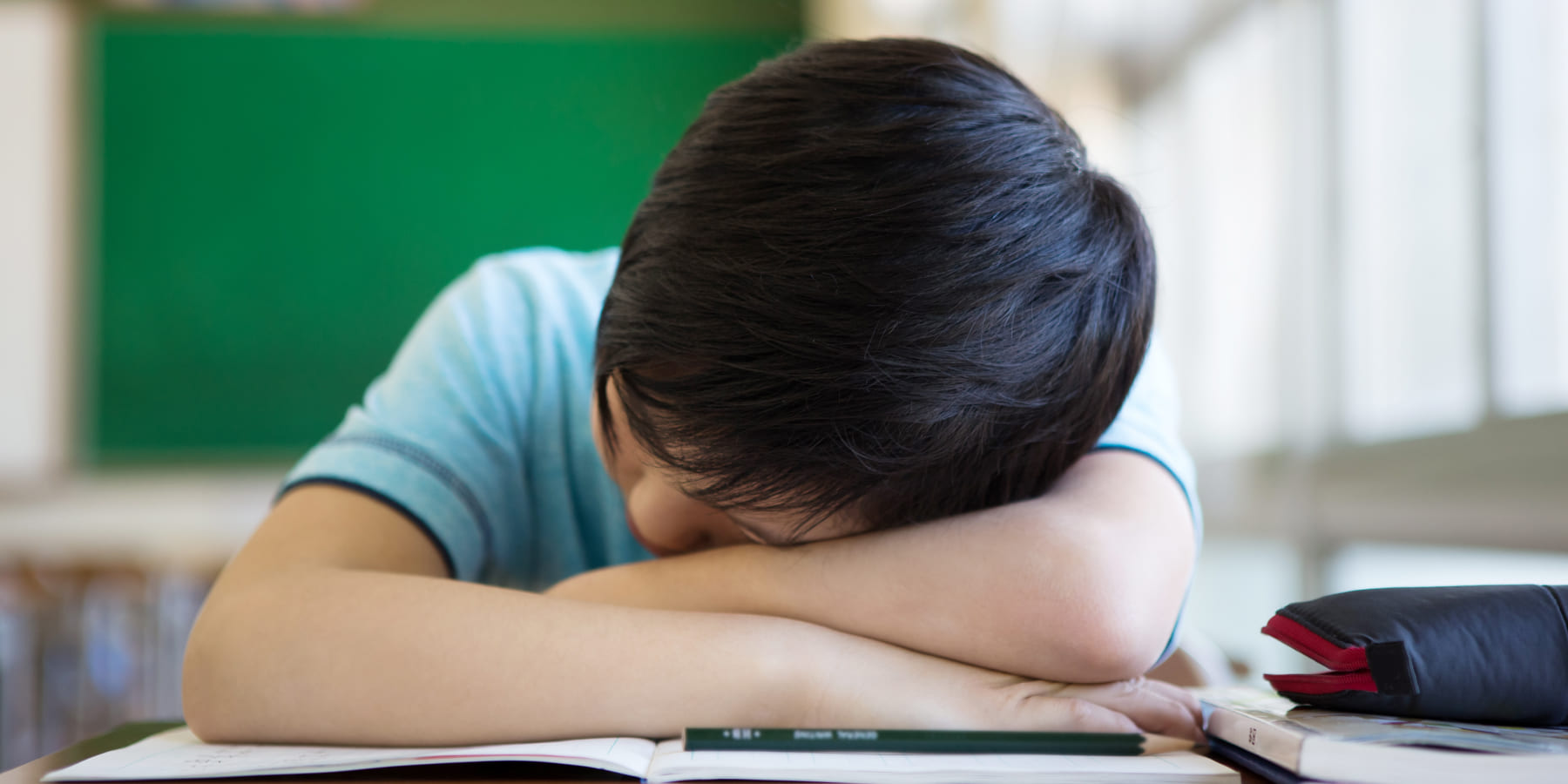
どんな症状があれば受診を検討すべき?
医療機関の受診を検討すべきサインとしては、朝の強い倦怠感やめまい、午前中の激しい頭痛や日中の強い眠気が数週間以上続くとき。さらに、学校を休みがちになったり、不登校の兆候が見られるときには、早めに医療機関に相談してみるのがおすすめです。
自己判断で「そのうち良くなるだろう」と様子を見ていると、かえって長引いてしまい、学習や生活に影響が出てしまうこともあります。
東京医科大学病院の呉宗憲先生(小児科・思春期科)も、起立性障害は「頭痛、吐き気、倦怠感、腹痛、立ちくらみや時に失神、朝起きることが困難であるといった症状を訴えます。日本では思春期に多く、学校に登校することができなくなるなど日常生活にも支障をきたすほどの症状を持つ人もいます」と話しています【※7】。
こうした専門家の言葉を聞くと、「やっぱり怠けているわけじゃないんだ」とホッとしますよね。親としては「どう声をかけてあげたらいいのかな」と悩むことも多いですが、まずは一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも子どもを支える大事な一歩なのだと思います。
起こし方を工夫しても改善しない場合
朝は優しく声をかけたり、カーテンを少しずつ開けて光を入れたり、好きな音楽を流したり…。きっと親としてできる工夫は、すでに色々試されている方も多いと思います。ただ、それでもなかなか改善が見られないときは、「単なる夜更かし」や「生活リズムの乱れ」だけが原因ではないのかもしれません。
実際には、起立性調節障害など医学的なサポートが必要なケースもあります。「病気かもしれない」と思うと親としては不安になりますが、早めに専門家とつながることで、症状の長期化を防ぎ、子どもの生活や学習への影響を小さくできることがあります。
「親の工夫が足りなかったのかな」と自分を責める必要はありません。むしろ「ここまでやっても改善しないから、一度専門家に相談してみよう」と切り替えることが、子どもにとっても大きな安心につながっていくのだと思います。
起立性調節障害のしくみと治療法
起立性調節障害は、思春期を迎える前後に自律神経が乱れやすくなることで起こる症状です。特に、朝の起床時にめまいや立ちくらみ、頭痛が強く出やすく、学校に行く準備がスムーズに進まなかったり、午前中の授業に出られなかったりすることもあります。
「なんで朝だけ調子が悪いの?」と戸惑う親御さんも多いと思いますが、実は小学生でも発症する子は少なくないんですね。一般社団法人 起立性調節障害改善協会によると(監修:伊藤信久 医師)でも、小学生全体の約5%が起立性調節障害に罹患するとされ、決して珍しい病気ではないことが指摘されています【※8】。
治療の基本は、規則正しい睡眠・食事・運動といった生活リズムの見直しで、水分や塩分をこまめにとることも効果的とされていています。厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」【※2 】や、同協会の解説でも、「生活習慣の調整」が“改善の第一歩”として推奨されています。
ただ、症状が強い場合には薬で血圧をコントロールしたり、心理的なサポートと「専門的なサポートをうまく組み合わせること」。家族や学校が協力して長い目で支えていくことが、子どもにとって大きな安心感につながります。
血圧変動と自律神経の関係
では、どうして朝になると特に症状が強く出やすいのでしょうか。その背景には“血圧の変動”と“自律神経の働き”が深く関わっています。
本来なら、朝起きて立ち上がった時には交感神経が働いて血圧を保ち、脳にしっかり血液が届くようになっています。ところが、自律神経の乱れによってこの働きが弱かったり遅れたりすると血圧が急に下がり、頭に血が回らずにめまいや強いだるさが出てしまうのです。特に寝起きは血圧が安定しにくいため、「朝が一番つらい」と感じる子が多いのも納得できます【※9】。
こうした医学的な仕組みを知っておくと、子どもの様子をより客観的に見守れるヒントになるかもしれません。
薬物療法とカウンセリングの必要性
生活リズムを整える工夫をしてもなかなか良くならない場合には、医師の診断のもとで薬を使って自律神経や血圧のバランスを整える方法もあります。薬だけで「治す」ものではないのかもしれませんが、つらい症状をやわらげて、子どもが少しでも過ごしやすくなるよう支えてくれることもあるんですよね【※10】。
それと同じくらい大切にしたいのが心のケアです。朝起きられないことが続くと、「自分だけできない」「怠けていると思われるかも」と子ども自身が不安を抱えてしまいがち。そんな気持ちに寄り添うために、カウンセリングなど心理的なサポートを並行して受けることも効果的とも言われています。【※11】
身体と心の両面から支えていくことで、すぐに劇的な変化が見られるわけではなくても、時間をかけて少しずつ回復への道がひらけていくかもしれません。そしてなにより、親子だけで抱え込まず、信頼できる大人や専門家と一緒に歩んでいけること自体が、大きな安心につながるんだと思います。
どのような場合に専門医を受診すべき?
「このまま様子を見ても大丈夫かな…」と迷う親御さんも多いと思います。でも、朝起きられない状態が数週間以上続き、学校生活や家庭生活に大きな支障をきたしているときには、早めに専門医の受診を検討した方が安心です。
まずは小児科や内科で相談し、必要に応じて心療内科や精神科といった専門のサポートにつながるケースもあります。起立性調節障害は、対応が早ければ早いほど改善がスムーズになりやすいといわれています。
「怠けているのでは?」と悩み続けるよりも、「体の不調だから専門家に見てもらおう」と切り替えることが、子どもにとっても親にとっても安心につながります。
朝起きられない場合の対処法と実践的アプローチ
「どうしても朝がつらい」という子どもには、生活のちょっとした工夫や家族の関わり方で、負担をやわらげられることがあります。完璧に早寝早起きを徹底するのは、大人だってなかなか難しいもの。だからこそ「できることから少しずつ」で大丈夫。ここでは、日常の中で取り入れやすい工夫を紹介していきますね。

睡眠衛生の整え方
朝なかなか起きられないときには、睡眠環境を見直すことも大切です。たとえば、寝室の照明を明るすぎない程度に抑える、室温を快適に保つ、寝具を心地よいものに変えるといった工夫だけでも、眠りやすくなることも。
また、寝る前はスマホやゲームを控え、代わりに入浴や軽いストレッチ、読書など「気持ちがほっと落ち着く時間」を取り入れるのも効果的です。
厚生労働省がまとめた「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」【※12】でも、こうした環境づくりや生活習慣の調整は“子どもの睡眠の質を高めるカギ”になると示されています。
睡眠習慣を少しずつ整えていくことで、自然に寝つきが良くなり、翌朝の目覚めもスッキリしやすくなります。「朝起きられない」を改善するためには、まず日々の小さな環境づくりから始めてみるのがおすすめです。
家族で取り組む早寝・早起き習慣
小学生が自分だけの力で早寝早起きを続けるのは、やっぱり難しいですよね。なので、なるべく家族みんなで協力して生活リズムを整えていくこともポイントです。家族と一緒にやることで、一体感が生まれて自然と続けやすくなるんですよね。
夕食やお風呂の時間をできるだけそろえたり、寝る前はテレビやスマホを控えるルールを一緒に決めたりと、そんな小さな工夫でも、少しずつ習慣にしやすくなります。
とはいえ、毎日きっちりそろえるのは現実にはなかなか難しいもの。気が向いたときに「今日はちょっと早めに寝室に行こうか」くらいの声かけからでも十分だと思いますよ。
無理に起こさないサポートのポイント
起立性調節障害のように体調不良が背景にある場合は、無理に起こすと子どもへの負担が大きくなることもあります。実際に、私が関わったご家庭でも「学校に行かせなきゃ」と毎朝必死に抱き起こしていたら、かえって子どもが起きられなくなり、親子関係もぎくしゃくしてしまったケースがありました。
まずはカーテンを開けて朝の光を入れる、声をかけながらゆっくり体を起こす、水分をとって落ち着かせる…そんな小さな工夫から始めてみるのがおすすめです。特に体調不良が背景にある場合は、専門医と連携しながら「その子のペース」で整えていくことが、長い目で見ても安心と改善につながります。小さな歩みでも、その積み重ねが子どもにとって確かな支えになっていくはずです。
多様な教育ナビゲーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね