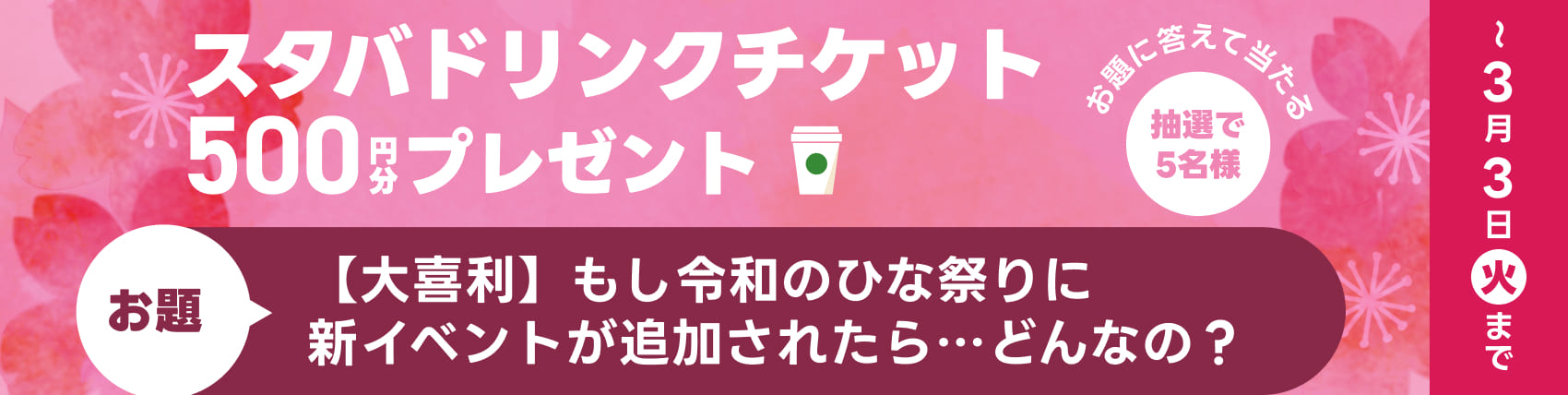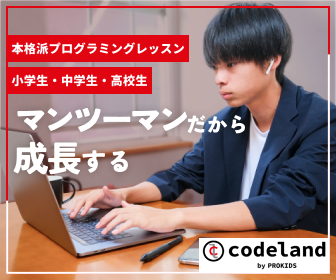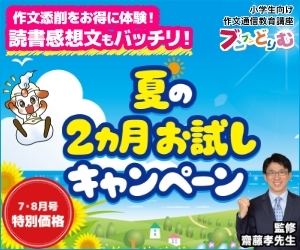忙しい親でも安心!小学生の夏休みを乗り切るための完全ガイド
親子で“ゆるく”夏休みを乗り切るには?
学校

忙しい親でも安心!小学生の夏休みを乗り切るための完全ガイド
こんにちは、あずみのこです。
今回ご縁があって、てつなぎ編集部のコラムライターとしてデビューすることになりました。読んでくださる方が、少しでも「気がラクになった」「読んでよかった」と思えるようなコラムをお届けできたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします!
ちょっとだけ自己紹介をすると、私は小学6年生と中学2年生の子どもを育てる共働きママ。普段は、子どもや保護者の居場所づくりに関わる仕事をしていて、不登校や発達特性、子育てや家庭の悩みなど、100組以上の保護者や子どもたちと向き合ってきました。
とはいえ、私自身も日々バタバタで、うまくいかないことばかり。夫は週の半分リモートワークだけど、家のことにはほぼノータッチ。私が在宅勤務でなんとかやりくりする毎日で、理想どおりにいかない毎日や子育てに、「どうしよう…」と頭を抱えることもしょっちゅうです。
だからこそ、「完璧じゃなくて大丈夫」「迷っても、うまくいかなくてもいい」という気持ちを込めて、“ちょっと一息つける時間”を共有できたら嬉しいです。
さて、気がつけばもうすぐ夏休み。みなさんはもう夏休みの計画や準備はされていますか?ちなみに、うちはまだ予定はほぼノープラン(笑)。
子どもたちにとっては楽しみな長期休みだけど、親にとっては「毎日お昼ごはん作らないといけない...」「子どもたちをどこに連れていこう」「預け先は?」と、頭を悩ませるシーズンですよね。
てつなぎの掲示板でも、こんな声がありました。
本来であれば「子どもたちと過ごす時間が増えてうれしい!」となると思うんだけどなぁ。せめて夫の協力があればまた違うのだけど、そこはなかなか期待できない。悩ましい。”
― てつなぎ掲示板より
思わず「わかる…」と共感してしまう投稿。「子どもが楽しみにしている夏休み」と、「親にのしかかる現実」。そのギャップに戸惑う気持ち、きっと多くの方が感じていると思います。
ちなみに、てつなぎではこんなアンケートも実施されていました。
「夏休み、1日自由にできるとしたら何をやる?」
→ アンケートの結果はこちら
寄せられた回答は、「ただ寝たい」「一人でぼーっとしたい」「何も予定を入れたくない」など、思わず「それ、それ〜!」と叫びたくなるような本音ばかりで共感しまくりました(笑)
この記事では、そんな気持ちを抱える方に向け、夏休みの過ごし方や準備のコツ、ちょっとした工夫などを、わが家のリアルなエピソードを交えながらお伝えしていきます。
無理せず、罪悪感なく、「わが家なりのちょうどよさ」を見つけるヒントになればうれしいです!
小学生の夏休みを乗り切るには?親子でできる“ゆるい計画”がカギ

毎年、夏休み直前になると「今年はどうしよう…」と、予定表とにらめっこするのが、わが家の恒例行事になっています。学研が2022年に行った調査でも、小学生の保護者の約8割が「夏休み中の子どもの過ごし方や学習方法に悩んでいる」と答えており(出典:学研エデュケーショナル)、この“夏のモヤモヤ”は多くの家庭の共通課題なのだと感じます。
でも、夏休みをうまく乗り切るコツって、実はそんなに特別なものじゃないのかもしれません。
わが家で毎年心がけているのは、「ざっくりとでも予定を立てておく」こと。「この週は旅行に行こう」「この日はおばあちゃん家」「ここらへんで宿題やろうか?」と、子どもと一緒に“ゆるい計画”を立てるようにしています。
このとき大事なのは、「自分で決めたこと」として子どもが関われるようにすること。アメリカの教育心理学者Zimmerman(ジマーマン)氏も、「自分で目標を立てることが、やってみようと思える力=自己効力感を育てる」(参考:『Theory Into Practice』掲載、Spring 2002年)と語っています。
完璧じゃなくても、まずは一緒に考えてみる。そのスタートがあるだけで、夏休み全体がちょっとラクになる気がします。
子どもの預け先・過ごし方をどうする?共働き家庭のリアルな選択肢
夏休みが近づくと、「仕事中、子どもはどこでどう過ごせばいいんだろう?」と焦る日が出てきます。わが家でも、学童を申し込んだのに子どもが「行きたくない」と言い出したり、頼りにしていた親戚にドタキャンされたり…。思いどおりにはいかないことばかりでした。
祖父母や親戚にお願いする場合は、できるだけ事前に生活リズムや宿題の進め方、食事やアレルギーのことなども共有しておくのがおすすめです。「どうしても難しい日は、ちょっとだけお願いできるかな」と、早めに声をかけておくだけで、気持ちの余裕がぜんぜん違います。

学童・ファミリーサポート・ベビーシッターの選び方
学童やファミサポ、ベビーシッターなどのサービスも、選択肢としてはありがたい存在。ただうちの場合、学童は毎年あっという間に定員が埋まってしまい、「申し込み合戦に間に合わなかった」なんて年もありました。
実際、こども家庭庁の調査によると、2024年5月1日時点で全国の学童(放課後児童クラブ)の待機児童は17,686人。前年より1,410人も増えていて、東京都・埼玉県・千葉県の3都県だけで全体の約4割を占めているそうです(出典:こども家庭庁「令和6年 放課後児童クラブの実施状況調査結果(速報値)」2024年5月1日時点 (こども家庭庁公式サイト))。
ファミリーサポートは、自治体によって利用条件や料金が大きく異なるので、早めに確認しておくのがおすすめです。わが家では、登録会に行ったものの、「利用できるのはまだ先だった…」なんてこともありました。
ベビーシッターは費用がネックになりやすいけれど、「この日だけはどうしても!」というときに、ピンポイントでお願いしたこともあります。
いずれのサービスを選ぶにしても、事前に安全面や利用者の口コミを確認しておけると、より安心してお願いできます。自分たちが納得して選べることが、なにより大事ですよね!
どれも完璧には頼れないけれど、少しずつ組み合わせながら「なんとかなるかも」をつくっていく。その感覚があるだけで、夏のハードルがちょっと下がる気がしています。
近所のママ友と助け合う仕組みづくり
そして、意外と助かるのが“近所のママ友とのゆるい助け合い”。私はもともとママ友づきあいが得意な方ではないのですが、「この日はうちで見るよ」「じゃあ来週はお願いね」といった関係性があると、本当に救われるなと感じます。おやつやゲーム時間のルールをざっくり決めておくだけでも、お互い安心できますよね。
とはいえ、誰もが気軽に頼れる関係性を持っているとは限りません。実際、約4人に1人(24.2%)の働くママが「気軽に相談できる母親仲間がいない」と感じているという調査結果もあります(出典:フロンティア株式会社・株式会社PRIZMA「母親の孤立に関する調査」2025年3月)。
だからこそ、ほんの少しの声かけや「お互いさま」の気持ちが、お守りのように心強く感じられるのかもしれません。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね