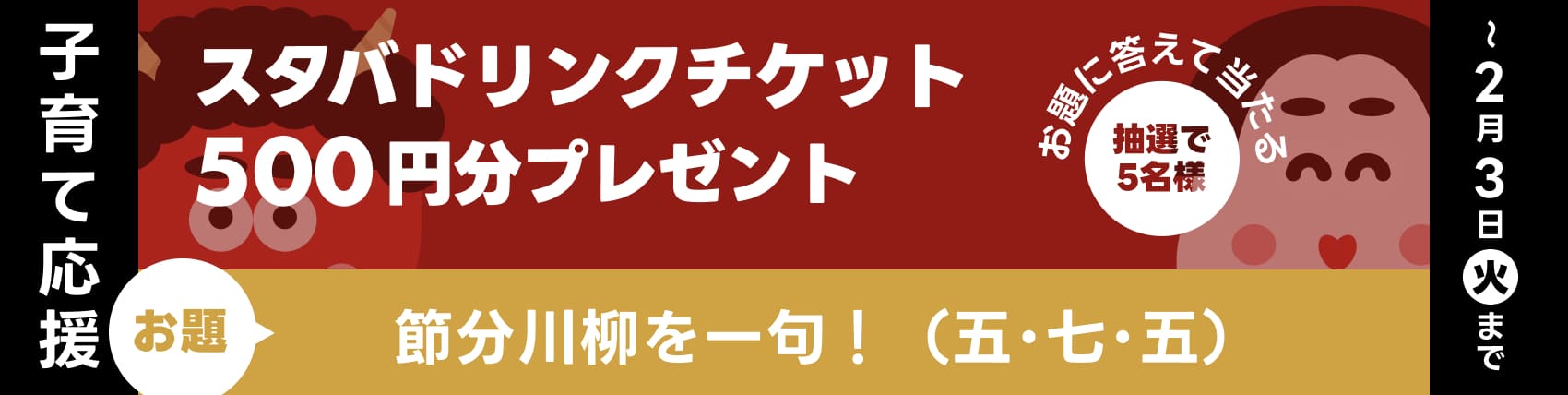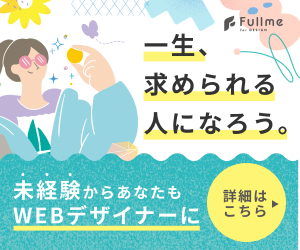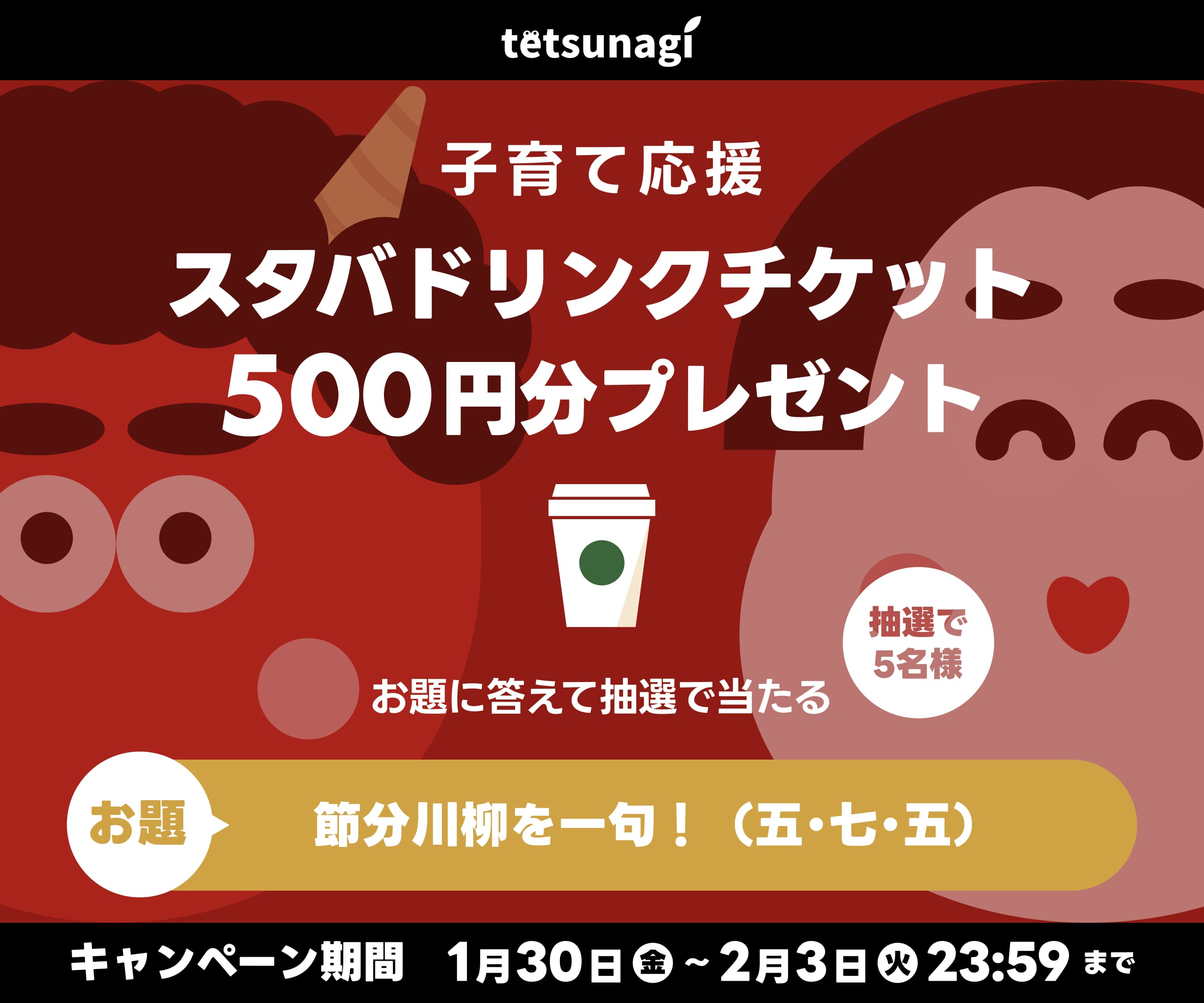子どもの自己肯定感を上げる最善の方法!基本から実践まで徹底解説
親子の日常の中で自己肯定感を育てる
しつけ/育児

子どもの自己肯定感を上げる最善の方法!基本から実践まで徹底解説
こんにちは、あずみのこです。
「うちの子、すぐ自信なくすなぁ...」「ちょっと注意しただけですごい落ち込むし...」そんなふうに感じたこと、ありませんか?
最近よく耳にする「自己肯定感」という言葉。でも、いざ「どうやって育てたらいいんだろう?」と考えると、なにが正解か分からなくてモヤモヤしてしまうこともありますよね。わたしも、子どもが「やっぱ無理...」と諦めそうな時に、どんな言葉をかけたらよかったのか悩んだことが何度もあります。
実際に、てつなぎの掲示板でも、日々こんな声が寄せられています。
そんなふうに悩みながらも子どもと向き合う姿を見て、わたしも何度も「自分だけじゃないんだな」と背中を押されてきました。
ちなみに、こども家庭庁が2024年6月に公表した調査(令和5年度)では、「自分に満足している」と答えた日本の子どもはたったの27.6%。これはOECD11か国中で最も低い水準なんだそうです【出典: こども家庭庁】。
一方で、国立青少年教育振興機構の調査では、自然体験が豊富だったり、生活リズムが整っていたりするほど自己肯定感が高い傾向にあることが示されています【出典: 国立青少年教育振興機構「子どもの頃の体験が自己肯定感に与える影響に関する調査」(令和3年)】。
つまり、特別なことじゃなくて、日々のちいさな体験や関わりが「わたし、大丈夫かも」と思える心の土台をつくっていくのかもしれません。そんな“心の根っこ”を育てていくヒントを、いっしょに探していきましょう。
この記事では、「自己肯定感ってそもそも何?」「家庭でできる具体的な関わりって?」という疑問に寄り添いながら、親子の日常の中で自己肯定感を育てるヒントや、失敗への寄り添い方、声かけの工夫などをわかりやすくまとめました。すぐに実践できるアイデアも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
無理せず、できることから。そんな気持ちで読み進めてもらえたらうれしいです。
自己肯定感とは何か?子どもにとって重要な理由
自己肯定感って、よく聞くけれど、「実際どんな意味なの?」「子どもにとってどんな力になるの?」と感じたことはありませんか?
自己肯定感とは、「できる・できないに関係なく、このままの自分で大丈夫」と思える気持ちのこと。ありのままの自分を受け止め、「わたしはわたしでいい」と思える“心の土台”です。
この考え方は、アメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズが提唱した「self-esteem(セルフ・エスティーム)」に端を発し、100年以上にわたり心理学や教育の分野で大切にされてきました。
では、なぜ子どもにとって自己肯定感が重要なのでしょうか?
それは、自己肯定感が育っていると、子どもは失敗を必要以上に恐れず、「やってみよう」「次はこうしてみよう」と前向きに行動できるようになるからです。また、困難な状況に出会っても「自分なら乗り越えられるかも」と思える、心のしなやかさも育っていきます。
実際、日本の研究でも、自己肯定感を高める授業を受けた小学生に「自分の気持ちを言えるようになった」「友だちと協力できるようになった」といった変化が見られたと報告されています(阿部ほか, 2021『人間環境学研究』)【出典:J-STAGE】。
つまり、自己肯定感は、子どもが「挑戦する力」「人と関わる力」「困難を乗り越える力」のすべての土台となる大切な感覚なんです。

子どもの成長と自己肯定感の深い関係
子ども時代は、「自分ってどんな人なんだろう?」と少しずつ自分を知っていく、大切な時間です。この時期に育まれる自己肯定感は、まるで“心の根っこ”のようなもの。ぐらつきやすい時期だからこそ、この根っこがしっかりしていることで、子どもはぐんと伸びていきます。
自己肯定感が育っている子は、自分の思いや行動を素直に受け止めることができて、「やってみよう」と思える前向きな姿勢が自然と身についていきます。勉強でつまずいたときも、「やればできるかもしれない」と感じたり、友だちとのすれ違いにも「話してみようかな」と一歩を踏み出せたり。失敗したとしても、「また次がある」と気持ちを切り替える力を少しずつ育てていけるのです。
自己肯定感が高い子どもは、このような小さな成功体験を積み重ねることで、「自分には乗り越える力がある」と信じられるようになり、次も新しいチャレンジを怖がらずに試してみるという好循環が生まれやすいと言われています。
こうした積み重ねが、学習意欲や人間関係、そして気持ちの回復力にも、じわじわと良い影響を与えていくんですね。
子どもの自己肯定感が高い子・低い子の特徴
自己肯定感って、目には見えないけれど、子どものちょっとしたしぐさや言葉に、ふわっと表れてくるんですよね。
「やってみる!」と前向きに挑戦する子もいれば、「どうせムリ…」とすぐにあきらめてしまう子もいます。その違いって、実はこれまでの関わりや、日々の小さな経験の積み重ねから生まれていることが多いんです。
たとえば、何かができたときに「がんばったね」「うれしいね」って声をかけてもらった経験が積み重なると、その後も「やってみようかな」と思いやすくなるもの。反対に、うまくいかなかったときに「なんでできないの?」「また?」と責められることが続くと、「自分なんて…」って気持ちになってしまうこともあります。
わたしもこれまで、たくさんの保護者の方とお話してきましたが、「うちの子、自信がなくて…」という声は本当によく聞きます。でも、自己肯定感って、生まれつきじゃないんですよね。あとからでも、関わり方や経験のなかで、ちゃんと育っていくものなんです。
「もう遅いんじゃないかな…」なんて思わなくて大丈夫。子どもはもちろん、わたしたち大人も一緒に少しずつ育てていける力です。どんなときにニコッと笑うのか、どんな言葉をかけたらホッとしているかなど、そんな“ちいさなサイン”に気づくことが、自己肯定感の芽を育てる第一歩になります。今日から、できることから、ゆっくり始めていきましょう。

自己肯定感が高い子どもの特徴
自己肯定感が高い子って、「ま、なんとかなるかも」と前向きに考えられる力を持っていることが多いです。 たとえば、自由研究で初めての実験に挑戦した小学生が、「うまくいかなかったけど、次はこうしてみようかな」と自分なりに工夫をくり返していたり。 絵を描くのが好きな子が、うまく描けなかった日にも「また今度チャレンジしよっと」と自然に切り替えていたり。
そんな姿を見ていると、自己肯定感って「うまくいった自分」を誇るだけじゃなく、「うまくいかなかったときの自分」も受け止められる力なんだなぁと感じます。
では、その力はどこから育まれるのでしょうか。
文部科学省が行った分析では、「先生が認めてくれる」「家の人にほめられる」と感じている子どもたちは、「自分には自分らしさがある」「長所がある」など、自己有用感や満足度の意識が高い傾向があるとされています【出典:文部科学省「教育再生実行会議 第十次提言 参考資料」資料3-2, 2015年】。
つまり、「自分は大切にされている」「ちゃんと見てもらえている」と感じられる関わりの中で、子どもは安心して自分らしくいられるようになり、少しずつ「大丈夫」と思える気持ちが育っていくのかもしれません。
自己肯定感が低い子どもの特徴
反対に、自己肯定感がちょっと低めの子は、ほんの少しの失敗や注意でも「自分なんて…」と落ち込んでしまう傾向があります。 たとえば、「また間違えた…やっぱりダメだ」とつぶやいたり、発表の前に「どうせ笑われるし」と自信をなくしてしまったり。小さなつまずきが、「自分には価値がない」と感じる引き金になってしまうことも。
まわりの目を気にしすぎて、自分を責めすぎたり、新しいことに挑戦するのを避けてしまったりする様子が見られたら、それは心のサインかもしれません。
「うちの子、最近なんだか自信がなさそう…」そんなふうに感じるときは、「がんばったね」よりも、「そのままで大丈夫だよ」というひとことのほうが、子どもの心にやさしく届くのかもしれません。
大事なのは、“今ここ”の状態を見つめること
お子さんの今の姿が、自己肯定感が高い子に近くても、そうでなくても、それが「ずっとこのまま」というわけではありません。
日々のなかで、「ちょっとできた」「わかってくれる人がいた」といった経験が積み重なることで、子どもは少しずつ「自分って、けっこういけるかも」と思えるようになっていきます。
そして、わたしたち大人も、「また怒っちゃったな…」「ちょっと比べすぎたかも」と感じる日があっても大丈夫。そうやって“気づけた”ことこそが、変化のはじまりです。
子どもの“心の根っこ”を育てる時間は、実は、大人自身が「わたしも、これでいいかも」って自分を信じ直していくプロセスなのかもしれません。
自己肯定感が低下する原因と親の影響
子どもの自己肯定感が下がってしまう背景には、実は、家庭の中での“ちいさな関わり”が大きく影響していると言われています。たとえば、「また忘れたの?」「どうしてできないの?」などと否定的な言葉をつい口にしてしまったあと、ふと子どもの表情が曇っていることに気づいて、ハッとしたことはありませんか?わたし自身も、忙しさや疲れで余裕がないときほど、あとから「もう少し言い方があったかも…」と後悔することがあります。
自己肯定感というのは、「このままの自分でいいんだ」と思える心の土台。文部科学省の調査でも、家庭でのあたたかいまなざしや声かけが、子どもの自己肯定感に深く関係していることが報告されています【出典:文部科学省「教育再生実行会議 第十次提言 参考資料」資料3-2, 2015年】。
とくに気をつけたいのが、「比べる言葉」や「感情的な叱り方」が続いてしまうこと。他人との比較や結果ばかりを強調されると、子どもは「失敗しちゃダメなんだ」「ちゃんとやらないと認めてもらえない」と思い込みやすくなります。
文部科学省の審議会資料でも「他者からの評価が過度になると、自らの良さを見失い、自己表現や挑戦する意欲を弱める可能性がある」と指摘されています【出典:無藤 隆(2015)「育成すべき資質・能力とは」中央教育審議会 教育課程企画特別部会資料7-1】。
そうした関わりが続くと、子どもは「どうせムリ」「がんばっても認められない」と感じて、自信をなくしてしまいます。でも反対に、「あなたらしくていいよ」「ここまで頑張ったね」と声をかけてもらえた経験は、子どもの中に「自分を認める力」を育ててくれます。
日々のちょっとした関わりが、自己肯定感の芽を育てている—。そんな視点で、わたしたちも子どもに寄り添っていけたらいいですね。

言葉がけや“さりげない比較”の落とし穴
「うちは毎日ピアノの練習させたいんだけど、『あの子はちゃんとやってるのに…』って、思っちゃって…」以前、そんなふうに話してくれた保護者の方がいました。
きっと、悪気なんてまったくないんですよね。ただ、「わが子にも頑張ってほしい」「できた喜びを味わってほしい」という、そんな親心から出た言葉なんだと思います。
最近では、「○○ちゃんはできるのに、なんであなたは…?」みたいな“ストレートな比較”は減ってきているかもしれません。でも、「○○くんは忘れ物しないんだって」「△△ちゃんは毎日ちゃんと練習してるみたいよ」…そんな、なんとなくの一言が、子どもの心には意外と残っていたりするんですよね。
ほんのささいな言葉でも、子どもはとても敏感です。「また比べられた」「あの子みたいにならないとダメなのかな」そんなふうに感じてしまうことって、案外多いんじゃないかなと思います。
だからこそ、「あの子と比べてどうか」ではなくて、「あなたはどう感じた?」「今日もがんばってたね」そんなふうに、子ども自身にちゃんと目を向けた言葉を届けていけたらいいなって思うんです。
「自分は自分でいいんだ」というその感覚こそが、子どもが自分らしく歩いていくための、いちばんの安心材料になるんじゃないかなって感じています。
叱り方・ほめ方のアンバランスが招く問題
愛情をもって叱ることって、ぜんぜん悪いことじゃないと思うんですよね。ただ、それが多くなりすぎちゃうと、子どもはだんだん「また怒られた」「自分ってやっぱりダメなんだな」って感じることもあります。逆に、がんばってもあんまり気づいてもらえなかったり、結果だけ見られたりすると、「どうせ努力しても意味ないし…」って、力を抜いちゃうこともあるんですよね。
でもね、たとえばこんなふうに声をかけるだけで、子どもの気持ちがふっと軽くなることがあるんですよ。
✗「なんで100点じゃなかったの?」
〇「まちがえたところ、自分で気づいて直せたんだね。すごいね」
こんなふうに、結果よりも「どんなふうに頑張ったか」とか「ちょっとでも成長した部分」に目を向けてあげると、子どもは「わたし、けっこうやれてるかも」って思えるようになるんじゃないかと思います。
叱るときも、「あなたが悪い!」じゃなくて、「あのとき、どうすればよかったかな?」って、一緒に考える感じで声をかけてあげると、子どもも「次はこうしてみよう」って思いやすくなります。
もちろん、わたしたち大人だって、毎日がんばってるからこそ、つい感情的になっちゃうこともあるし、「言いすぎちゃったかも…」って後悔する日もありますよね。でも、そうやって立ち止まれること自体が、子どものことをちゃんと見ている証なんだと思います。
叱るのも、ほめるのも、関わり方は日々の中でちょっとずつ育てていけるもの。そうやって、子どもの心の“土”を少しずつ耕していけたら、それだけで、ほんとうにすてきなことだなって思います。
子どもの自己肯定感を高める具体的アプローチ
「うちの子、最近なんだか自信なさそう...」そんなふうに感じること、ありませんか?
自己肯定感って、なにか特別なことじゃなくて、「ぼくって、これでいいのかな」「わたしも、やってみたいな」と思える、小さな“心の土台”のようなもの。じゃあその土台って、いったいどうやって育つんでしょう?
わたし自身、子育てを通して気づいたのは、やっぱり「日々のやりとりの積み重ね」が何より大きい」ということでした。たとえば、子どもが話しかけてきたときに「うんうん、それでどうしたの?」と目を見て聞いてみたり。「このプリント、◯◯の部分、がんばったんだよね」と、努力に気づいて声をかけてみること。
そんなふうに、“がんばり”に気づいてもらえた経験って、子どもの中に「ちゃんと見てもらえてる」っていう感覚を育ててくれるんですよね。それはわたし自身も、日々の子育ての中で、じわじわと実感していることです。
もちろん、毎回そんなふうに関われるわけじゃないし、余裕がない日はつい流してしまうこともあります。でも、「今日はちょっと意識して声をかけてみようかな」と思えた日には、親子の空気がふわっとやわらかくなるー。そんな小さな変化を、ついつい見過ごしてしまいがちだからこそ、意識して丁寧に関わってみる。それこそが、自己肯定感の“芽”を育てることにつながるんじゃないかと思います。

プロセス重視のほめ方と声かけ
「頑張ったね」って言葉は、多分みなさんも日頃からよく使うと思います。わたしも以前は、それだけで十分伝わってると思ってたんですよね。でもあるとき、「どこをがんばったって思ったんだろう?」ってふと考えてみたら、声かけの仕方がちょっと変わってきました。
たとえば、「最初はわからなかったけど、自分で調べてたよね」とか、「途中であきらめずにやりきったの、見てたよ」って伝えると、子どもがちょっと照れくさそうにしながらも、うれしそうな顔をするんです。「ちゃんと見ててくれたんだ」って感じてくれたのかな、って。
たとえうまくいかなかったときでも、「ここは工夫してたね」とか「途中で変えてみたんだね」って声をかけてみると、子ども自身も「そこに気づいてもらえた」って感じるみたいで、落ち込みすぎずに前を向けるんですよね。
大事なのは、結果よりも“そこに至るまでのプロセス”に目を向けること。一度きりじゃなくて、日常のなかで少しずつ意識していくと、「やってみようかな」って気持ちが育っていくように感じます。
ほめるって、ただ褒めちぎることじゃなくて、「ちゃんと見てるよ」「そこ、大事だと思ったよ」って伝えることなんだなって、思っています。
失敗や挫折への向き合い方
うまくいかなかったときって、つい言いたくなる言葉、ありますよね。「だから言ったのに…!」とか、「なんでちゃんとやらなかったの?」とか。
でも、たいてい本人がいちばん、分かっていたりするんですよね。「ああ、やっちゃったな…」って。そんなときにさらに責められてしまうと、「もうダメかも」って、心がしぼんでしまうこともありますよね。
失敗って、だれにでもあるものだし、完璧にできる子なんて、どこにもいません。だからこそ大事なのは、うまくいかなかったあとにどう向き合うか。「じゃあ次は、どうしてみようか?」そんなふうに一緒に考えること。それだけでも、子どものなかに少しずつ“前に進む力”が育っていくように感じています。
そして、そういうやりとりの積み重ねが、「自分って、大丈夫かもしれない」そんなふうに思える心の土台——つまり、自己肯定感を育てていくのかな、と思っています。
親自身の自己肯定感を保つ工夫
「また怒っちゃったな…」「ちゃんとできてない気がする」そんなふうに感じる日、きっと誰にでもありますよね。わたしもよくあります。 でも、そんなときこそ、心の中でこうつぶやいてみてほしいんです。「今日も、なんとか一日やりきった。えらいよ、わたし」って。
完璧じゃなくていいんです。うまくできなかったことがあっても、立ち止まって、また進もうとしている。それだけで、もう十分にすごいこと。
親が自分を認める姿や、ちょっと失敗しても「じゃあ次はこうしてみよう」と立ち直る姿。疲れたら休むことを選べる姿勢。そういう日々の姿って、子どもにとってとても大きな学びなんですよね。
2024年にNTTデータ経営研究所が実施した報告書でも、親の心の状態や家庭での安心感が、子どもの発達や自己肯定感に深く関係していることが報告されています。【出典:NTTデータ経営研究所『子どもの健やかな育ちと親のこころに関する調査』2024年】
でもだからといって、「親がいつも穏やかで、心に余裕がなきゃいけない」なんて思わなくて大丈夫。わたし自身も、そんなふうに理想と現実の間で揺れる日々です。大切なのは、“余裕がないときにどうするか”を少しだけ意識してみること。落ち込んだときに「わたしも疲れてるな」と気づいて、ひと息つくこと。それも、子どもにとっての安心になることがあります。
親自身が自分を認め、心の余裕を少しでも取り戻そうとすること。それは、子どもにとって“安心できる土台”にもなっていくはずです。だから まずは、自分自身にもやさしくしてあげてくださいね。それが、子どもの心にも、じんわりと伝わっていくと信じています。

文部科学省推奨!家庭や学校で実践できる取り組み
文部科学省がすすめている方法のなかには、家庭や学校で今日から取り入れられるヒントがたくさんあります。 たとえば、家での小さなお手伝いをお願いしてみるのもおすすめです。洗濯物をたたむ、ごはんの準備を手伝うなど、そういう小さな役割が、「自分って頼りにされてるんだ」と思えるきっかけになります。
国立青少年教育振興機構の調査でも、「手伝いをしている」と回答した子どもほど、自己肯定感が高い傾向にあることが示されています【出典: 国立青少年教育振興機構『子どもの体験活動等に関する意識調査』2021年】
学校でも、ただ結果だけを見るのではなく、「ここまでがんばったね」とプロセスを認めてもらえるような関わりがあると、子どもは安心して挑戦できるようになるんですよね。
さらに、自然のなかで体を動かしたり、文化的な体験を楽しんだりすることも、自分の世界を広げる大事な時間です。「こんなこともできた」「知らなかったことを知れた」と、そんな気づきの積み重ねが、自己肯定感の土台を育ててくれるのだと思います。
周囲の力を活用する!学習塾や習い事の選び方
塾や習いごとを考えるときって、続けられるかとか、できる・できないに目がいきがちですよね。でも実は、「その子らしさを活かせるかどうか」っていう視点も、とっても大切なんじゃないかなと思うんです。
たとえば、「これ、やってみたい!」と子ども自身がワクワクするような内容だったら、自然と前向きな気持ちになれるし、「通いたい!」という気持ちが続きやすくなります。その「やってみたい」の中に、思いがけない“成長のチャンス” がひそんでいることもありますよね。
それと、教えてくれる先生との相性も、すごく大事なポイント。できたことを一緒に喜んでくれたり、「がんばってるね」って声をかけてくれる大人がそばにいるだけで、子どもは安心して挑戦できるようになります。
逆に、「順位」や「成績」ばかりが評価の中心になってしまうと、「自分はこれじゃダメなのかも…」って、自信をなくしてしまうことも。だからこそ、子どもの性格やペースに合った環境を選んであげることが、その子らしさを伸ばすいちばんの近道かもしれません。
親が「ここなら大丈夫」と思える場が見つかると、きっとその安心感は、子どもにもじんわり伝わっていくはずです。
まとめ:子どもの内なる力を引き出し、未来を輝かせるために
子どもが「自分って大丈夫」と思える気持ち—。それが、自己肯定感の土台です。その感覚があれば、失敗しても「もう一回やってみよう」と前を向く力になりますし、自分の可能性を信じて歩いていけるようになります。家庭や学校など、子どもが日々過ごす場所でこそ、「そのままの自分でいていい」と思える関係性が少しずつ育まれていきます。
そのためにできることは、大きなことじゃなくていいんです。子どもの小さなつぶやきに耳を傾けたり、「ここまでよくがんばったね」と、結果ではなくプロセスに目を向けたり。そんなひとつひとつの関わりが、子どもの心をそっと支えてくれます。
もちろん、わたしたち親だって完璧じゃありません。怒りすぎてしまう日もあるし、余裕がなくて反省ばかりの日もあります。それでも、「じゃあ次はどうしようか」と一緒に考えられたら、それだけで十分です。
そしてもうひとつ、大事にしたいこと。わたしたち大人が、自分らしく毎日を過ごしている姿も、子どもにとっては大きなメッセージになるんだと思います。うまくいかない日があっても、笑ったり、工夫したりしながら生きていく姿—。それがきっと、子どもの心のどこかに、そっと残っていくはずです。
自己肯定感を育てる取り組みは、特別なことじゃなく、毎日の暮らしの中にある小さな積み重ね。あせらず、比べず、ひとつずつ。子どもが「わたしって、これでいいんだ」と思える未来に向かって、一緒に歩んでいけたらいいですね。
今日も、ここまで読んでくださったあなたは、きっと子どものことを思って、いろんな気持ちと向き合っているのだと思います。うまくいかない日があっても、その中で「どうにかしたい」と感じる気持ちこそが、なによりの愛情です。
どうか、自分自身のことも大切にしながら。ゆっくりで、大丈夫。わたしも、となりを歩いています。
—— あずみのこ
てつなぎ編集部
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね