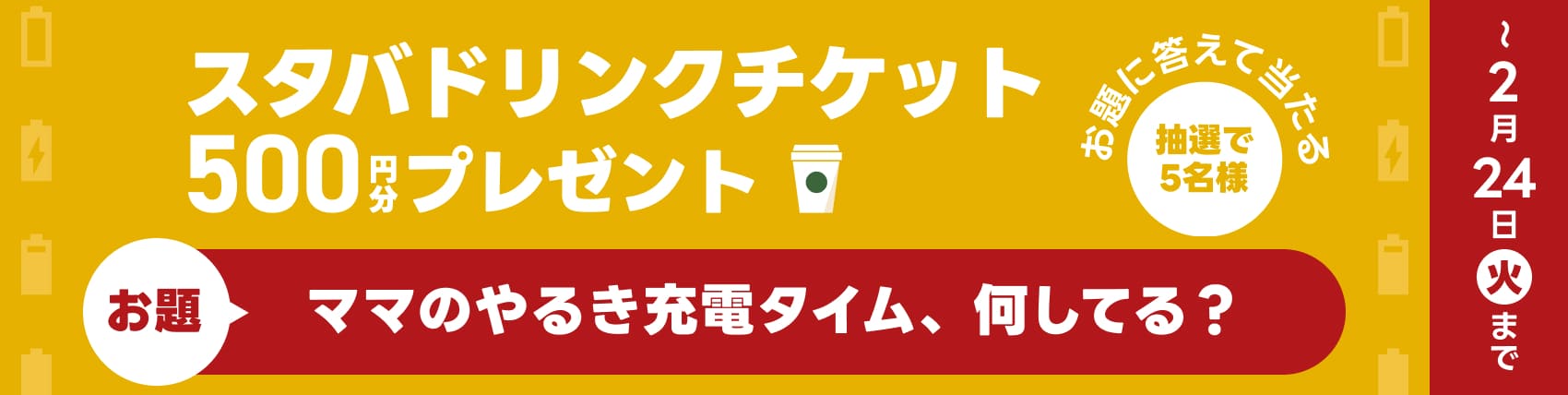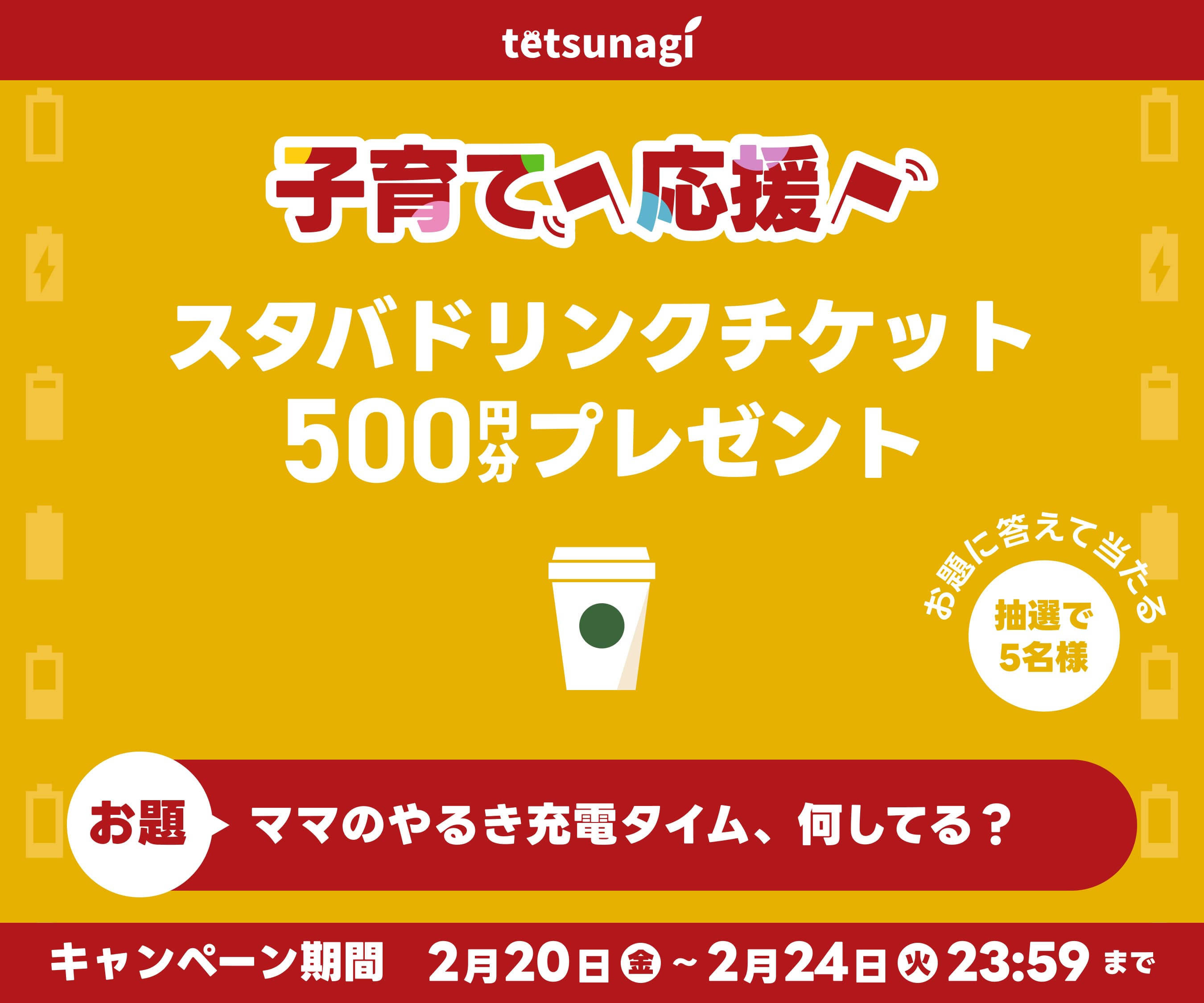うちの子にスマホを持たせる前に ⎯ 小学生のLINEあるあるトラブルと親の関わり方(第2回)
LINEトラブルが起きたときの保護者ができるサポートのコツと安心して使える工夫
人間関係

うちの子にスマホを持たせる前に ⎯ 小学生のLINEあるあるトラブルと親の関わり方(第2回)
こんにちは、多様な教育ナビゲーター・あずみのこです。
15年以上子育て支援に携わり、2人の小中学生を育てる現役共働きママの視点から、コラムをお届けしています。
本コラムは「うちの子にスマホを持たせる前に――小学生のLINEあるあるトラブルと親の関わり方(第1回)」の続編コラムになります。
スマホやSNSが当たり前になった今、「そろそろ子どもにもスマホを…」と悩む保護者が増えています。特に小学生の間ではLINEが友達との連絡手段として定着し、便利さの一方で使い方に不安を感じる声も多く聞かれます。
今回のコラムでは、LINEトラブルが起きたときの保護者ができるサポートのコツをリアルな視点でお伝えします。“禁止”ではなく、“安心して使える工夫”を。親子でネットとのちょうどいい距離感を、いっしょに見つけていきましょう。
親が介入すべきタイミングと対応策
どんなに気をつけていても、LINEでのトラブルって、ある日突然起きてしまうもの。 大切なのは、「早く気づいて、そっと寄り添うこと。たとえば、急にスマホを見せなくなったり、なんとなく元気がなかったり。そんな小さな変化が、“困っているサイン”になることもあります。
詮索しすぎるのは逆効果だけど、放っておくのも心配ですよね。「なんかあった?」と、いつでも子どもが声をかけられる空気をつくっておけるといいですよね。子どもが安心して話せる雰囲気があるだけで、トラブルは大きくなりにくくなります。

トラブル発生のサインを見逃さないために
スマホを見ながらため息をついていたり、学校から帰るなりLINEを気にしていたり。 そんなときは、心の中で何かが起きているサインかもしれません。
うちでも、息子が「別に何もない」と言いながら、明らかにテンションが低い日があって。あとで聞いたら、「グループでちょっとした言い合いがあった」そうです。そういう小さなことでも、子どもにとってはすごく重く感じるんですよね。
「なんか元気ないね」「何かあった?」そんな一言から、子どもがポロッと話してくれることもあると思います。普段から“話せる関係”を作っておくことが、いざという時のいちばんの安心につながる気がします。
子どものプライバシーと安心のバランス
「勝手にスマホを見るのはよくないかな…」 そう感じる方も多いと思います。でも、安全を守るためには、ある程度“見守る範囲”を決めておくことも大切だと思います。「困ったときは一緒に見ようね」「イヤなことがあったら、まず話してね」などと約束をしておくだけでも、子どもは安心すると思います。
親がすべてを把握する必要はありませんが、もし一線を越えそうな時には、“すぐ助け舟を出せる距離”にいること。それが、子どもの自立と安心、どちらも守るための関わり方なのだと思います。
ただ、それでも、家庭だけで抱えるのが難しいケースもあります。次は、いじめや深刻なトラブルが起きたときに、学校や専門機関とどう連携していけばいいのかを見ていきましょう。
いじめ・トラブルが起きたときに:学校や専門機関との連携
LINEをきっかけにしたトラブルやいじめは、どんな家庭でも起こり得ることなので、「うちの子に限って」と抱え込まず、早めに周りの大人とつながることが何より大切だと思います。
まず頼りたいのは、学校やスクールカウンセラーなどの“身近な専門家”。早めに相談することで、子どもの心の傷を小さく抑えられるケースは少なくありません。特に小学生のうちは、家庭と学校が連携して支えることで、当人同士の関係も少しずつほぐれていくことが多いです。
「先生に話したら、かえってややこしくならないかな…」と不安に感じるときは、まず親が先生と話してみるのも一つの方法です。同じクラスの保護者と情報を共有し合うだけでも、見えてくるものがあります。
そして、もし状況が深刻な場合には、外部の専門機関をためらわずに頼ってください。スクールカウンセラーや教育センター、児童相談所など、第三者の視点が入ることで冷静な対応がしやすくなります。
必要に応じて、法的なサポートや心理カウンセリングにつなげることもできます。「相談する=大ごとにする」ではなく、「子どもを守る第一歩」と考えて、どうか一人で抱え込まないでくださいね。

トラブルが起きたときの対処方法
もし子どもがLINEなどのトラブルに巻き込まれてしまったら、まずは慌てずに、落ち着くことを意識してみてください。
そして何より大切なのは、子どもの話をゆっくり聞くことです。「何があったの?」「どんな気持ちだったの?」と、一つひとつの言葉を確かめるように話を聴いていくと、きっと子どもは少しずつ安心して本音を話してくれるようになりますよ。
このとき、「どうしてそんなことしたの!」と責めるよりも、「それはつらかったね」「一緒に考えようか」と寄り添う言葉をかけることが、子どもの心を守る大きな力になります。
また、やり取りの記録を残しておくことも大切です。 LINEのメッセージやスタンプは後から確認できる貴重な証拠になります。必要に応じてスクリーンショットやメッセージ履歴を保存しておくと、学校や専門機関に相談するときに、状況を客観的に伝えやすくなります。
そして、焦って相手の子や保護者に直接連絡を取る前に、いったん深呼吸をして、どう動くのが最善かを学校や専門家と相談してみてください。第三者の冷静な視点が入ることで、感情的なもつれを防ぎ、より穏やかな解決につながることが多いと思います。
冷静な対応が、子どもを守る力になる
トラブルが起きたときに、親が感情的に動いてしまうと、話がこじれたり、子どもが「自分が悪いことを言っちゃったかも」と不安を感じてしまうこともあるので、そんな時こそ親が落ち着いている姿を見せることが、子どもにとって何よりの安心になるのはないかと思います。
まずは深呼吸をして、状況を一緒に整理していきましょう。やり取りの記録を残し、冷静に事実を確認する。その姿勢そのものが、子どもに「大人は味方なんだ」と伝わる大切なメッセージになります。
そして忘れないでほしいのは、「トラブルが起きた=失敗」ではないということ。それは、子どもが人間関係や社会のルールを学んでいく途中の出来事にすぎません。親がそばで寄り添いながら、必要に応じて先生や専門家につなげていくことで、子どもは安心してまた前を向けるようになります。
失敗を責めるのではなく、「次にどう活かせるか」を一緒に考える。その積み重ねが、子どもの“生きる力”を育てていくのだと思います。
そしてもう一つ大切なのは、「トラブルを防ぐ力」を育てていくこと。このあとは、親子で一緒にできるネットリテラシー教育の工夫についてお伝えします。
正しい使い方を学ぶためのネットリテラシー教育
ネットやLINEのトラブルを防ぐためにいちばん大切なのは、 “子ども自身がどう使えば安心か”を少しずつ知っていくことだと思います。
「冗談のつもりだったのに」「悪気はなかったのに」と、そんなすれ違いが起きてしまうのは、まだ“相手の気持ちを想像する力”を育てている途中だからかもしれません。
たとえばニュースでネットトラブルの話題が出たときや、子どもが友達とのやり取りで少しモヤッとしていたときなどに、「LINEって、どんなときにイヤだなって思う?」と聞いてみるなど、そんなふうに“ついでの会話”として話してみるのがおすすめです。
正面から「ルールを守りなさい」と言うよりも、自然な会話の中で気づきを促すほうが、子どもの心にも届きやすいように感じます。
そして、もうひとつ伝えておきたいのが「情報は残る」ということ。ネットに出した言葉や写真は、消しても完全にはなくならない。「これ、誰かに見られても大丈夫かな?」と、そんな“ひと呼吸”を置く習慣が、子ども自身を守る力につながっていくのだと思います。

SNSのメリット・デメリットを理解する
ここまで読んで、「やっぱりSNSって怖い」と感じた方もいるかもしれません。でも、SNSにはもちろん良い面もたくさんありますよね。
離れて暮らす家族とつながれたり、同じ趣味の友達と出会えたり。LINEで友達と笑い合う時間も、子どもにとって大切な“つながりの経験”ですよね。
ただその一方で、言葉の行き違いがあったり、うその情報を信じてしまったり、気づかないうちにトラブルのきっかけになってしまうこともやっぱりあります。まだ情報を見分ける力が育っている途中だからこそ、「便利さ」と「気をつけること」の両方を伝えていくことが大切だと思います。
使わせない”より、“一緒に学ぶ”。そんな関わり方が、子どもの「自分で判断する力」を育てる第一歩になるのだと思います。
関連するてつなぎ掲示板:子どもが事件やいじめに巻き込まれないように(足あとペタちゃん👣 30代)
オンラインでの言動がもたらす影響を知る
ネットの世界では、顔も声も見えないぶん、言葉が想像以上に強く伝わってしまいがち。リアルでは何気なく言えたひとことも、文字だけになると冷たく感じたり、誤解を生んでしまったり…。そんな経験、きっと誰にでもありますよね。
子どもたちにも「これを言われたら、自分はどう感じるかな?」と、相手の立場を少し想像してみる習慣を持てるといいなと思います。その“想像する力”こそが、ネット上のトラブルを減らすいちばんの近道だと思います。
そしてもう一つ大切なのは、「ネットでもやさしさはちゃんと伝わる」という感覚を、親がそっと伝えていくことじゃないかと思っています。「ありがとう」「ごめんね」「うれしい」。そんな小さな言葉こそが、画面の向こうにいる誰かの心をあたためてくれる気がします。
親がそんな姿勢を日常的に見せながら、子どもと一緒に“言葉のやさしさ”を育てていく。それが、これからの時代を生きる子どもたちにとっての、大きな安心につながっていくのかもしれません。
まとめ:安心してLINEを使いこなし、子どもをトラブルから守ろう
子どもがLINEを使うようになると、 「友達ができたんだ」「自分で連絡を取っているんだ」と、うれしく感じる瞬間もありますよね。その一方で、「ちゃんと使えているかな」「トラブルはないかな」と、不安がよぎることもあると思います。
でも、親が正しい知識を持ち、日常の中でさりげない声をかけていくだけで、その不安は小さくできると思います。家庭と学校がつながって、ルールを共有したり、実際のトラブル事例を学び合ったりすることも大切ですよね。
そして何より、親子の「話せる関係」を日々育てていくこと。それこそが、どんな安全設定よりも、子どもを守るいちばんの力になるのだと思います。
LINEやスマホは、上手に使えば、子どもの世界を広げてくれるもの。 “危ないからやめさせる”ではなく、“どう使えば安心か”を一緒に考えていけたらいいですね。
今日からできる小さな一歩として、「夜はスマホをお休みする時間をつくる」 「困ったときは必ず話す」そんなシンプルな約束から始めてみるのもいいかもしれません。
そして、親だって一人で背負わなくていいんです。「子どものスマホ、これでいいのかな」「LINEのトラブルが心配…」などと不安に感じたときは、てつなぎの掲示板に気持ちを書いてみてください。
きっと「わかるよ」「うちも同じだよ」と、共感してくれる親御さんがたくさんいるはずです。誰かに話すことで、気持ちが軽くなることもあります。
子どもとの関係も、ネットとの付き合い方も、すぐに完璧にはならなくて大丈夫。焦らず、試行錯誤しながら、少しずつ“我が家のペース”を見つけていけたらいいと思います。
今日もうまくできなかった日があっても、「ここまで頑張れた自分」をどうか認めてあげてくださいね。親も子も、ぼちぼちでいい。ゆっくりでも確実に、親子の力は積み重なっていきます。どうか今この瞬間を、あたたかく受けとめながら過ごしていけますように。
多様な教育ナビゲーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね