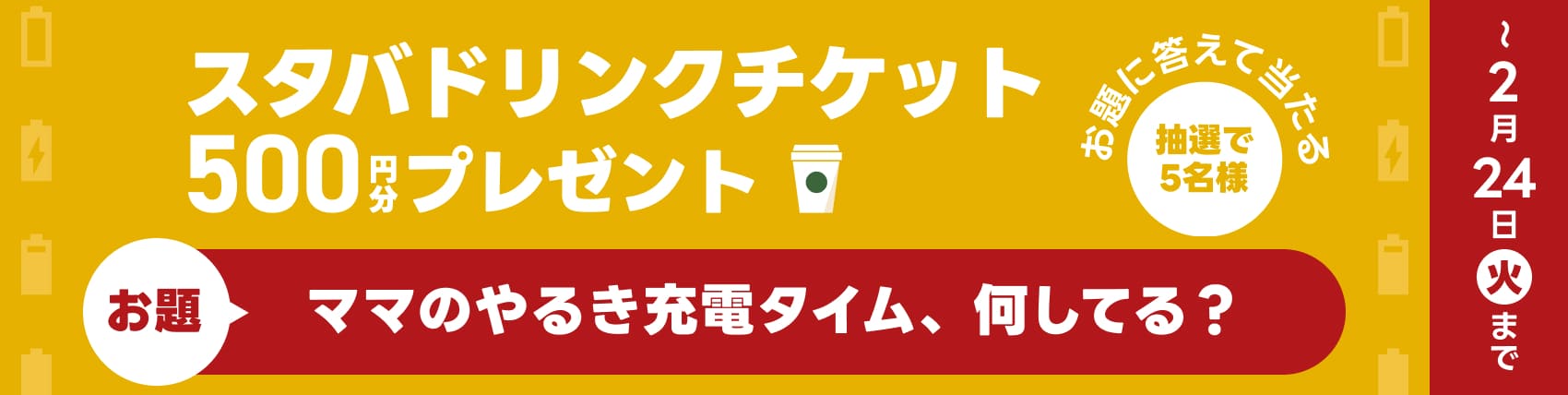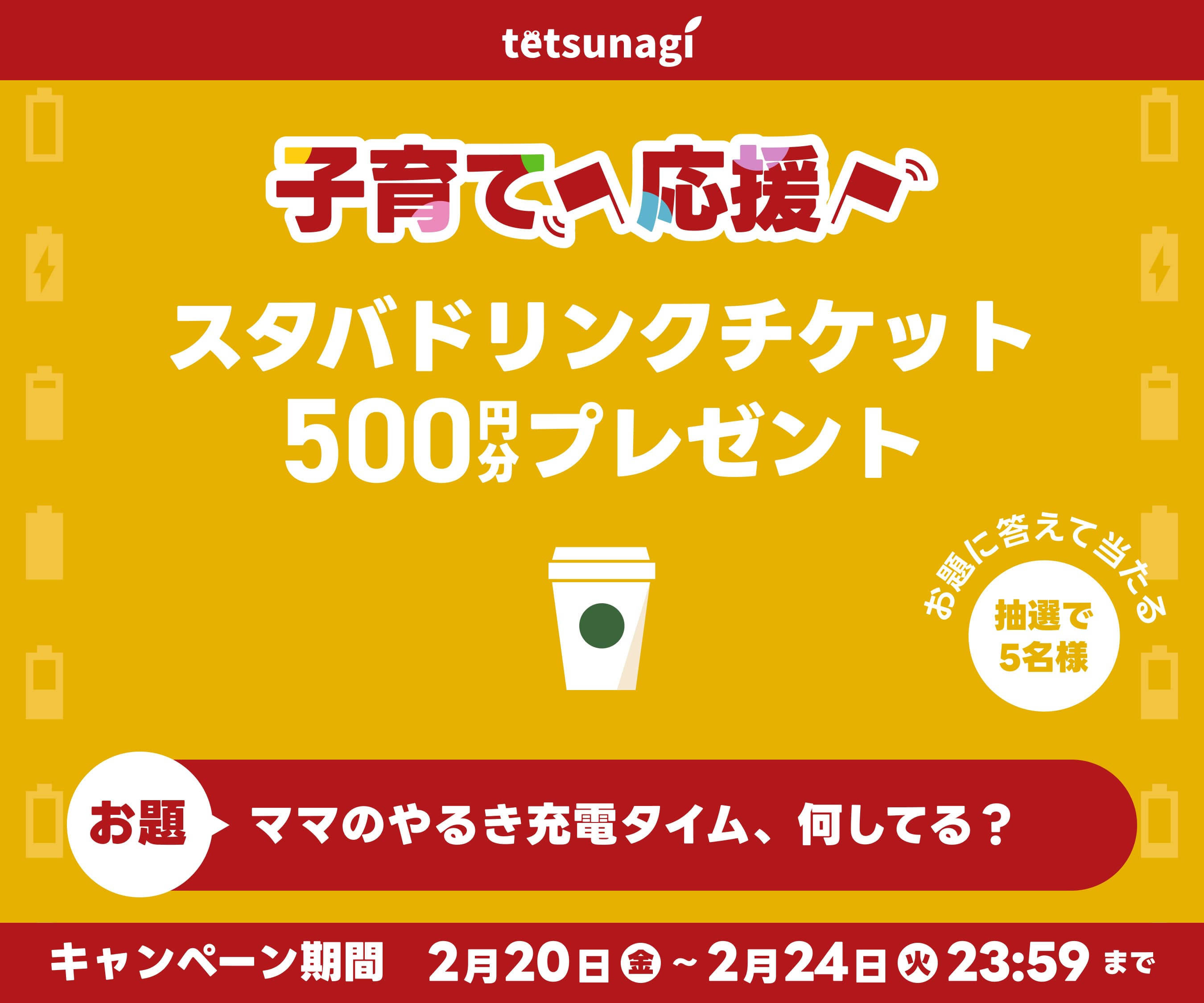うちの子にスマホを持たせる前に ⎯ 小学生のLINEあるあるトラブルと親の関わり方(第1回)
小学生に多いLINEトラブル事例と親が知っておくべきLINEの基本設定
人間関係
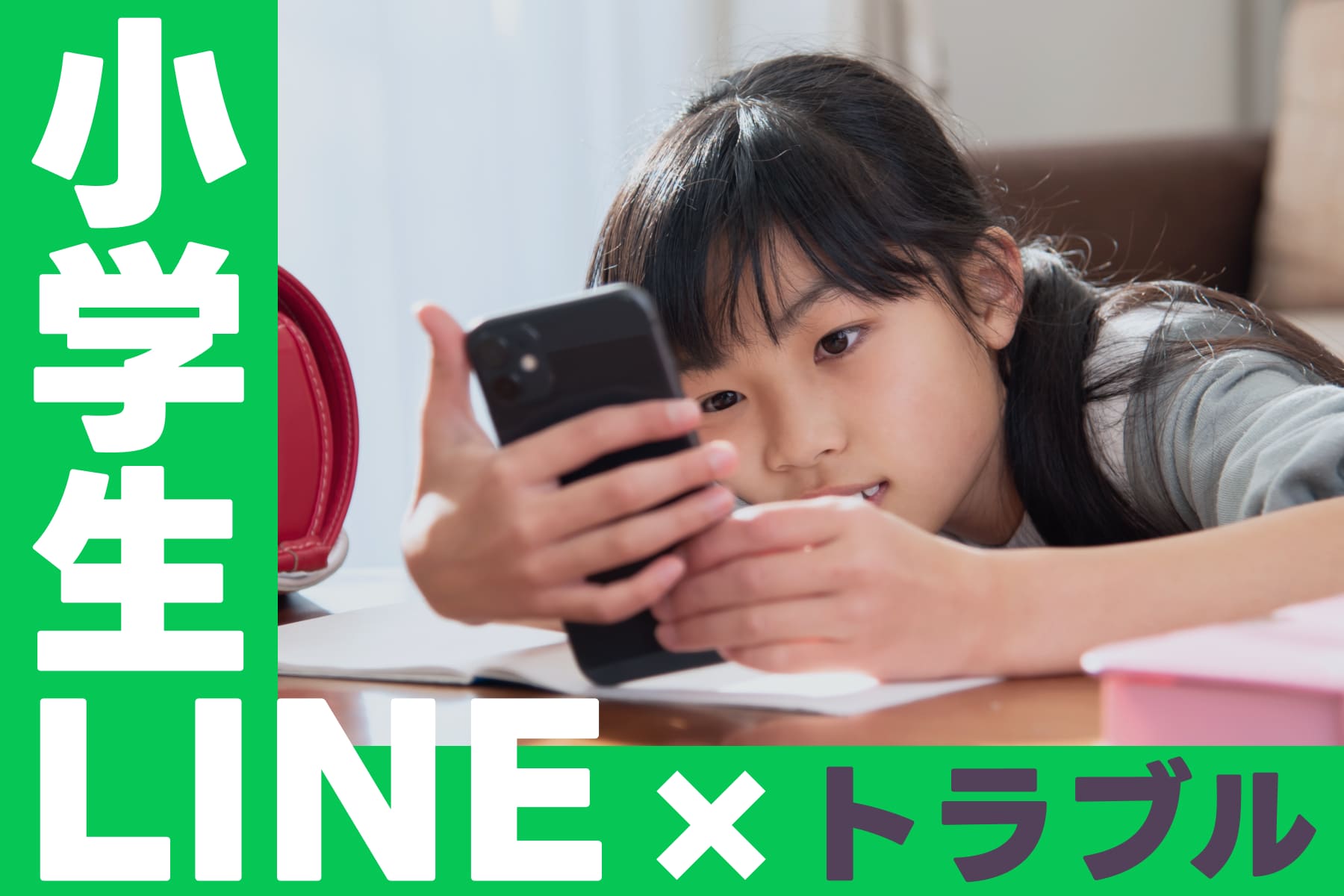
うちの子にスマホを持たせる前に ⎯ 小学生のLINEあるあるトラブルと親の関わり方(第1回)
こんにちは、多様な教育ナビゲーター・あずみのこです。
15年以上子育て支援に携わり、2人の小中学生を育てる現役共働きママの視点から、コラムをお届けしています。
「うちの子にもそろそろスマホを持たせようか…」と悩む保護者の方、最近本当に増えていますよね。スマホやタブレットが身近になり、小学生でもSNSやメッセージアプリを使うのが当たり前の時代。
その中でも特に「LINE」は、友達との連絡や情報共有に欠かせないツールになっています。
気軽にスタンプを送り合ったり、グループで予定を決めたり。便利で楽しい一方で、ちょっとした行き違いが“トラブルのきっかけ”になるという話もよく聞きます。たとえば 「既読をつけたのに返事がない」「グループから外された」「夜遅くまでやり取りして寝不足」など...、どれも“あるある”ですよね。
正直、大人だってグループLINEには気をつかいますよね。通知が止まらず「そろそろ抜けたいな…」と思ったり、既読スルーにも妙な勇気がいったり(笑)。そんな経験をしているからこそ、子どもたちがLINEでつまずく気持ちも、なんとなく想像できます。今、家庭や学校、そして社会全体で「安全な使い方」を“一緒に考えていく”ことが、いちばん大切なのかもしれません。
今回のコラムでは、全2回に渡り、小学生に多いLINEトラブルの実例と防止策、そして保護者ができるサポートのコツを、リアルな視点でお伝えします。“禁止”ではなく、“安心して使える工夫”を。親子でネットとのちょうどいい距離感を、いっしょに見つけていきましょう。
小学生とLINE:普及状況と日常的な使用実態
いまや小学生にとっても“生活の一部”になりつつある「LINE」。「防犯のため」「連絡用に」と持たせたスマホが、いつの間にかメインの用途が“友達とつながるツール”になっていた...。そんなご家庭も多いのではないでしょうか。
便利な一方で、夜遅くまでメッセージが続いてしまうと、睡眠不足や集中力の低下につながることも。やっぱり親にとって、スマホは“安心”と“不安”が混ざる存在ですよね。
我が家でも、「もう寝る時間だよ〜!スマホ終わり!」に「あとちょっとだけー!」のやり取りが恒例です(笑)。ときには、つい言いすぎて反発されたり、“見守るつもりが監視っぽく”なってしまうこともあります。でもやっぱりいちばん大事なのは、「何かあった時に話せる関係」を残しておくことかなと思います。
子どもがスマホを持つようになっても、“話せる親”でいられるように...。そんな思いで、私も日々試行錯誤しています。
みんなの声:あなたにとっての理想の母親像ってなに?

スマホ所持率とSNS環境の現状
ここ数年で、子どもたちのスマホとの付き合い方は本当に変わりましたよね。「みんなLINEやってるよ!」という子どもの言葉に、ドキッとしたことがある方も多いのではないでしょうか。
うちの場合、息子が小5のときに 「まわりみんなやってるからLINEやりたい!」とお願いされて、 “まあ試しに…”とOKしたのですが...結果、数か月でギブアップ。LINEの中での陰口やグループ外しなど、想像以上に陰湿なやり取りが多くて、「これはちょっと距離を置いたほうがいい」と判断し、一度やめてもらったことがありました。その後、様子を見ながら少しずつ話し合いを重ね、家庭でルールを決めて再開しましたが、やっぱり親としての心配は尽きません。
スマホは便利な一方で、使い方しだいで安心にも不安にもなる...。まさに、家庭での向き合い方が問われる時代だと感じます。
🔗関連する掲示板の投稿:グループLINE (三兄妹ママ 30代)
NTTドコモ モバイル社会研究所の調査(2024年1月)によると、小学6年生のスマホ所有率は初めて5割を超え、高学年では4割以上が自分専用のスマホを持っているそうです【※1】。 また、教育ネット総合研究所の「2023年度ネット利用における実態調査」(2024年7月発表)では、小学6年生のLINE利用率が67%と報告されています【※】。「クラスの半分以上がLINEを使っている」という話が、もはや珍しくない時代になりました。
でも、スマホやSNSは、結局“使い方しだい”ですよね。家庭でも学校でも、少しずつルールやマナーを学びながら、子どもが安心して使えるようにサポートしていくことが大切なんだと思います。
家庭では「時間を決めようか」と声をかけたり、学校ではITリテラシーを学ぶ授業があったり。家庭と学校の両方で子どもたちを支えられると心強いですよね。
「見守る」と「任せる」のバランスは本当にむずかしいですが、子どもたちがネットと上手につき合う力を育てるために、親も“いっしょに悩みながら学ぶ姿勢”を持てること。それが、いちばん理想的な形なのかもしれません。
🔗関連する掲示板の投稿:スマホって何を持たせていますか? (中受挑戦中(小5)さん 40代)
通話やグループチャットなどにおける利用方法
小学生のLINEの使い方でよくあるのが、友達どうしのグループチャット。「明日の持ち物なに?」「放課後どこで遊ぶ?」など、まるで教室の続きをスマホの中でしているようですよね。
最近では、LINE通話で話したり、ビデオ通話で顔を見ながら盛り上がったりと、“放課後の延長”のようにオンラインでもつながり続ける子も増えています。
スタンプや写真を送り合う楽しさの一方で、「既読なのに返事がない」「スタンプだけだった」などの小さな行き違いに、気づけばモヤモヤしてしまう子も少なくありません。夜遅くまでグループトークが続き、翌朝つらくなるというそんな光景も、いまや“あるある”ですよね。
親ができるのは、「メッセージを送る前に一呼吸おこうね」といった、さりげない声かけや見守りの姿勢を持つこと。日々のやり取りを通して、子ども自身が「どうすれば心地よく使えるか」を少しずつ学んでいけるといいのではないかと思います。
スマホを通して、子どもたちは人との距離感や思いやり、そして「ことばの選び方」までも学んでいきます。ただその一方で、LINEがきっかけで思わぬトラブルに発展してしまうことも。
次は、実際によくある小学生のLINEトラブルについて見ていきましょう。
よくある小学生のLINEトラブル事例
LINEはとても便利な一方で、ちょっとしたすれ違いが大きなトラブルに発展してしまうこともあります。最近では、低学年の子どもでも同じようなトラブルを経験するケースが増えているようです。
まだ心が成長途中の小学生にとって、相手の気持ちを想像したり、言葉の裏を読み取ったりするのは、なかなか難しいこと。軽い気持ちで送ったメッセージが、思いがけず相手を傷つけてしまった……。そんな話を耳にすることも少なくありません。
ほんの小さなやり取りがきっかけで、仲間外れやいじめにつながってしまうケースも実際にけっこうありますよね。学校で起きているトラブルの背景に、実はLINEでのやり取りが関係していた...そんなことも、もう珍しくなくなってきました。
ここでは、特によく見られるトラブルのタイプをいくつか紹介します。

既読スルー・無視から始まるいじめ
メッセージを読んでも返信がない「既読スルー」。大人なら「忙しいのかな」と受け流せても、小学生にとっては“無視された”ように感じてしまうことも多いようです。
実際には、ただタイミングが合わなかっただけのことも多いのに、まだ気持ちの整理や言葉の距離感が難しい年ごろの子どもにとっては、それだけで「嫌われたのかも」「仲間外れにされたのかな」と、不安がどんどん膨らんでしまうのかもしれません。
特にグループチャットでは、返信が少ない子が“のけものにされた”ように見えてしまうことも。ほんの小さな誤解が、悪口や不信感に変わってしまうこともあるようです。
悪口や陰口の広がりとクラス内不和
チャットでの何気ないひとことが、思いがけず誰かを傷つけてしまうこともよくあります。 冗談のつもりでも、受け取る側の気持ち次第で深く刺さってしまうんですよね。
特に小学生のうちは、まだ言葉の選び方や距離感が難しい時期。悪気はなくても、「○○が言ってたよ」「あの子ちょっと変だよね」なんて会話が、気づけば“陰口のバトン”になってしまうこともあります。
怖いのは、それがスマホの中だけで終わらないこと。たった一言でも、“翌日の学校で気まずくなったり、クラス全体の空気がギクシャクしてしまうこともあるようです。“文字として残る”からこそ、あとから見返してショックを受けたり、友達関係がこじれてしまうケースも少なくありません。
グループ外しや勝手な退会
気に入らない子をグループから外したり、本人に知らせず退会させてしまったり。そんな行為が、子どもたちの世界では思っている以上に大きな傷を残すこともあります。
「気づいたらグループから外されていた」...これ、大人でもつらいですよね。子どもにとってはきっとその何倍もショックが大きいもの。「自分は必要ないんだ」と感じてしまう瞬間も、きっと多くあるのだと思います。顔を合わせていれば言いにくいことも、スマホの画面の中だと“ボタンひとつ”でできてしまう。その手軽さこそが、SNSの難しさでもありますよね。
長時間利用による睡眠不足や学業への影響
グループトークが夜遅くまで続いて、「みんなまだ起きてるから」「返信しないと悪いかな」と、ついスマホを手放せなくなる...。そんな話も、よく聞きますよね。寝るのが遅くなると、翌朝がしんどくて学校でもぼんやり…。そんなふうに生活リズムが乱れると、勉強への意欲まで下がってしまうことにもつながります。
とはいえ、「もう使っちゃダメ!」と完全にやめさせるのは、現実的にはなかなか難しいと思うので、少しずつ“ほどよく使う”方向に近づけていけたらいいと思います。たとえば、「この時間はスマホをお休みしようか」と親子で決めてみるのもいいかもしれません。そんな“お休みの時間”をつくる工夫が、安心してLINEを使うための大事なステップにもなると思います。
次は、そんな「安全な使い方」を支える基本設定について見ていきましょう。
親が知っておくべきLINEの基本設定
子どもがLINEを使い始めるとき、「どこまで設定しておけば安心なんだろう…?」と不安になりませんか?でも実は、ほんの少しの初期設定や安全機能のチェックで、トラブルの多くは防げるんです。
私も最初は「設定ってどこまでやればいいの?」と迷いました。細かいところまですべて把握するのは難しいけれど、“ここだけは押さえておくと安心”という基本のポイントがあります。それが「年齢制限」と「利用ルール」です。

年齢制限・利用制限のポイント
LINEは本来、18歳未満の利用者に対して一部の機能を制限しています。たとえば、年齢認証が済んでいないアカウントでは「ID検索」などが使えません。つまり、「小学生は使えない」というわけではないものの、子どもが安心して使うためには大人のサポートが前提となっています【※3】。
小学生が使う場合は、「どうすれば安全に使えるか」を親子で話し合いながら決めることが重要になってくると思います。
たとえば、スマホを渡す前に「年齢認証をどうするか」「どんな機能を使うか」を確認しておくこと。さらに、「どの時間帯に」「どんな使い方をするか」といったルールも一緒に話し合っておくと安心です。「夜9時以降はお休みにしようか」「知らない人からメッセージが来たら教えてね」など、シンプルな約束で十分だと思います。
大切なのは、“親が決める”よりも“いっしょに考える”こと。子どもって、自分で決めたことのほうが、ちゃんと覚えているものですよね。そんな話し合いの時間こそが、「自分でコントロールする力」を育てるきっかけになるのだと思います。
次に、そんな“設定まわりの安心ポイント”を見ていきましょう。
通知管理とプロフィールの公開範囲
LINEの通知音って、鳴るたびについ反応してしまいますよね。「ピコン♪」が気になって、結局スマホを手に取ってしまう……。これは子どもだけじゃなく、私たち大人にも“あるある”です(笑)。
夜は通知をオフにする、返信の時間を決めるなど、 “スマホとちょうどいい距離”をつくる工夫があるといいかもしれません。
また、プロフィールの公開範囲にも注意が必要です。知らない人から見られないように「友だちのみに設定」し、スタンプや“ひとこと欄”にも個人情報を書かないように意識をもてるといいですね。
こうした小さな設定の積み重ねが、子どもをトラブルから守るための“大きな安心”につながります。そして、親子で設定を確認する時間そのものが、「スマホを一緒に使いこなしていく練習」にもなるのだと思います。
🔗関連する掲示板の投稿:子どもにスマホを持たせるのはいつから? に関する投稿
家庭で決めるべきルールとマナー
「LINEを使わせてみたけれど、このままで大丈夫かな…」と、実際に使い始めてから“思っていた以上に難しい”と感じる方も多いですよね。設定や制限を整えることももちろん大切ですが、家庭の中で“どんな関わり方をするか”を話しておくことも同じくらい大切だと思います。
たとえば、「LINEでイヤな気持ちになったら、どうする?」「友達にどんな言葉をかけたい?」など、“気持ちのやりとり”に目を向けてみる。きっちり決める必要はなくても、「困ったときは話してね」と伝えておくだけでも違う気がします。
LINEとの付き合い方には、「知らない人とのつながり方」「使う時間の区切り方」「言葉の伝え方」など、機能面のルールと心のルールの両方があると思います。
ここからは、そんな“家庭で決めておきたい3つのポイント”を紹介していきます。

連絡先の追加基準と友だち管理
「知らない人から“友だち追加”がきたんだけど…」 子どもからそんな報告を受けたら、ちょっとドキッとしますよね。ネットの世界では、顔が見えない分、相手を“いい人”だと思い込んでしまうこともあるので「知らない人は追加しない」「ID検索はオフにしておく」といった基本設定を、親子で一緒に確認しておくと安心です。
それに加えて、危険な相手や迷惑なメッセージがきたときの対処法も、事前に話しておけると心強いと思います。ブロックや削除の方法を一緒にやってみるだけでも、「困ったときはこうすればいいんだ」と子どもが理解できて、安心につながると思います。
使用時間や通話時間の制限
友だち関係のことと同じくらい、悩ましいのが“使う時間”。「もうそろそろ終わりだよ」の声かけでやめることって、実際むずかしいですよね。 毎回の声かけも、お互いストレスになるものです。
聞くと、最初から「夜はスマホをリビングに置いておく」というルールを決めている家庭も少なくないそうです。 手の届かないところにあるだけで、余計な通知も気にならず、自然と夜更かしを防げるのかもしれませんね。
てつなぎ掲示板にもこんな声が届いています。
スマホにしてから、お友達と何やら毎日楽しそうにしているわけだけど
その中でも、最近すんごーーーくしつこく連絡よこしてくる女の子がいるんよね。笑
一つ上の学年の子なんだけどご飯食べてても、風呂入ってても、宿題してても、ひたすら電話きてる😇まじ、なに?こわい😇
(🔗てつなぎ掲示板|息子にしつこく連絡してくる女子)
こうした“通話が止まらない”トラブルも、LINEあるあるですよね。時間を決めるって、簡単なようで本当に難しい。うちも「もうおしまい!」と言っても聞こえないふりをされたり、「あと5分!」が永遠に続いてますから…(笑)。
でも、そんなやり取りの中で、少しずつ「何時までなら大丈夫そう?」「どんな時はやめにくい?」と話していくうちに、“自分で区切れる力”が育っていくのかもしれませんね。
時間のルールを話し合うこと自体が、子どもが自分で考えて行動する練習にもなっていくのかなと思います。
言葉遣いやスタンプの使い方
スタンプひとつでも、受け取る人の感じ方はさまざま。「ふざけたつもりが、怒ってると思われちゃった…」なんてこと、LINEではよくありますよね。特に文字だけの世界では、伝えたい気持ちと受け取られ方のズレが生まれやすいと思います。
スタンプやメッセージを送る前に、「これ、どう受け取られるかな?」と一呼吸おく。そんな視点を、親が日常の会話の中で少しずつ伝えていくことも大切かなと思います。「気をつけなさい」と注意するより、「もし自分が言われたらどう感じる?」と一緒に考えてみる。その積み重ねが、“言葉を大切にする力”を育てていくのかもしれません。
多様な教育ナビゲーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね