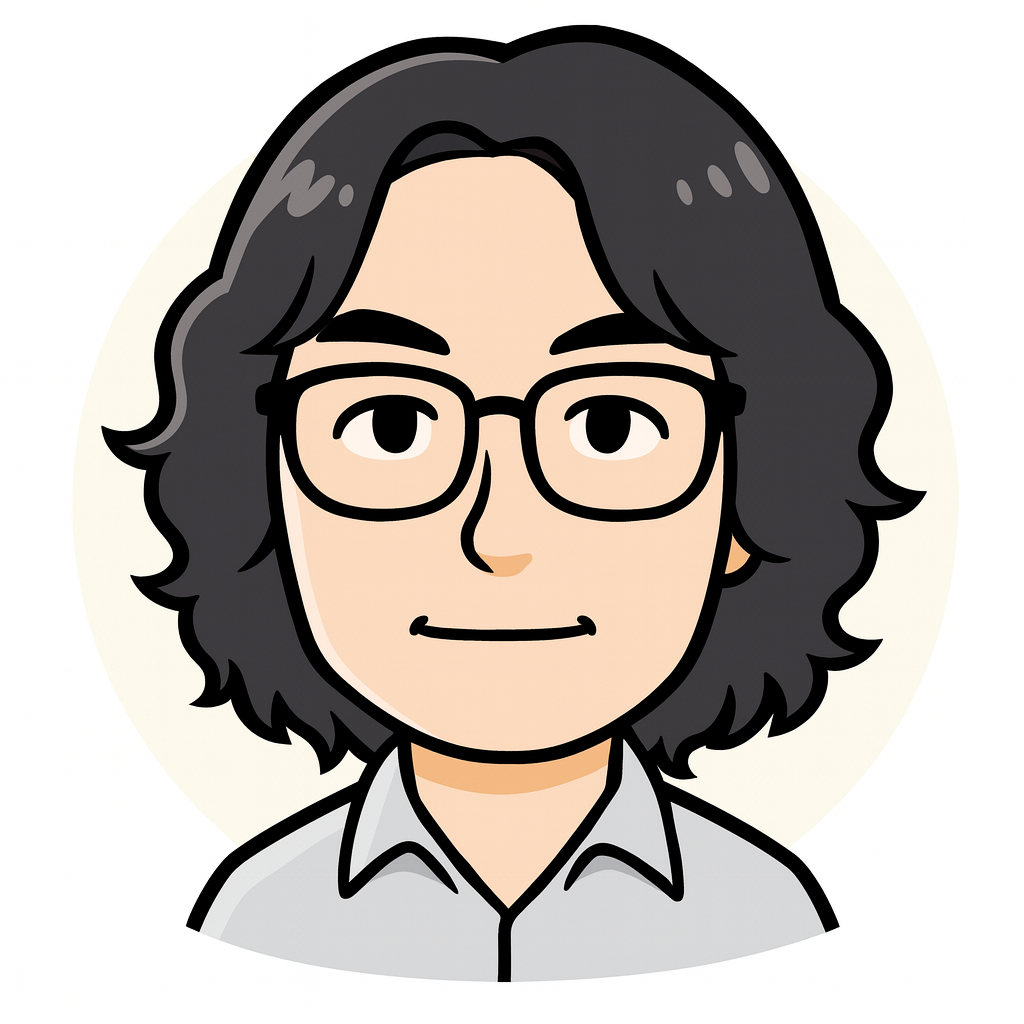【掲示板の声×公認心理師】子どもに『学校に行きたくない』と言われたとき(第2回)
大切なことは“細く長く”学校や社会と繋がっていくこと
インタビュー
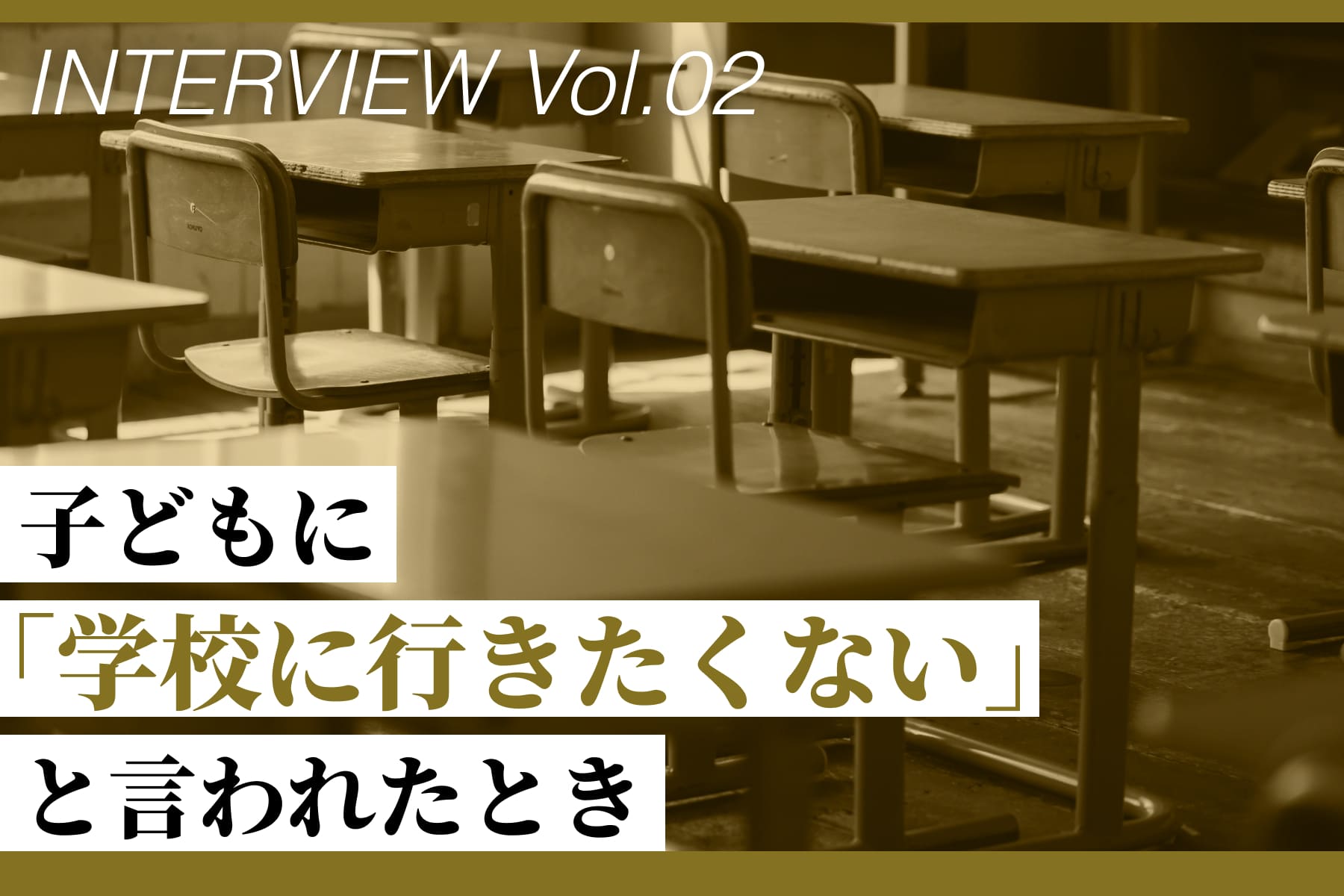
【掲示板の声×公認心理師】子どもに『学校に行きたくない』と言われたとき(第2回)
―不登校の今と、専門家が語る親の対応と声かけ方(公認心理師 / カウンセラー・田村俊作先生インタビュー)
朝、子どもが学校に行けない日が続くと、親としてどうしたらいいのか分からなくなってしまいますよね。「無理にでも行かせるべき?」「そっとしておいた方がいいの?」そんな迷いの中で、心が疲れてしまう方も多いと思います。
文部科学省の令和6年度調査【※1】によると小中学生の不登校児童生徒は過去最多の35万3,970人、高校生を含めると42万人を超える規模と報告されています。
てつなぎ掲示板にも、「子どもが学校に行きたくない」「どう接したらいいかわからない」といった投稿が多く寄せられています。
そんな中、てつなぎ編集部では「公認心理師さんに聞いてみた!」連載コラムをスタート。教育・福祉・メンタルヘルスの現場で約20年間支援を続ける、公認心理師・カウンセラーの田村俊作先生に、“不登校の今と親子の支え方”について伺いました(全3回の第2回/最初から読む)。
不登校は「負け組」じゃない。― 社会の偏見を越えて、子どもの生き方を考える

「不登校=負け組」という偏見と、社会に残る固定観念
このような偏見が残る今の社会で、私たち大人は、不登校への理解や受け止め方をどう広げていけばよいでしょうか?
でも、不登校になったとしても、結局「学校がすべて」じゃないですから。ある種、学校って、生きていくための“過程”でしかない。
じゃあ東大に行ったからっていい会社に入れるかというと、 入れるっちゃ入れるけど、続くかどうかはまた別の話だし。学校って、その人が将来、生活していくための「通過地点」でしかない。
学校の外でも育つ、“自分の力で生きる”ための準備
そのための準備は、学校に行っていなくてもできる。たとえば、好きなことを見つけて続けていくことや、人と関わる中で小さな達成感を積み重ねていくことだって、立派な“社会との関わり方”の時間なんですよ。だから、不登校になったからといって負け組ではないし、敗北者でもないと思います。
よく私たち、「納税者になってもらうことが大事だ」って言うんですよ。つまり、自分でお金を稼いで、自分の力で社会に参加できること。それが将来的にできれば十分。
そのためには、やっぱり、“自分の好きなこと”や“できそうなこと”を見つけていく力、自分の得意・不得意を知って「これならできるな」って客観的に見られる力が大事なんです。それが“実行機能(自分の行動をコントロールして計画的に実行する力)”とか“自己理解”につながる。
だから、「学校に行けるかどうか」よりも、“自分のペースで生きる力”を育てていけることのほうが、よほど大切だと思います。
「不登校」は終わりじゃない ― 新しい生き方を見つける始まり
不登校を「終わり」ではなく「始まり」として捉える視点を持つことが、親にも社会にも求められているのだと感じます。 とはいえ、目の前の子どもが「行きたくない」と言っているとき、親としてはどう対応すればいいのか、迷ったり、悩んだりするのも、保護者のリアルな姿ですよね。
行かせる?休ませる?ー“細く長くつながる”という考え方

実際、不登校や登校しぶりに悩む保護者の中にも、同じように迷う方は多いと思います。「行く・休む」を判断するときの基準や、意識しておくといい視点はありますか?
情緒不安定なときこそ、波があって“行ける・行けないタイミング”もあるだろうから。“細く長く”学校や社会と繋がっていく方がいいかなと思います。
実際、親としては「今日は行けそう」と思えば背中を押したくなるし、逆に子どもの顔を見て「もう無理かも」と感じる日もある。そのたびに、“どこまで関わっていいのか”“押しすぎじゃないか”と迷う親御さんは本当に多いと思います。
どんなときに「もう行かせない方がいい」と判断したらいいんでしょうか?
「もう行かせない方がいい」サイン ― 心や体に出るSOS
学校との連携のコツ ― “無理せず、つながりを保つ”ために
学校の理解がどこまであるかわからないですし、相談室があるかもその学校によりますが、本人のキーパーソンなるような人に「一言伝えておく」だけでも、子どもが安心できるかなと思います。
不登校のとき、学校との関係をどう保つか ― 不信感・転校・相談先の選び方

このように、不登校の子どもをめぐって学校や先生への“不信感”を抱いたとき、保護者はどんなスタンスで関わっていけばよいでしょうか?
学校への“不信感”を抱いたとき ― 無理せず、専門家を頼っていい
できれば、今いる学校の中で、少しでも安心できる関わり方を見つけたい場合、先生のおっしゃる通り、担任の先生だけでなく、スクールカウンセラーや養護教諭など、“少し距離のある立場”の専門家に相談してみるのも一つの方法ですよね。
ただ、それでもやっぱり、「カウンセラーも結局“学校の人”だから相談しづらい」と感じる保護者の声もよく聞きます。
そういった場合、不登校の相談ができる“学校外”のサポート先として、どんな機関を考えればよいでしょうか?
学校の外にも支援の手がある ― 教育相談センターや教育委員会を活用
基本的に、その子にとってどんな生活がいいのか、どんな学校生活がいいのか、そしてその子の人生がどうあるのがいいのか。そこを考えるのがスクールカウンセラーの役割。
ただ、現実的には、対応の仕方にばらつきがあるのも事実です。あとは自治体の教育相談センターや教育委員会などでもいいと思うんですよね。
自治体のカウンセラーがソーシャルワーカーを兼ねていることもありますし、不登校のようなケースでは、ソーシャルワーカーさんがメインで受けるケースも多いと思います。そういった学校の外部のリソースを使うことは、保護者にとっても「一人で抱え込まない」ためにも、とても大事だと思います。
どこに相談すればいい?スクールカウンセラーとソーシャルワーカーの違い
私はもともとスクールソーシャルワーカーがベースで、体感としては6割がその仕事ですね。環境を整えたり、外部機関とつないだりするのが主な役割です。
ただ、最近は兼任している人も多いんですよ。ソーシャルワーカーがカウンセラーのように面談したり、カウンセラーが福祉的な動きをしたり。立場よりも、「その人がどこまで対応できるか」によるところが大きいです。
公認心理師
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね