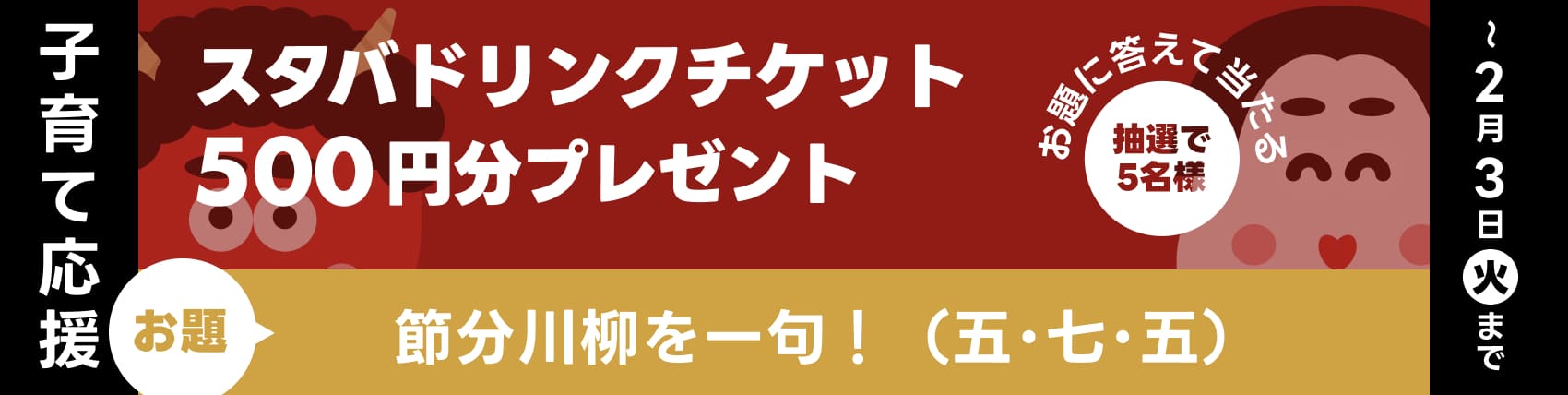不登校児ゼロ教師が伝える――過保護でも放任でもない「ちょうどいい距離感」を見つける
壁に突き当たって苦しいときも、思い通りにならなくて泣きたくなったときも、「子ども日記」は、それを乗り越え、前を向いて歩み続ける皆さんの心強い存在となるでしょう。必要なのは、ノートとペンだけ。子ども日記は「親が子どものために書く日記」です。
学校

7年間不登校児ゼロを実現した元教師が、自身の経験と失敗から編み出した“子ども日記”。親子が心から繋がり、家庭が居場所になる。日記が「幸せな関係」を築くヒントと実践例を多数紹介する一冊。
上村公亮先生著書の『不登校児ゼロ教師が伝える 親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』から一部転載・編集してお届けいたします。
過保護でも放任でもない子どもとの「ちょうどいい距離感」を見つける
小学6年生の息子さんが夏休み明けに不登校になってしまったと、あるお母さんから相談を受けました。
そのお母さんは、お兄さんが小学生のころに私が担任をしていたというご縁があります。
弟さんはもともとHSP(感受性が高く、繊細な人)の傾向はあったのですが、学校には通えていました。
しかし、夏休み中に親御さんが体調を崩して休職することになり、息子さんは「家にいればお母さんと一緒にいられるんだ」と考えるようになったようです。
お母さんとしては、自分を頼ってくれる息子さんが可愛い。
でも、家でずっと一緒にいるのがいいとは思えないし、悩んでいるという相談でした。
私は子ども日記を勧めるのと同時に、「体調が回復したら仕事に戻ってくださいね」と念押ししました。
お互いに依存しているように感じたからです。
一番の問題は、そのお母さんが旦那さんからDVを受けていて、お子さんたちもお母さんも苦しんでいることでした。
だから共依存になってしまうのもムリはないのですが、それだと余計に苦しくなるだけだと思うのです。
そこで、「『おやおや日記』で怒りも苦しい気持ちも悲しい気持ちも、嬉しい気持ちも喜びもすべて吐き出してください。自分のどんな感情も認めてあげてください」と伝えました。
そのお母さんは、子ども時代に父親から暴力を振るわれて育っています。
そのような幼少期のトラウマのある方は、インナーチャイルド(内なる子ども)が傷ついているので、自分に自信が持てず、孤独を感じやすいなどの症状が大人になってから出てくると言われています。
実際に、そのお母さんは「おやおや日記」の字がとても薄いので、自信がない感じが字からも伝わってきます。
ですので、インナーチャイルドを癒してあげるのが先決だとアドバイスしました。
「おやおや日記」を始めたばかりのころは、毎日2ページぐらいにわたって、びっしりと書き込んでいました。
ここで原文をそのままご紹介します。
意味がわかりづらいかもしれませんが、それぐらいの勢いで書いていることを感じ取れるのではないでしょうか。
「今日は写真撮影。洋服もバッチリ、髪の毛もセット時間がかかると思ったから早めに支度してたつもりだけど、宿題やってたからその分ロスしてた。お兄ちゃんのワックスをつけたけどうまくいかず、洗い流してドライヤー。やはり気に入らずパニックになり、もう行かないと。先生に電話して玄関まで迎えに来てくれた。『ママー』って半ベソになりながら手をつないで登校」
「『修学旅行は行かない。楽しくなさそうだもん』『行ってもいないのにわからないじゃん』って言ったら、『ああもう学校も無理 』となり、また先生に頼り電話をした。それから待ち合わせをしようって、先生と通った道でって。なんて言ってたのか聞いても『わかんない、声が漏れてたから』。だから、『じゃあママと手をつないで先生と待ち合わせのところまで行こう』って出発。先生と会えてそこでお母さんとバイバイして『一人で行っておいで』って、それを受け入れて一人で先生の元まで歩いて行った」
息子さんが登校前にパニックになり、先生に迎えに来てもらうまでのやりとりを事細かに会話まで再現しています。
そのやりとりを読んでも、過干渉になりつつあるのは明らかでした。
1か月ぐらいその状態が続いて、お母さんは職場に復帰することになりました。
必然的に一緒にいる時間が減り、お母さんは自分の生活のことも考えないといけなくなったので、日記の分量が激減しました。
すると、息子さんは登校するようになったのです。
お母さんは、「忙しくてあまりかまってあげないほうが学校に行けるのかも」と気づきました。
お母さんとしては、息子さんがだんだん大きくなっていくのが寂しくて、まだまだ一緒にいたい気持ちもあるのですが、それを「私は私でいいんだ。寂しくていいんだよ」と認めてあげたら、以前よりも自分に自信が持てるようになったと語っていらっしゃいました。
「息子との距離のとり方はまだまだ模索中ですが、不安を書き出すことで、感情を吐露する場所ができてラクに子育てできるようになりました」とのこと。
「おやおや日記」を数か月書いて読んで振り返る過程を経て、ここまで気持ちに変化が起きるようになりました。
子どもは親に関心を持ってもらいたいのだと前述しましたが、だからといって過干渉になってしまうと、子どもをかえって苦しめてしまうことになりかねません。
過保護でもない、放任でもない、ちょうどいい距離感を子ども日記を通して見つけられると思います。
押してばかりの親御さんは、「しばらく引いて見守っていたほうがいいかも」と考えたり、逆に関心を持たなすぎの親御さんは「もうちょっと声をかけたほうがいいかも」と気づくきっかけになります。そのように引いたり押したりしながら、
お子さんと自分とのちょうどいい加減を見つけられればベストです。
私自身も、子どもたちとのちょうどいい距離感は、日々探っている感じです。
私の息子は、私が仕事に出かけようとしているときに、みかんの皮をむき始めたことがありました。
親としては、「むいてあげるね」とさっさと皮をむきたくなる場面ですが、私はあえて待つことにしました。
そして、むき終わって「頑張ったね」と褒めると、息子は嬉しそうな表情をしていました。
仕事に遅れて怒られたとしても、今この瞬間の息子の成長を見守ることのほうが大事だろうと思ったのです。
子どもの成長はあっという間ですから。
ときには関わり、ときには見守り、信じて、待つ。
結局のところ、子育てはその繰り返しなのではないでしょうか。
特定非営利活動法人この子キャリア応援団理事長
帝京大学教育学部教授/放送大学客員教授
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね