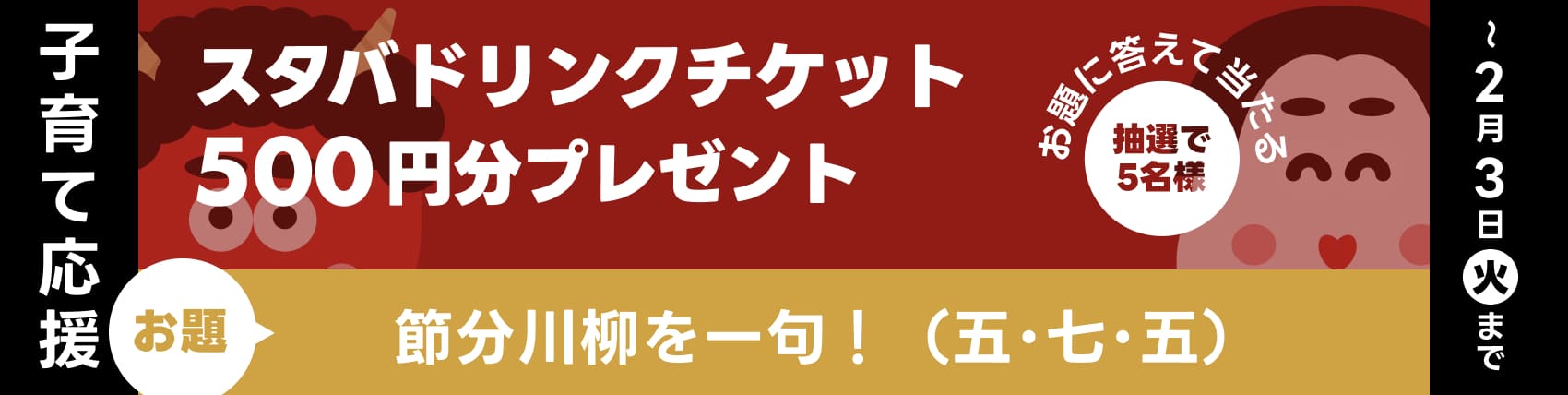不登校児ゼロ教師が伝える――「子ども日記」で家庭を「居場所」にする
壁に突き当たって苦しいときも、思い通りにならなくて泣きたくなったときも、「子ども日記」は、それを乗り越え、前を向いて歩み続ける皆さんの心強い存在となるでしょう。必要なのは、ノートとペンだけ。子ども日記は「親が子どものために書く日記」です。
学校

7年間不登校児ゼロを実現した元教師が、自身の経験と失敗から編み出した“子ども日記”。親子が心から繋がり、家庭が居場所になる。日記が「幸せな関係」を築くヒントと実践例を多数紹介する一冊。
上村公亮先生著書の『不登校児ゼロ教師が伝える 親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』から一部転載・編集してお届けいたします。
「幸せな居場所」ってどんな場所?
皆さんの考える「幸せな居場所」はどんな場所でしょうか。
私の考える「幸せな居場所」とは、自分のやりたいことをやり、言いたいことを言える、自分を丸ごと受け止めてくれる場所、というイメージです。
これは子どもだけではなく、大人にも当てはまります。
それが、学校であっても、塾であっても、友達といる場であっても、学童保育やフリースクールのような場であってもいいでしょう。
願わくは、私は子どもにとって幸せな居場所が家庭であってほしいと思います。
しかし、私が関わっているお子さんの中には、家庭自体に問題があり、居場所がない子もいます。
その場合は、入所施設や児童相談所との連携は必要不可欠です。
どこかに自分が安心していられる場があれば、それだけで子どもは生きていく力をもらえるはずです。
私が支援させていただいているあるお子さんは、大勢がいる場が苦手なので、学校に行くのは週に1度、それも、金曜日とこの子が好きな給食のときだけ行っています。
それ以外は公的な登校支援教室に週2日、通級指導教室に週1回通っています。
支援教室に通っていれば、学校に出席しているのと同じ扱いになるので、お子さんに負担のない方法で学ぶ場をつくっているのです。
とくに発達凸凹のお子さんにとって35人もクラスメイトがいる場でやっていくのは至難の業です。
自分に合った学ぶ場を見つけて、自分が行けるときに行けば十分ではないでしょうか。
今、不登校の小中学生は3万人を超え、高校生を入れると4万人を超えます。
それはやはり、学校になじめなくて居場所にならないから不登校になっているのでしょう。
だからといって、親の立場で学校を幸せな居場所にするのは簡単ではありません。
学校と連携していかなくてはならないけれども、先生たちは仕事が多すぎて時間を取れないのが現実です。
それなら、家庭を幸せな居場所にしていくのが、もっとも子どもにとっていい解決策なのではないかと思います。
家庭が子どもにとって安心安全な場になったら、学校での状況が変わらなくても登校できるようになった例を、今までたくさん見てきました。
子どもは「親が味方になってくれる」と思ったら、学校が大変な場であっても「行こう」とトライする気持ちが生まれるものなのでしょう。
ただし、不登校が悪いことだなんて私は思っていません。
「行けたら行く」ぐらいで十分です。
今は選択肢がたくさんあるので、前述したように、自分が合わない場にムリに通わなくても、自分が心地よい場を他に見つければいいと思います。
ムリに学校に通わせようとすると、さらにお子さんは苦しくなり、親御さんも苦しくなる負の連鎖が起きるのだと感じています。
そうはいっても、家庭をどのように幸せな居場所にすればいいのか、「それができればやっている」と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
子どもにとって幸せな居場所にするには、その場所が親御さんにとって幸せな居場所になっていることが大前提になります。
もし、親御さんにとって今の家庭が幸せな居場所になっていないのなら、その原因は何なのか、「おやおや日記」で探ってみてはいかがでしょうか。
自分や家族を客観的に見ることができれば、家庭が幸せな居場所になっていない原因が見えてくるかもしれません。
私が親御さんによくお話しするのは、「ないもの」を求めるのではなく、「今あるもの」に目を向けましょう、ということです。
「ないもの」を求め出したらキリがなく、「あの子はテストでいい点を取っているのに」「あの子は運動神経がいいのに」「あの子はハキハキあいさつできるのに」と、無限に何かと比較してしまいます。
目の前のお子さんには、たくさんできることがあって、たくさんの可能性があります。
今はそれに気づけていないだけです。
子ども日記を続けるうちに、お子さんのいいところ、素晴らしいところが、どんどん見つかっていきます。
そうすれば親御さんも幸せになり、親御さんが幸せになれば、お子さんも幸せになる。
そうやって幸せの連鎖が起きていくのが、子ども日記の最大の効果だと思っています。
子どもが一番欲しいもの
皆さんは、子どもたちが一番欲しいものは何だと思いますか?
クリスマスのシーズンにおねだりするオモチャやゲーム、スマホではありません。
私が今まで大勢の子どもと関わってきた経験から言えるのは、「他者からの関心」です。
親に関心を持ってほしいと、親が考えている以上に、子どもたちは切実に望んでいます。
親だけではなく、先生などの大人や、友達にも認められたいと思っています。
その気持ちがさまざまな形で表れて、友達にちょっかいを出して泣かせてしまったり、親が「やめなさい」と注意すればするほど、暴れたりするのだと考えられます。
子どもは自分の感情をうまく言葉で表現できないから、まったく違う行動で表してしまうのですね。
子ども日記は、まさに親が子どもに関心を持つためのツールです。
もちろん、皆さんもお子さんに対して関心を持っているから、日々悩みながら衝突しているのだと思います。
でも、その思いがお子さんにきちんと届いていない場合があります。
お子さんの心に届いていないのはなぜなのか。
お子さんの話を最後まで聞こうとせず、途中で遮っているからかもしれません。
親御さんが何気なく言った言葉に傷ついているからかもしれません。
そのような自分の行動を振り返れるのが子ども日記です。
あるいは、お子さんがSOSを出しているのに、気づいてあげられない場合もあるでしょう。
「最近、ぐずってばかりだな」「元気がないな」といった変化も、子ども日記をつけるうちに気づけるようになります。
子ども日記をつけていると、子どもの行動や表情をよく観察するようになるので、小さな変化にも敏感になっていきます。
それを言葉にして、「最近、元気がないけれど、どうしたの?」と伝えたら、「自分のことを見てくれているんだ」とお子さんも感じるはずです。
親になるトレーニングを受けて親になる人はいません。
2人目、3人目の子どもなら、ある程度は経験則で対処できるでしょうが、それでもそれぞれの子どもの性格は違うので、予測不能なことばかり起きるでしょう。
野球ではいきなり投げられたボールを打つのは簡単ではありませんが、止まっているボールなら打ちやすくなります。
止まっている蝶はつかまえられますが、飛んでいる蝶をつかまえるのは至難の業です。
コミュニケーションも相手がどのような発言をするのかわからないのに、その場のアドリブで受け答えしようとするから、お互いに思いを伝えられずにヒートアップしてしまって、収拾がつかなくなるのかもしれません。
子ども日記は「止まっているコミュニケーション」のトレーニングになります。
ラリー日記で、お子さんの書いたコメントに対して、「どうやって返せばいいのか」と考えてから自分の思いを書くというラリーを繰り返すうちに、「こういう場面ではこう返せばいいんだ」とコツがつかめてきます。
もしくは、「おやおや日記」で「あのときの子どもの行動に、どう対処すればよかったのか」と分析すると、「この伝え方ではわかってもらえなかったから、次回はこう伝えてみよう」など、次に備えられます。
心の中の感情を暴走させないように、理性の手綱でコントロールするのです。
止まっている段階でしっかりと返せるようになったら、普段のコミュニケーションでも落ち着いて対処できるようになっていくでしょう。
特定非営利活動法人この子キャリア応援団理事長
帝京大学教育学部教授/放送大学客員教授
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね