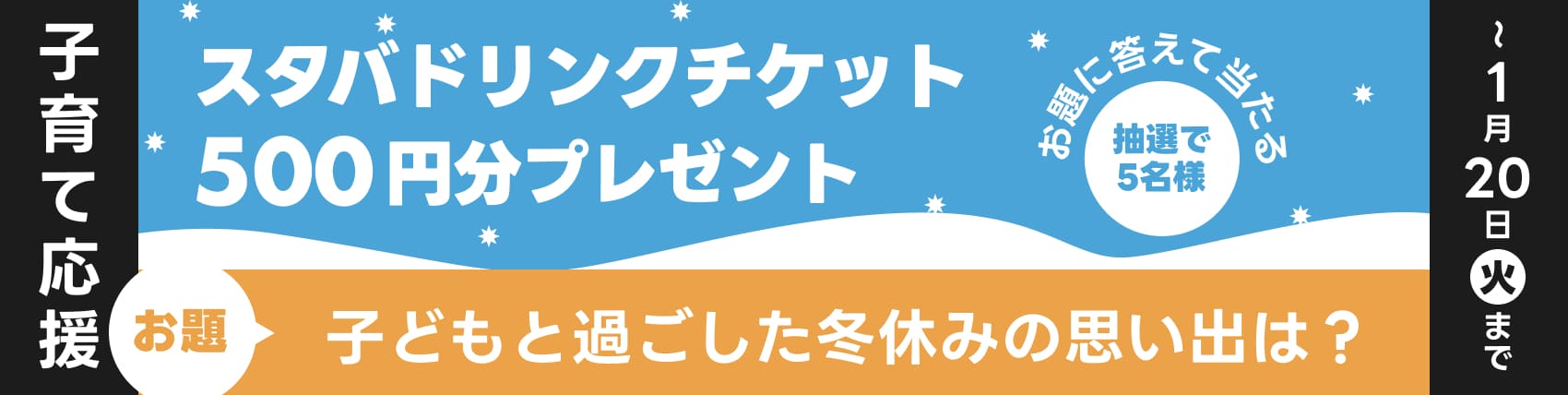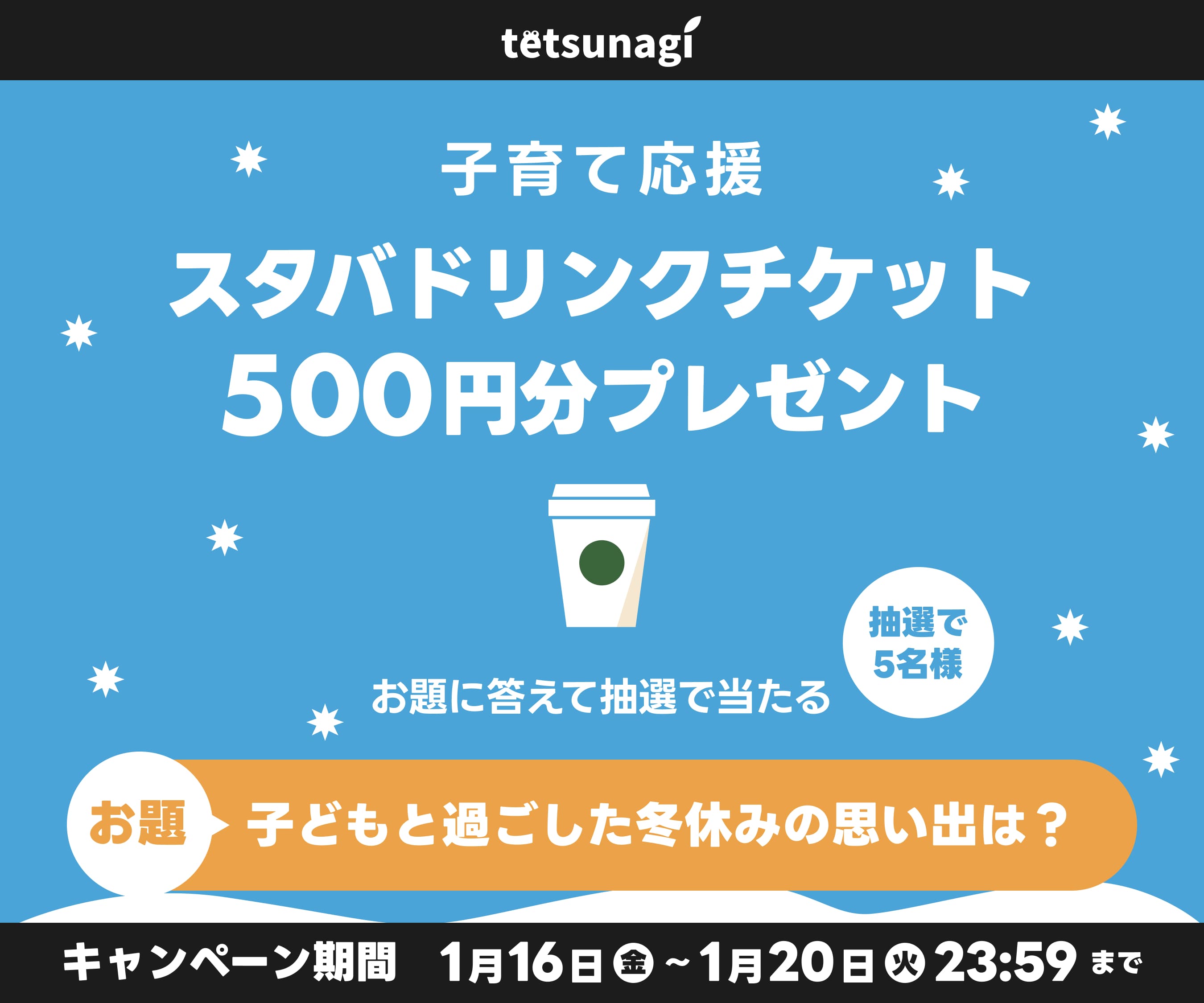【小学生】朝起きられない原因と対策を徹底解説|起立性調節障害の可能性も(第2回)
朝起きられない小学生の我が子を支えるために親ができること。
健康/病気

【小学生】朝起きられない原因と対策を徹底解説|起立性調節障害の可能性も(第2回)
こんにちは、多様な教育ナビゲーター・あずみのこです。15年以上子育て支援に携わり、2人の小中学生を育てる現役共働きママの視点から、コラムをお届けしています。
子育ての現場に立ちながら、同じ母親として「理想どおりにいかないなぁ」「どうしたらいいんだろう」と悩むこともしょっちゅう。だからこそ、このコラムでは専門的な視点と、等身大の母親目線の両方を交えて、“親も子も少しラクになれるヒント”をお届けできたらと思っています。本コラムは【小学生】朝起きられない原因と対策を徹底解説|起立性調節障害の可能性も(第1回)の続編となります。
不登校につながる心配と学校との連携
朝起きられない状態が長く続くと、学校に行くこと自体がだんだん難しくなり、結果的に不登校につながることもあります。特に起立性調節障害のある子どもは午前中の登校が大変で、周囲に理解されにくいことから孤立してしまうケースも少なくありません。「少し休むだけ」のつもりが続いてしまうと、学習の遅れや心の負担が大きくなってしまうこともあります。
そんなときに大切なのは、親が一人で抱え込まないこと。学校とのやりとりを早めに重ねておくことで、安心につながることもあります。医師の診断書を提出する、担任や保健室の先生に状況を伝える、スクールカウンセラーに話をしてみるなど、できる範囲で学校と共有しておくと、子どもが過ごしやすくなるだけでなく、「親も一人じゃない」と思える支えになることがあります
登校時間を調整したり、保健室からのスタートを認めてもらったりと、柔軟に対応してもらえるだけでも親子の負担は軽くなるかもしれません。

出席扱いへの配慮や相談窓口
体調不良で休む日が続くと、「このまま進級や進学に影響したらどうしよう」と親としてはとても心配になりますよね。
でも実際には、医師の診断書など正当な理由があれば、自宅学習や保健室登校を「出席扱い」として認めてもらえる場合もあります。自治体や学校ごとに仕組みは少しずつ違うので、まずは担任の先生に早めに聞いてみると安心です。
また、学校以外にも教育委員会や地域の相談窓口など、頼れる場は意外とたくさんあります。「全部を親だけで背負わなくてもいいんだ」と思えること自体が、親子にとって大きな支えになりますから。
スクールカウンセラー・保健室との連携
朝から授業に入るのがしんどい日には、まず保健室で少し休んでからスタートしたり、カウンセラーに気持ちを話したりするだけでも、「学校とのつながりは切れていない」と感じられて、安心できることがあります。
「教室にいけなきゃダメ」と思うと、どうしても親子ともに苦しくなってしまいますよね。でも、保健室やカウンセラーとのやりとりも立派な“学校生活の一部”。そうした小さな積み重ねが、子どもにとって「学校に行けた」という自信につながり、結果的に朝の起きづらさや登校への不安をやわらげるきっかけになることもあります。
うつとの違いと注意点
起立性調節障害と、子どもの「うつ病」や強いストレス反応は、症状が似ているため誤解されやすいと言われています。たしかに「朝起きられない」「体がだるい」「やる気が出ない」といった点だけを見ると、とてもよく似ていますよね。
ただ、背景には大きな違いがあります。 一般社団法人 起立性調節障害改善協会によれば、うつ病は理由がなくても気分の落ち込みや自己否定感が長く続くのに対して、起立性調節障害は“日内変動”といって、朝〜午前中に強い倦怠感が出るものの、午後になると元気が戻ってくるのが特徴だそうです【※13】。この違いを理解しておいて、見極めの参考にしてみてくださいね。

起立性調節障害と重なる症状に要注意
このように、起立性調節障害とうつ病は、まったく別の病気ですが、見た目の症状が重なって見えることも少なくありません。「体がだるい」「やる気が出ない」といったサインだけでは、どちらなのかを親が見極めるのはとても難しいのです。
大切なのは、親が一人で判断しようとしないこと。本人の様子だけを見て「怠けているのかな」「心の問題かも」と決めつけず、医師の診察や検査を通して専門的に見てもらうことが安心につながります。
「ちょっと気になるな」と思ったタイミングで相談してみるだけでも、親子の気持ちがラクになることがあります。放っておくことで長引いてしまうより、早めに専門家に話してみることが、子どもの回復への大きなきっかけになるかもしれません。
精神科・心療内科への相談タイミング
もし「気分の落ち込みが長く続いている」「自己嫌悪が強い」「自傷念慮が見られる」といったサインがあるときは、うつ病の可能性も視野に入れて、心療内科や精神科に相談してみるのが安心です。厚生労働省も「気分の落ち込みが2週間以上続き、生活に支障が出ている場合は、うつ病の可能性があり」としています【※14】。
親としては「精神科」「心療内科」と聞くと、どうしてもハードルが高く感じられるかもしれません。でも実際には、相談=すぐに薬を使う、ということではなく、まず話を聞いてもらうだけでも安心につながることが多いです。
病院に行く決断は、本当に勇気がいることですよね。でも、一度相談してみることで、「早めに動いてよかった」と感じられることも少なくありません。無理に一人で抱え込まず、信頼できる専門家に頼ることも、子どもを支えていく大切な一歩になるのだと思います。
朝起きられない小学生が改善するまでの期間
「いつまで続くんだろう…」「本当に良くなるのかな?」と、親としてはどうしても気になりますよね。
起立性調節障害の場合は、思春期の成長とともに症状が少しずつ和らいでいくケースが少なくありません。数カ月で「朝がラクになってきた」と感じる子もいれば、数年かけて少しずつ改善していく子もいます。個人差は大きいですが、焦らずに“長い目”で見守ることが大切です。

成長に伴う改善の目安
小学生のうちはまだ有病率は低めですが、高学年から中学生の思春期にかけて症状が本格化することが多いといわれています。ただ、身体が成熟して自律神経が安定してくるにつれて、少しずつ朝のつらさがやわらぐ傾向もあります。
一般社団法人 起立性調節障害改善協会によれば、発症から1年後に約50%、2〜3年後には約80%の子どもが改善傾向を示すとされています【※15】。多くのケースでは高校卒業の頃までに症状が落ち着くとされますが、個人差は大きいため「必ずそうなる」と楽観視しすぎないことも大切です。心配が続くときは、無理に抱え込まず専門医に相談してみることが安心につながります。
再発防止に必要な習慣づくり
せっかく朝起きられるようになっても、生活リズムが乱れると「朝起きられない」状態がぶり返してしまうことがあります。特に学年の変わり目や季節の変化、受験などストレスが重なる時期は要注意。
毎日の生活で「なるべく同じ時間に寝て起きる」「ストレスをためすぎない」「自分の体調を客観的に把握する」といった習慣が、再発防止のポイントにもなります【※16】。
家族と一緒に「今日はちょっと早めに寝てみようか」など、無理のないペースで積み重ねていけると安心です。完璧にやろうとすると親子で疲れてしまうので、“今日はここまでできたからOK!”くらいの気持ちで続けていくのがちょうどいいんだと思います。私も「早く寝ようね」と言いながら親の方がスマホをダラダラ見ちゃったり(子も同じく)…なんて日もよくありますからね(苦笑)。
まとめ|朝起きられない小学生の我が子を支えるためにできること
小学生のお子さんが朝起きられないとき、その背景には「起立性調節障害」などの体の不調や、生活リズムの乱れ、環境の影響が隠れていることがあります。決して「夜更かしや怠け」だけで片づけられる話ではありません。
親としては「このままで大丈夫かな」と不安になることもあると思いますが、家族や学校と協力しながら生活リズムを徐々に見直したり、必要に応じて専門医に相談したりすることで、改善の道はきっと見えてきます。
時間がかかることもあるかもしれません。でも、正しい知識と寄り添いがあれば、子どもは少しずつ自分のペースを取り戻していけます。朝、布団から顔を出してくれた...と、そのほんの小さな一歩こそが、前に進んでいる証です。
なかには「うちは前に進めていない」と感じる方もいるかもしれません。でも、それも自然なこと。足踏みに見える時間も、子どもにとっては次に進むための大事な休憩になっていることがあります。
そして正直なところ、親のほうも「あと5分…」と布団から出られない日がありますよね(笑)。それでも大丈夫。完璧じゃなくても、親子でゆるやかに歩んでいければ、それが何よりの支えになるのだと思います。
そして、疲れて誰かにつぶやきたいときは「てつなぎ」の掲示板に書いてみてください。「あずみのこ」もときどきのぞいているので、見かけたら「うんうん、そうだよね」と一緒にうなずいていると思います。
※ここでお伝えした内容はあくまで参考情報です。実際の診断や治療に代わるものではありません。個々の症状や健康状態に関する懸念がある場合は、必ず早めに医師や専門家にご相談ください。
多様な教育ナビゲーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね