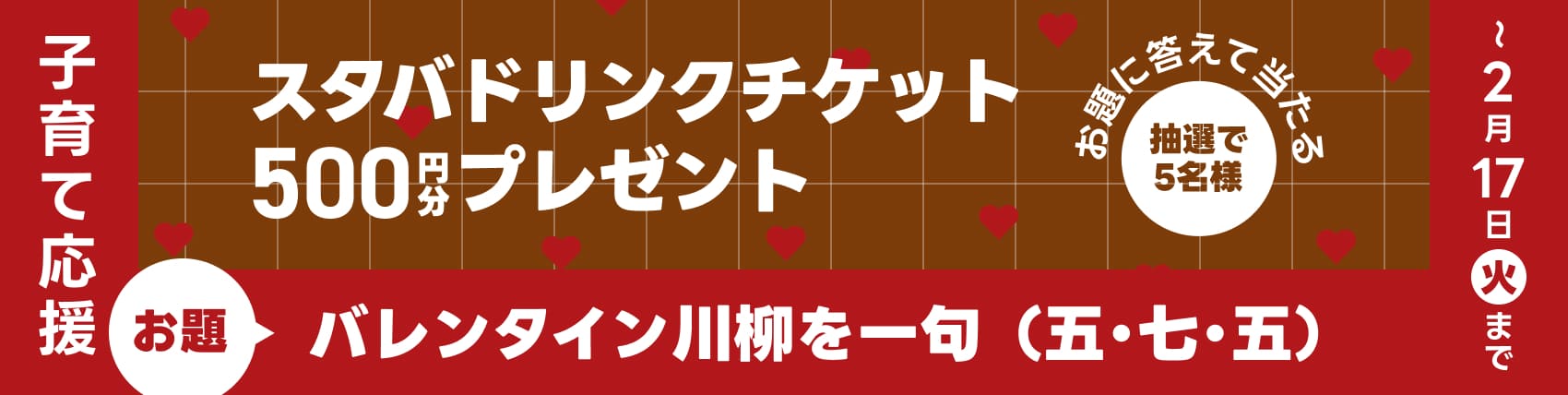【第2回】動画見せすぎかも?家庭でできる工夫と付き合い方
子どもと動画、もはや切っても切れない令和の子育て。親子でどう付き合っていくかをまとめました。
しつけ/育児
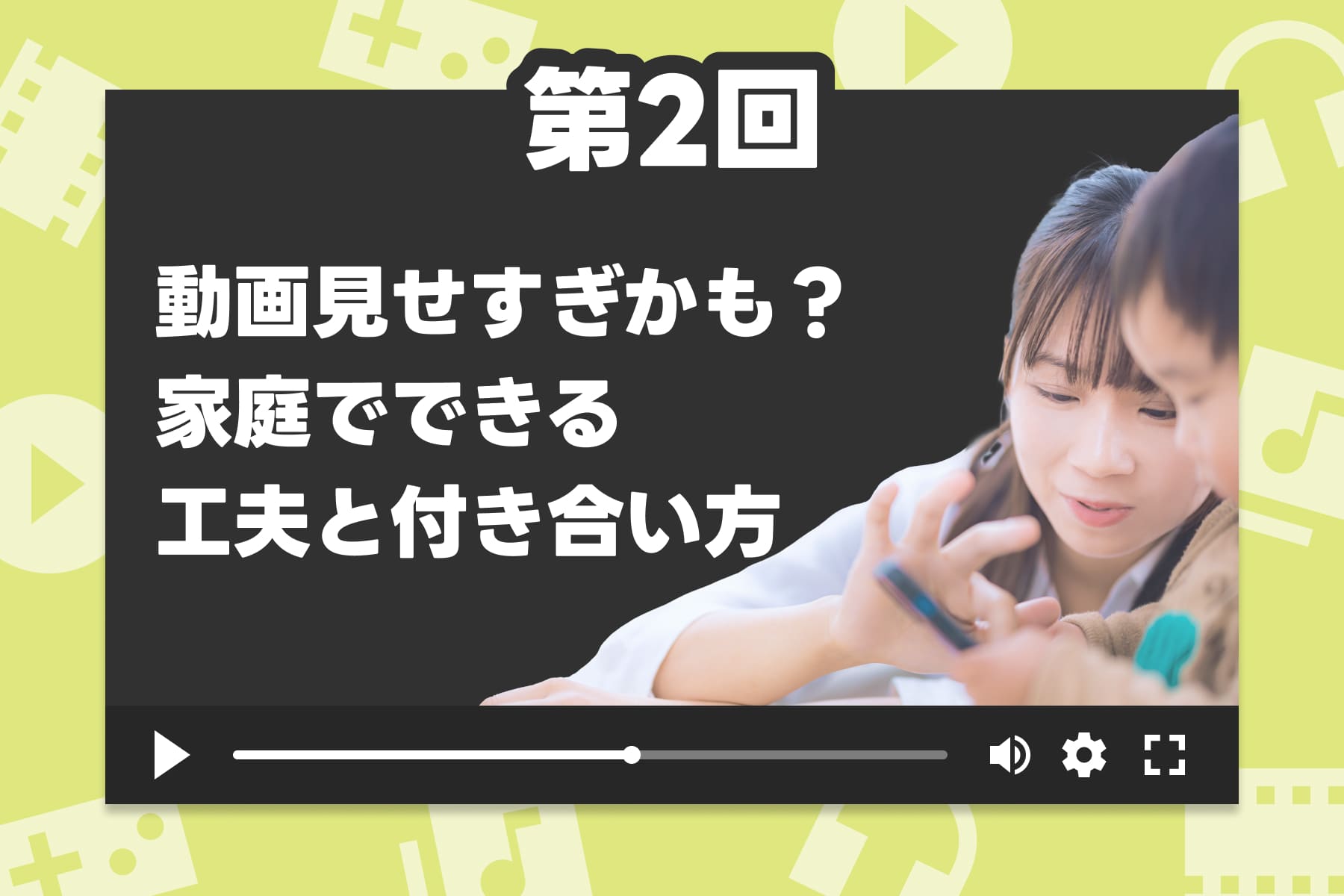
【第2回】動画見せすぎかも?家庭でできる工夫と付き合い方
「最近の子って、どうしてあんなに動画に夢中なの!?」そう感じること、ありませんか?でもその背景には、じつは子ども自身の変化だけじゃなく、わたしたち親の暮らし方や働き方の変化も、大きく関わっているんだと思います。本コラムは【第1回】動画見せすぎかも?家庭でできる工夫と付き合い方の続編になります。
年齢や状況に応じたスマホ・テレビとの付き合い方
「仕事中は動画に頼ってしまう…」——そんな日、私は正直何度もあります...(苦笑)。
在宅ワークの合間や、家事を片づけたいタイミングで、子どもが静かに過ごしてくれる時間って、ほんとうにありがたいんですよね。
でもその一方で、「ちょっと見せすぎかな?」「このままで大丈夫かな…」と、モヤモヤすることも多々ありで...。
こんなふうに、スマホやタブレットを“完全に取り上げる”のがむずかしいご家庭も多いと思います。だからこそ、子どもの年齢や発達段階に合わせて、「どう使うか」「どこで見るか」「誰と楽しむか」をちょっと工夫してみることが大事だなと感じています。
たとえば、
・未就園児なら、なるべく短時間&リビング限定で視聴する
・3歳以上なら、見た後に「どんなお話だった?」と一緒にふり返る
・小学生なら、学習アプリや興味に合わせた知育系の動画を選ぶ
動画を見ること自体を“悪いこと”にしないで、「どうしたら心地よく使えるか」を、親子で話し合っていけたらいいのかもしれません。
「ちょっと一緒に見る」「終わったら一緒に感想を話す」など、そんなふうに、“ひとり時間の道具”から“親子の共通体験”に変えていくだけでも、動画との付き合い方が少しずつ変わっていくように思います。

視聴時間の制限とルール作り
「つい長くなってしまう」動画視聴。ここでは、わが家で試してきた“生活リズムの中での工夫”や、ルールづくりのヒントをまとめてみました。
「1日〇分以内!」と決めても、実際はなかなか難しいものですよね。だからうちは、「ごはんのあとにしようか」「朝の準備が終わったらOK」など、生活の流れの中に動画タイムを組み込む形にしていました。目安はだいたい1日30分〜1時間くらいですが、時間そのものよりも、「いつ見る?」「なにをしたら見ていい?」という“前後の過ごし方”を整えることで、子ども自身も気持ちの切り替えがしやすくなるように感じています。
ママ友の家では、キッチンタイマーを使って「あと15分ね〜」と予告する方法をとっているそう。“そろそろ終わる”がわかると、子どもも納得しやすくなるみたいです。
それから、子どもと一緒にルールを決めるのも効果的です。「どれくらいなら気持ちよく終われそう?」「あと何分なら納得できる?」と相談してみると、自分で決めた感覚が芽生えて、ちょっとした納得感や自立心にもつながります。
……とはいえ、 家族全体で意識をそろえるのって、ほんとに難しいんですよね(ため息)。うちなんて、夫がず〜っとスマホ。食事中も画面を見ながら、もぐもぐ……という日も多々あって(苦笑)。そんな姿を見ている子どもにだけ「スマホやめようね」と言っても、そりゃあ説得力ないですよね。
で、結局その矛先が私に向いてきて、私のイライラが爆発…。ちいさなスマホ1台が、夫婦のすれ違いの火種になることもあるんだなあって、しみじみ思います。
だから、「どう付き合っていくか」は子どもだけの問題じゃなくて、大人も含めた“家族全体のテーマ”なのかもしれません。
たとえば、てつなぎの掲示板には、こんな本音が寄せられています。
「息子が宿題やらずに、ずーっとyoutube見てることに、今日爆発して、タブレットを隠しました。しばらく当分長い間、出しません。ルールを遵守できないなら、こうなるんだってことを知らしめる。教育論とか知らん。あと旦那、携帯ばかり見るのやめてくれ。少なくとも子どもの前でやめてくれ。同じようにタブレットばっか見るんだよ、子どもが。受験するなら親の意識も変えてくれよ。どいつもこいつも…滝行でも行ってこいや!」(🔗てつなぎ掲示板|“タブレット隠しました”)
強火な叫びに、思わず「わかる…!」とうなずいた方もいるのでは。
別の投稿では、こんな声も。
「外食中や仕事しているときにわめき散らす子どもにYouTubeを見せていたのですが、これが悪かったのか口を開けば「YouTube見たい」と言います。見せてしまったことを後悔しています。ダメと言ったら「ママ大嫌い」と逆ギレしてきます。見せてしまった私が悪いのですがイライラがマックスになります。」(🔗てつなぎ掲示板|“YouTubeについて”)
どちらの投稿にも、「このままじゃダメかも」という焦りや葛藤がにじんでいて、胸に響きます...。
うまくいかない日があってもいい。完璧じゃなくてもいい。少しずつ、わが家に合ったルールや使い方を、親子で一緒に見つけていけたら——それだけで、ちゃんと前に進めていると思います。
子どもが癇癪を起こしたとき
「もう終わりだよ」と声をかけた瞬間に、怒ったり泣いたり…。そんなやりとり、ありますよね。わたしも、何度「はい、またキレた〜!」と心の中でつぶやいたことか…。
「YouTube禁止!」と決意してみたけれど、今度は子どもが暴れてしまって、逆にこちらが限界…という声もよく聞きます。
「禁止にしたら暴れ狂って、私が耐えられないという…(笑)」(🔗てつなぎ掲示板|“YouTube禁止にすると、うるさすぎて耐えられない”)
この投稿、わかりみが深すぎて…。「もうどうしたらいいの…」という気持ち、ほんとうによくわかります。「今いいところなのにー!」って怒ったり泣いたりする子どもを前に、こっちの心が折れそうになることもありますよね。
そんなとき、わたしが試してうまくいったことのひとつが、“次の楽しみ”をそっと提案すること。「終わったらおやつにしようか」「シール貼りしようか」など、ほんのひと言でも気持ちが切り替わることがあるんですよね。
でも、完璧にコントロールなんて、きっと誰にもできません。おたがい、今日もよくがんばってる。そうやって、子どもにも、自分にも、やさしいひと言をかけてあげられたら、少しだけ肩の力が抜ける気がします。
動画以外でも一緒に楽しめる遊びや学習法
「動画以外に、何したらいいのかわかんない…」そんな“お手上げモード”、ありませんか?私はけっこうありました(笑)。正直、こっちに余裕がないと、「一緒に遊ぼう」って気持ちにすらなれなくて、「もう、今日は動画で…」とつい頼ってしまうこと、何度もあります(苦笑)。
でも、「動画じゃない時間」って、なにも特別なことじゃなくてもいいんですよね。少しでも手や体を動かすだけで、子どもの気持ちが切り替わったり、気づけば笑顔が戻っていたりすることも。
次の章では、わが家でもよく取り入れていた“ちょこっと遊び”のアイデアをご紹介しますね。

お絵かき・ブロック・ごっこ遊び
たとえば、お絵かきやぬりえ、ブロックや積み木、一緒に折り紙を折る、かんたんなクイズやしりとりゲームなど。どれも特別な準備がなくても始められる“ちょこっと遊び”のです。
子どもの“想像する力”や“考える力”を育てながら、親子の対話のきっかけにもなってくれるのがいいところ。「うちの子、動画ばっかり…」と悩む時こそ、“手を動かす・話をする・一緒に笑う”そんなアナログな時間が、心のリズムを整えてくれる気がしています。
さらに、こうした“体を動かす遊び”に加えて、次の章では「読み聞かせ」や「音楽」など、もう少し静かな“インプットの時間”のヒントもお伝えしますね。
読み聞かせや音楽・リトミックでのふれあい
お絵かきやブロックのような“手を使う遊び”にくわえて、もうひとつ、わが家で意識していたのが「静かなふれあいの時間」。
たとえば、寝る前の読み聞かせ。親の声でことばや物語の世界を届けられる、やさしい時間ですよね。当時は「たくさん読んであげよう」と意気込んで絵本をそろえたものの、実際は、忙しさに負けて、本棚の奥で眠っていた本もたくさんありますが...(苦笑)。
でも、「今日はこれにしようか?」と一冊の絵本を手に取るだけで、子どもがピタって寄ってきて、そこに小さな安心が生まれる—。そんなひとときは、我が子への愛おしさをダイレクトに感じられる、かけがえのない時間でした。今では読み聞かせをすることもほとんどなくなりましたが、あの時間を思い出すたびに、「やっぱりあれは、親子にとっての宝物だったな」と改めて感じます。
音楽やリトミックも、特別な準備がいらない“音を使ったふれあい”としておすすめです。手を叩いたり、一緒に歌ったり。リズム感や表現力が育まれるだけでなく、子ども自身が“心地いい”を感じ取るセンスも自然と育っていくように思います。
でも、完璧じゃなくて大丈夫。読み聞かせが3分の日があってもいいし、音楽を一緒に聴くだけの日があってもいい。「今日はこれだけできたから、いいかも」と、そんな小さな満足感を、一日の終わりに親子で感じられたら、それだけで十分なんだと思います。
保護者同士で情報交換するメリット
「これって、うちだけ…?」と不安になること、子育てしてると山ほど出てきますよね。「動画見せすぎかな」「このアプリ、安心して使えるのかな」…そんな“育児のもやもや”は、日々わが家にも常駐中です(笑)。
でも、ほかの保護者の話を聞くと、「それ、うちも一緒ー!」と笑えたり、「そんな手があったか!」と目からウロコが落ちたり。「うちはこうしてるよ」「この動画は寝かしつけに神だったよ」なんてリアルな口コミ、ほんとありがたいんですよね。

育児ストレス軽減と悩みの共有
動画のルールづくりって、正解がないぶん、本当に迷いがち。わたしも、「今日は何分まで?」「この動画って見せても大丈夫なの?」と、毎回ちがうモヤモヤと格闘しています(苦笑)。
そんなとき、ほかの人の体験談を読むだけで、「あ、うちだけじゃなかったんだ」とふっと気がラクになったり、「えっ、それアリ!?(でも真似したい)」と、思わず笑ってしまったり。そんな“育児のリアル”にふれる時間が、ときに大きな救いになることもあるんですよね。
とはいえ、わたし自身、ママ友100人できるタイプではなく…(笑)、リアルで相談するのはちょっとハードル高め。だからこそ、「てつなぎの掲示板」は、私にとってとても心強い場所です。
たとえば、先ほども紹介したこの投稿—— 「息子がYouTubeばかりで爆発。タブレット隠した。ルール守らん奴には滝行だ!」みたいな投稿を読んで、笑いながら共感し、ちょっと元気をもらったり。
家庭の中だけで考えていると視野が狭くなりがちだけど、誰かのやり方を知るだけで「あ、それでいいんだ」と肩の力が抜けることもあるんですよね。
そして、そういう会話のなかでよく出てくるのが、「どんな動画見せてる?」「おすすめのアプリある?」といったコンテンツ選びの工夫です。
コンテンツ選びのコツや使用アプリの工夫
周りでいろんな話を聞くなかで、「これって本当に年齢に合ってるの?」「安心して見せられるの?」という視点で“動画やアプリを選ぶ”って、やっぱり大事なんだなと感じるようになりました。
知育アプリや子ども向け動画って、本当にたくさんあって、「どれを選べばいいのか…」と迷うこともありますよね。わたしも、ママ友にすすめられたアプリを試してみたら、たしかに子どもの興味関心や学びにピッタリな内容で、かなり助かったことがありました。
そうやって“誰かのおすすめ”に出会えるって、本当にありがたいなぁと思います。「うちはこうしてるよ」「この動画は安心だったよ」なんて体験談をシェアし合えるだけで、気持ちが少し軽くなるんですよね。
最近では、ペアレンタルコントロールの機能がついたアプリも増えていて、視聴時間を制限したり、履歴をチェックしたりもできるようになっています。ちょっとした工夫を知っているだけで、「これなら大丈夫かな」と安心して見せられるものが見つかると、子どもとの時間も、少しラクに、ちょっと心地よくなっていく気がします。
まとめ:適切なルールと親子の交流がカギとなる
子どもと動画、もはや切っても切れないご時世。だからこそ、「どう付き合っていくか」は、親子で一緒に探っていきたいテーマです。
「これが正解!」なんて万能ルールはないけれど、わが家にフィットする“ちょうどいい距離感”を見つけられたら、それだけで十分。
たとえ「見せすぎたかも…」と思う日があっても、親子で「明日はこうしようか」とゆるっと軌道修正できればOKです。反省会という名の“おやつタイム”をしながらでも(笑)。
アナログな遊びやふれあいの時間も、できるときに、できるぶんだけ。「今日は読み聞かせ3分で終了〜」「ブロックは片付けで燃え尽きた」なんて日も、ぜんぶ含めて大切な子育ての一部です。
完璧じゃなくて、大丈夫。モヤモヤしつつも笑えたり、ちょっと一息つけたり。そんな日々のなかで、「まあ、いっか」と心がゆるむ瞬間が、またふいにやってくるはずです。
てつなぎ編集部
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね