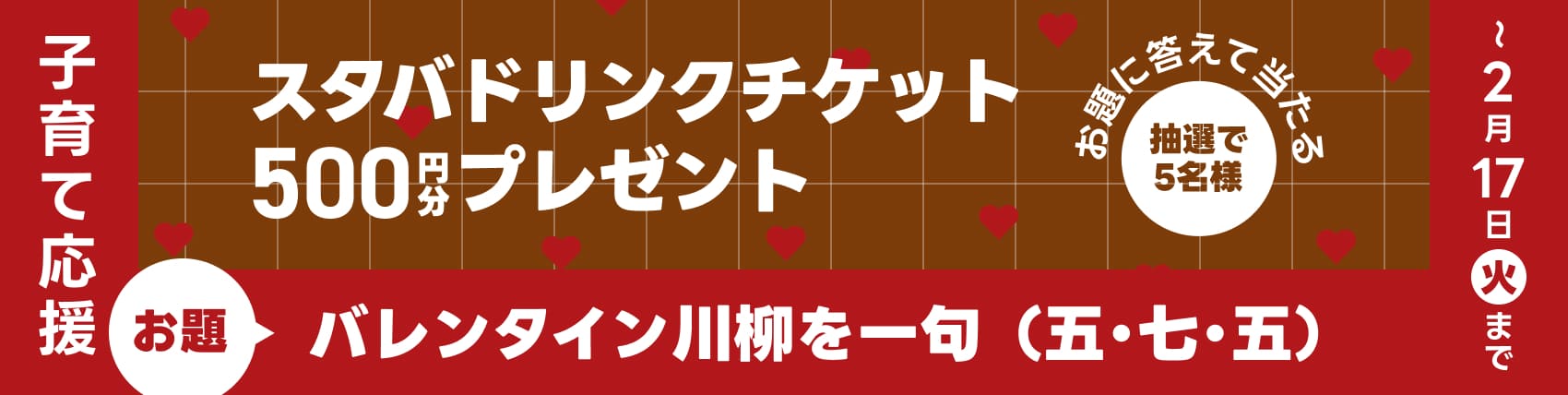【第1回】動画見せすぎかも?家庭でできる工夫と付き合い方
子どもと動画、もはや切っても切れない令和の子育て。親子でどう付き合っていくかをまとめました。
しつけ/育児
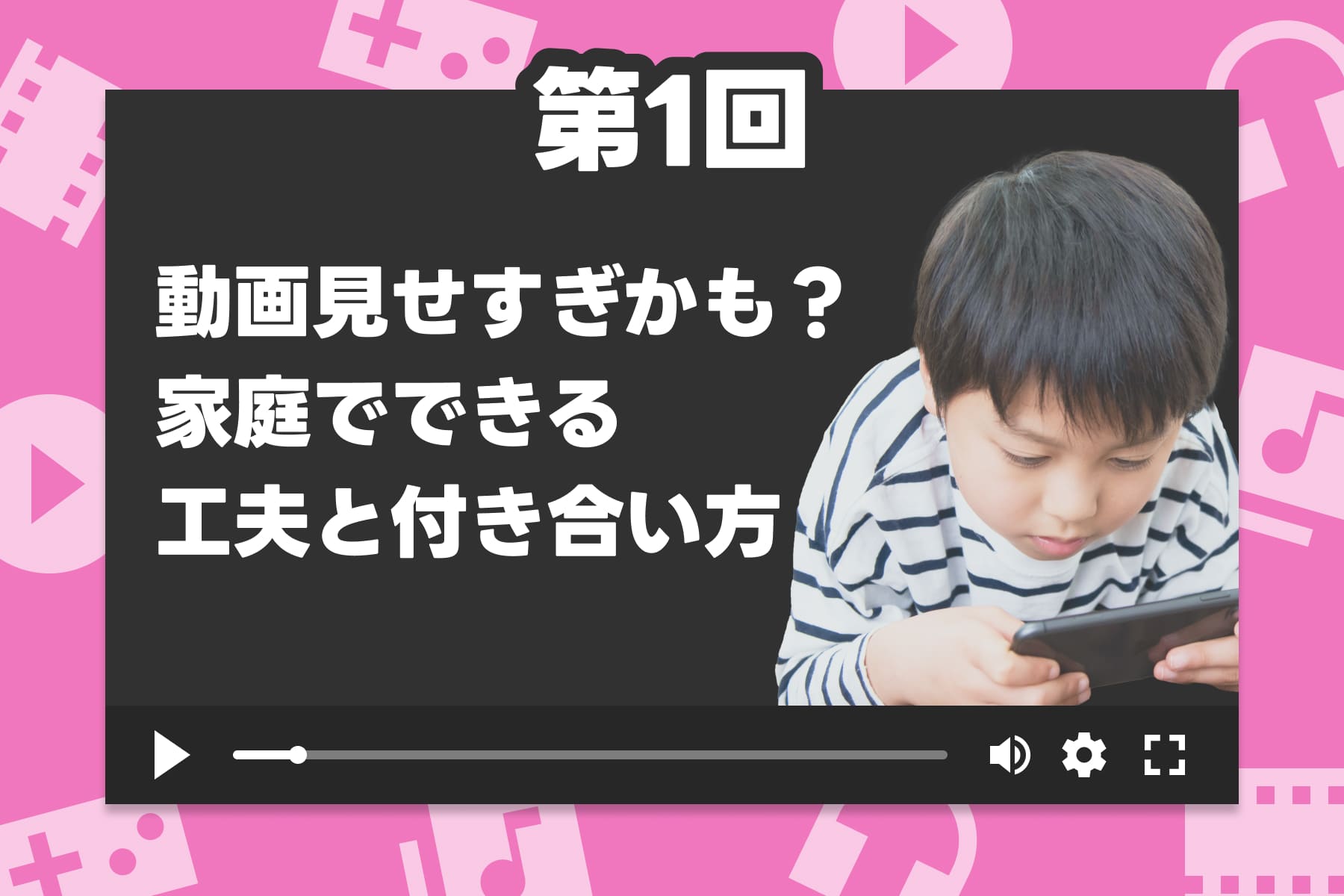
【第1回】動画見せすぎかも?家庭でできる工夫と付き合い方
こんにちは、あずみのこです。
最近、「気づけばうちの子、ず〜っと画面見てるんですけど…?」って思うこと、ありませんか?わたしもよくあります。「ちょっとだけね」ってスマホ渡したはずが、ふと見ると、
\まだ見てるやん!しかも次の動画に行っとるやん!/
ってツッコミたくなること、もう何回あったか分かりません(笑)。
動画って、本当に便利でありがたい存在なんですよね。ごはん作らなきゃ!でも子どもが「ヒマ〜」「つまんない〜」と騒いでる…そんな時の“神アシスト”として、わが家でも大活躍してきました。
ただその一方で、なんとなく心のどこかに残るモヤモヤ…。「うち、見せすぎかも…?」「子どもの成長に影響ある?」そんな不安を感じたことも、きっと少なくないと思います。
本コラムでは幼児の「動画見せすぎ問題」について取り上げました。動画見せすぎかも?家庭でできる工夫と付き合い方(全2回の第1回)
“幼児の動画見せすぎ問題”について、
●どんな影響があるの?
●どう付き合えばいい?
●家庭でできる工夫って?
など、専門的な情報もまじえながら、やさしく整理してみました。
私自身の「スマホ育児あるある」も交えつつ、ちょっと肩の力を抜いて読んでもらえたらうれしいです。
なぜ「動画見せすぎ」が増えているのか?
「最近の子って、どうしてあんなに動画に夢中なの!?」そう感じること、ありませんか?でもその背景には、じつは子ども自身の変化だけじゃなく、わたしたち親の暮らし方や働き方の変化も、大きく関わっているんだと思います。
共働き、在宅ワーク、ワンオペ育児…。子どもとしっかり向き合いたい気持ちはあっても、現実には時間も気持ちも足りない日がたくさんあって。そんなとき、スマホやタブレットって、手の届くところにあって、すぐに静かにしてくれる“便利すぎる味方”になってくれるんですよね。
でも、最初は“15分だけOK”のはずだったのに、気がつけば30分、1時間……あれ?もうこんな時間!?みたいな(わたしはよくあります)。
しかも子どもにとっても、動画ってすごく魅力的。カラフルで、テンポがよくて、好きなものを好きなタイミングで選べる。楽しくてしかたないのは、ある意味当然ですよね。
だからこそ、「ちょっとだけ」のつもりが、いつのまにか“日課”になってしまう。その流れの中に、親も子も、がんばりすぎてる日常があるのだと思います。
最近では、親自身もSNSや仕事の連絡、ニュースのチェックなどで画面を見る時間が増えていて、気づけば「家族でちゃんと話す時間、減ってるかも…」なんてことも。
つまり、子どもが動画に夢中になるのは、「最近の子は〜」という話じゃなくて、いまの暮らしのかたちが映し出されているのかもしれません。だからこそ、責めるんじゃなくて、「どう付き合う?」を一緒に考えていけたらいいな、と思っています。
動画視聴が子どもにもたらすメリット
「動画ってそんなに悪いもの…?」と感じる方も、きっと少なくないはず。 確かに、“使い方しだい”で、動画は子どもの成長にとって、意外と頼れる味方にもなるんですよね。
たとえば、知育動画や体操・歌の動画。楽しみながらことばを覚えたり、体を動かしたり。「わたしもやってみたい!」という気持ちがふくらむきっかけにもなります。
うちの子も、YouTubeで覚えたダンスを幼稚園でお友だちとノリノリで踊っていた時期があって、「あれ、これ意外と社会性育ってるのでは…?」なんて思ったことも(笑)。
動画がきっかけで、「できた!」という気持ちを持てたり、誰かといっしょに楽しめることがあったり。そういう小さな経験の積み重ねって、子どもの自信や好奇心につながっていく気がします。
もちろん、見せ方や内容の選び方には気をつけたいけれど、「動画=悪」って切り捨てるのではなく、「どう使う?」を一緒に考えていけたらいいですね。

親の負担をちょっと軽くしてくれることも
「ちょっとだけ静かにしててほしいな」と、そんなときに、動画が助けになってくれることも、正直かなりありますよね。
家事や仕事に追われているとき、子どもが動画に夢中になってくれると、その間にごはんの準備をしたり、深呼吸して気持ちを整えたり。ほんの10分でも、親にとっては貴重な“自分の時間”になるんですよね。
もちろん、「動画に頼りすぎてるかな…」と罪悪感を感じる時もあるけれど、そんなときは「じゃあ今日は時間を決めて見ようね」と声をかけたり、見たあとに「どんなお話だった?」と一緒にふり返ったり。無理せず、ゆるやかに工夫できたら、それで十分だと思っています。
上手に選べば、学びや楽しみのきっかけに
最近の子ども向け動画って、本当によくできていて、ついつい大人のほうが「へぇ〜!」と感心しちゃうこともありますよね(笑)。アニメや知育番組、音楽・ダンス系のコンテンツなど、楽しみながら自然にことばやリズム、表現にふれられるものもたくさんあります。
「これ好き!」「やってみたい!」という子どもの気持ちに合わせて選んであげることで、理解力や想像力を育てるきっかけになることも。
うちでも、ある動画に出てきた言葉をまねして「ママ、これは〇〇って意味なんだよ!」と得意げに教えてくれたときは、「へぇ〜…ほんとに!?」と内心びっくり&助かりました(笑)。
ただ一方で、刺激の強すぎる映像や、広告がやたらと入るような動画には注意も必要です。日本小児科医会も、メディアとの付き合い方について「内容の質」を意識することが大切だと提言しています。たとえば、乳幼児ならスクリーンタイムは1日2時間以内が望ましいという目安もあるそうです【※1】。
だからこそ、「これは安心して見せられそうだな」と思えるコンテンツを、親の目でていねいに選んであげたいところ。全部を完璧にこなすのは難しいけれど、日々の中で「これはいいかも」と思えるものを少しずつ見つけていけたら、それだけで十分だと思っています。
動画見せすぎがもたらすリスクとデメリット
とはいえ、やっぱり気になるのが、「うち、見せすぎちゃってるかも…大丈夫かな?」ということ。便利だからこそ、ついつい頼りたくなる気持ち、すごくよくわかるんですが、やっぱり気になる“影響”についても、知っておくと安心ですよね。
たとえば、国立成育医療研究センターと千葉大学の共同研究(2023年)では、1〜3歳の子どもたちのテレビ・DVD視聴時間と発達の関係を調べた結果が発表されています。この研究によると、画面を見る時間が長い子どもほど、1年後の発達スコアが低くなる傾向があるそうなんです。
もう少し詳しく言うと、
・1歳で長く見ていた子は、2歳になったときの「ことばのやりとり(コミュニケーション)」に影響が
・2歳で長時間視聴していた子は、3歳の「運動」や「人との関わり(社会性)」に影響が出やすい……という結果が出ています。【※2】
こう聞くと「やっぱりダメなんじゃん!」と思ってしまいそうですが、研究チーム自身も「だからといって一律に“動画=悪”と決めつけるべきではない」とも言っています。
たとえば、「どうしてその子の視聴時間が長くなっているのか?」「家庭ごとにどんな工夫ができるか?」といった背景や事情も大切なポイント。今後さらに研究が必要だとされています。それに、実はこの調査、まだスマホやYouTubeが今ほど普及していない時代のデータをもとにしているため、「いまの子育て」にピタリと当てはまるとは限らないとも言われています。
だからこそ、「いますぐ全部やめなきゃ!」と焦るのではなくて、わたしたち親子にとっての“ちょうどいい距離感”を、少しずつ見つけていけたらいいのかな、と思うんです。便利なものは、使い方しだい。そのヒントを、これから一緒に探していけたらうれしいです。

言葉の発達への影響:言葉の遅れや発音への懸念
子どもが言葉を覚えるときにいちばん大事なのは、「やりとり」。「これなぁに?」「◯◯してみようか」なんて、大人との会話や絵本の読み聞かせのような“キャッチボール”のなかで、子どもは少しずつ、ことばの意味や使い方を覚えていくんですよね。
でも、動画はどうしても一方通行。反応を返す必要がないぶん、「話す」「やりとりする」時間が減ってしまいがちです。 その結果として、
●言葉の数がなかなか増えない
●自分の思いをうまく表現できない
●発音が少し不明瞭に感じる
…といった“ちょっとした気がかり”が出てくるケースもあるそうです。
実際、日本小児科学会も、長時間のテレビやビデオ視聴が言語や社会性の発達に影響を及ぼす可能性があると伝えています。全国の1歳6か月児を対象にした調査では、視聴時間が長い子ほど「意味のある言葉」が出るのがゆっくりだった、という傾向が見られたそうです【※3】。
とはいえ、「あのとき見せちゃったから…」と自分を責める必要はありません。むしろ、「じゃあ、これからどう関わろうかな?」と考えていけば、それで十分。
たとえば、
・一緒に動画を見ながら「これ、何の動物かな?」と話しかけてみる
・見終わったあとに「おもしろかったところ、どこだった?」と聞いてみる
そんなちょっとした“ことばのやりとり”をプラスするだけでも、子どもの言葉の世界って、ぐっと広がる気がします。
情緒面と注意力への悪影響:癇癪や集中力低下
「あと5分だけ…」「もうやめなさいって言ったでしょ!」—そんなやりとり、うちでも日常茶飯事です(苦笑)。動画やゲームに夢中になる子どもの姿に、ついイライラしたり、不安になったり。どの家庭でも“あるある”な風景かもしれませんね。
でも実は、こうした行動の裏には「子どもの脳の発達の仕組み」が関係しているとも言われているんです。
子どもの脳は、まだまだ成長の途中。なかでも「集中する」「我慢する」「気持ちを切り替える」といった“自制”を担う前頭葉は、25歳ごろまでゆっくり発達していく場所なんですね。
つまり、上手にブレーキをかけられないのは、子どもにとっては“当たり前”。親として「なんでわかんないの〜」って思ってしまうけど、実は“まだできなくて当然”なんです。
さらに、動画やゲームを見ているときには、脳内で「快」を感じるドーパミンという物質がたくさん分泌されるそうです。これが「もっと見たい!」「やめたくない!」という気持ちをぐんと強くしてしまうんですね。
藤原小児科クリニックの藤原医師は、このドーパミンの過剰分泌が前頭葉の働きを弱め、ネットやゲームへの依存傾向を高めるリスクを指摘しています【※4】
また、東北大学の研究チーム(川島隆太教授ら)によるMRI調査では、インターネットやゲームの使用頻度が高い子どもほど、前頭葉や側頭葉といった「感情」や「集中力」に関わる部分の発達がゆるやかになる傾向があると報告されています【※5】
仙台市の5〜18歳の子どもたちを3年間追跡した結果では、ネットを「ほぼ毎日」使っていた子の脳では、灰白質や白質といった“脳の体積の増加”がほとんど見られなかったそうです。
——いやもう、私もこの話には「え、マジで!?」と声が出ました(笑)。でも、こうした研究は「だから今すぐやめなきゃ!」と焦らせるためのものじゃないと思うんです。むしろ、「じゃあ、どう付き合ったらいいかな?」と考えるヒントになるもの。
いまの時代、完全にゼロにするのは現実的じゃない。だからこそ、「どのくらいの時間がちょうどいいか」「どんな場面で使うか」「見たあとにどんな会話ができるか」など、少しずつ工夫を重ねていけたらいいですよね。
完璧じゃなくても大丈夫。我が家も「あと5分ね詐欺」を何度もやりながら、なんとかやってます(笑)。
視力・身体面への懸念:長時間画面を見続けるリスク
最近、まわりで「うちの子、目が悪くなってきてて…」という話、よく聞くようになった気がしませんか?実はそれ、気のせいではないようです。
文部科学省の「令和5年度 学校保健統計調査」によると、裸眼視力が1.0未満の子どもは、小学生で約37.8%、中学生で約60.9%、高校生では約67.8%にものぼるそう【※6】。うちも毎年、視力検査の結果にドキッとさせられています(通知表に「C」って書いてあると、妙にリアルにへこみます…)。
こうした視力の低下の背景には、スマートフォンやタブレット、ゲーム機など、近くの画面を長時間見続ける生活習慣があると指摘されています【※7】。昔みたいに「外でどろんこになって遊んでた時代」とは、だいぶ環境が違いますよね。
実際、文部科学省や医療現場からも、近視の進行には「遺伝だけでなく、生活スタイルそのものが深く関係している」との報告があります。屋外活動の減少、スマホの使用時間の増加…。まさに“目にも体にも静かに効いてくる”日常なんだと思います。
さらに、厚生労働省は「子どもたちの身体活動量の低下」に警鐘を鳴らしていて、運動不足が将来的に生活習慣病や身体機能の低下を招くリスクがあると報告しています【※8】。
我が家でも、休日に動画を見ていたら、あっという間に1〜2時間経過…。見終わった後に「首がいたい〜」「肩こる〜」って言う我が子を見て、「お前はOLか」と内心つっこみたくなるとき、正直あります(笑)。
だからこそ、「そろそろ目を休めようか」「ちょっと買い物行こうか」といった、小さな声かけや切り替えの習慣がすごく大事なんだと思います。外の空気を吸うだけでも、体も気分もリフレッシュできるんですよね。
とはいえ、「じゃあ、どのくらいなら見せてOKなの?」って、気になるところでもありますよね。このあと、専門機関が出している“スクリーンタイムの目安”を一緒に見ていきましょう。
専門機関の推奨時間とガイドライン
スマホやテレビ、動画の時間って、つい“感覚”で決めてしまっているご家庭、多いのではないでしょうか。うちも「今日はまあいっか…」の積み重ねで、いつのまにか2時間コース。 「えっ、もうこんな時間!?」って、毎回ちょっとびっくりしてます(苦笑)。
でも実は、子どもの動画視聴時間については、いくつかの目安が出されているんです。
たとえば、世界保健機関(WHO)やアメリカ小児科学会(AAP)では、
・2歳未満の子どもには画面視聴を避けること
・2歳以上でも1日1時間以内が望ましい
といったガイドラインが示されています【※9】。日本小児科学会も、「低年齢での長時間視聴は控えて」と注意を呼びかけています【※3】。
……と聞くと、「うち全然守れてないんですけど!」と焦る方もいるかもしれません。はい、わたしもそのひとりです(笑)。って、現実には「今ちょっとだけお願い…!」って頼りたくなる場面、多すぎますよね。
それに、WHOが根拠とする研究については、「エビデンスの質が低いものもある」と指摘されていて、「本当にテレビを控えることで効果があるのかは明確じゃない」とする専門家の声も紹介されています(朝日新聞などでも取り上げられています)【※10】。
だからこそ、「まったく見せない方がいい!」と極端に構えるよりも、
・家庭ごとの生活リズムや状況に合わせて
・子どもの様子を見ながら
・“ちょうどいいバランス”を探していくこと
が、大切なのかなと感じています。
動画をゼロにするよりも、「どんなふうに付き合うか」を考えること。わが子がどんなふうに見て、どう感じているか。その“ちょっとした観察力”が、いちばん頼りになるのかもしれませんね。

日本小児科学会や米国小児学会の見解
テレビや動画、どう付き合えばいいのか…。たくさんの情報を知れば知るほど、「あれ?うちは大丈夫?」と迷ってしまいませんか?わたしも、「見る時間、うちちょっと長いかも…」と検索しまくって、さらに混乱した経験があります(苦笑)。
たとえば、日本小児科学会や米国小児科学会(AAP)は、「2歳未満の子どもには長時間の視聴を避けてほしい」と呼びかけています【※3】【※9】。とくに言葉がぐんぐん育ってくるこの時期に長く見せていると、「意味のある言葉(有意語)」が出てくるのがゆっくりになることもある、という報告もあるんですね。
でも、その一方で、日本小児科学会の資料にはこんな記述も。「テレビを契機とした親子のコミュニケーションが生まれる」【※3】。
たしかに、「一緒にテレビを見ていると、子どもと自然に会話が生まれるな」と感じたこと、ありませんか?うちでも、「このごはん、おいしそう〜」なんて話しながら見ていると、あとから子どもがその話を思い出してまたその話から話題が広がる、なんてこともありました。
つまり、「動画=悪」じゃない。どう関わるかで、テレビの時間も“育ちの時間”になっていく、ということなんだと思います。
もちろん、長くなりすぎれば、視力や姿勢、ことばの育ちへの影響も気になります。でも、「一切見せないようにしなきゃ!」と気を張るより、
・いっしょに見て、ちょっと声をかける
・見終わったら、ちょっとだけ体を動かす
・内容や時間を、ゆるやかに一緒に決めてみる
そんな“小さな工夫”で十分だと思うんです。
2歳未満に見せる場合の注意点
2歳未満の子どもには、基本的には動画視聴を避けるのが望ましい——これは、日本小児科学会や世界保健機関(WHO)も伝えている、大切なポイントです。とはいえ、現実の子育てって、ほんとうに「理想通り」にはいかないんですよね。
でも、そんなときにちょっと意識したいのが、“ただ見せる”だけじゃなくて、ちょっとだけ関わってみること。「これ、わんわんだね」「お花、きれいに咲いてるね」などど、そんな一言をそっと添えるだけでも、“見る”が“つながる時間”に変わっていくのだと思います。
もちろん、「完璧にできなくちゃダメ!」なんてことはありません。「見せすぎちゃったかも…」と落ち込むより、「今日はちょっと声かけできた」そんな小さな〇を、自分にもつけてあげてほしいなと思います。
てつなぎ編集部
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね