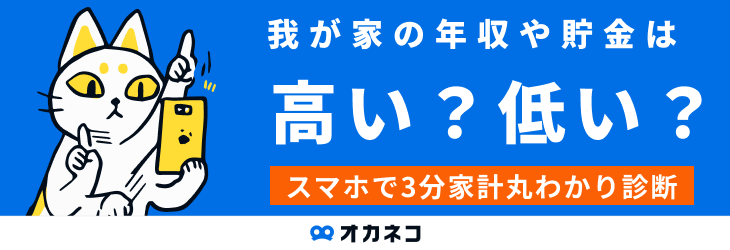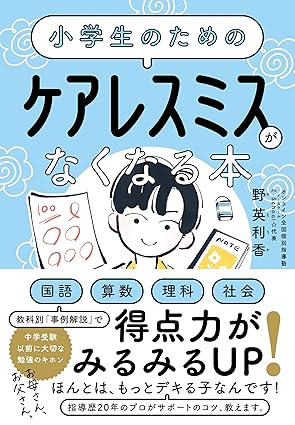おうちの生活習慣でケアレスミスがなくなる――ゲームや動画との付き合い方
国語 算数 理科 社会。教科別「事例解説」で得点力がみるみるUP!指導歴20年のプロがサポートのコツ、教えます。中学受験以前に大切な勉強のキホン。
教育

ゲームや動画との付き合い方
楽しくても悪影響を忘れずに
男の子の場合はゲーム、女の子はYouTubeやTikTokばかりで勉強をしない、という悩みをよく聞きます。
2023年、内閣府の調査によると、小学生のネット利用率は9割以上。利用内容について上位3位までを見ると、小学生では動画視聴90.5%、ゲーム87.5%、検索72.8%となっており、やはりゲームや動画視聴が圧倒的に多いことがわかります。
なかには、ゲームやスマホの依存症になってしまう子どももいます。
ゲームや動画は、そもそも制作側が少しでも視聴者の滞在時間が長くなるために、どうしたらよいかを考えて作っているからです。
私たちのホルモンの中に、「ドーパミン」というものがあります。
これは「やる気ホルモン」とも言われ、幸せホルモンの一つですが、中毒性のあるホルモンでもあります。
達成感や、ワクワク感、楽しさを与えてくれ、やる気が出たり、集中することができたり、モチベーションが上がったりもします。
この仕組みを良い方向に使うことができればよいのですが、悪い方向に使ってしまうと、自分の行動をコントロールできなくなっていくのです。
ドーパミンが脳で分泌されると快楽を感じ、「もっとほしい」「もっとやりたい」と依存度が増していきます。
ゲーム、スマホ、SNS、たばこ、お酒、買い物、糖質など、世の中の中毒性のあるものの多くは、このドーパミンが脳で放出されるようになっています。
スティーブ・ジョブズが、自分の子どもにはスマホを持たせなかったという話は有名です。
知識のある制作側は、子どもに悪影響を与えることを十分に理解しているので、そもそもその機会を与えないのです。
これだけ中毒性のある「ゲーム」や「スマホ」を自制するのは、子どもには難しいことです。放っておくと、やめるべきときにもやめられなくなり、お風呂や宿題も後回し、夜ふかしで睡眠不足になり、だんだん授業にも集中できなくなってしまいます。
親子で一緒にルールを作る
では、このように危険なゲームやスマホとどのように付き合っていくとよいのでしょうか。
子どもは自分で自分を制御するのがまだまだ難しいので、おうちでルールを作ることが大切です。
〇たとえば、おうちに帰ってきたら、スマホ置き場に置く。
〇そして、宿題が終わったら、時間を決めてスマホを使う
〇寝るときも、寝室とは別の部屋のスマホ置き場に置く
というように最低限決めておくと、スマホと上手に付き合えるようになってきます。
ゲーム機やタブレット、パソコンの場合もルールを作ります。
ルールを作るときは、頭ごなしに親が決めてしまうのではなく、子どもの意見も聞きながら決めていくとうまくいきやすいです。
強制感のあるルールよりは、共感のあるルールのほうが守ってくれます。
「一日何時間までとするのか」「使う時間帯はいつか」「使うアプリはどれか」「土日は少し時間を増やしてもよいか」など、お互いが気持ち良く生活していくために、そして何よりも子ども自身が健やかに成長していけるようなルール作りが大切です。
また、ゲームやスマホ中心の生活にならないためにも、子どもが日々「目的」を持って過ごせているかどうかも重要です。
私たち大人も、目的がないと、なんとなくだらだら過ごしてしまうことはありませんか?
流れてくるTikTokやInstagramの画面を漫然と眺めたりしていないでしょうか。
もし、自分の趣味や学びたいことがあれば、それに夢中になるはずです。
子どもも同じです。
何のために勉強をするのか、将来どうなりたいかなど、大まかにでも目標があると、「ゲームもしたいけど勉強もしなきゃいけない」と思うようになるはずです。
そうして取り組む毎日の勉強の中にも、喜びや達成感は必ずあります。
「ついにできた」「難しいけどわかった」。
そんなワクワクを一つでも増やしていくことが、スマホやゲームともバランスよく付き合う近道です。
ルールを守れなかったときは
しかし、親が気をつけていても、子どもがルールを守れないことはあります。
そんなとき、頭ごなしに叱ったり、ゲーム機やスマホを取り上げたりはしないでください。
反発心がメラメラ燃え上がってしまいます。
ここがお母さまお父さまにとっては、大変しんどいところなのですが、いったん見て見ぬふりをするのです。
そして、落ち着いたタイミングで、冷静になって子どもと話し合いの時間を設けます。
感情的になった勢いで話をしてしまうと、子どもとの心の溝が大きくなるばかりです。
それより、落ち着いたタイミングで話し合うことで、子どもも冷静に考えることができます。
また、ゲームやスマホなどへの依存が、自分たちの体にどのように影響をするのかについても、ぜひお子さんと話し合っていただきたいです。
子どもは、親が単に勉強させたいからゲームやスマホを取り上げるんだと思っていることも多いです。
そうではなく、本当に私たちの体に悪影響があることを伝えるのも親としての役目だと思います。
また、先にも触れましたが、生徒の親がスマホでゲームをしながら「勉強しなさい」と言っていることをしばしば聞きます。
もちろん、これでは説得力がありません。
私たち親自身も、自分自身の体を守るためにもドーパミンとはうまく付き合っていく必要があります。
オンライン全国個別指導塾「E-School☆」代表
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね