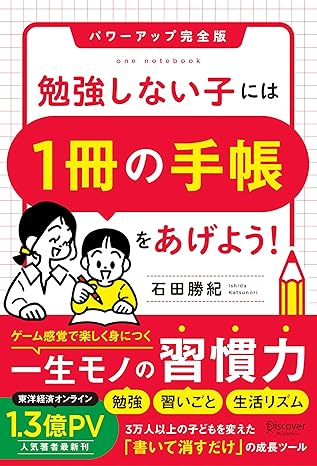子どもが変わる!「1冊の手帳」――「子ども手帳」で実感できる3つの効果
1日で100万PVを超えた人気記事の書籍化! 勉強・習いごと・いい生活リズムが習慣化され、 「子どもが変わった」実例続々!
教育

「子ども手帳」で実感できる3つの効果
ここでは、「子ども手帳」の効果について説明します。
手帳の使用者が増えるにしたがって、子どもへの素晴らしい効果がいくつもあることがわかってきました。
手帳の効果1 自走力がつく
最近は、自ら動ける能力のことを「自走力」というようです。
もちろん未就学児の頃は、自分でスケジュール管理をするわけではないので親から言われないと動けないことが少なくありません。
しかし、子どもが小学生、中学生、場合によっては高校生になっても自ら動かない状況は親としてもイライラの温床になります。
では、自走力をつけるにはどうすればいいでしょうか。
まず、これは声かけでは変わりません。
いくら声をかけても、それは単なるアラーム機能にしかならないからです。
子どもが「登園できたこと」=「成長を見える化」することで、幼稚園へ行くモチベーションが高まります。
自分から登園=「自走」できることで、幼稚園へ行くために必要な準備を自分で用意する=「自律」できます。
やがて、親の意見は関係なく自分の意思だけで登園する「自立」するようになります。
人間の深層心理では、成長することにわくわく感を覚えます。
成長の見える化は、自走力を鍛えるための必需品です。
もちろん成長の見える化は必要なく、勉強が好きだから、興味があるからと進められる子であれば、そのままで大丈夫です。
生活習慣についても、いちいち親から言われなくてもきちんとできるようであれば、見守っていればいいでしょう。
しかし残念ながら、そのようなケースは多くありません。
子どもに自走力がないことは、保護者のイライラの原因になってしまうのです。
そんなときはぜひ「子ども手帳」を作って実践してみてください。
子どもの変わりように驚くでしょう。
手帳の効果2 自己肯定感が高まる
「子ども手帳」は、自己肯定感を上げるための手帳といっても過言ではないほどの効果があります。
自己肯定感とは、「短所も含めて今の自分がイイね」と思える気持ちです。
日本の子どもたちは、自己肯定感が低いという実態が統計データによって示されています。
つまり、自分のことを「イイね」と思えない子どもがたくさんいるのです。
私は4500人以上の子どもたちを指導してきた経験から、子どもたちの自己肯定感を下げている原因は勉強だと考えています。
学校や塾で「できないところ」を指摘されて、苦手科目を克服することに重点を置いた指導ばかりされていたら、自己肯定感は下がる一方です。
さらに、毎日学校や塾へ行って授業を受けても、目に見えて学力が上がるのを実感できなければ、子ども自身が自分は成長しているという実感を得ることは難しいものです。
本当は新しいことを一つ知ったらそのぶん賢くなり、自分の間違えた問題が一つわかるようになったら一問ぶん成長しているのですが、そのような実感はわかないでしょう。
「子ども手帳」はテストの点数が取れたからポイントが入るのではなく、宿題が完了したらポイントが追加され、プリントを1枚やったらポイントが加算されます。
また生活習慣においても、一つのタスクができたらポイントゲットです。
つまり、結果に対してではなくプロセスに対してのポイント追加になるので、行動さえすればポイントが入ります。
そして、ポイントは毎日累積されていくので、日々自分が成長していることが数字で実感できる仕組みになっています。
これが、自己肯定感が高まる理由です。
ポイントが日々どんどん増えていくことで、「自分って、もしかしてイケているんじゃない?」「伸びているんじゃない?」と思えるようになります。
自己肯定感が上がると心に余裕ができて、苦手なこと・嫌いなこと・欠点・短所でも、克服できる確率がぐっと高まります。
その結果として、宿題、勉強といった子どもたちにとってマイナスイメージの強い物事に対しても、前向きに取り組めるようになるのです。
自己肯定感が高まった子どもの姿を見ることは、親にとっても大きな喜びになるでしょう。
手帳の効果3 ポジティブな習慣が身につく
「子ども手帳」の最終目的は、ポジティブな習慣が身につくことです。
この手帳の仕組みを試してみるとわかりますが、毎日ある一定のパターンが形成されていきます。
人間は決まった時間に決まったことを繰り返すことで、それが歯磨きのように自然と習慣化されていきます。
通常、子どもはやりたくないことは後回しにして、やりたい遊びを先にやる傾向があります。
これは大きな問題ではありませんが、結局やらなければならないことが終わらなくなって、子どもの寝る時間が遅くなってしまった経験をした保護者も多いのではないでしょうか。
それが習慣になってしまうと、その非生産的なサイクルから抜けだすことが難しくなります。
しかし「子ども手帳」の仕組みを活用すれば、いい習慣が身につきます。
やりたくないけれどやらねばならないことほどポイントの点数を高くすると、やるべきことを先にやるようになり、しかもそれが習慣化できるのです。
これは、ロールプレイングゲームにおいて、弱い敵を倒しても加算される経験値が少ないのに対し、強い敵を倒すと高い経験値をもらえるのと同じ原理です。
この仕組みを使えば、初めはやりたくなかったことでも続けられるので、それが自然と習慣化され、やがて成果がでます。
勉強なら成績が伸び、生活習慣が改善されれば親から褒められるので、子どもは喜びが強くなり、その習慣を継続するモチベーションが相乗効果で高まります。
ここまでくれば、「継続は力なり」の法則が働くため、子どもたちはもはや「子ども手帳」がなくても習慣の力で行動できるようになっていくのです。
一般社団法人教育デザインラボ代表理事。国際経営学修士、教育学修士。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね