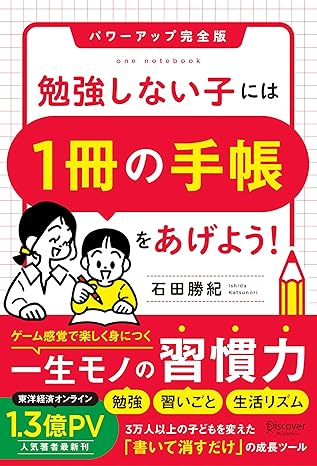子どもが変わる!「1冊の手帳」――子ども手帳が続かない3つの決定的な理由
1日で100万PVを超えた人気記事の書籍化! 勉強・習いごと・いい生活リズムが習慣化され、 「子どもが変わった」実例続々!
教育

手帳が続かない3つの決定的な理由
実際には「子ども手帳」を始めてみたけれど、続かない人もいます。
勉強や生活面での毎日のやるべきことを完了させられる習慣が身についていれば、「子ども手帳」を続ける必要はありません。けれども、習慣化の前に続かなくてやめてしまったケースもあります。
そこで多くの実例から続かない理由を調べたところ、次の3つのいずれかがクリアされていないことがわかりました。
続かない理由1 子どもに手帳を使う許可をとっていない
子どもの許可を得ずに親の一方的な考えで進めると、子どもはすぐにやめてしまいます。
必ず子どもに「手帳を使ってポイントがたまる楽しい方法があるけど、やってみる?これで、やるべきことができるようになるらしいよ」と話し、子どもが「やりたい」と言ってから始めましょう。
子どもの許可が必要だからといって、子どもを説得してやらせたケースもあります。
しかしこれは、無理やりやらせたことと同じです。
あくまでも、子どもが興味を持って「やってみたい」と純粋に思う気持ちが大切です。
この出発点を間違えると、「子ども手帳」が親のための手帳となり、本来の機能を果たせません。
子どもが「やりたくない」と言ったときは、手帳は使わないようにしましょう。
ただし、ここで一つ留意してほしいことがあります。
子どものやりたくないは「今はやりたくない」という気持ちであって、「今後もずっとやりたくない」という意味ではありません。
実際に、1か月後に話をしたら「やる」という子もいます。
とくに春夏冬の長期休みは、「子ども手帳」をイベントのように楽しく提案しやすい時期です。
そのため、子どもが「やる!」と積極的になるケースが増えます。
つまり、子どもが今「子ども手帳」を拒否しても、それは今後もやりたくないという意味ではないので、タイミングをみて子どもに再度話すのがおすすめです。
続かない理由2 手帳を「継続するべき」と親が思い込んでいる
保護者の中には、「子ども手帳」を始めたら継続することにこだわる人がいます。
継続は確かに重要ですが、継続するには終わりを設定してから始めてください。
とくに、最初の1週間は試行期間として大切な時期です。
この1週間で子どもが「やっぱりやめる」と言ってきたら、素直にやめましょう(前述したように、子どもはのちのち「やる!」と言うときがきます)。
1週間たって、更新するかどうか子どもの意向を聞いたときに「やる」という意思が確認できたら、さらに1週間行います。
このように終わりを設定しないと、子どもに「一体いつまでやるの?」という気持ちが芽生えてマンネリ化します。
その結果ダラダラやるようになり、いつしか義務感へと変わってしまうのです。
何事も、終わりを決めてから始めることが大切です。
これは「子ども手帳」だけに限りません。
大人の会議もそうですよね。
開始時間は書いてあるのに、終了時間が書いていないので、ついダラダラと会議が長引いてしまった経験はないでしょうか。
終わりを決めると、人はそこに向かって全力でやり抜くようになります。
習慣化できるまでは、手帳を実践する期限を決めておくことが重要です。
その点で考えると、長期休みの場合は元々終わりがあるため実践しやすいでしょう。
学校のある平常時で期間が区切りにくい時期は、まずは1週間。
そのあとも続けたいなら、さらに1週間。
それが1か月続いたら1か月毎の更新にしていくと、やがて習慣化されていきます。
続かない理由3 手帳を使って親が子どもを管理しようとする
「子ども手帳」が続かない最大の理由がこれです。
親が子どもの管理ツールとして手帳を使ってしまうケースです。
「子ども手帳」は、子どもが自分で自分を管理していくツールであって、親のための管理ツールではありません。
ただし、手帳の使い方やポイント設定などで子どものサポートはします。
サポートと管理することは、まったく異なります。
親が管理ツールだと思っている場合、次のような言葉がでてきます。
・「今日はポイントチェックしたの?」
・「今日はまだ書いてあることやっていないよね」
・「手帳に書いてあること、いつになったらやるのかな?」
保護者からこのような言葉がでていたら、「子ども手帳」の機能が失われている可能性が高くなります。
再度、手帳を実践するかどうか、子どもに確認することから始めてください。
ここまで「子ども手帳」が続かない3つの理由についてお話ししてきました。
逆に言えば、この3つがクリアできていれば「子ども手帳」は十分に機能します。
お子さんには「絶対に今やらせたい」と考えるのではなく、ゲーム感覚で「やってみない?」というアプローチをしてみてください。
また、子どもは「今」の感覚しかないので、今やりたくなくても、その先の気持ちがどう変わるのかは誰にもわかりません。
もしかしたら、今は嫌でも、数週間後にはやってみたくなるかもしれないのです。
その点も考慮しながら、「子ども手帳」に取り組んでみましょう。
一般社団法人教育デザインラボ代表理事。国際経営学修士、教育学修士。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね