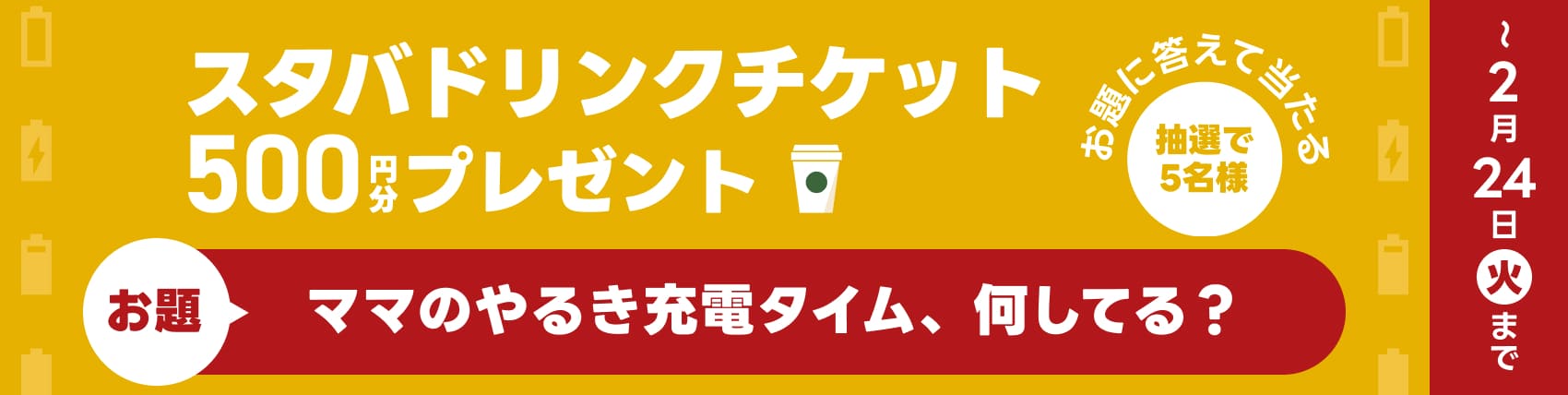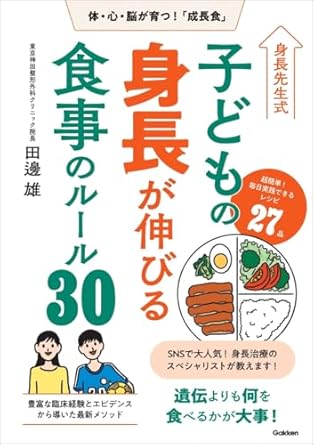集中力・感情・学習能力は食で変わる!「幸せホルモン」を増やす朝ごはんのコツ
やる気も集中力も、食卓で育ちます。おさかなキライ!フライドポテトしか食べたくない!にんじんはマズイ!がんばりすぎなくても大丈夫。毎日のシンプルな〈ごはん〉が子どもの力になる!
食事

「うちの子、どうしてやる気が続かない?」その原因は性格ではなく“栄養の偏り”かもしれません。食事で子どもの心と脳を育てるコツを具体的に伝授。すぐに試せるレシピも満載の一冊。
藤川里奈先生著書の『子どものやる気を育てる〈ごはん〉の法則』から一部転載・編集してお届けいたします。
集中力・感情・学習能力は食で変わる!
「幸せホルモン」を増やす朝ごはんのコツ
「朝ごはんは食べたのに、なぜかイライラ……」
「朝から不機嫌で、ちょっとしたことで泣いたり怒ったりする」
そんなうまくいかない朝の原因、実はセロトニン不足かもしれません。
セロトニンとは、感情を落ち着かせたり、前向きな気分をつくったりする幸せホルモンのひとつ。
脳内の神経伝達に関わり、心の安定や睡眠の質、やる気、集中力にも深く関係しています。
このセロトニンが不足すると、気分が不安定になったり、ちょっとした刺激に敏感になったり、感情のコントロールが難しくなることがあります。
このセロトニンを増やすために欠かせないのが、トリプトファンという栄養素です。
トリプトファンはアミノ酸の一種で、セロトニンの材料になります。
体内ではつくることができないため、食事から摂取する必要があります。
トリプトファンをしっかり摂ることで、セロトニンの分泌がスムーズに行われ、心の安定につながるのです。
特に、朝ごはんでトリプトファンをしっかり摂り、朝の光を浴びることが、セロトニンの合成にとても効果的だといわれています。
なぜなら、セロトニンは朝のリズムによって脳内でつくられるからです。
起きたらカーテンを開け、朝日を浴びながらごはんを食べる——それだけで、セロトニンの分泌が促進され、気持ちが前向きに整いやすくなります。
朝の光を浴びることで、体内ではビタミンDも生成されます。
ビタミンDは、骨の栄養素として知られていますが、実は免疫や気分の安定にも関わる大切な栄養素です。
不足すると幸せホルモンのセロトニンの合成に影響することも報告されています。朝の日光は、心と体にとって、かけがえのない栄養源。
つまり「何を食べたか」だけではなく「どう朝を過ごすか」も子どもの感情や集中力を支えるカギなのです。
機嫌よく一日をスタートするには、セロトニンづくりを意識した朝ごはんがカギ。
栄養バランスを意識した朝ごはんと、朝の太陽の光。それは、脳と心に効く最高のプレゼントかもしれません。
トリプトファンを多く含む食品
・納豆や豆腐などの大豆製品
・バナナやナッツ類、白米などの炭水化物
・卵やチーズ、牛乳などの乳製品
・赤身の肉や魚(特にまぐろ、かつお、いわし)
朝ごはんを抜くと集中力が下がる本当の理由
「朝ごはんを食べる時間がなくて……」
「うちの子、朝はあまり食べたがらなくて......」
そんな理由で、抜いてしまうことさえある朝ごはん。
でも、それによって子どもの脳は深刻なエネルギー不足に陥っているかもしれません。
私たちの脳は、眠っている間もエネルギーを使い続けています。
特に朝はガス欠状態になっており、朝ごはんを摂らないと、うまく働き出せません。
集中できない、ボーッとする、反応が遅れる......そんな朝の困った状態は、栄養が足りていないサインかもしれないのです。
エネルギー不足が続くと、低血糖に近い状態に陥ることもあります。
血糖値が下がると、脳に必要なブドウ糖が届かず、イライラ、不安感、立ちくらみ、判断力の低下などを引き起こしやすくなります。
特に小さな子どもは血糖を安定させる力が弱いため、朝ごはん抜きは大きな影響を与えるのです。
大人は「朝を抜いても平気」と言う方もいますが、子どもは違います。
子どもは大人よりもエネルギー消費が旺盛で、体も脳もどんどん成長しています。
成長中の子どもは一度にたくさんの栄養を蓄えることが難しいため、こまめなエネルギー補給が必要です。
朝ごはんでブドウ糖やタンパク質、ビタミンB群などをしっかり補うことで、脳にスイッチが入り、感情や行動も落ち着きやすくなります。
また、集中力や学習意欲も高まり、一日のスタートがスムーズになるのです。
「朝はなかなか食べられない」という子には、少量でも栄養のあるものを選ぶのがポイン
おにぎり+味噌汁、ゆで卵+フルーツ、パン+バナナ、具だくさんスープなど、手軽でも栄養バランスが整う朝ごはんはたくさんあります。
頭が良くなる?食事のタイミングのヒミツ
「頭が良くなるのは、どんな食べ物?」
そんなふうに思ったことはありませんか?
実は、何を食べるかだけでなく、いつ食べるかも、脳にとってはとても大事なポイントです。
脳がもっとも活発に働くのは、朝〜午前中の時間帯といわれています。
このタイミングに必要なエネルギー(ブドウ糖やビタミンB群など)をきちんと届けられるかどうかで、集中力や記憶力に差が出るのです。
脳の主なエネルギー源は「ブドウ糖」。
貯蔵がきかず、朝までにほとんど使いきってしまうため、朝食での補給がとても重要です。
東京大学やカリフォルニア大学の研究でも、朝食を摂った児童のほうが集中力が高く、記憶力テストの成績が良好だったという報告があります。
また、ビタミンB1やB6といったビタミンB群は、脳の神経伝達物質をつくるサポートをしており、これらが不足すると集中力不足の状態になりやすいこともわかっています。
朝食を抜いて、夕方~夜にまとめてたくさん食べると、エネルギーが必要な時間帯に間に合わず、脳の働きがダウンしてしまうことがあります。
夕方以降のドカ食いは血糖値の乱高下や睡眠の質にも悪影響を及ぼすため、できるだけ避けたいところです。
子どもたちは、日中は保育園や幼稚園などで規則正しい時間に給食やお弁当を食べているかもしれませんが、お休みの日になると、ママたちもゆっくり起きて、朝ごはんの時間が遅くなりがちです。
朝と昼が一緒になってしまったり、夜の食事も遅くなってしまうことで、脳のエネルギーの流れが乱れ、心と体のリズムも崩れやすくなります。
食事の内容だけでなく、タイミングにも少し目を向けることで、子どもの集中力や学習の効率がぐんと変わってくるのです。
朝食には、ブドウ糖のもとになるごはんやパンなどの炭水化物に加え、ビタミンB群を多く含む卵、納豆、海苔、豚肉などを組み合わせるのがおすすめです。
食事のタイミングは、脳と心のゴールデンタイムを支える大切なカギなのです。
子どもがイライラするのは「血糖値」のせい?
「朝は機嫌が良かったのに、急に怒り出した」
「さっきまで笑っていたのに、急に泣いたり叫んだりする」
そんなジェットコースターみたいな子どもの感情の波に、困った経験はありませんか?実はその原因、血糖値の乱れかもしれません。
血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度のこと。
脳にとってのエネルギー源は、ほぼこのブドウ糖だけなので、血糖値の安定は、感情の安定にも直結します。
食事で血糖値が急激に上がると、体はそれを下げるためにインスリンというホルモンを大量に分泌します。
すると今度は血糖値が急激に下がり、低血糖に近い状態に......。
この血糖値の乱高下が、イライラ・不安感・眠気・癇癪につながるのです。
特に子どもは大人に比べて代謝が活発で、体も小さい分、血糖値が急に変動しやすい傾同にあります。
そのため、朝食を抜いたり、甘いお菓子やジュースを空腹時に摂ると、その後に急激な血糖値の上がり下がりが起こりやすくなります。
実際に、国内外の研究でも、食後の血糖値変動と子どもの行動異常には相関があるという報告があります。
2012年にアメリカの「臨床栄養学ジャーナル」で発表された論文では、血糖値の乱高下が感情制御に関連する前頭前野の活動に影響を与える可能性が示唆されています。
また、血糖値が急に下がることで、脳が危険と判断し、コルチゾール(ストレスホルモン)が分泌され、パニック的な反応を引き起こすというメカニズムも知られています。
「うちの子、育てにくいなぁ」「かんしゃくが多くて困る」と感じていたら、それは性格やしつけの問題ではなく、血糖コントロールの課題かもしれません。
甘いものを完全に禁止する必要はありませんが、空腹時に単独で与えるのは避け、タンパク質や食物繊維と一緒に摂るように意識すると、血糖値の急上昇を防ぐことができます。
また、白砂糖の摂取を控えることもおすすめです。
白砂糖は吸収が速く血糖値を急激に上昇させやすいため、アガベシロップやはちみつ、きび糖、ココナッツシュガーなど、血糖値の上昇が穏やかな甘味料に置き換える工夫も役立ちます。
子どもの才能を育てるおうちごはんの専門家、調理師、ケーキ店オーナー。
医師・医学博士/三重大学名誉教授/桑名市総合医療センター理事/学校法人湘央学園・湘央生命科学技術専門学校学校長。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね