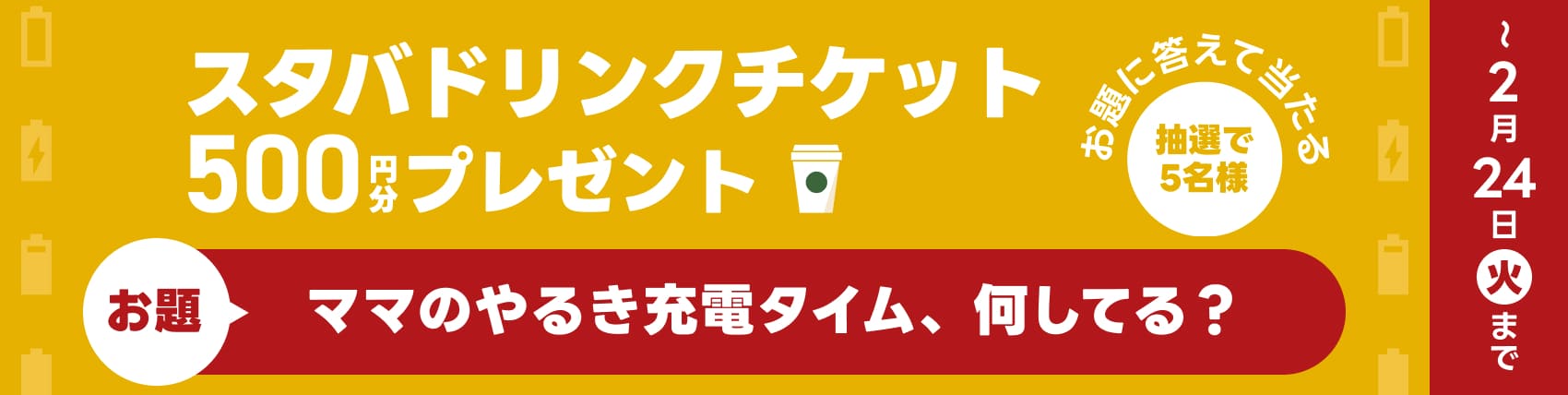食べたもので脳はつくられる!子どもの未来を変える栄養のヒミツ
やる気も集中力も、食卓で育ちます。おさかなキライ!フライドポテトしか食べたくない!にんじんはマズイ!がんばりすぎなくても大丈夫。毎日のシンプルな〈ごはん〉が子どもの力になる!
食事

「うちの子、どうしてやる気が続かない?」その原因は性格ではなく“栄養の偏り”かもしれません。食事で子どもの心と脳を育てるコツを具体的に伝授。すぐに試せるレシピも満載の一冊。
藤川里奈先生著書の『子どものやる気を育てる〈ごはん〉の法則』から一部転載・編集してお届けいたします。
食べたもので脳はつくられる!子どもの未来を変える栄養のヒミツ
脳をつくるって具体的に何が必要?カンタン栄養ガイド
「脳を育てるには、幼児教育や知育玩具が大切」
そんなふうに思っていませんか?
もちろん、教育や経験も大切です。
けれど、それ以前に――そもそも“脳そのもの”をつくっているのは、毎日の「食べ物」なのです。
脳の約60%は脂質でできており、残りの大部分をタンパク質や水分が占めています。
そして、神経の伝達に必要なミネラルやビタミンがなければ、情報をうまく処理したり、記憶したりすることもできません。
いい脳をつくるためには、きちんと栄養を摂ることが何よりの土台になります。
同じ時間、同じ勉強方法を行ったとしても、脳の質によって、学習効果には大きな差が出るのです。
子どもが集中できなかったり、イライラしやすかったりするのは、「やる気の問題」ではなく、脳の材料が足りていないサインかもしれないのです。
ここからは、脳の働きを支える4つの栄養素について、少し詳しく見ていきましょう。
脳の柔軟性と神経伝達を支える
DHA・EPA(脂質)
DHAやEPAは、魚に多く含まれる良質な脂質。
脳の細胞膜をやわらかく保ち、情報をスムーズにやりとりするために欠かせません。
特にDHAは「考える力」「記憶力」に関わる働きをし、乳幼児期の脳の成長には非常に重要な成分です。
体内ではほとんどつくることができないため、食事からの摂取が必要不可欠です。
神経伝達物質の材料となる
タンパク質
セロトニンやドーパミンといった「感情」や「やる気」に関わる神経伝達物質の原料となるのが、タンパク質。
脳だけでなく、体づくりにも不可欠な栄養素ですが、朝食やおやつでは不足しがちです。肉、魚、卵、大豆製品など、1日3回こまめに取り入れることが大切です。
集中力を支える
鉄分
鉄は、脳へ酸素を届ける「赤血球」の材料です。鉄不足になると、頭がぼんやりしたり、
イライラしやすくなったりします。
特に、女の子は2歳以降、男の子は運動量が増える頃から不足しがちです。
レバー、赤身肉、あさり、卵などを積極的に取り入れましょう。
吸収率を上げるには、ビタミンCと一緒に摂るのがポイントです。
脳のエネルギー代謝をサポートする
ビタミンB群
ビタミンB群は、糖や脂質をエネルギーに変える「代謝」を助け、神経の働きを安定させる栄養素です。
特にB1(玄米・豚肉)、B6(バナナ・まぐろ)、B22(魚介類・卵)は神経系と関係が深く、イライラや疲れやすさの改善にも役立ちます。
加工食品や白米中心の食生活では不足しやすいため、意識して取り入れることが必要です。
「脳にいい食べ物」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実は、スーパーで買えるいつもの食材の中に、脳に必要な栄養素がたくさん詰まっています。
難しい知識や特別な料理は必要ありません。
まずは「脳の材料になるものを意識する」ことから始めてみましょう。
鉄分で集中力がアップするってホント?
「ごはんはしっかり食べているはずなのに、なんだか集中できない」
そんな子どもの様子が続いていたら、鉄分不足が隠れているかもしれません。
鉄は、脳に酸素を運び、思考や記憶に必要なエネルギーを生み出すための必須ミネラル。
不足すると、知らないうちに「集中できない」「疲れやすい」状態になってしまうのです。「鉄分って、貧血に関係あるんでしょ?」
と思う方も多いかもしれませんが、実はそれだけではありません。
鉄は“集中力”“やる気”“感情の安定”に深く関係している、大切な栄養素なのです。鉄が不足すると、脳に十分な酸素が届かず、神経伝達もうまくいかなくなります。
その結果、集中が続きにくく、感情が不安定になったりするのです。
最近は、子どもの「隠れ貧血」が増えているといわれています。
朝ごはんに菓子パンや白いごはんだけ、という食生活では鉄分が不足しやすくなります
牛乳の摂りすぎやお菓子を大量に食べる食習慣も、鉄分の吸収を妨げる要因になります。鉄分には「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」があり、吸収率の高いヘム鉄は主に動物性食品(レバー・赤身肉・魚など)に含まれます。
一方、植物性食品(小松菜・ひじき・大豆など)に含まれる非ヘム鉄は、ビタミンCと一緒に摂ることで吸収率がアップします。
たとえば、レバー炒めに赤ピーマンやブロッコリーを添えたり、ひじき煮を小松菜のお浸しと一緒に出すのもおすすめです。
昔は、鉄分=ひじきでしたが、調理の際に鉄鍋を使用しなくなったことにより、ひじきの鉄分含有量は、1950年から2020年の70年間で、100gあたり55mgから6.2mgまで、減ってしまっています。
ですから、鉄分をしっかり摂るには、「鉄鍋」や「鉄玉子」など、調理器具を工夫するのもひとつの方法です。
集中力・落ち着きのなさが、神経伝達に必要な鉄分不足だったとしたら、ちょっとした食生活の見直しが、子どもの毎日をぐんとラクにしてくれるかもしれません。
「鉄分=貧血予防」ではなく、「鉄分=集中力の土台」として、ぜひ意識してみてください。
おなかの調子と気分はつながっている!「腸内環境」の話
「子どもがイライラするのは、性格のせい?」
と考えがちですが、その原因は、意外にもおなかにあるかもしれません。
腸内環境の乱れが、気分や感情の安定に影響することがわかってきているので、
「最近なんだか機嫌が悪い」
「よく泣いたり怒ったりする」
といった様子が続くときは、ぜひおなか(腸)の調子にも注目してみてください。
腸は“第2の脳”と呼ばれるほど、脳と密接な関係があります。
この関係は『腸脳相関』と呼ばれ、医学的にも注目されている分野です。
腸と脳は、迷走神経という神経を通じて双方向につながっていて、腸の状態がそのまま脳に伝わる仕組みになっています。
腸内環境が良いと脳もリラックスしやすく、感情の安定にもつながるというわけです。そしてもうひとつ大切なのが、セロトニンというホルモン。
セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、感情の安定や睡眠の質にも関係しています。驚くべきことに、このセロトニンの約90%以上は、腸でつくられており、腸の健康は心の安定とも関わっていると考えられています。
つまり、腸の状態が悪いと、セロトニンの分泌も低下し、気分の不安定さや不眠、イライラにつながることがあります。
便秘がちな子、軟便が多い子、食べムラやおなかの張りが気になる子は、腸内環境の見直しが必要かもしれません。
腸内環境を整えるには、善玉菌を増やすことはもちろん、腸内細菌のバランスを保つことが大切です。
納豆などの発酵食品、食物繊維、オリゴ糖などを意識して食事に取り入れてみましょう。また、加工食品や食品添加物、白砂糖の摂りすぎは腸内環境を悪化させる原因になるため、できるだけ控えることが大切です。
子どもの情緒の安定を支えるために、腸という視点からもサポートできることがあると考えると、日々のごはんの選び方が、もっと意味のあるものに感じられるかもしれません。
子どもの才能を育てるおうちごはんの専門家、調理師、ケーキ店オーナー。
医師・医学博士/三重大学名誉教授/桑名市総合医療センター理事/学校法人湘央学園・湘央生命科学技術専門学校学校長。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね