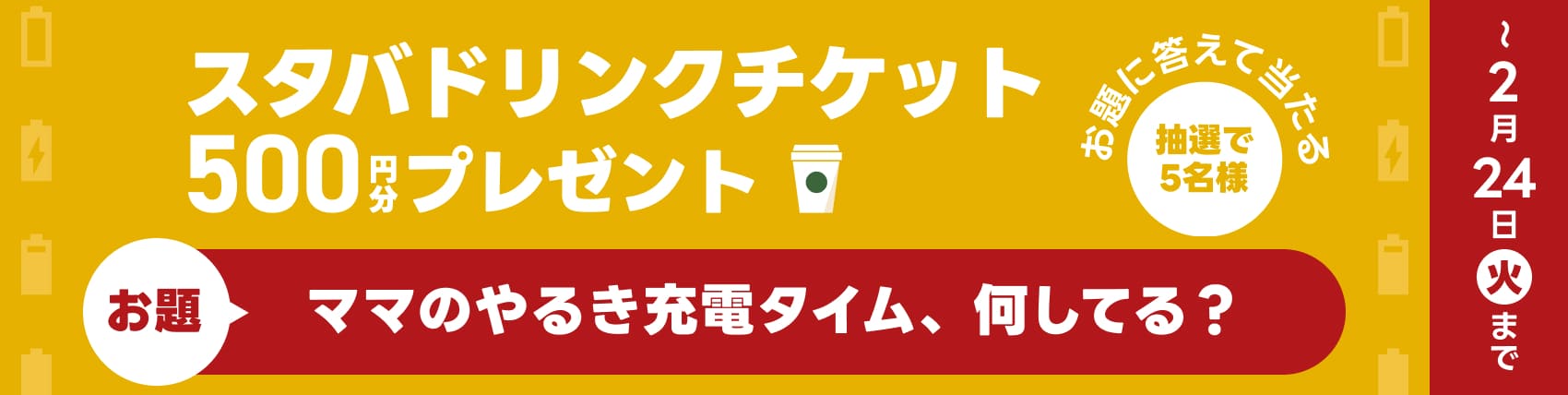現役ママ歯科医が伝える!噛む力が子どもの脳を育てる――年齢別アドバイス食育編 0~5か月
「噛む回数」が増える食材の切り方とおいしいメニュー 、口と舌を鍛える楽しい歌と遊び……など、0歳~小学生へ 歯と口のママドクターが年齢別アドバイス。子どもの脳がぐんぐん育つ食育と生活習慣を伝授する一冊。
食事

噛む力が子どもの成長に与える影響を探る本書。集中力や心の強さを育む方法を、具体的な実践例と共に紹介します。
生澤右子先生の著書『集中力が高まり、心の強い子になる!噛む力が子どもの脳を育てる』から一部転載・編集してお届けいたします。
年齢別アドバイス食育編
年齢ごとに食育において気をつけるべきポイントについて解説します。
覚えておいていただきたいのは、おっぱいは生まれた瞬間から反射的に飲めるのに対し、食事は脳の発達とともにトレーニングして、徐々に習得していくものということです。
0~5か月(歯が生える前)※月齢は目安です
Q1 おっぱいは赤ちゃんの脳やロの発達に関係がありますか?
赤ちゃんは生まれた直後には、原始的な脳といわれる脳の奥(脳幹)の働きで、反射としてチュパチュパとおっぱいを飲んでいます。
あごや舌の筋肉を使うその刺激が脳に伝わったり、おっぱいを飲んだ経験(学習)が蓄積されたりして脳(大脳皮質)が発達していき、おっぱいを吸う反射がなくなっていきます。
また、かむリズムを作る脳の部分もだんだん発達して、離乳食を始めるのによい段階になっていきます。
赤ちゃんがおっぱいを飲むときは、舌で前後にしごくようにします。
この動きが強ければ、さらにあごが大きくなったり、口の周りの筋肉に力がついたりしていきます。
つまり、大事なことは深く乳首をくわえさせて、おっぱいを飲んでもらうことです。
もし乳首のくわえ方が浅いと、舌の手前にしか乳首が届かないので、しごく力も全力でなくてよくなります。
刺激が少ないので、あごや筋肉の成長が弱くなってしまいます。
これは、哺乳びんでも同じですので、気をつけましょう。
ミルクが出る穴が大きすぎると、簡単に飲めてしまうので、赤ちゃんは必死になって舌を動かす必要がありません。
Q2 ロの発達をうながす授乳のポイントは?
乳首を深くくわえさせるには、赤ちゃんの口が120度以上に大きく開いて、下くちびるの赤い部分がめくれているかどうかを確認してください。
また、赤ちゃんの口に対して、乳房が横長になるように手を添えましょう。
例えば、まだ新生児の赤ちゃんならば、授乳のときにフットボールのように抱っこしますが、そのときは、くわえさせる乳房と同じ側の手を下からUの字に乳房にあてて、少し真ん中に寄せるようにします。
イメージとしては、サンドイッチを食べるときに断面が横になるように食べるほうが、断面が縦よりも食べやすいですね。
口の横幅とサンドイッチの横の断面を合わせるということです。
それと同じように、乳房の向きを赤ちゃんの口に合わせるようにします。
そうすると、赤ちゃんにとって、しごきがいのあるおっぱいになります。
その分、たまっているおっぱいが出てきますし、しごくのによりパワーが必要です。
すると、舌や口の周りの筋肉のトレーニングになり、あごにも刺激がいき成長を促します。
赤ちゃんが成長してきたら、徐々に頭を立てるようにして本来の食事の姿勢に近づけていきましょう。
歯科医師・歯学博士。「親子のためのはははクラブ」「こどもはいしゃアカデミー」主宰。株式会社Dental Defense代表取締役。
医師・脳生理学者。東邦大学医学部名誉教授。セロトニンDojo代表。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね