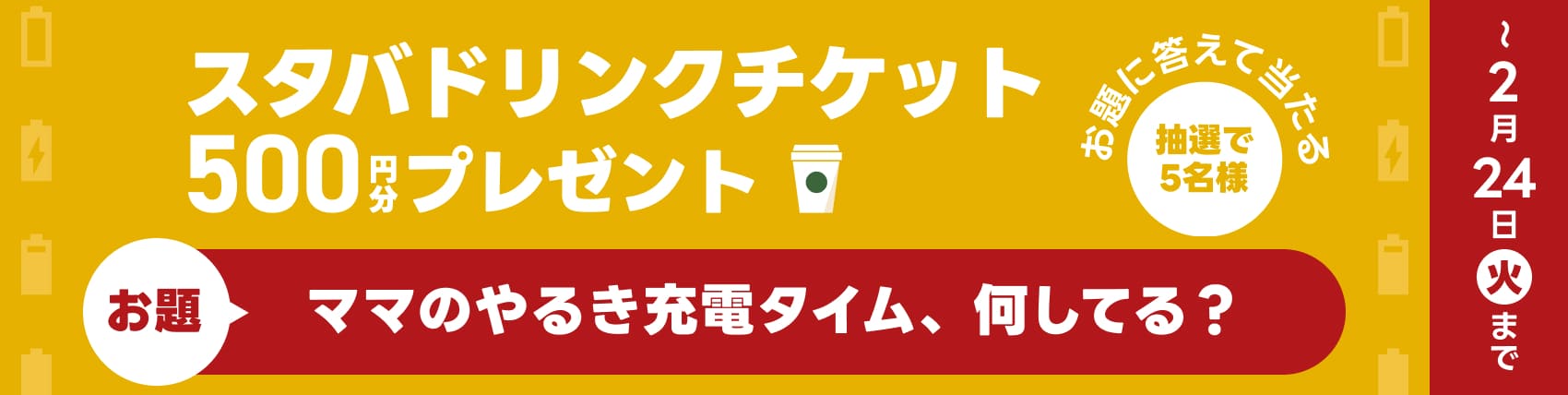現役ママ歯科医が伝える!噛む力が子どもの脳を育てる――年齢別アドバイス食育編 3歳~小学校低・中・高学年
「噛む回数」が増える食材の切り方とおいしいメニュー 、口と舌を鍛える楽しい歌と遊び……など、0歳~小学生へ 歯と口のママドクターが年齢別アドバイス。子どもの脳がぐんぐん育つ食育と生活習慣を伝授する一冊。
食事

噛む力が子どもの成長に与える影響を探る本書。集中力や心の強さを育む方法を、具体的な実践例と共に紹介します。
生澤右子先生の著書『集中力が高まり、心の強い子になる!噛む力が子どもの脳を育てる』から一部転載・編集してお届けいたします。
年齢別アドバイス食育編
3歳~5歳(乳歯が生えそろう安定期)
Q4 子どもの歯がすべて生えたようです。大人と同じ食事でいいですか?
3歳で20本の乳歯がそろい、奥歯でもかめるようになり、”かむ機能"が完成します。
ただ、大人のかむ力には遠く及ばないので、弾力のあるもの、繊維質のもの、硬いものはまだ食べにくいです。
大人と同じ食材の場合は、長めに火を通したり、小さく切ったりして少し食べやすいように工夫が必要です。
この段階では、味わってよくかむことと口を閉じて飲み込むこと、みんなで楽しく食事をすることを覚えてもらいましょう。食事に集中できるような環境も整えます。
3歳以降にかむ機能”を訓練しても効果が低いことがわかっています。この時期に気になることがあったら、放置せずに専門家に相談しましょう。
6歳~小学校低・中学年(永久歯が生え、乳歯が抜ける)
Q5 くちゃくちゃ食べる音が気になります。どうしたらよいですか?
常にどこかの歯が抜けたり、生えたりしている忙しい時期です。
子どもの歯がグラグラしたり、痛かったりして食事に集中できないこともあります。
特に、前歯がない時期は食べにくくて大変です。
子どもの前歯が抜けて隙間があるときに、舌を前に出して飲み込むクセが一時的に復活していないでしょうか。
また、大人の大きな前歯が生えてきて、口を閉めづらくなっていたり、お口ポカンになったりしていないでしょうか。
口が開いていると、くちゃくちゃと食べる音が出ます。
歯の生えかわりの場合は、舌を出すクセがちゃんとなくなるか、口を閉じるように声がけして、様子を見ていくことも大事です。
お口ポカンの場合や歯並びに問題がある場合は、歯科医院に相談しましょう。
それでも、この時期限定の歯の隙間にストローを入れて「見て!口を閉じても、こんな飲み方できるよ」と楽しませてくれるかもしれません。(笑)
しっかりかむことと、水分で流し込んで食べないように習慣づけていくことも重要です。
そこで、おすすめしたいのがキシリトールガムをかむことです。
キシリトールガムは、天然の甘味料で、むし歯になりません。
たくさんかんで唾液を出し、あごにもよい刺激を伝えましょう。
かむリズムでセロトニン神経も元気になり、集中力や記憶力が鍛えられたり、心が安定したりと、いいことがいっぱいです。
また、かむ力を色で見ることができる面白いガム[「キシリトール咀嚼チェックガム」東京医科歯科大学(現・東京科学大学)と(株)ロッテの共同開発]もあります。
緑色のガムが、かむ力が強いほど赤く変化します。
かむ力がどれくらいか、お子さんと一緒に比べ合いっこをしても楽しいでしょう。
小学校高学年以上(永久歯がほとんど生える)
Q6 子どもが勝手にジュースやお菓子を飲み食いしています。大丈夫でしょうか。
このころになると、自由に行動できる範囲が増えて、親の目が届かなくなっていきます。
そして、友達の影響もおおいに受けます。
友達とおやつ持参で公園集合!なんてことも。
今、お子さんが小さかったら想像もつきませんよね。
私も最初にわが子から待ち合わせのことを聞いて、「ついにそんな日が来たのか~」と、うれしいやらびっくりするやら、でした。
さて、そんなとき、「おやつは持って行くけれど、飲み物は甘くないお茶がいいよね」とお子さんが自分で選べればいいですね。
また、友達の話からファストフードに憧れを持ってしまうこともあるけれど、それは本当にたまに、ということでわかってくれればいいと思います。
バランスの取れた食事や間食のコントロールを、お子さん自身でも理解できるようにしていきましょう。
これは、やがて生活習慣病の予防にもつながります。
歯科医師・歯学博士。「親子のためのはははクラブ」「こどもはいしゃアカデミー」主宰。株式会社Dental Defense代表取締役。
医師・脳生理学者。東邦大学医学部名誉教授。セロトニンDojo代表。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね