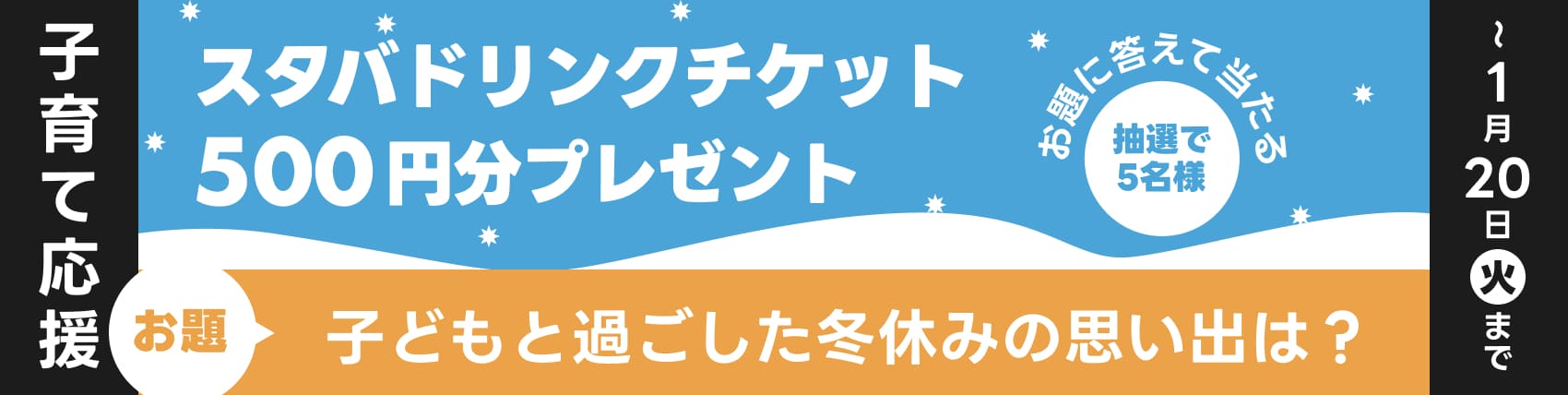脳科学者の著者が伝える!「子育て上手は質問上手」
しつけ/育児

子どもの将来を大きく左右するのは、学力だけではありません。自信ややり抜く力、協調性といった「非認知能力」が成長の要となります。
本書は脳科学の知見に基づき、日常に取り入れられる17の習慣を具体的に紹介。今日から家庭で実践できるヒントが満載な1冊。
西 剛志先生の著書『脳科学的に正しい! 子どもの非認知能力を育てる17の習慣』から一部転載・編集してお届けいたします。
子育て上手は質問上手
脳は命令されるのが大嫌い
公園や電車の中など公の場で、「早く帰るよ!」「そんなことしちゃダメ!」と大きな声でお子さんを怒る親御さんを見かけます。
いくら厳しく言っても、聞いてくれない。
また、その場では聞き入れてもしばらくたつと目の前で同じ光景が繰り返される―。
そんな経験はみなさんにもあることでしょう。
これは、私たちが命令に従わないどころか、逆のことをしたくなる性質を持っているからです。
人は「箱を開けないでね」と言われると見事に開けてしまいますし、「勉強しなさい」と言われるとやる気をなくします。
脳は命令されて縛られるのが大嫌いで、強制されると自由を求めて反発したくなるのです。この性質を心理的リアクタンスと言います。
少し変わった例ですが、私の知人で、3人のお子さんを育てた女性がいます。
その方は、ことあるごとに子どもたちに「勉強するな」と言っていたそうです。
「勉強したら父親みたいになっちゃうから勉強するな」
「知識だけ詰め込んでもアホになるから勉強するな」
などと言い続けて子どもたちを育ててきました。
その結果、お子さん3人はどうなったかというと。
一人は医学部、一人はアメリカの大学、一人は芸術系の道へと進み、それぞれの夢に向かって自立した生活を送っています。
お母さんの願いに反して、子どもたちは勝手に勉強に励んでいたというわけです。
まるで冗談のような話ですが、このような例もあるぐらい命令は逆効果なのです。
命令を質問に変えるだけで脳の反応が変わる
私がこれまでに出会ってきた子育ての天才たちは、命令に頼ることがほとんどありません。彼女(彼)らが使っているのが、マンガでも紹介している「質問」です。
具体的には「~しなさい」という命令を「~できるかな?」という質問に変換するだけ。
とても簡単です。
たとえば、子どもの食事中に「食べ物を大事にしてほしいな」と感じるシーンがあったとします。
このとき「食べ物を大事にしなさい」と命令調で伝えるのではなく、
「食べ物を大事にできるかな?」
と質問を投げかけるのです。
これで子どもたちは、伝えたことを受け入れやすくなります。
では、なぜ質問がいいのでしょうか?
先ほど脳は命令が大嫌いと書きましたが、それは人には「自分で選択したい」という欲求があるからです。
みなさんも、ビュッフェ方式のレストランで和洋中のメニューがずらりと並んでいると、何を選ぼうかとワクワクすることはありませんか?
これは、私たちが複数の選択肢の中から何かを選ぼうとするとドーパミンが出て、やる気や意欲(内発的動機)が高まるからです。
先の食べ物の例で言うと、「食べ物を大事にできるかな?」と問いかけると、子どもに「食べ物を大事にする」と「食べ物を大事にしない」という2つの選択肢を渡すことになります。
仮に「大事にする」ことを選択したら、その瞬間にドーパミンが出て、その子自らが食べ物をもっと大切にしようと思ってくれるようになるのです。
一方、「食べ物を大事にしなさい」という命令は、ひとつしかない答えを有無も言わさず押しつけている状態のため、選択の欲求が満たされず、やる気が起きなくなるというわけです。
質問で行動をイメージさせる
「命令」より「質問」がよい理由はもうひとつあります。
それは、子どもの脳内に行動しているイメージが浮かぶことです。
「食べ物を大事にできるかな?」と問いかけられたとき、子どもたちは「できるかなあ」「どうだろうなあ」と考えてから答えを返します。
このとき、言葉を認識する左脳と一緒に、右脳の上側頭回後部を含む場所も活性化され、食べ物を大事にするイメージがしやすくなります。
時間にしたらほんのわずかかもしれませんが、この「時間」が重要なのです。
子どもが「できるよ」と答えた瞬間に、脳内には「食べ物を大事にする」イメージが生まれ、実際の行動に移しやすくなるわけです。
イメージさせることが、どれだけ行動に大切かがわかる面白い実験があります。
私たちには目の前に大好きな食べ物があっても、我慢できる力があります。
これは、専門用語で「満足遅延」といって、目の前の快感を先送りして、未来まで報酬を待つ力です。
すぐに衝動的になったり、貯金ができない子は、この満足遅延の力が弱いからです。
特に小さい子どもほど、我慢できません。
そこで、イスラエルの研究者たちは、まだ満足遅延の行動ができない未就学児の子どもを集めて実験をし、子どもたちが我慢強くなる「ある方法」を発見しました。
それは、「スーパーマンのマントをつけて、スーパーマンになりきってもらう」という方法でした。特に、「スーパーマンは我慢強くて、すごい人なんだよ」と説明された子どもは、より我慢強くなりました。
つまり、よりイメージができた子たちほど、我慢できるようになったということです。
逆に言うと、行動できないのは、イメージができないからなのです。
子どもがなかなか言うことを聞いてくれないときは、まるで子育ての天才になったようなフリをして、「質問」をしてみてください。口調まで変わって驚くかもしれません。
脳科学者
宮城県多賀城市出身のイラストレーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね