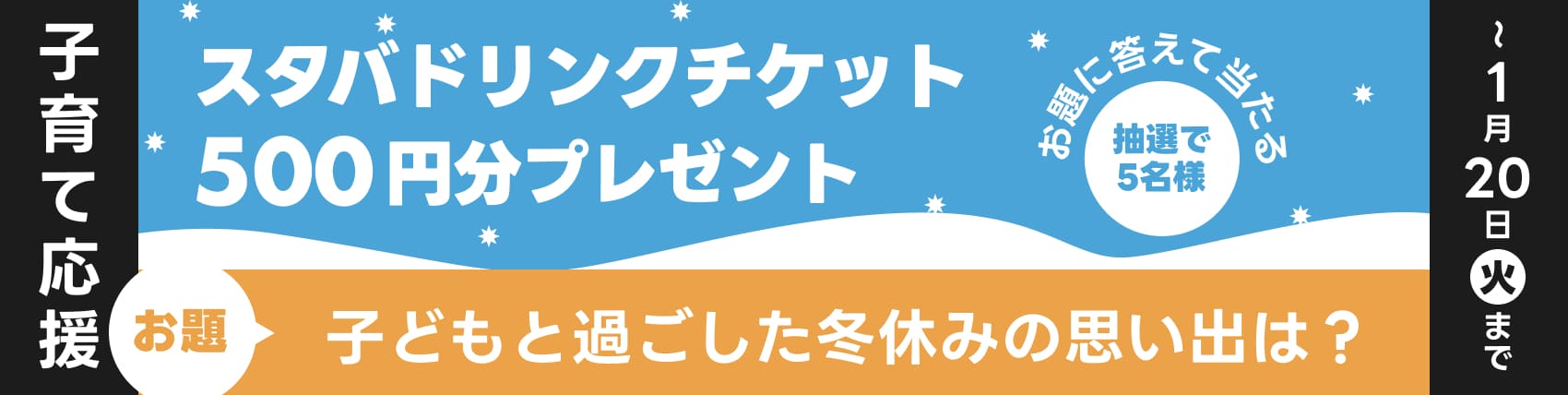脳科学者の著者が伝える!「努力をほめてレジリエンスを育てよう」
しつけ/育児

子どもの将来を大きく左右するのは、学力だけではありません。自信ややり抜く力、協調性といった「非認知能力」が成長の要となります。
本書は脳科学の知見に基づき、日常に取り入れられる17の習慣を具体的に紹介。今日から家庭で実践できるヒントが満載な1冊。
西 剛志先生の著書『脳科学的に正しい! 子どもの非認知能力を育てる17の習慣』から一部転載・編集してお届けいたします。
努力をほめてレジリエンスを育てよう
ほめると子どもが消極的になる?
日々の子育ての中で、「よくやったね」「素敵だね」「すごいね」とお子さんをほめたくなるシーンは数えきれないほどたくさんあることでしょう。
実際に親の95%が子どもをほめることは大切だと信じているようです。
私は全国の幼稚園や小学校などで保護者向けの講演を行っていますが、最近の親御さんはとにかくよくほめる人が多いように感じます。
しかし、海外の数々の研究を中心に、最近では「ほめるだけの教育」には意外な落とし穴があることがわかってきました。
特に有名なのが、スタンフォード大学のほめる実験です。
研究者は、10~12歳の子どもにパズルを解いてもらい、2つのグループに分けました。
①ほめるグループ(点数を伝える+ほめる)
②ほめないグループ(点数を伝えるだけ)
ちなみに、ほめるグループには、こんな言葉でほめました。
「こんなにパズルが解けたのは、頭がいい証拠だ(すごいね!)」
すると、子どもたちに面白い変化が起きました。
ほめるグループは、やさしい問題ばかり選んで、難しい問題にチャレンジしなくなってしまったのです。
むしろ、ほめないグループのほうが難しい問題に挑戦する子が多くなりました。
私もはじめて聞いたときは驚きましたし、にわかには信じられませんでした。
しかし、何度やっても結果は同じでした。
なぜ、こんなことが起きるのでしょうか?
その理由は「頭がいいね」とほめられると、「頭がいい自分でいたい」と子どもが思ってしまうため、失敗を極度に恐れるようになるからです。
新しいことにチャレンジして失敗したら、それは自分=「頭がよくない」ことになってしま
ます。だから、子どもは、「頭がいい」ことをキープするために、できる問題ばかりをやって、難しいことにチャレンジしなくなってしまったのです。
普段の生活で、「すごいね、すごいね」と才能や能力をほめると、自己肯定感が高まるように思えるかもしれません。
しかし、それはやさしいことしかやらない「偽りの自己肯定感」を育ててしまうことになりかねません。本来のやる気(内発的動機)や困難を乗り越える力が失われてしまい、逆効果になってしまいます。
ほめ方ひとつで子どもの能力は変わる
ここまでお話しすると、かなりショックを受ける方も多いかもしれません。
実際に講演会でもこの事実をお話しすると、たまに立ち直れなくなるほど落ち込んでしまう保護者もいらっしゃいます。
ただし、このほめる実験には、続きがあります。
能力ではなく、ほかの点をほめられたグループが存在していたのです。
それが「努力をほめるグループ」でした。
「こんなにできたのは、努力した証拠だね(すごいね!)」
研究者たちがそう伝えると、なんと多くの子どもが難問にチャレンジするようになりました。
たとえば、勉強やスポーツでよい結果を出したとき、
「こんな成績が取れたのは、一生懸命努力してきたからだね!」
「いつも頑張ってるね。感心するよ」
と伝えられたら、どんな気持ちになるでしょうか?
私たちは努力をほめられると、脳の報酬系(線状体)が活性化して、やる気の脳内物質であるドーパミンが分泌されます。
報酬系は脳の奥にあるため、内側からやる気が湧いてくるような状態になります。
それが、困難を乗り越える力(レジリエンス)を育むことにつながるのです。
私もこれまで17年ほどうまくいく人を研究してきましたが、やることすべて100%うまくいく人はこの地球上で一人もいませんでした。
うまくいかなかったとしても、チャレンジして乗り越えていき、小さなことでもコツコツ努力していく人は、収入も高く、健康的で、社会的な活動も活発だという報告もあります。
結果はどうであれ、最後まであきらめずに行動したこと、毎日練習していること、先生の話をよく聞こうとしていること、お絵描きでキレイな色を選ぼうとした気持ちなど、どんな小さな努力(意欲)もほめてあげることが大切です。
また、電車で静かに過ごせた、公園でお友だちに順番を譲ってあげるような人のために行った行為をほめることは、セルフコントロール力や共感力といった能力を伸ばすことにもつながります。
ほめる習慣は年齢によっても変わる
ちなみに努力をほめることは、何歳くらいから大切なのでしょうか?
意外で驚かれるかもしれませんが、もっとも早い年齢は1~3歳です。
努力をほめられた14~38ヵ月の子どもたちは、小学校2~3年生になってチャレンジ精神が高くなり、さらに4年生になったときには算数の力と読解力まで高くなったのです。
また、5~6歳の子どもが挫折したときは、能力よりも努力をほめたほうが、子どもがより粘り強くなる傾向もありました。
平均して9歳頃には能力と努力の区別を明確にできるようになりますが、小さい頃から努力をほめることには大きな効果があるようです。
お子さんが1歳未満のうちは、能力と努力は関係なく、できたことに反応してあげたり、ほめてあげることは大切です。
子どもがスプーンを持ったり、立って歩いたりと新しいことを習得する乳幼児の時期は、能力をほめても応援されていると感じるため、どんな言葉でもプラスに働く可能性があります。
就学前に「頑張ってよくやったね」といった温かい言葉をかけられ、愛情をたっぷり受けて育った子どもは、脳で記憶を司る海馬の発達スピードが2倍早まるということも報告されています。
また、小学校に上がってからよりも就学前にたっぷり愛情をかけて育った子どもは、思春期になってからの感情コントロール力まで高まるようです。
ただし、小学生以上になると、ほめ方とほめる頻度には特に注意が必要です。
4歳児や5歳児は、ほめられた回数が多いほど評価されていると感じやすいのですが、小学校に上がってから、むやみにほめると効果が下がってしまう傾向があるからです。
これは脳が発達するにつれて、ほめられることに慣れが生じ、ほめ言葉を素直に受け取ってもらえなくなることに原因があります。
専門用語で「ハンフレイズ効果」と言いますが、いつもほめられる環境にあると脳がそれを当たり前のことだと認識して、ほめられても行動が強化されなくなるのです。
さらに、小学生以上になって簡単なことをほめられると、ほめた人の能力を低く評価するようになることもわかっています。
能力が低い人から「○○さんはすごいね!」とほめられても、あまり嬉しくありませんよね。
簡単なことばかりほめてしまうと、ほめ言葉の効果が失われてしまうのです。
ですので、小学校の、特に高学年以降のお子さんの場合は、いつほめられるのかわからない状況でほめるほうが効果的です。
カウンターパンチのように「ここぞ」というタイミングを見計らってほめるようにしましょう。
「能力がすごい!」という言葉は、裏を返せば「あなたはすごい力をずっと維持できる」という大きな無言のプレッシャー(過剰な期待)となります。
一方で、「この成果は努力したからだね」という言葉はプレッシャーではなく、「努力で能力はどこまでも伸びる、人の能力はコントロールできて、最終的にその人次第だ」という子どもを支援するメッセージを伝えることができます。
「能力は努力で伸ばせる」と信じている中学生は成績も伸び、粘り強く努力する小学生は先生や周りからのサポートを受けやすく、より才能が伸びやすくなることが研究からもわかっています。
小さい頃から努力を効果的にほめる習慣に取り組んでいきましょう。
脳科学者
宮城県多賀城市出身のイラストレーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね