新生児が泣きやまない…その原因と対処法を総ざらい!(第1回)
赤ちゃんが泣きやまないときは空腹やオムツ以外の小さな原因も考えられます。
しつけ/育児
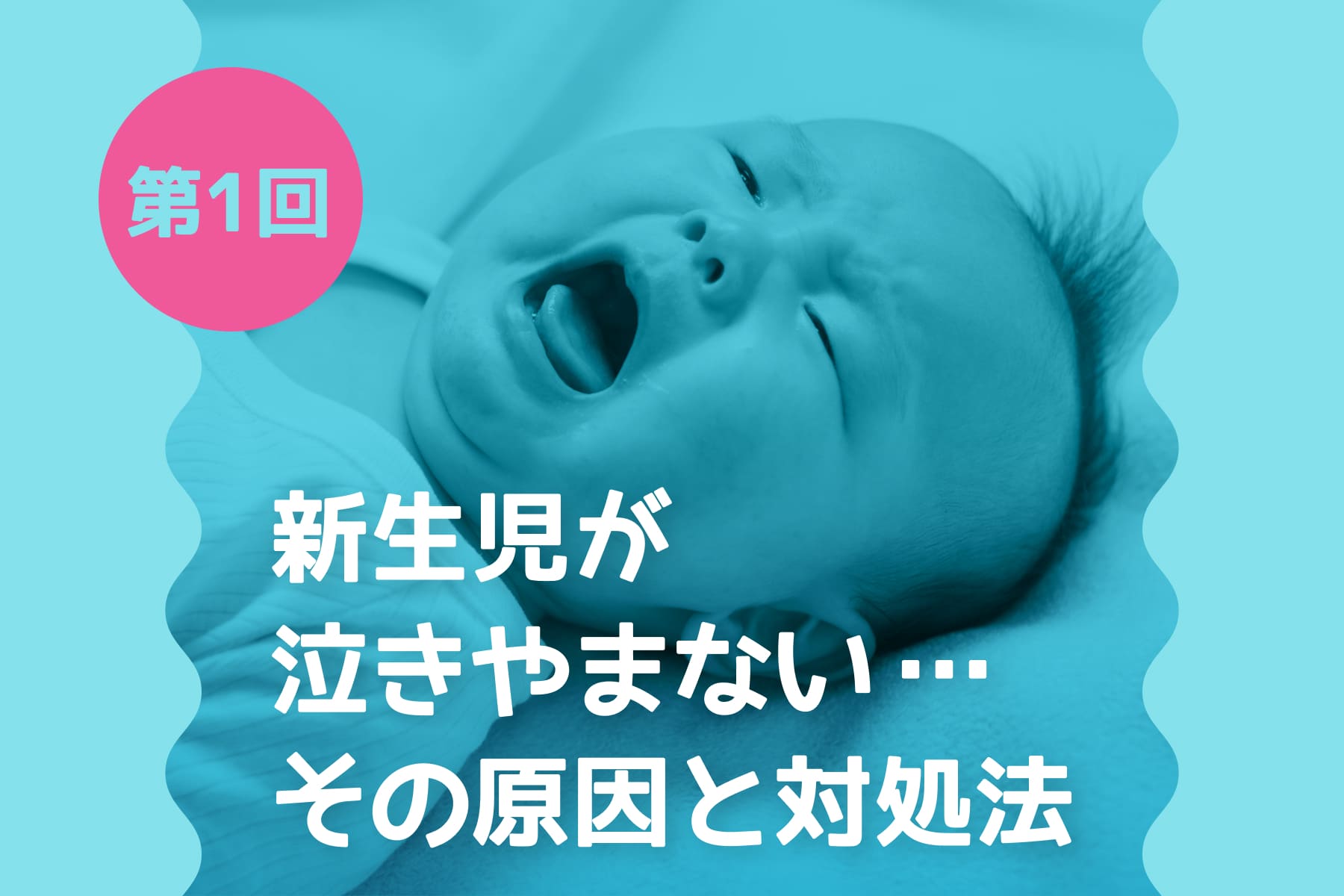
新生児が泣きやまない…その原因と対処法を総ざらい!(第1回)
こんにちは、多様な教育ナビゲーター・あずみのこです。15年以上子育て支援に携わり、2人の小中学生を育てる現役共働きママの視点から、コラムをお届けしています。
初めての育児は、うれしさと同じくらい「どうしよう」も多いですよね。今日は、その中でも多くの親が最初に直面する「新生児が泣きやまない」というテーマについてお話しします(全2回の第1回)。
うちの子も赤ちゃんの頃、抱っこしていないとずっと泣くタイプで。夜も延々と抱っこが続いた時期がありました。眠すぎて、自分でも驚くような体勢(布団の上で横になったまま足で抱っこ!)で仮眠したこともあります。今では懐かしい思い出となっていますが、当時は「もう限界かも」と思うほどしんどかった記憶があります。
まだ言葉を持たない新生児にとって、泣くことは唯一のコミュニケーション。空腹やオムツの不快感みたいに「すぐわかる理由」もあれば、「魔の三週目」と呼ばれる時期特有のぐずりや、「黄昏泣き」や「コリック(乳児疝痛)」みたいに成長の途中でよくある現象もあります【※1】。ほとんどは病気ではないけれど、赤ちゃんの体や心に負担がかかることもあるので、こうした「新生児の泣き」に関する情報は、事前に知っておくだけでも安心です。
このコラムでは、赤ちゃんが“泣く理由”と私たちママ・パパがその時“できること”を、助産師や小児科医の知見、そして私自身や「てつなぎ」ユーザーさんのリアルな体験とあわせてご紹介します。読んだあと、少しでも安心してもらえるきっかけになれば嬉しいです。
赤ちゃんが泣く仕組みとは?
赤ちゃんにとって「泣くこと」は、生まれてすぐから使える唯一の“お知らせ方法”。新生児はまだ言葉を話せないため、泣くことで空腹やオムツの不快感、暑さや寒さ、眠さなどを伝えます。これは、自分の身を守るために、生まれつき備わっている大切な仕組みなんですよね。
脳の中では、生まれたときから働いている扁桃体・視床下部・脳幹といった部分が主役になって“泣く”スイッチを押します。一方で、記憶や思考をつかさどる海馬や前頭前野はまだ未発達。だからこの時期の出来事は言葉では覚えていませんが、安心して抱っこされたり、お世話をしてもらったときの感覚は「手続き記憶」として体にしみ込んでいくそうです【※2】。
つまり、赤ちゃんの泣きは「ただの声」ではなく、安心感を育てるための大切な合図。「泣く → 大人が応える → 安心する」というやり取りが繰り返されることで、脳の中に「ここは安心できる場所」という回路が少しずつ育っていくんだとか。
泣き方の種類もさまざまで、お腹が空いた、眠い、オムツが深いなどで、それぞれ声の高さやリズムも少しずつ違います。育児を続けていると、「これは眠いサインかな?」と少しずつ見えてくることもあります。最初は区別が難しくても大丈夫。だんだん親子で息が合っていくようになります。
ただ、いつもより長く泣き続けていたり、嘔吐や発熱などの症状があるときは、迷わず小児科へ。「ちょっと心配かも…」と思った時点で診てもらうだけでも、少し気持ちが落ち着くはず。

新生児にとって泣くことは「言葉」の代わり
生まれたばかりの赤ちゃんは、まだ視力も聴力も育ち途中。だからこそ「お腹すいたよ」「なんだか不快だよ」という気持ちを、泣き声にのせて伝えています【※3】。
大人には些細に思えること…例えば、肌着の湿りや光のまぶしさなんかも、赤ちゃんには大きなストレスになることも。それを知らせるのが、「泣く」の大切な役割なんですよね。
私も最初の頃、抱っこ以外は何をしても泣いてしまう日が続いていて「なんで泣いてるのお〜〜!?...」と半泣き状態の日々がありました。でも少しずつ、「これは眠いときの泣きかな?」と、その子が何を求めているのか分かるようになってきたんですよね。振り返れば、そんな時間の積み重ねが、親子の最初の愛情関係を育ててくれていたのだとも思います。(その真っ只中は、とてもそうは思えませんでしたが…苦笑)
泣き方を少しずつ理解してあげることが、赤ちゃんにとっても大人にとっても安心につながっていきます。
泣き声の種類とサインの見極め
毎日聞いているはずなのに、「これはお腹すいたってこと?それとも眠いだけ?」と迷うこともありますよね。 そんなときは、オムツ・授乳(母乳やミルク)・室温・明るさ…と原因を順番にチェックするのがおすすめ。わたしも、この“消去法リスト”にずいぶん助けられました。
赤ちゃんの泣き声には、「眠い」「お腹がすいた」「オムツが不快」などいくつかのパターンがあると言われています。たとえば、空腹のときは短くリズミカル、眠いときは「おぉ〜」のように伸びる声、という特徴があるのだそう。オーストラリアの研究者プリシラ・ダンスタン氏が提唱する「ダンスタン・ベビー・ランゲージ(DBL)」でも、以下のように整理されています【※4】。
●「おぉ〜」「あぉ〜」= 眠い
●「ねぇ〜」= お腹が減った
●「へぇ〜」= おむつが汚れている
もちろん、泣き声だけで原因をピタリと当てるのは難しいですが、観察を重ねるうちに直感でわかる瞬間が増えてくるはずです。
最近は、国立成育医療研究センターとの共同研究から生まれた、泣き声を録音して分析してくれるスマホアプリ「パパっと育児@赤ちゃん手帳」というものも登場しています。モニター調査では、なんと正答率80%超えという結果も出たそうです。こうした情報やツールを上手に取り入れてみるのも、育児を少しラクに楽しむコツかもしれません。
よくある「泣きやまない」理由と具体例
長く泣きやまないときは、空腹やオムツといった“王道の理由”だけでなく、いくつもの小さな原因が重なっていることもあります。
たとえば、昼夜の気温差で暑すぎたり寒すぎたり。お腹が空いているのに気づくのが遅れて、不快感がじわじわ積み重なってしまったり。
抱っこを求めて泣くのは、よくあるパターンですよね。人肌のぬくもりは、赤ちゃんにとって“世界一の安心毛布”。甘えやわがままではなくて「安心したいよ〜」のサインなんです。これは“赤ちゃんの自然な発達の一部”だから、「泣かせてしまった」「うまくできない」と、自分を責めなくても大丈夫。あなたがそばにいてくれること、それだけでもう、赤ちゃんにとっては十分な「安心」なんです。
また、基本的なケアをしてもどうにも泣き止まないときは、「コリック(乳児疝痛)」や「黄昏泣き」と呼ばれる現象の可能性もあります。成長過程でよく見られるもので、病気ではないことがほとんどですが、知っておくと少し安心できるかもしれません。

空腹やオムツの不快感、気温の影響
赤ちゃんが泣く理由で一番多いのは、やっぱり空腹とオムツの不快感【※5】。授乳(母乳やミルク)やオムツ替えをしたつもりでも、ちょっとしたタイミングのズレで不快度が高まることもあります。
でも、意外と見落としがちなのが「暑すぎ・寒すぎ」です。新生児は体温調節がまだ苦手なので、室温や湿度の影響を受けやすいんですよね。夏は26〜28℃・湿度50〜60%、冬は18〜20℃・湿度40〜60%が目安だそう【※6】。
手足が冷たくても、おなかや背中が温かければ快適な状態のことも多いそうです。私も最初は「手足が冷たい=寒い」と思い込んでいましたが、このことを知ってからは、まず背中やおなかをそっと触って確かめるようになりました。
それから、首まわりの締め付けや抱っこの角度など、ほんのちょっとした姿勢の違いが「泣く理由」になることも。服をゆるめたり抱き方を変えるだけで、泣きやむこともあるので、よかったら試してみてくださいね。
眠いのにうまく寝つけない・昼夜逆転
新生児はまだ体内時計(サーカディアンリズム)が未発達なので、昼夜の区別なく寝たり起きたりを繰り返します。夜にパッチリ目が覚めたり、昼間によく眠って夜はなかなか寝つけなかったり…いわゆる「昼夜逆転」になりやすい時期なんですよね。
大人からすると「こんなに眠そうなのに、なんで寝ない?」って不思議ですが、赤ちゃんにとって“眠りたいのに眠れない”のは大きなストレス。そのもどかしさを、全力で泣いて伝えているんですよね。
生後3〜4か月頃になると、眠りを促すホルモン「メラトニン」が分泌され始めて、少しずつ生活リズムが整いやすくなるそうです【※7】。そのためにも、朝はカーテンを開けて日差しを浴びる、日中はスキンシップや遊びで活動量を増やす、夜は明かりを落として静かに過ごすなど、寝かしつけや生活リズムを整えるための小さな工夫が役立ちます。
ただ、眠れないときに無理に寝かせようとすると逆に目が冴えてしまうことも。静かな音楽を流したり、部屋を少し暗めにしたりして“自然に眠気を待つ”くらいの気持ちでいることが、親も赤ちゃんもラクになれるヒントです。
黄昏泣き・コリック(乳児疝痛)の可能性
夕方から夜にかけて、新生児が理由もなく激しく泣き続けることがあります。毎日のように「なかなか泣き止まない」と感じるとき、「黄昏泣き」や「コリック(Colic/乳児疝痛)」かもしれません。生後2〜3週間頃から始まり、4〜5か月頃まで続くことも珍しくないそうです。
特徴としてよく知られているのが「3の法則」。1日に3時間以上泣く状態が、週に3日以上、3週間以上続く場合を指します【※8】。必ずしも病気ではありませんが、腸内ガスや消化機能の未熟さが関わっていることもあるため、気になる場合は早めに小児科医に相談すると安心です。
毎晩のように泣き続けられると、「何か間違ってんのかな...」と心がくたびれてしまう日もありますが、でも、「新生児期にはこういう黄昏泣きがあるんだ」と知っているだけで、気持ちが少しラクになることもあります。大丈夫、この泣きの嵐にも、必ず落ち着く時期がやってきます。
では次に、少しでもラクに過ごすための「環境づくり」や「対策」をご紹介しますね。
魔の三週目とは? いつもの泣きと違うポイント
生後3週目ごろから始まる「魔の三週目」。新生児の泣き方がこれまでより激しく、長時間泣きやまないことが増えるため、多くのママやパパが戸惑う時期です。抱っこしても授乳しても泣きやまない…そんな「新生児がなかなか泣き止まない」日が続くのも、この時期の特徴です。
この呼び名は育児書や先輩ママ・パパの会話でもよく登場しますが、実際には赤ちゃんが成長していくうえで通る“ひとつの節目”。お腹の中から外の世界へ、体も心も慣れていくためのプロセスなんですね。
この時期は、黄昏泣きやコリック(乳児疝痛)と重なることも少なくありません。海外では、この時期の泣き方の特徴を「PURPLE CRYING(パープルクライング)」という6つの要素で説明する方法があります。
PURPLEの特徴【※9】。
P:Peak of Crying(泣きのピークがある)
U:Unexpected(予想できない)
R:Resists Soothing(なだめられない)
P:Pain-like Face(痛そうな表情)
L:Long Lasting(長く続く)
E:Evening(夕方に多い)
名前だけ聞くと不思議ですが、「夕方に多い」「泣きやむまで長い」など、まさに魔の三週目ごろの泣き方そのものです。
一般的には生後4〜5か月頃には落ち着いてくることが多いので、長いトンネルのように思えても必ず出口があります。
もちろん、発熱・嘔吐・下痢など、いつもと明らかに違う症状がある場合は別です。そんなときは「様子を見よう」と抱え込まず、早めに小児科を受診して安心材料を増やしていきましょう。
泣き止まない夜が続く時期と対策
魔の三週目の大きな特徴は、夜になると新生児の泣きが長引きやすいこと。昼間は穏やかでも、日が暮れるころから急に泣き始め、抱っこしても授乳してもなかなか泣き止まない…そんな「夜泣きに悩まされる日」が続くこともあります。
まずは、赤ちゃんが少しでも安心できる環境づくりから。
● 部屋の照明を落として刺激を減らす
● 抱っこで心拍のリズムを感じさせてあげる
● 静かな音楽や子守唄でやさしく包む
こうした工夫で、泣き声が少し落ち着くこともあります。
とはいえ、夜中に泣き止まない赤ちゃんに向き合い続けるのは、体力も気力も消耗する大仕事。私も長男のとき、夜中に何時間も抱っこしながら「早く朝になって…」と本当に辛かった時期がありました。
だからこそ、無理してひとりで抱え込まないで。家族で交代制にしたり、地域の子育てサポートや一時預かりを使ったりして、負担を分け合ってほしいなと思います。
「ちょっと休める時間」をつくるのは、罪悪感を持つことではなく、“明日も笑顔でいるためのエネルギー補給”。どうか安心して、手を伸ばせるところに頼ってくださいね。
病気を疑うべきか?診察の目安
「魔の三週目」や「コリック(乳児疝痛)」によって、新生児がなかなか泣き止まない夜泣きが続くことは珍しくありません。多くの場合は病気ではなく、赤ちゃんの発達過程の一部と考えられています。
ただ、泣き方に加えて高熱・嘔吐・下痢があるときは注意が必要です。こうした場合は「夜泣きだから大丈夫」と自己判断せず、小児科を早めに受診することが大切です。
また、「なんだかいつもと泣き方が違う」「顔色が冴えない」といった親の直感も大切なサイン。次のような症状があるときは、休日や夜間でもすぐに受診が推奨されています【※10】。
● 生後3か月未満で38℃以上の発熱
● ぐったりしている/呼びかけに反応しない
● 息苦しそうにしている
● 顔色が青い・白い
新生児の体調は急変しやすいため、「泣き止まない原因が発達なのか病気なのか」を正しく見極めるには、医師に診てもらうのが一番安心です。
もし判断に迷ったら、厚生労働省の子ども医療電話相談事業(#8000)に連絡を。小児科医や看護師が、症状に応じて受診の目安を教えてくれるので、不安な夜でも心強い味方になってくれます。
多様な教育ナビゲーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね

































