新生児が泣きやまない…その原因と対処法を総ざらい!(第2回)
赤ちゃんの睡眠リズムを整えるための生活習慣づくりのポイントをまとめました。
しつけ/育児
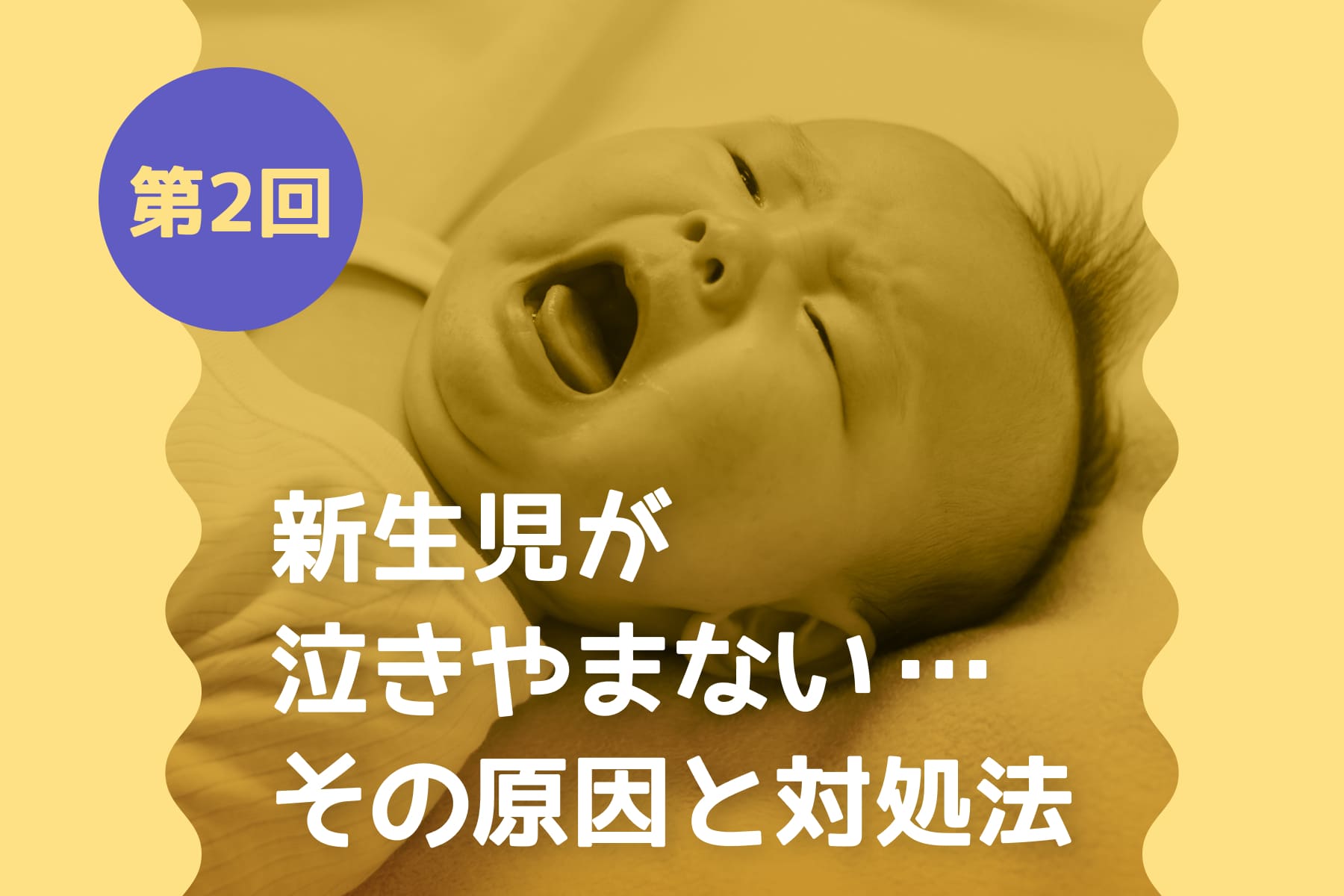
新生児が泣きやまない…その原因と対処法を総ざらい!(第2回)
こんにちは、多様な教育ナビゲーター・あずみのこです。15年以上子育て支援に携わり、2人の小中学生を育てる現役共働きママの視点から、コラムをお届けしています。
初めての育児は、うれしさと同じくらい「どうしよう」も多いですよね。今日は、その中でも多くの親が最初に直面する「新生児が泣きやまない」というテーマについてお話しします(全2回の第2回)。第1回では赤ちゃんが泣く仕組み、泣きやまない理由とその具体例、「魔の3週目」とその対策についてのコラムになります。目を通していただければうれしいです。
泣きやまない原因と具体的な対処法
赤ちゃんが泣き止まない理由は本当にさまざまです。「なんで泣き止まないのか?」と考えながら、まずは次のような“基本のケア”から試してみるのがおすすめです【※15】。
● 抱っこやスキンシップ:ぬくもりで安心感を与える一番シンプルな方法
● 授乳(母乳・ミルク):お腹がすいていないかを確認
● オムツ替え:不快感を取り除くだけで泣き止むことも
毎回完璧に対応できなくても大丈夫。できる範囲で繰り返していくことが、赤ちゃんにとっては何よりの安心になります。
また、ママやパパが「泣き止ませなきゃ!」と強く力んでしまうと、その緊張感が赤ちゃんにも伝わってしまいます。私自身も必死になりすぎて、余計に疲れてしまったことがありました。そんなときは、
● 赤ちゃんを安全な場所(ベビーベッドやベビーサークルなど)に置く
● 深呼吸して、数分だけクールダウンする
といった工夫も効果的です。
大切なのは、「赤ちゃんが安心できること」と「大人が無理しすぎないこと」のバランス。そうやって親自身の肩の力を抜ける瞬間が増えると、不思議と赤ちゃんも、少しずつ落ち着いてくれる気がします。

抱っこ・スキンシップで安心感を与える
赤ちゃんにとって抱っこは「甘やかし」なんかじゃありません。生きていくために欠かせない、大切な時間です。人肌のぬくもりや心拍のリズム、やさしく伝わる体温は、「ここにいて大丈夫」という感覚を、赤ちゃんの全身に育んでいきます。
身体心理学の専門家・山口創先生(桜美林大学教授)によると、肌と肌がふれあう抱っこは赤ちゃんの愛着形成に欠かせない要素。オキシトシンというホルモンが分泌され、親子の絆を深め、ストレス反応をやわらげてくれる働きがあるそうです【※11】。
抱っこは、授乳(母乳・ミルク)と同じくらい赤ちゃんに安心感を与える大切な方法なんですね。そっと包み込むように支えて、背中やお腹をなでながら「大丈夫だよ〜」とやさしく声をかけると、泣き声がやわらぐこともありますよ。
縦抱き、横抱き、スリング、腕の中でのゆらゆらなど、赤ちゃんによって落ち着く抱き方や揺れ方は本当に違います。「この子はどれが好きかな?」と試しながら探す時間も、あとで振り返れば懐かしい宝物になるはずです。
もし激しく泣いて嫌がるときは、無理に抱っこにこだわらなくても大丈夫。声や手のぬくもりだけでも、ちゃんと赤ちゃんには届いていますから。
授乳タイミングやオムツ替えのこまめな確認
「さっき授乳したし、オムツも替えたから大丈夫」と思っても、実はまだお腹がすいていたり、オムツが湿っていたりすることも実はけっこうあります。赤ちゃんは自分で不快を解消できないからこそ、私たちの「ちょっとした確認」が頼りになるんですね。
私もそうでしたが、「あれ、さっきやったのに〜」となるのは、きっと多くのママ・パパが経験しているはず。てつなぎ掲示板にも、こんな声が寄せられています。
「最近、授乳がうまくいかず、娘も泣き止まないことが増えています。母乳の出が少ないのか、吸い付きが悪いのか、何が原因なのだろう…😢」(🔗 てつなぎ|授乳中の悩み。。)
ピジョンの育児情報サイト(監修:榎本美紀助産師)によると、授乳は泣いてからよりも「泣く前に」あげるのが理想だそうです。赤ちゃんは泣く前から、おっぱいが欲しいサイン(口をもぐもぐ動かす・手を口に持ってくる・体をもぞもぞ動かすなど)を出していて、大泣きしてしまうと舌が上がって乳首をうまくくわえられず、さらに泣きがひどくなることもあるのだとか【※12】。
授乳後もぐずぐずが続くときは、母乳(ミルク)が足りていないこともあります。授乳間隔や授乳頻度を少し調整するだけで落ち着くケースもありますよ。
オムツも「泣いたらまずチェック」を習慣にすれば、不快の原因をひとつ減らせます。肌が濡れたまま長く過ごすと不快感が増すだけでなく、肌トラブルにつながることもあるので、こまめにのぞいてあげると安心です。
完璧じゃなくても大丈夫。できるときに、ちょっとのぞいて、ちょっと直す。それだけで、赤ちゃんは「ちゃんと見てもらえてる」と感じ、私たちも「今日もやれてるな」と思える。そんな小さな積み重ねが、親子の安心を少しずつ育てていきます。
寝かしつけのテクニック:ゆらし方・光の調整
赤ちゃんが泣き出したときは、とりあえず「抱っこして歩く」。そんな「育児あるある」、きっと経験したことがある方も多いですよね。実際、抱っこで自然と泣き止むことはとても多いんです。
理化学研究所の研究によれば、生後7か月以下の赤ちゃんを抱っこして5分歩くと全員泣きやみ、そのうち半分はスヤ〜っと夢の世界へ。さらに、そのまま5〜8分抱いてからそっと下ろすと、起きにくいそうです【※13】。この反応は“輸送反応”と呼ばれ、動物にも共通する本能的な行動なんだとか。つまり、廊下を行ったり来たりしているその姿は、最新科学に裏づけられた立派な寝かしつけ法。
揺らすときは、強く振らず、小さくやわらかく。歩くスピードはゆったり散歩くらいで、横揺れやリズミカルな足音も赤ちゃんに安心を与えてくれます。赤ちゃんの頭や首に負担をかけないことが大切です。「だいじょうぶだよ〜」と全身で語りかけるイメージで。
照明も心強い味方です。夜はカーテンを少し閉めて光をやわらげ、「そろそろ休もうね」と部屋全体でおやすみモードに。抱っこしている私たちも、ゆったり動くうちにまぶたが重くなってきて……あれ? 先に寝ちゃうのはこっちかも、なんてことも(笑)。そんな時間も、後になればきっと大切な思い出になりますよ。
強く揺さぶらない:一時的に離れる選択肢を持つ
泣きやまない赤ちゃんを前にすると、どうしても焦って力が入ってしまうこと、ありますよね。けれど、強く揺さぶるのは絶対にNG。頭や首に大きな衝撃が加わり、命に関わる深刻なケガにつながることがあります【※14】。
「もう無理」と感じたら、赤ちゃんをベビーベッドやベビーサークルなど安全な場所に寝かせて、いったん深呼吸を。数分でも気持ちをリセットするだけで、また向き合いやすくなります。
大事なのは、赤ちゃんの安全と同じくらい、ママやパパ自身の心の余裕。頼れる家族にバトンタッチしたり、一時預かりや子育て支援サービスを利用するのも立派な作戦です。泣き止まない状況に追い詰められず、「一人で抱え込まなくていい」と思えることが、安心して育児を続ける力につながります。
睡眠リズムを整える:生活習慣づくりのポイント
新生児のうちは、昼も夜も関係なく授乳やオムツ替えの連続。生活リズムなんて、あってないようなものですよね。
それでも、少しずつ「昼」と「夜」を意識してあげることで、赤ちゃんが安心して眠りやすくなったり、泣く原因を減らせることがあります。たとえば日中はカーテンを開けて自然光を取り入れ、明るい部屋で過ごす。夜は照明を落として静かな環境にするなど、ほんの小さな切り替えでも十分です。
大切なのは、一気に整えようとしないこと。「毎日きっちり」じゃなくて大丈夫。「今日は少しできたな」くらいで十分です。むしろ「今日はぐちゃぐちゃだったな〜」なんて日があるのが普通。大人だって夜更かしする日、ありますからね(笑)。
そして、家族や地域の子育て支援を頼ることも立派な選択肢です。大人に余裕があるほうが、赤ちゃんも安心できますから。「全部自分でやらなきゃ」と思い込まなくて大丈夫。肩の力を抜いて、ゆるやかに続けるくらいがちょうどいいんです。
こうして少しずつ生活のリズムを作っていく中で、特に意識したいのが「昼」と「夜」の環境の差。次の章では、その“メリハリ”をつけるための具体的なヒントをご紹介します。

昼夜の区別をつける環境とメリハリ
昼と夜の環境をしっかり分けることは、赤ちゃんの生活リズムを育てる大切な刺激になります。産婦人科オンラインによると、生後3〜4か月頃から眠りを促すホルモン「メラトニン」が分泌され始め、昼夜の区別がつきやすくなるそうです【※8】。
昼間はカーテンを開けて日光をたっぷり取り入れ、会話や遊びでにぎやかに。夜は照明を落とし、テレビや音を控えめにして、話し声もゆったりスローモードにする。そんな小さな工夫だけでも、「今は休む時間なんだな」と赤ちゃんが感じやすくなります。
このメリハリがあると、体内リズムが整いやすくなり、泣きやまない時間も少しずつ減っていくことがあります。もちろん、毎日きっちりやらなくても大丈夫。“今日は半分できたな”くらいで上出来です。親も子も肩の力を抜いて、“ほどほど”で続けていければ十分です。
家族や地域の協力で負担を分担する
赤ちゃんが泣き続ける日が続くと、夫婦だけではどうにも回らなくなることってありますよね。とはいえ、両親や親戚にお願いするのは気を遣ってしまって、なかなか頼みにくい…という方も少なくありません。私もそうでした。
そんなときこそ、自治体やNPOの子育て支援サービスを活用してみてください。代表的な制度には、
● ファミリー・サポート・センター
● 産後ヘルパー派遣
● 一時預かり事業
● 訪問型子育て支援ボランティア
などがあり、市区町村の「子育て支援課」や「母子保健担当」窓口で案内してもらえますよ。
支援を利用することで、親が安心して休息をとれるだけでなく、赤ちゃんにとっても安全で落ち着ける環境を整えることができます。負担を分担することは弱さではなく、長く育児を続けるための大切な力なんです。
赤ちゃんが泣き止まない夜こそ自分をいたわる
夜中に泣きが長引くと、眠れないつらさと「早く泣き止ませなきゃ」という焦りで、心も体もすり減ってしまいますよね。特に新生児期は、大人の体力も削られやすい時期。だからこそ「休めるときに休む」を、どうかいちばんに考えてほしいんです。
てつなぎ掲示板にも、こんな声が寄せられています。
「夜中突然火が付いたように泣いて、抱っこしても泣き止まず…。私も眠いし、旦那はこの泣き声でも全然起きないし、この泣き声に胸が苦しくなります。 1時間半は寝付けないのが当たり前で、あきらめて最近は抱っこしたまま朝を迎えます。」(🔗 てつなぎ|夜泣きで精神崩壊中)
きっと、この言葉に「わかる…!」とうなずくママ・パパも多いのではないでしょうか。夜泣きのつらさは、誰にでも起こり得るもの。だからこそ、短い時間でも体を横にしたり、深呼吸をして気持ちを落ち着けたりするだけでも違います。
完璧にやろうとせず「今日はここまででいいや」と割り切ることは、育児を続けるための大事な力。泣き声が続いても、それは赤ちゃんの成長のひとつのプロセスです。少しでも余裕を取り戻せれば、またやさしい気持ちでわが子に向き合えるはずです。

「泣き止ませなきゃ」に追い込まれないために
「なんとか泣き止ませなきゃ!」って、どうしても力んじゃうとき、ありますよね。私も長男のときは、泣き声を聞くたびに心臓がドキドキして、“早く泣き止ませなきゃ”って頭の中がいっぱいになっていました。けれど、ずっとその気持ちでいると、親の方がヘトヘトになってしまいます。
泣くことは、赤ちゃんにとって大切な“おしゃべり”のひとつ。でも、ママやパパの心だって同じくらい大事です。安全や健康に問題がないか確認して、授乳・オムツ替え・抱っこなどできることをやったら、「今日はここまででOK」と割り切ってもいいんです。
正直、ずっとそばにいるのがしんどくなる日だってあります。でもそれは“育児放棄”ではなく、“人間として自然なこと”。泣き止ませることよりも、「安心してそばにいる時間」を大切にしてほしいです。
それは“24時間べったり”じゃなくても大丈夫。ほんの数分、別の部屋で深呼吸したり、水を一杯飲んだりするだけでも、また少しやさしい気持ちで向き合えるようになりますから。
ママ・パパのセルフケアとサポート先
産後は、寝不足や体の回復の遅れ、初めての赤ちゃんのお世話などが重なって、想像以上に心も体も揺れやすい時期。泣き声がすごくしんどい日や「この先やっていけるかな…」と不安になる日もありますよね。だからこそ、“自分をいたわる時間”と、“すぐ頼れる窓口”を手元に持っておくことが大切です。
ここでは、全国から利用できる産後サポート先をピックアップしました。
● 地域の保健センター
妊娠期から育児まで、保健師による支援あり。母子手帳の連絡先をチェックしてみてください。
● 日本助産師会「子育て・女性健康支援センター」
妊娠〜産後の授乳・離乳食・体調相談に対応。毎週火曜は無料電話相談も。
● 日本産後ケア協会「Dream time Call」
産後ママ専用の夜間無料サポートライン。授乳・夜泣き・育児不安を相談できます。
● エンゼル110番(森永乳業)
妊娠中〜就学前までの子育てを、保健師や管理栄養士が無料で相談対応。
● こども家庭庁「親子のための相談LINE」
18歳未満の子と保護者が、子育てや親子関係についてLINEで相談可能。
番号やサイトをスマホや手帳にメモしておくだけで、「いざ」というときの心のよりどころになります。
ひとりで抱え込まなくても大丈夫。赤ちゃんを守るためにも、まずはママやパパ自身の心と体を守ることから始めましょう。
そしてもし、気持ちをちょっと吐き出したいなと思ったときは、「てつなぎ掲示板」に書き込んでみてくださいね。同じように泣き声と格闘してきた人たちが、「それわかる〜!」って返してくれると思います。私もときどきコメントしているので、「あ、あずみのこだ」って見つけてもらえるかもしれません(笑)
まとめ:「赤ちゃんの泣き」に寄り添うコツ
赤ちゃんが泣くのは、「生きてますよ」というサイン。まだ話せない小さな口から、一生懸命に「お腹すいたよ」「ちょっと寒いよ」「なんだか寂しいよ」と伝えてくれているんですよね。
泣きやまないときは、まず空腹・オムツ・暑さ寒さなどの基本チェック。それでも続くなら、黄昏泣きやコリック(乳児疝痛)、眠りのリズムの乱れなど、成長の中でよくある“泣きの波”かもしれません。魔の三週目のように、特定の時期だけ増えることもありますが、多くは病気ではなく、気づけばおさまっていくものです。
それでも「やっぱり不安…」というときは、小児科や助産師さんに早めに相談してください。ひとりで抱え込まなくても大丈夫。家族や地域のサポート、産後ケアサービスを頼ることは、弱さではなく“親を続けるための知恵”です。
泣き止ませることだけをゴールにしなくていいんです。抱っこしても、そばに座って声をかけるだけでも、「ここにいるよ」という気持ちはちゃんと伝わります。ずっと一緒にいるのがしんどい日も、数分でも離れて深呼吸できれば、それは立派なケア。
完璧じゃなくて大丈夫。泣きやまない時間さえも、赤ちゃんとのコミュニケーションのひとつ。ママ・パパがそばにいること、それが赤ちゃんにとっての“なによりの安心”なんです。そしていつか、今は泣き声でいっぱいの夜が、「こんなに小さな声で呼んでくれていたんだ」と懐かしく思える日が必ず来ます。
その日を迎えるまで、どうか自分を責めずに、肩の力を抜いていてください。あなたがそばにいるだけで、赤ちゃんはもう十分に守られているのですから。
多様な教育ナビゲーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね


































