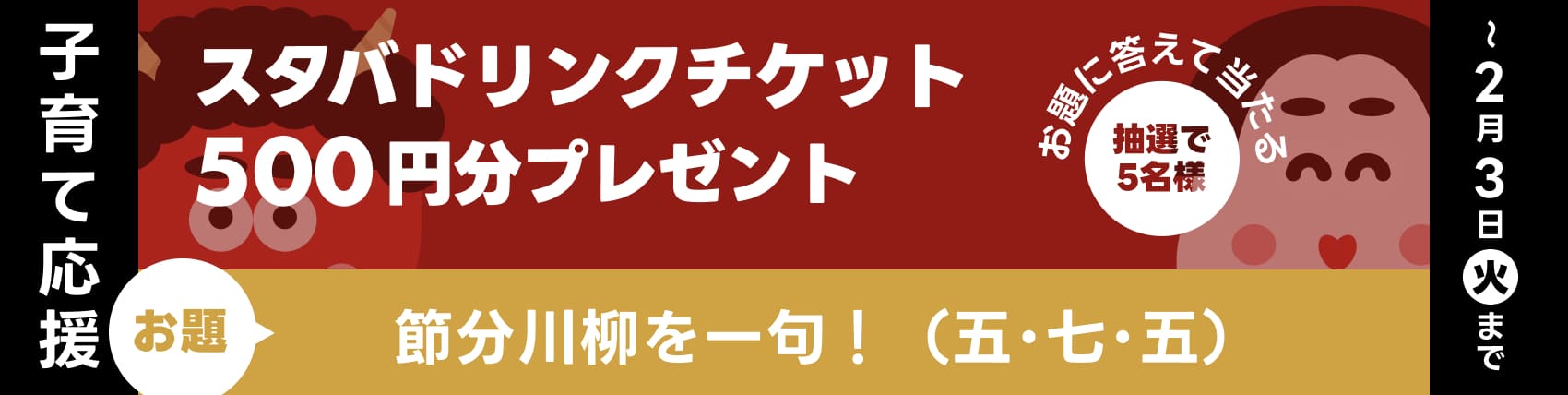「自分で考える子」に育つ!――年齢によって与える「楽しさ」の種類を変える
全国各地から指導の依頼が殺到!NHK『プロフェッショナル仕事の流儀』出演の少年野球指導者が語るスポーツで子どもを伸ばす9の導き方
しつけ/育児

年齢によって与える「楽しさ」の種類を変える
私は「楽しい」をいくつかの段階に分けて考えています。
先ほど少し触れた通り、単純に笑顔でワイワイやって盛り上がればいいということだけではありません。
最初はもちろん、チームが活動する滋賀県犬上郡多賀町にある滝の宮スポーツ公園のグラウンドの雰囲気が「楽しい」というところからのスタートだと思います。
全員が同じ場所に集まりながら学年ごとにスペースを分けて練習し、あちこちでワッと盛り上がっている。
幼児教室もするようになったここ数年はさらにガヤガヤとした雰囲気で、初めて来た親子は足を踏み入れた瞬間、休日に大きな公園へ遊びに来たような感覚になるみたいです。
そこから野球をすることの「楽しさ」を感じてもらうわけですが、まず私が考えているのは「成功体験」についてです。
幼児教室や初心者の体験入部で最初に行うのは、ボールを捕ること。
いきなり自力で捕るのは難しいので、このときは指導者が調節してボールをグラブに入れてあげます。
ボールが入る感覚を経験させたら、次は緩いゴロを転がしたり、それを左右にずらしたりバウンドをつけたり。
これを捕ることができたらさらに楽しくなりますし、ボールを捕ってカゴに入れたら走って戻るというのを二人で競争させたりすると、勝っても負けてもキャッキャ言いながら喜んでいます。
ゴロの後は手投げで軽くフライを上げて捕ってもらったり、また前後左右に動かしたり。
そうやって「捕る」ということができるようになれば、子どもたちの中ではボールに対する恐怖心がなくなっていくのです。
あとはボールの投げ方を教え、時間があるときはバッティング練習もしたり、小さいスペースでカラーバットを使った野球をしたり。
速いボールを投げたり、バットにボールが当たったりするのも楽しいでしょう。
ここからさらに成長すると、今度は試合に対する「楽しい」が入ってきます。
私たちのチームの場合、幼児から小学校1年生までは仮入部扱い。
一方、2年生からは正式な部員となって、実戦に近い練習を行ったり紅白戦や練習試合などを組んだりしていきます。
試合を経験すると、自分が上手くなるという楽しさだけでなく、それが試合につながるという楽しさ、さらには野球という競技そのものの楽しさや試合に勝つことの楽しさも感じられます。
個としての「楽しい」に加えて、グループとしての「楽しい」も生まれてくるわけです。
これが両方あるというのが、団体スポーツの良さだと私は思います。
5~6年生になると、逆にチームプレーのことを考えすぎて力を発揮できなくなってしまっている子もたまにいます。
そういう場合、私は「チームのことは考えないでいいから、気持ち良く野球をやろう!」と言ってグラウンドに送り出します。

そもそも昔はみんな何も考えず、思い切り腕を振って速いボールを投げたり、思い切りバットを振ってボールを遠くへ飛ばしたりすることが楽しかったはずなのです。
たとえば、走者を進めようとゴロを狙っている打者がいて、バットでコツンと軽く当てるような消極的なスイングをしたとします。
その場合はこんなやり取りになります。
辻「最終的に今の目的は何?」
選手「しっかり転がして走者を進めることです」
辻「じゃあフルスイングをして、最悪ボールが転がったらええやんか。そうすれば、上手く当たったらホームランにもなるし。最低でも走者がひとつ進むようなスイングに変えたらいいんじゃない?」
実際のところ、チームとしては野球の戦術の部分をしっかり教えているのですが、そこにこだわりすぎると子どもたちのスケールが小さくなりやすいというデメリットもあります。
だから、見逃し三振をした打者に対しては「昔はボール球でも全部振ってなかったか?いつの間にストライクも振らないようになったんだ。思い切り振ったらいいんじゃない?」。
野手同士が間のフライを譲り合ってポトンと落としてしまったときには「昔は他の人のボールまで捕りに行っていたやん」。
そうやって野球を始めた頃の楽しさをもう一度思い出させ、エネルギーを溜めていくことも必要。
その感覚に戻してからまたチームプレーを意識させてあげると、子どもたちが思い切り動けるようになって、楽しく良いプレーが出ることがよくあるのです。
少年野球指導者。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね