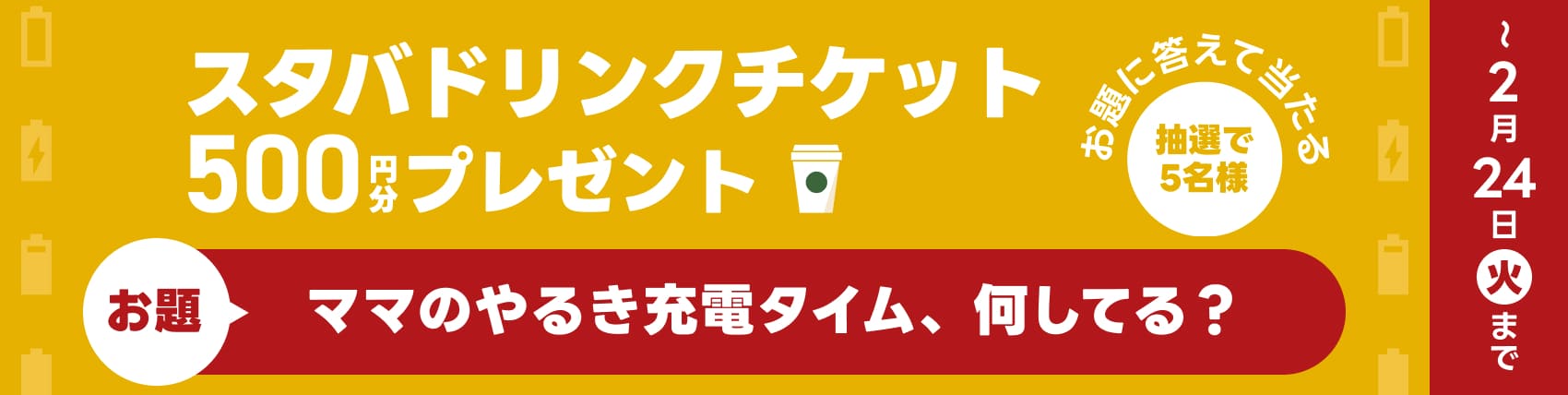人の気持ちを考える物語が子どもの能力を伸ばす!
読み聞かせの最中に親子で「やりとり」をするだけ!思考力・読解力・伝える力が伸びる いつもの絵本が最高の教材に変わる!
教育

わたしとあそんで 〜人の気持ちを考える格好の物語〜
わたしとあそんで
マリー・ホール・エッツ文・絵 与田準一訳 福音館書店
マリー・ホール・エッツの代表作には、1944年に発表されたモノクロの絵本『もりのなか』(福音館書店)もありますが、私のおすすめは、この『わたしとあそんで』です。
アメリカのウィスコンシン州の自然豊かな田舎町で育った彼女が幼少期に森のなかで動物たちと遊んだ思い出をもとに描かれた作品です。
その絵は全体的に温かみのあるクリーム色で描かれており、使う色を制限することで主人公と動物・昆虫が際立つようになっています。
原っぱに1人で遊びに行った女の子は、遊び相手を求めてバッタ、カエル、カメ、リス、カケス、ウサギ、ヘビに次々と声をかけますが、逃げられてしまいます。
仕方がないので池のそばの石にじっと腰掛けていると、先ほど逃げた動物や昆虫が少しずつ戻ってきて女の子を取り囲み、さらに子鹿がやってきて女の子のほっぺをなめてくれるというお話です。
そして最後は「ああ わたしはいま、とっても いま、とってもうれしいの。とびきりうれしいの。なぜってみんながみんながわたしとあそんでくれるんですもの」という印象的なことばで終わります。
刻々と変化する主人公の気持ちを、ぜひ子どもに想像させてあげてください。
では、具体例を挙げましょう。
何質問・答えの拡張
主人公の女の子が登場するシーンで、次のように質問し、その答えを拡張すると、子どもの表現力が培われます。
また、この絵本には、たくさんの動物が出てきますから、「これなあに?」と質問するだけで、子どもが読み聞かせに参加できるわけです。
そして、「そうね。リスさんね」というふうに子どもの回答を肯定・評価していくことで、自信を与えることにもなりますし、絵本を読むことが楽しいとも思ってもらえるでしょう。
私も、この絵本で「カケス」という鳥の名前を知りましたが、なじみのない動物の名前はその絵を指して「カケスっていう鳥だね」というふうに理解を促すといいと思います。
この絵本をアメリカ人の母子に読んでもらっていたときに、面白いことが起こりました。
動物たちが主人公の女の子のところに戻ってくるページで、3歳の子どもが「バンビ」と叫んだのです。
いままでバンビは登場していなかったので、母親は「え、バンビ? いままで出てこなかったのに」としばらく読むのを止めて絵をしっかり見直したところ、草陰に子鹿が描かれているではありませんか!
そこで「あ、ほんと。バンビもいるね」とコメントしたのですが、子どもたちは、読んでもらっている間にも絵をしっかり観察しているのだと思ったしだいです。
文章を完成させるやりとり
主人公の女の子は、森のなかで、バッタ、カエル、カメなどの動物たちと遊ぼうとしますが、その際のフレーズはみな同じ、「○○さん、あそびましょ」です。
最初はそのまま読んで、このパターンを子どもが理解したと思ったら、たとえば 「リスさん」で止めて、「あそびましょ」を子どもから引き出してください。
このように予測を立てながら読むことは、「読解力」の成長につながります。
決まった答えのないやりとり
遊びたかった動物たちが、みんな逃げていってしまったシーンでは、「だあれも遊んでくれないね。どうしてかな?」とか、「みんな逃げていっちゃったね。どうしてかな?」 というように、子ども自身に考えさせる問いかけをしましょう。
子どもの生活と関連した質問
同じシーンで、「○○ちゃんもこの前ニャンニャンと遊ぼうとしたとき、ニャンニャンは遊んでくれた?」というように、子どもの体験と結びつける質問も適しています。
また、主人公だけではなく、動物や昆虫の気持ちを想像させてあげることもポイントです。
子どもが勇気を出して見知らぬ子に「あーそーぼー」と声をかけたのにもかかわらず、よそよそしくされた経験はきっとあるはずです。
でも、子どもがよそよそしい態度をとるときは、別に声をかけてくれた子が嫌いなわけではなく、恥ずかしさや警戒心が原因。
だから必要以上に気落ちしたり、後追いしたりしなくてもいいし、時間に任せればいいんだよ、といったことを、子どもに教えることができます(それを象徴するのが、すべてのページで描かれているにこやかな太陽です)。
こうしたやりとりを通じて、絵本の世界と現実の世界は、かけ離れたものではないと理解するようになるのです。
物語の終盤では、逃げていった動物たちや子鹿までが女の子のところにきて遊んでくれるようになります。
そこで、「どうしてみんな戻ってきたのかな?」と最後の質問をして、その理由を子どもに考えてもらってください。
大阪女学院大学・短期大学学長/大阪女学院大学国際・英語学部教授。Ed.D(教育学博士)
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね