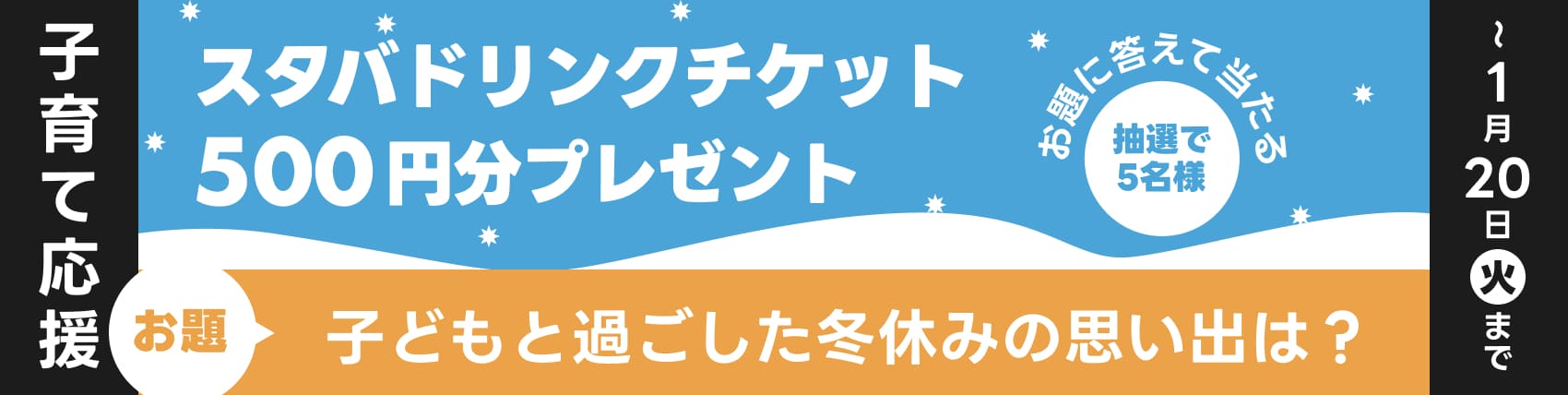30年以上不登校の相談を受けてきた心療内科医が伝える――不登校とは「学校と子どもが合わない」という状態
診察室や相談の現場で、このような相談を30年以上受けてきた心療内科医が 不登校児童が増える今、「これだけは伝えたい」と思ったことを一冊にまとめました。
学校

「不登校は甘えじゃない」。状況を焦らず見守る大切さ。昼夜逆転やゲーム漬けの日々でも、それは大切な回復への一歩。
30年以上親子に寄り添った心療内科医が、いちばん大切なことをわかりやすく伝える実践本。
明橋大二先生の著書『不登校からの回復の地図』から一部転載・編集してお届けいたします。
不登校とは「学校と子どもが合わない」という状態です
まず私は、不登校とは一言で言うと、「本人にとって、学校が合わない」状態」だと考えています。
どうして「合わない」状態になるのか、そのいきさつとしてよく語られることが、私の経験では2つあります。
ひとつは、学校の環境に関すること
たとえば、いじめなど、友達関係で傷ついたとか、先生が怒ってばかりの先生で、自分が怒られているわけではないのに、教室が怖くなってきたとか。
あるいは、学級崩壊気味のクラスで、授業中も騒がしくて、ちっとも勉強に集中できない、先生もただ怒るだけで、教室が殺伐とした雰囲気になっていて苦しくなったとか、そういう場合もあります。
また教室の雰囲気だけでなく、勉強の内容がまったく分からない、それで教室にいることが苦痛になった、ということもあります。
まったく授業が分からないのに、朝から夕方までじっと座っていることほど、つらいことはありません。
私も以前、中国で講演したときに、同じような経験をしたことがありました。
普段は通訳の人がついて、質疑応答なども通訳を通じて理解できるので問題ないのですが、そのときは、シンポジウムで、講師が順番に30分ずつレクチャーをする、というものでした。
私の講演の場合は通訳者がついて通訳してくれました。
しかし、他の講師の話の内容については、もちろん中国語で話されるのですが、通訳がなかったため、内容がまったく分かりません。
しかもシンポジストなので、最前列に席が用意されており、席を外すこともできない。
結果、数時間もの間、まったく内容の分からない話を聞き続けなければならない、ということになりました。
それは本当に苦痛な時間で、そのとき、授業の内容が分からず一日学校にいる子どもの気持ちは、こんな気持ちなのかと深く納得がいった次第です。
もうひとつは、子ども本人の状態に関することです。
たとえば、子どもが月曜日から日曜日まで、授業が終わった後も、塾や習い事に追われ、家に帰るのが毎日夜10時というように、まるで都会のサラリーマンなみに疲労が蓄積して学校に行けなくなる、ということがあります。
また、本人の状態としてもうひとつよくあるのは、HSC、ひといちばい敏感な子の場合です。HSCは、「HighlySensitiveChild」の略で、「ひといちばい敏感な子」と訳します。
これはアメリカの心理学者、エレイン・N・アーロン氏が2002年に提唱した概念です。
HSCは、5人に1人の割合で存在すると言われ、障がいや病気ではなく、特性、持って生まれた性質です。
一言で言うと、感覚的にも人の気持ちにも敏感な子どもを言います。
感覚的に敏感というのは、ちょっとした物音を聞きつける、においに敏感肌触りにも敏感で、チクチクした肌着が苦手、などです。
そういう特徴を聞くと、発達障がいではないかと思われる人も多いのですが、HSCと発達障がいは違います。
どこが違うのかというと、発達障がい(特に自閉スペクトラム症)の人は、人の気持ちに関しては汲み取りにくい、空気を読むのが苦手、ということがあるのに対して、HSCはむしろ人の気持ちが分かりすぎるくらい分かります。
そういう点が、発達障がいとは真逆なのです。
HSCは、人の気持ちが分かるので優しいところがあったり、人が気づかないところに気づくので、危険予知に優れたり、長所もたくさんあるのですが、その一方、特に学校などの集団生活ではつらくなる場面も多いのです。
もちろん、HSCは、5人に1人の割合で存在すると言われますから、HSCがすべて不登校になるわけではありません。
しかし特に、大きなきっかけなく不登校になる子を見てみると、HSCであることが多いです。
それはやはり、学校生活の中にはHSCがつらくなる場面が多々あるからだと思います。
たとえばHSCが学校に行きづらくなるきっかけとしてよくあるのは、「先生の叱り声が怖い」というものですが、別に自分が叱られているわけではない、他の子が叱られているのに、共感力の高いHSCは、それを自分のことのように受け取って、そこから教室が怖い、学校が怖い、となってしまうのです。
他にも、学校では、友達の悪口やからかい、暴言や喧嘩、人前での発表、給食など、HSCが苦手とする場面が多々あります。
それが積み重なることで、学校がつらくなってしまうことがあるのです。
ただここではっきり知っていただきたいのは、「だからHSCは弱い」とか、「HSCは環境に適応できない」と、HSCにネガティブなレッテルを貼ってはならない、ということです。
実は、1つの種に、敏感な個体とそうではない個体と2種類あるということは、すでに人間だけでなく、100種以上の種において確認されています。
それは、生き物の生存戦略として、この2タイプがあるということが、有利に働くからです。
たとえば、サバンナに生活するシマウマの群れの場合、シマウマの中には、遠くからライオンが近づいてくるかすかなにおいを感知する個体が必要です。
そういう個体が危険を感知して、群れに「逃げろ」と指示する必要があるのです。
しかしそのように敏感な個体は、環境を変えることに慎重である傾向があります。
群れは同じところばかりにいては、餌である草を食べ尽くしてしまいます。
ですから、多少の危険を顧みず「移動しよう!」と言う大胆な個体も必要です。
種が生き延びるためには、このように敏感タイプと大胆タイプと、両方が必要なのです。
どちらかが弱いとか強いとかいう話ではないのです。
人間にも、敏感タイプと大胆タイプの両方が必要です。
もし学校が、大胆タイプだけが過ごしやすく、敏感タイプが過ごしにくい環境にあるとするならば、双方が過ごしやすくなるように、環境を変えてゆかねばならない、ということです。
以上のようなことが、不登校になったいきさつとしてよく語られることですが、この2つが重なっていることもあります。
また、最初にお話ししたように、1000人いれば1000通りのいきさつがあるので、これ以外の理由もあると思います。
大切なことは、子どもが不登校になるのは、必ずそれだけの、よくよくの事情があったんだ、ということを理解することだと思います。
心療内科医。子育てカウンセラー。NPO法人子どもの権利支援センターぱれっと理事長。一般社団法人HAT共同代表。児童相談所嘱託医。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね