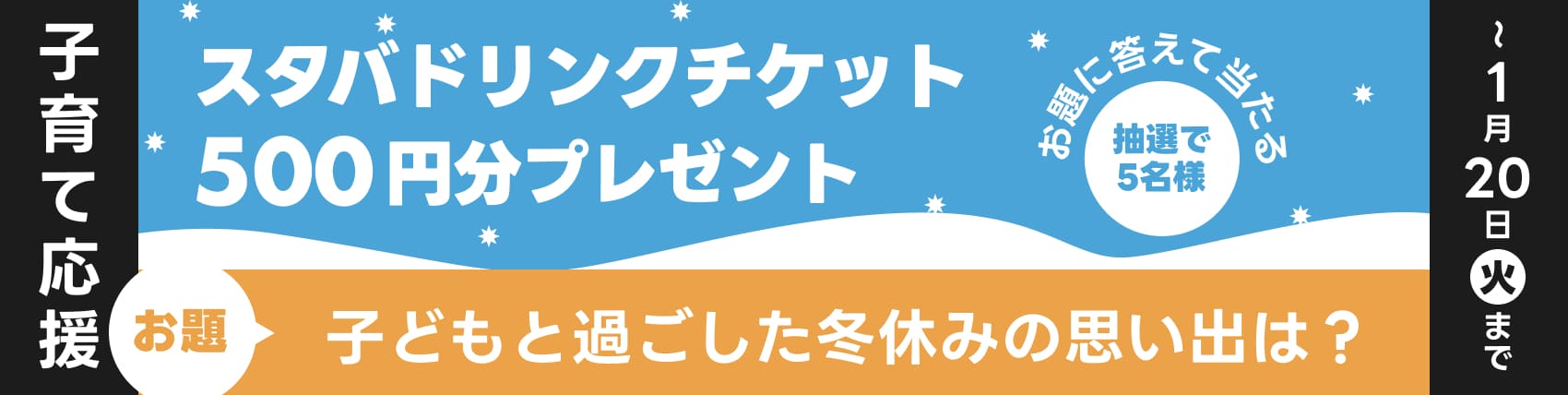30年以上不登校の相談を受けてきた心療内科医が伝える――「行けない理由」は分からなくていい
診察室や相談の現場で、このような相談を30年以上受けてきた心療内科医が 不登校児童が増える今、「これだけは伝えたい」と思ったことを一冊にまとめました。
学校

「不登校は甘えじゃない」。状況を焦らず見守る大切さ。昼夜逆転やゲーム漬けの日々でも、それは大切な回復への一歩。
30年以上親子に寄り添った心療内科医が、いちばん大切なことをわかりやすく伝える実践本。
明橋大二先生の著書『不登校からの回復の地図』から一部転載・編集してお届けいたします。
「行けない理由」は分からなくていい
子どもが不登校になると、親も学校の先生も、「なぜ行けないのか」と原因を探そうとします。
しかし要因はたいてい1つではないし、後から分かることもあります。
いきさつはさまざまで、1000人の不登校の子どもがいたら、1000通りのいきさつがあり、すべてに当てはまる明確な原因などはありません。
そもそも、子ども自身が、最初から学校に行けない理由を語れることはまずありません。
子ども自身、考えたくない場合もあるし、本当に分からない場合も多いからです。
それを無理やり理由を問い詰めようとすると、最終的には子どもを責めるような形になってしまいます。
「理由があるなら言いなさい」ということは、裏を返せば「理由が言えないなら行きなさい」ということになるからです。
「原因探し」は最終的には、子どもの問題、親の問題というところに帰着し、結果として、親子を追い詰めることになりがちです。
ですから、子どもが不登校になったとき、理由がすぐに分からないなら、私はそれはそれでいいと思っています。
今まで学校に行っていた子どもが、あるときから行けなくなったということは、間違いなくそれだけの事情があったからで、それをまず信ずる。
そして行けないときはしっかり休ませる。
それこそが必要で、それによって子どもは必ず元気になっていきますし、回復してゆきます。そこに「理由」は必須ではないのです。
子どもが不登校の理由を話したとき、注意してほしいこと
それでも、私は、どうしてこの子が学校に行きづらくなったのか、そのいきさつを考えることは必ずしも悪いことではないと思っています。
その理由は2つあります。
ひとつはそのいきさつの中で、もし現在にも影響していることがあるなら、それを取り除くことが子どものつらさを軽減することになるかもしれない、ということです。
たとえばある子が、1人の男の子から繰り返し暴言を浴びせられたことで、怖くなって、学校に行けなくなっているとするなら、4月のクラス替えのときに、その子とは別のクラスにしてもらうことで、学校に行きやすくなることがあるかもしれません。
もうひとつの理由は、たとえその理由を取り除くことができないとしても、少なくとも子どものつらさを理解する助けにはなる、ということです。
最初は、ただ学校に行きたくない、と言うだけで、理由も何も分からないときは、どうしても甘えているとか、なまけているとしか思えなかったのが、こういういじめがあったとか、これだけ学校で大変なことがあったんだ、ということが分かれば、「行けなくなるのも無理はないな」と少しは理解できるし、子どもにも少し優しくなれるのではないかと思います。
実際、私には、子どもたちが、ずいぶん後になってから、「実はこんなことがあった」と、不登校になった経緯を話してくれた経験がたくさんあります。
そういうのを聞くと、「そんなことがあったのか。それなら不登校になるのも無理ないよ」「よく、そんなつらいところを毎日学校に行っていたよね。そっちのほうがすごいよ」と言いたくなることがしばしばあります。
それによって、子どものつらさに少しでも共感できるようになることが大切なのだと思います。
ただ気をつけないといけないのは、少し子どもが語ったからといって、それがすべての原因と思い込んではいけない、ということです。
またそういうときに無理に子どもを問い詰めることもよくありません。
子どもはそんなに簡単に、すべてのいきさつを語れるものではないし、それを無理に問い詰めると、「そのときに言えることだけ言う」ということになってしまいます。
親はついつい「それが原因だったんだ!」と思ってしまいますが、本当の理由は、もっと別のところにあったということが後から分かることもあるからです。
本当のことは、子どもがかなり回復して初めて言葉にできることもあるので、それまでとにかく安心・安全な環境を提供して、子どもが語り出すのを待つことが大切だと思います。
心療内科医。子育てカウンセラー。NPO法人子どもの権利支援センターぱれっと理事長。一般社団法人HAT共同代表。児童相談所嘱託医。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね