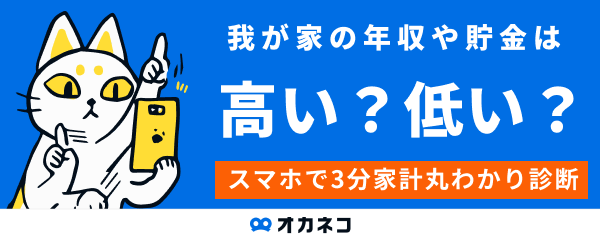累計200万部突破の著者が実践!――美学を伝える
人工知能や脳科学の専門家として、 生き方の指南書が好評を呼んでいる著者による 子育て本の決定版!
しつけ/育児

子育てのキャンペーンコピー
彼を産んだとき。
彼に、多大な敬意を感じたそのとき。
母も惚れるいい男。
私は決心したのだった。
このまま、息子を、惚れ惚れするような男に育てよう、と。
そこで、私は、さっそく息子に伝えた。
母も惚れるいい男になってね。
あなたのことを愛してる。
今まで愛した男への愛をすべて足して百倍しても、あなたへの愛にはかなわないわ。
おそらく、人生で一番あなたを愛するのは母だもの、母を惚れさせないで、他の誰があなたに惚れてくれるのでしょう。
これが、私たちの育てと育ちのキャンペーンコピーになった。
生まれてきた日から、息子は、そのキャンペーンコピーを耳にすることになった。
企業のキャンペーンコピーは、社員やユーザの動機づけのためにある。
動機づけがしっかりしていれば、日々の細かいことで互いの合意が得られやすい。
事業経営と一緒だと、私は直感的にそう思ったのだが、間違っていなかった。
なぜなら、このおかげで、私は、彼を叱る必要がなかったから。
たとえば、保育園時代、お友だちを我が家に連れてきたのに、おもちゃを貸せなかったとき。
「男としてカッコ悪いよ」と言ったら、「おう」と返事して、おもちゃを差し出した。
箸がうまく使えないときも、「魚が美しく食べられない男はカッコ悪い」とひとこと言えば十分だった。
あとは自分で観察して分析し、やがて、エレガントに魚を食べるようになった。
高校時代、期末試験の前日にバイクで遠乗りして試験がさんざんだったときも「男としてカッコ悪すぎる」とため息をついたら、「すまない」と言って、セルフコントロールするようになった。
ここにおいて、「なぜ、それがカッコ悪いわけ?」という質問は、入り込む余地がない。
なぜなら、彼の目標は、“母も惚れるいい男”だからだ。
母がカッコ悪いと思えばアウトなのである。
美学を伝える
私の父は、どんなときにも、問えば「なぜそれをするのか(しないのか)」を説明してくれた。
私の母は、けっして「ひとさまに後ろ指を指されるから」という理由で私を叱ったことがなかった。
娘の言動が自分の美学に反しているとき、それにNOと言ったのだった。
日本舞踊の名取だった母は、みっともないしぐさ(空間にそぐわない大声も含め)が何より嫌いだった。
私は、二人のこの方針がとても気に入っていたので、それをもっと合理的に踏襲したのだ。
「母も惚れるいい男になって」と言っておけば、あとは短いことばで私の美学を息子に伝えられる。
しかも「なぜそれをするのか(しないのか)」が「カッコイイから」と「カッコ悪いから」の二通りですむから、とても楽なのだ。
育てと育ちの方針を、わかりやすいことばでキャンペーンすること。
そのとき、世界を股にかけて活躍する大人の彼(彼女)を想定すること。
これが、キャンペーンコピー開発のコツである。
「お友だちに優しい子」とか「誰にでも好かれる子」みたいな、世間受けのいい"いいこちゃん"をイメージするのはNGだ。
評価軸が「世間」になって、他人の目を気にして生きることになっちゃうから。
思いつかなければ、私のキャンペーンコピーを真似してもらってもいい。
男の子にはとてもよく効くし、女の子に「母が惚れ惚れするような、いい女になって」と応用してもいいはずだ。
あるいは「凜とした女子」とか。
子育てにゼロリスクはありえない
親の思い込みでいいの?もちろん、いいのである。
結局のところ、どんな子も、親の思い込みで育てられることになる。
トップゴルファーや天才棋士は、幼児期からゴルフや将棋を習っている。
成功した場合はいいが、そうじゃない場合は、バレリーナや宇宙飛行士になる可能性をつぶされたかもしれない。
早期教育も、ときには、脳の可能性をつぶす。
たとえば、アインシュタインのような世界をひっくり返す物理学の新法則を思いつく脳や、パーソナルコンピュータという世界を拓いたスティーブ・ジョブズのような世間の度肝を抜くような新発想をする脳は、放っておかれた脳からしか出ないはず。
しつけや優等生教育で、脳が好奇心の信号を発する前に、先に先に正解を教えてもらって育つと、「想定どおりの答えを、素早く正確に出すこと」が脳のミッションになってしまうから。
脳が自発的に欲する前に、大人が要領よく知識を与えてしまうと、好奇心が育たない。
脳が失敗して痛い思いをする前に、大人が安全な正解を渡してしまうと、脳はセンスを培えない。
しかし、優等生脳を促成栽培することはできる。
「導かれて、教わる」ことで、脳は「世間が目論む、いい脳」に誘導されるのだ。
ただし、世間をあっと言わせるような発見は、その脳からは出てこない。
天才は、それとはまったく逆方向の、変わった配線構造の持ち主なのである。
とはいえ、優等生にしたかったら、早期教育を受けさせたほうが手っ取り早いし、エリートになる確率も上がる。
自分の子の脳が『役に立つ天才脳』かどうかなんて、最後までわからない。
ならば、安全策を取るのも一つの戦略。
いずれにしても、親が思い込みで進めるしかない。
私自身は、この世にたった一つの脳として生まれてきた息子に、彼にしか見えないものを見てほしいと思ったので、彼を放っておくことに決めた。
早期教育は一切しなかったし、学習塾にも通わせたことがない。
小学校時代には優等生からは程遠く、中学お受験に戦々恐々としていた同級生のお母さんたちから「くろちゃん見てるとほっとする~。こんなんでも生きてていいんだって思えて」と言われる始末だった(苦笑)。
しかし、その後淡々と学業を修め、憧れだった自動車の設計開発エンジニアを経て、現在はわが社のコンサルタントとして新領域を拓いている。
冒険心も読書量も半端なく、ビジネスセンスもあるので、やがてもっと大きなステージに乗り出していくのだろう。
プライベートでは、愛してやまない伴侶に、心から敬愛されている。
彼を放っておくと決めたのは、ある意味一か八かの勝負だったが、とりあえず、この勝負には勝ったみたい。
でも、ゼロリスクだったわけじゃない。
脳科学上、子育てにゼロリスクはありえない。
脳というのは、何かを選べば、何かを捨てることになり、何も選ばなければ、何も育たない。
「あれも、これも」はありえない。
株式会社感性リサーチ代表取締役、人工知能研究者(専門領域:ブレイン・サイバネティクス)、感性アナリスト、随筆家。日本ネーミング協会理事、日本文藝家協会会員。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね