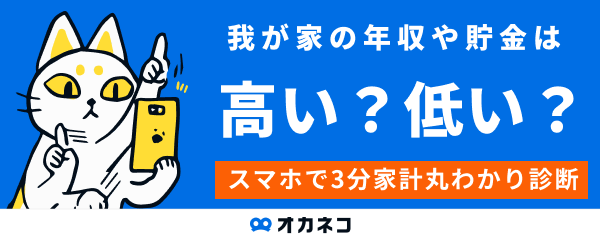「専業主婦」の年金の仕組みと「夫婦」での年金見直しを徹底解説
知っているようで知らない「専業主婦」の年金の仕組と「夫婦」で年金を増やしていく具体策をまとめました。
お金
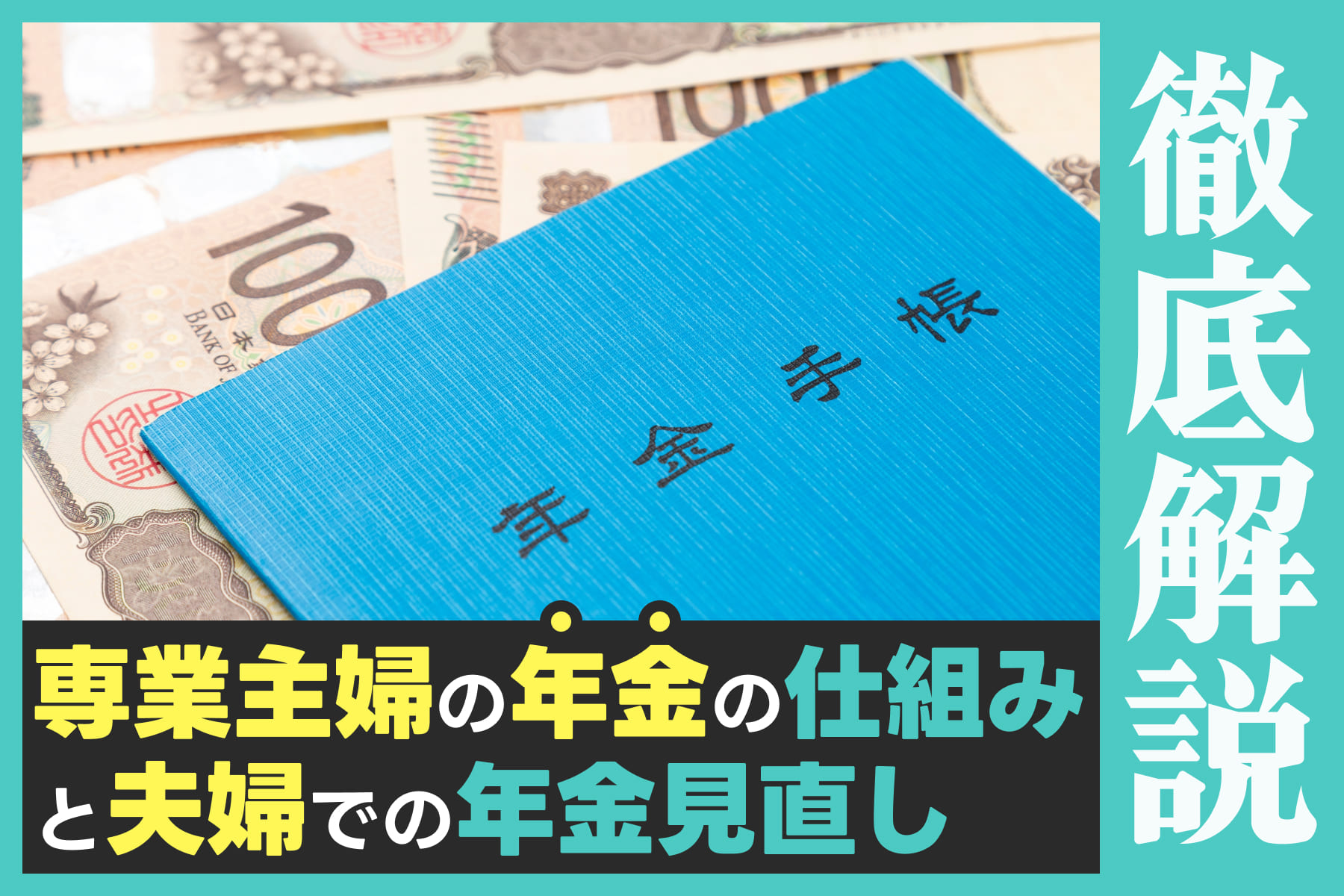
「専業主婦」の年金の仕組みと「夫婦」での年金見直しを徹底解説
専業主婦として日々の家事や育児に専念していると、将来の年金受給額に不安を抱えがちです。どれだけの年金が受け取れるのか、どんな制度を活用すれば良いのかなど、知っておくべきポイントは多岐にわたります。
本コラムでは、専業主婦が受給できる年金の仕組みや受給額の目安、第3号被保険者制度の今後の動向を解説するとともに、受給額を増やすための方法や働き方の選択肢まで詳しく紹介します。
専業主婦が受給できる公的年金の基本構造

専業主婦の年金制度と聞くと、「第3号被保険者」という言葉が思い浮かぶ方もいるでしょう。第3号被保険者とは、国民年金制度において、厚生年金に加入している会社員や公務員といった第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人を指します。
ここでは国民年金を中心に、第3号被保険者制度がどう位置づけられているのかを整理します。
まず最初に「公的年金」の説明から始めます。
公的年金とは、国が運営する年金制度で、主に老後の生活資金を保障することを目的とした社会保障制度です。原則として国民全員が加入する「国民年金」をベースとして、そこに会社員や公務員が加入する「厚生年金」を上乗せする2階建ての仕組みで成り立っています。
専業主婦の場合、国民年金の被保険者のうち第3号被保険者として扱われ、国民年金を納付しなくても配偶者が第2号被保険者であることを前提に年金が計算され、配偶者が厚生年金に加入している限り、老後の年金制度上の保障を受けることができます。
ただ、専業主婦は自ら国民年金保険料を納付しなくても基礎年金を積み立てられるメリットがある一方で、厚生年金部分がないため、受給額の総額は共働き夫婦と比べて少なくなる傾向があります。
国民年金について知っておきたいこと
続いて、国民年金をもう少し詳細に説明します。
国民年金は、老齢年金や障害年金、遺族年金などを給付する基礎的な部分であり、すべての国民が加入する制度です。
前項でもお伝えしましたが専業主婦は配偶者が第2号被保険者である場合に、第3号被保険者として国民年金の保険料を自ら負担せずに加入できます。この仕組みにより、家庭の経済状況を考えながら家事や育児に専念しつつ、最低限の老後保障を確保できる点は大きなメリットです。
ただし、国民年金の給付水準は生活費をまかなうほど十分ではありません。国民年金だけで老後の生活を続けるのは厳しいとされています。
そのため、夫婦で共に将来のプランを立て、家計全体での貯蓄やその他の資産形成を考慮する必要があります。国民年金に頼るだけではなく、生活設計に合わせた備えを検討することが不可欠です。
また、国民年金の加入期間や納付状況が老齢基礎年金(原則として65歳から受給できる年金)の受給額に直接影響するため、万が一、配偶者が仕事を辞めた場合などは種別変更の手続きが必要となります。知らずに未納状態が続くのを放置してしまうと、後から追納しても受給額に大きな差が出る場合があるため、法的手続きや条件に常に注意を払うことが重要です。
種別について
● 第1号被保険者:自営業、農業、学生、無職の人など
● 第2号被保険者:会社員、公務員など厚生年金や共済組合に加入している人
● 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)
第3号被保険者の条件と手続きの流れ
続いて、第3号被保険者になるための条件についてです。
配偶者が第2号保険者であることや、専業主婦自身の年間収入などいくつかの条件があり、それらをクリアすると、自動的に保険料免除で国民年金に加入できます。
第3号被保険者条件
● 厚生年金保険に加入している第2号保険者(会社員や公務員など)に扶養されている配偶者であること
● 20歳以上60歳未満であること
● 年収が130万円未満(障害者の場合は180万円未満)であり、かつ配偶者(第2号被保険者)の年収の2分の1未満であること
※別居の場合は仕送り未満の収入であること
● 日本国内に住所があること(住民票が日本国内にあること)
● 配偶者と事実婚関係にある場合も対象になることがあります
手続き自体は、配偶者が勤務する会社や共済組合などを通して行われ、提出書類の漏れがなければ比較的スムーズに認定が行われます。ただし、配偶者の就職や退職、専業主婦自身の就労状況が変化した際は、速やかに変更手続きを行うことが大切です。放置していると誤って保険料が未納扱いになる可能性があり、将来の年金額に影響することもあります。
また、離婚や配偶者の死亡によって扶養関係が解消された場合、第3号被保険者の資格を失います。その時点で第1号被保険者への切り替えを行わないと、年金の受給資格に空白期間が生じてしまい、老後に大きく響くかもしれません。人生の節目ごとに自身の被保険者種別を確認し、必要な変更手続きを適宜行うことが大切です。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね