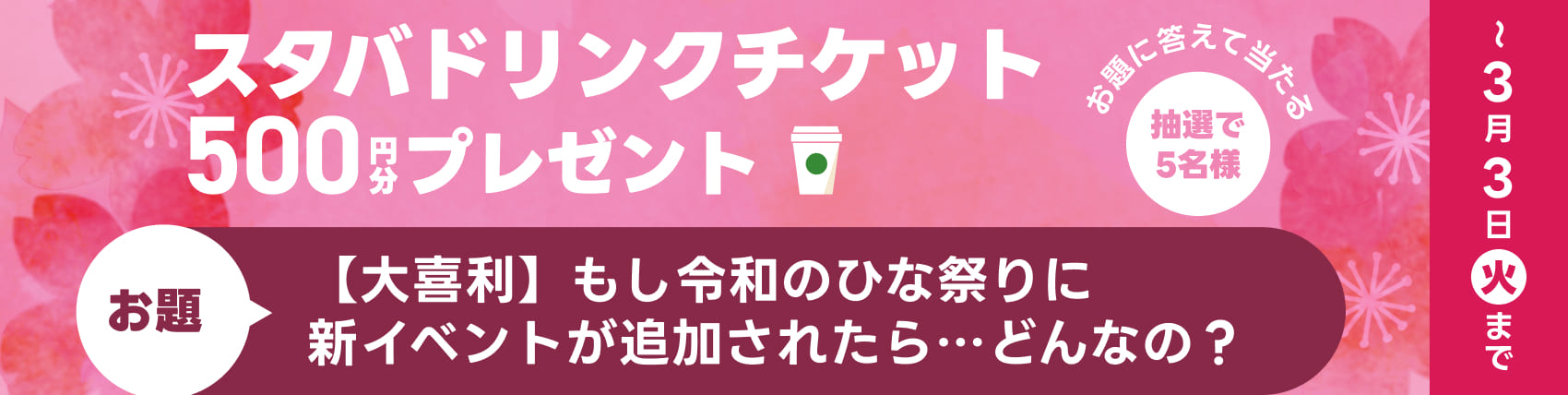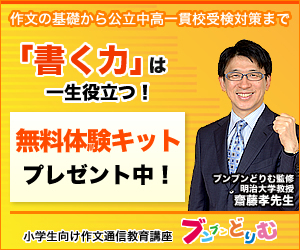小学生の夏休み宿題が終わらないときの対処法と親子で乗り切るポイント
夏休みの宿題はただの課題じゃなくて「学ぶの習慣作り」や「自己管理力」を育む練習期間です。
学校

小学生の夏休み宿題が終わらないときの対処法と親子で乗り切るポイント
こんにちは、あずみのこです。
「宿題まだ終わってない…」あの瞬間の心のザワつき、今年もまたやってきました(涙)。
夏休みは、子どもにとって学びのペースが緩み、遊びの誘惑が全方位からやってくる時期。「明日やればいいや」が何日も続いて、気づけば8月下旬……。そんなパターン、どこの家庭にも起こる“夏休みあるある”ではないでしょうか。
特に小学生は、宿題の意味や計画の立て方がまだあいまいなことも多く、進み具合は“保護者の声かけ次第”になることもしばしばです。でも、「全部手伝ったら意味ないよね…」「でも、このままだと間に合わない!」そんな“親の葛藤ゾーン”に、今まさに足を踏み入れている方も多いはず。
このコラムでは、小学生の夏休みの宿題が終わらないときに役立つ対処法を、親子それぞれの視点からまとめました。やる気スイッチの入れ方、1日で巻き返す宿題スケジュール術、自由研究・読書感想文の“ほどよい手抜きワザ”まで。忙しい毎日の中でもムリなく取り入れられるヒントをお届けします。
夏休みの宿題が終わらない子どもが多い理由
夏休みの終盤、「宿題終わってない」と焦る子どもたち。それ、めずらしいことじゃありません。むしろ、多くの家庭で毎年くり返されている“あるある現象”です。
背景にはいくつか共通パターンがあります。学校の決まった時間割から解放され、自由に過ごせる一方で、計画を立てて動く力=「自己管理力」がまだ発展途上の小学生にとっては、ペースを保つのが難しいんですよね。気づけば課題は山積み、最終日に慌てて片づける…そんな光景も珍しくありません。
特に自由研究では、「子どもが1人で進められない」が61.1%(キッズウィークエンド, 2023)と最多【※1】。ベネッセの調査(2022)でも、「テーマが思いつかない」(33.2%)、「研究を1人で進められない」(28.3%)が上位でした【※2】。低学年ほど保護者の全面サポートが必要な傾向もはっきり出ています。
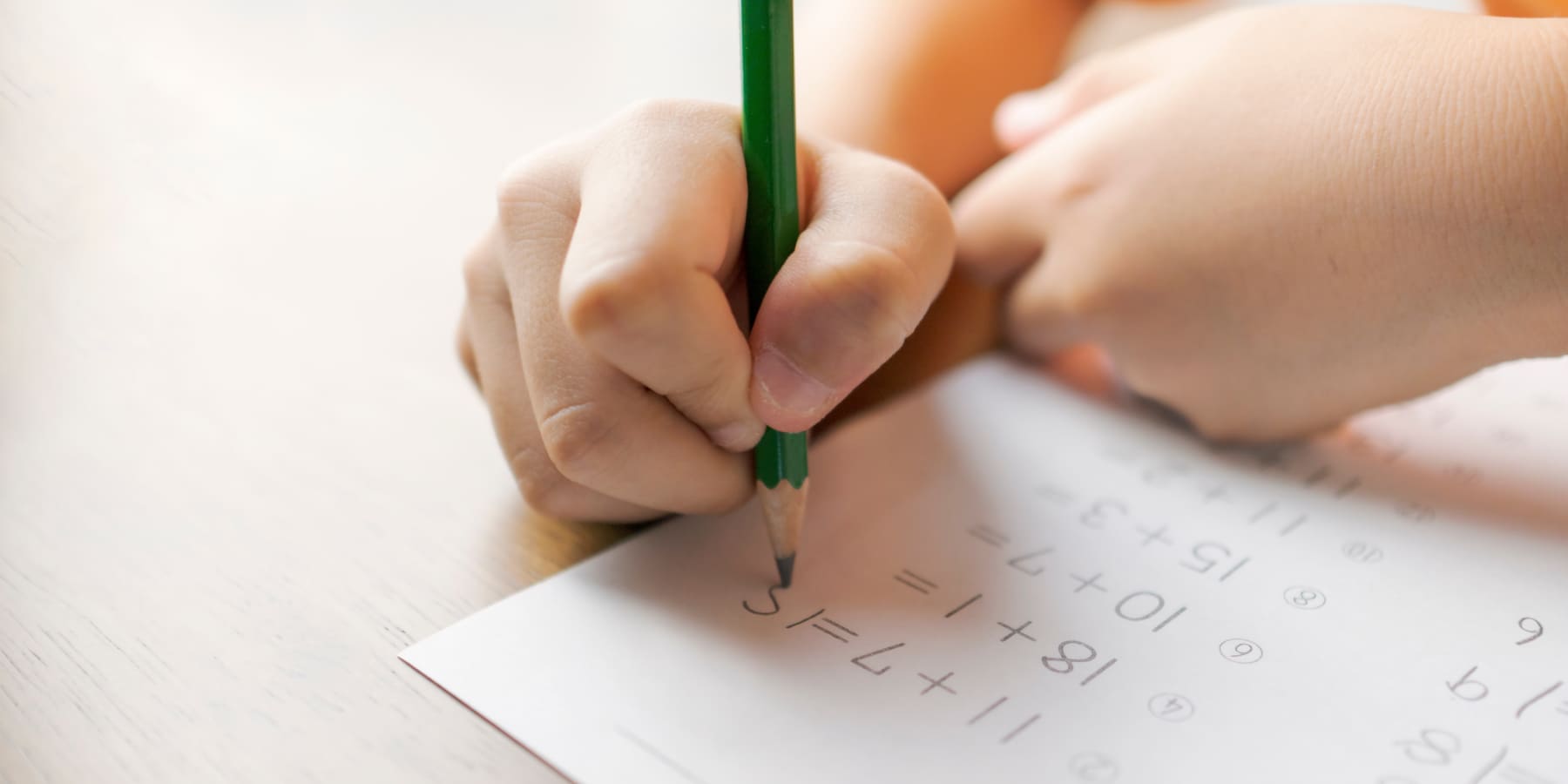
遊びの誘惑が強く、勉強を後回しにしがち
プールに花火、旅行、YouTubeにゲーム...。夏って学校の縛りから解放されて「今この瞬間を楽しみたい!」欲が全方向から子どもに押し寄せてきます。大人から見れば「10分あれば1ページ終わるのに〜」と思っても、子どもにとっては、遊びモードから勉強モードへの切り替えって意外とハードル高いんですよね。
キッズウィークエンドの調査でも「ぎりぎりまで手つかず」が24.6%にのぼっていました。さらに保護者の81.1%がテーマ選びで「子どもが楽しんで取り組めること」を重視しているそうです。やっぱり“楽しさ”は、やる気の火種になるんですよね。
夏休みは長いと思い込み、期限を意識できない
約40日ある夏休み。大人から見れば「そこそこ時間あるな」ですが、小学生からすると“終わりが見えないほど長〜い休み”に感じることもあるようです(笑)。
「まだ大丈夫〜」なんて言っているうちにお盆が過ぎ、自由研究や読書感想文など時間のかかる課題がまるっと残ってしまうパターンも多々。結果、期限ギリギリで詰め込み、内容が雑になったり、間に合わなかったり…。
ベネッセの調査では、「完全に子どもに任せる」保護者はわずか1%未満だそう。ほとんどの家庭が「一部を手伝う」か「全部手伝う」スタンスで、期限を意識させるための伴走や声かけは、やっぱり欠かせないというのが実情です。【※2】
保護者が感じるイライラを減らすために大切な視点
「そろそろやったら?」と、夏の終わりにくり返されるこのやり取り、もはや“季節の風物詩”かもしれません(笑)。つい声が強くなってしまい、「あぁ、また言いすぎちゃった…」と自己嫌悪。私も何度も経験済みです(苦笑)。でも、叱ってもお互いのストレスが増すばかりで、子どものやる気も下がってしまいます。
結局大事なのは、「どうやってやらせるか」ではなく、「どうやったら“自分から”やりたくなるか」なんですよね。「今日はどこまでやろうか?」と一緒に決めたり、「この問題が終わったらおやつにしようか」と小さく区切りの提案をしてみたり...。
そんな小さな声かけの工夫で“自然とやりたくなる空気”が生まれると、不思議と子どもも自分から動き出すようになり、結果的に、親のイライラも子どもの抵抗感も少しずつやわらんでいきます。…まあ、この空気作りが一番難しいんですけどね(笑)。

子どもと大人の「動機」の違いを理解する
親にとって宿題は、「やるべきこと」「期限を守るもの」という感覚がすっかり染みついていますよね。でも、子どもにとってはそうとは限りません。特に低学年では、“やる意味”や“ゴール”が見えないまま「とりあえず出されたからやる」というケースも多いもの。
だからこそ、「早くやって!」と急かすよりも、「これってどんなことに役立ちそうかな?」と子どもの視点でかみくだいて話すのもおすすめ。たとえば、計算ドリルなら「これが速くできるようになったら、ゲームでもっと得点できるかも!」、自由研究なら「調べたら〇〇博士みたいになれそうだね!」など、子どもの興味や関心と結びつけて、一緒にやりたくなる理由を見つけてワクワクしてみる。そんなやり取りから、「ちょっとやってみようかな」という気持ちが、少しずつ芽生えてくることもあるんですよね。
本当に困っているのは誰? 親子で考える重要性
「提出できなかったらどうしよう」「先生に怒られたらかわいそう」そう思って焦ってしまうのは、大人側の“先読み力”があるからこそ。でも実際に困るのは、子ども自身。だからこそ、「誰の宿題なのか」という原点に立ち返ることも、意外と大事かもしれません。
「どうしたら進められそう?」「どこが一番たいへん?」そんなふうに、一緒に困り感を言葉にしていくことで、子ども自身の気づきにつながることも。
“やらせる”より“一緒に考える”を大切にすることで、宿題への前向きさが、ちょっとずつ育っていくように思います。
子どもの自主性を育む夏休みの計画作り
夏休みの宿題、ただ“こなす”だけで終わらせるのは、もったいない気がしますよね。 この時期こそ、計画を立てる練習を通して、子どもの「自主性の芽」を育てるチャンスにもなります。
「今日は何をする?」「どれくらいで終わりそう?」そんな問いかけを、日々のなかに少しずつ混ぜてみるだけでも、子どもは“自分で考えて進める力”を少しずつ身につけていきます。
もちろん、急に一人で全部こなせる子なんて、ほとんどいません。だから保護者は“サポート役”に徹して、つまずきそうなときにヒントを出したり、一緒に作戦を練ったり。そうやって「できた!」の小さな達成感を積み重ねる関わりが大切になるのかもしれません。

全体像と分量を可視化して進捗を把握する
私が実際にやってみて「これはよかった!」と思ったのが、まず宿題をざっくり種類ごとに分けて“見える化”する方法です。 といっても細かく日割りを作るのではなく、「ドリル系」「自由研究」「読書感想文」「その他プリント」くらいに大まかに分類するだけ。
そのリストを大きめの紙などに書き出し、横に□をいくつか並べて“シール貼りスペース”を作ります。最初に「何をやったらシール1個」を決めておくのもポイント。たとえば「今日はドリル1ページできたから1個!」と、小さなゴールごとにシールを貼っていくと、進み具合が目に見えてわかり、ちょっとゲーム感覚でやる気が出るようです。全部を細かく書き出さなくても、“終わった感”を味わえるだけで十分なんですよね。
計画通りにいかない日ももちろんあります。でも実は、そこにも大事な学びのチャンスがあると思っています。「計画通りにいかない日があってもOK」という空気を持てると、親も子も気持ちが軽くなりますし、むしろ予定通りに進まなかったときこそ、「じゃあ明日はどうしようか?」と考える経験が、自主性の芽を育ててくれるんですよね。
失敗から学ぶメリットとタイミング
でも、予定どおりに進まないときって、「だから言ったでしょ!」ってついつい言いたくなる気持ちにもなりますよね。でも、そこでちょっと深呼吸。
小学生のうちに「やってみたけど間に合わなかった」という挫折を経験して、自分で修正する方法を見つけることは、「自己管理力」を育てるうえでとても大きな力になります。
また、デンマークで行われた実験では、「今は苦手でも、そのうち伸びる」という“成長マインドセット”の考え方を親が持つだけで、子どもの成績が数か月で向上したという結果が出ているんですね【※3】。 つまり、やり方や時間よりも、「できるようになるはず」という前向きな捉え方が、子どもの行動や意欲に大きく影響するということ。
「できなかった…」で終わらせず、「じゃあ次はこうしよう」に変えていく。その小さな積み重ねが、子どもの学びの底力を育てていくのかもしれません。そして、そんな姿を見て「前より少し成長したな」と感じられる瞬間が、きっと親にとっても大きなごほうびになるはずです。
短時間学習の積み重ねと朝学習の活用術
計画通りにいかない日もあれば、気持ちが乗らない日だってあるのが夏休み。そんなときこそ試したいのが「短時間×朝学習」です。「朝のうちに終わらせておけば、あとは遊ぶだけ!」というこの快感を知ると、意外と子どもはスイッチが入りやすくなります。
教育クリエイターの陰山英男氏も、「朝の10〜15分で頭のエンジンをかけておくと、その日の学習効率が上がる」と話しています【※4】。朝学習に向いているのは、計算ドリルや音読、漢字の暗記など、短時間で終えられる課題。こうした“パッとできる”内容を朝に取り入れることで集中力が高まり、その日の学び全体がスムーズになるそうです。
がっつり付き添わなくても、“ちょっと見ててくれる”安心感があると、子どもは意外と落ち着いて集中できるもの。朝の静かな時間を味方にすることが、子どもの「やろう!」を引き出す小さなコツになるのかもしれませんね。
保護者が意識したい子どもへのサポート方法
つい親心で「あれやった? これ終わった?」と口にしてしまいがちですが、言いすぎると子どもの自主性がしぼんでしまう可能性もあります。
そこでポイントになるのが、“伴走型”の関わり方。進み具合をそっと横目でチェックしつつ、必要なときだけサッと助け舟を出す。そんな安心感があると、子どもは案外すんなり宿題に向かいやすいようです。
ベネッセ教育総合研究所の庄子寛之氏も、子どもが困った時には「呼ばれたら行くが、呼ばれない時は見守る」姿勢が、自主性と安心感の両方を育てると指摘しています【※5 】。
つい手や口を出したくなる夏休みですが、今年はちょっと肩の力を抜いて、“必要なときにだけサッと動く”くらいの距離感で見守ってみるのもいいかもしれません。そうすると、親の気持ちもずいぶん楽になりますし、子どもも「やってみようかな」という気持ちを持ちやすくなるはずです。

計画表を一緒に作り、見える場所に貼り出す
「今日は何をやるんだっけ?」が一目でわかる計画表は、作る時間そのものがちょっとしたトレーニングになることも。やることを整理して、カレンダーや表に書き出してみるのもオススメです。できあがったら、リビングや机の横など、いつでも目に入る場所にペタッと貼っておくだけでOK。毎日「今日はここまでできたね」と一緒にチェックするだけでも、やり忘れ防止に効果ありです。
大事なのは、親が“監督”になってしまわないこと。京都教育大学の伊藤崇達氏の研究(2015年)でも、やることを細かく指示するより、子どもが自分でやり方や順番を決められるように支援するほうが、主体性や計画力が育ちやすいとされています【※6】。
声かけも「進み具合どう?」くらいの軽さで、横で支える“マネージャー”の距離感がちょうどいいんです。
声かけ・ほめ方のコツとNGワード
声かけのタイミングや言葉選びで、子どものやる気が一気に高まることもあります。例えば、成果を認めるときは「ここがよかったよ」と具体的に伝えると、子どもは達成感を感じやすくなるようです。
教育ライターの加藤紀子氏が紹介している「PNP(ポジティブ・ネガティブ・ポジティブ)法」では、まずほめ言葉(ポジティブ)から入り、次に改善点(ネガティブ)を伝え、最後にもう一度ほめて(ポジティブ)締める“サンドイッチ方式”が効果的だそうです【※7】。
逆に「まだ終わってないの?」といった否定的な言葉は、やる気スイッチをオフにしてしまいがち。「でも」より「だから」を使うだけでも、子どもの受け止め方はグッと変わります。小さな成長をキャッチして「お、いいね!」と声をかける。そんなひと言が、宿題タイムをちょっと前向きな時間に変えてくれるのかもしれません。
ご褒美やペナルティを設定する際の注意点
実は、我が家では「ご褒美制度」がちょこちょこ登場します(笑)。「これ終わったらアイスね」とか「1週間続けられたら推しグッズ1個」など。こういうわかりやすいご褒美は、やる気を引き出すのに確かに「即効性」があります。短期的には“やる気スイッチ”が入りやすいんです。
でも、続けているうちに「ご褒美がないとやらない」状態になってしまうこともあって、そこは要注意だなと感じています。ペナルティも同じで、おどすように使うと空気がピリピリしてしまい、かえって逆効果になることも。
教育心理学の調査でも、外的なご褒美や罰よりも、子どもが自分で方法や順番を決められるように支援する「自律性支援」のほうが、結果的に主体性や計画力の向上につながると示されています【※5】。
最近は、「どういうルールなら続けられそう?」と子どもと一緒に考えるように心がけてはいるんですが…、やっぱり忙しさのあまり、ご褒美作戦の“即効性”に私自身が甘えてしまっています(笑)。このあたりのバランスは、私もまだまだ修行中です(汗)。
大物宿題・自由研究をスムーズに進めるコツ
時間も手間もかかる“大物宿題”や自由研究は、着手が遅れると、あっという間に親子でバタバタ…なんてことになりがちです。
てつなぎの掲示板で「子供達の夏休みの宿題の中で私が最も嫌な事。自由研究。笑」(🔗てつなぎ掲示板|“夏休みの自由研究”)なんて読むと、もはや共感しかありません(笑)...。
最初の関門はテーマ選びですよね。ただ、ここで欲張ると最後までたどり着けないこともあるので、子どもの「やってみたい!」を大切にしつつ、無理なく終えられる範囲を見極めるのがポイントです。
ざっくりでも進め方を決めておくと、必要な材料や手順を早めにそろえられ、作業時間を効率的に使えます。親は難しい部分だけサポートしながら、なるべく子ども自身の考えや工夫を引き出す役に回れるといいですよね。

テーマ選びとアイデアの探し方
自由研究のテーマは、子どもの興味・関心を軸にすると、やる気が続きやすい...というのは、もう鉄則です。図書館やネットで探すのもいいですが、日常の「なんでだろう?」や好きな遊びから広げてみると、意外とスムーズに決まることがあります。たとえば、公園で見つけた虫や、おやつ作りでのちょっとした疑問も立派なテーマに。
大事なのは、子どもが「もっと知りたい」と思えるかどうか。「どうしてそう思う?」と一歩深掘りする声かけを意識できると、子ども自身が主体的に考えるきっかけになりそうです。
早めに取りかかるスケジュールと役割分担
大物宿題は、全体の流れをざっくりでもいいかから“早めにつかんでおく”と、あとが本当にラクになります。まずは「いつまでに何を終わらせるか」を逆算して、大まかなスケジュールを作るのがおすすめ。早めに動けば、途中で壁にぶつかっても立て直す時間が持てますからね。
親子で進める場合は、子どもができる部分を優先して任せ、サポートが必要なところだけ手を貸す形が理想です。
…とはいえ、計画どおりにいかない日も多く、気づけば親が半分以上やってしまっているなんてパターンもありがち。でも、それも最初から想定内(笑)。肩の力を抜いて、ぼちぼち進めていきましょう!
子どものやる気を引き出す方法
やる気さえあれば、子どもって思った以上にスイスイ進めるんですよね。得意なことや好きなことを活かして、小さな「できた!」を積み重ねることで、「自分でもやれるんだ」という気持ちが芽生え、次の課題にも前向きになりやすくなります。たまに軽い競争やチャレンジ要素を入れることで、飽きにくく自然と向上心もくすぐられるみたいです。
ただ、ずっと横で応援しすぎると、かえってプレッシャーになることも。声をかけすぎず、でも放置しすぎず…その“ちょうどいい距離感”を探すのが、案外いちばん難しくて、いちばん大事なのかもしれません。

好きな科目や得意分野から取り組む工夫
まずは、子どもが「これならやれる」と思える教科やジャンルから始めるのがポイントです。最初にポジティブな気持ちでスタートできれば、その勢いで苦手科目にも取りかかりやすくなります。
うちの場合も、とりあえず子どもが好きな教科からスタートすることが多いです。…と言っても、「今日はやらない!」と全拒否されて、しぶしぶプリント1枚だけで終わる日もありますが(汗)。それでも、少しでも“できた”があればOK。そんな日々の積み重ねが、宿題に向かう“型”になっていく気がします。
友達や兄弟と一緒に競い合うモチベーションアップ
同年代の子と「今日はどこまでやった?」と見せ合う機会は、意外とやる気を引き出すきっかけになることがあります。兄弟姉妹がいるなら、たまにお互いの進み具合をチェックし合うのも、小さな刺激になり案外いいモチベーションになることも。
いつもと違う雰囲気を作りたいときや、ちょっとマンネリしてきたときに、モチベーションアップに試してみるのもアリです。
夏休み最終日まで宿題が残ってしまったときの緊急対策
気づけば残り1日。机の上には終わってないプリントと、手つかずの自由研究…。 「どうしよう...」「終わった...」と一瞬お先真っ暗なりませんか?(笑)
でも大丈夫。まだ間に合います。完璧なんて、この際目指さなくてOK。まずは「提出する」ことを最優先にしましょう(笑)。時間がないからこそ、要所だけ押さえてとりあえず形にする”方向に切り替えるのがポイントです。
優先順位を決めて手をつけるポイント
焦って全部に手を出すと、どれも中途半端になるので、ここはもう割り切りが大事です。 「すぐ終わるやつからやっつける」でもいいし、「期限が厳しいやつから片づける」でもOK。とにかく「何をやるか」「やらないか」をはっきり決めること。大物に時間をかけすぎて、他が全滅…は避けたいですよね。提出可能ラインを見極めて、一気に攻めちゃいましょう。
完璧を目指しすぎず、提出することを最優先に
清書の字がちょっと曲がってても、図が白黒でも、この際OK!「終わらせる」ことをゴールにすると、不思議と気持ちも軽くなります。提出さえしてしまえば、とりあえずは夏休みの宿題ミッション完了(笑)。
そして毎年恒例、「来年こそは早めにやろうね」という親子の反省会で締め…(笑)。たぶんまた来年も同じやつ、やるんでしょうけど(苦笑)、それも良しとしましょう。
まとめ:夏休みの宿題を乗り越え、学習習慣を身につけよう
夏休みの宿題って、親から見ると「さっさと終わらせればいいのに…」ですが、子どもにとっては山のように見えるもの。 でも、計画とサポートをちょっと工夫すれば、ちゃんと乗り越えられます。
大人が「まだやってないの!?」と焦って叱るより、「今日はここまでやってみようか」と“寄り添う”ほうが、子どもの手はずっと動きやすくなるものです。
そして、全部やってしまうんじゃなくて、あくまで子どもが「自分で進められる」ように手を添えるのが大事なんですよね(…と書きながら、自分にも言い聞かせています)。
夏休みの宿題は、ただの課題じゃなくて「学びの習慣づくり」や「自己管理力」の練習期間。終わった瞬間の達成感も、思い通り出来なかったという反省も、ぜんぶが次につながるはずです。来年はもうちょっと早く…と毎年(笑)思いつつ、また親子で今年の夏休みを乗り越えていきましょう。
多様な教育ナビゲーター
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね