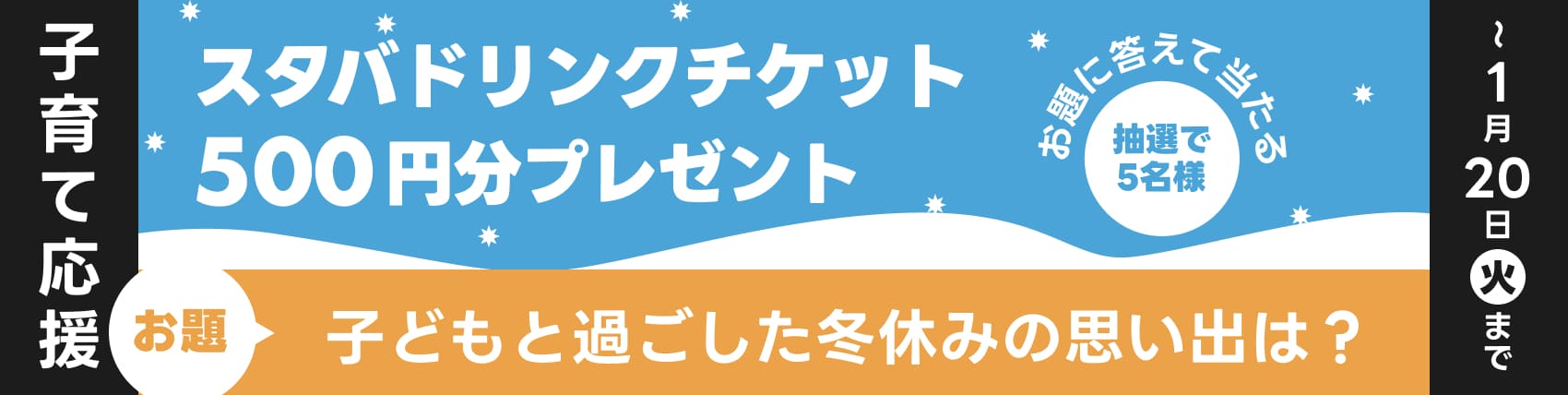累計200万部突破の著者が実践!――脳をメンテナンスする
人工知能や脳科学の専門家として、 生き方の指南書が好評を呼んでいる著者による 子育て本の決定版!
食事

脳をメンテナンスする
脳は、電気回路である。察する、感じる、思う、考える、好奇心、集中力、発想力、忍耐力。脳で起こることは、すべて電気信号によってまかなわれている。
したがって、電気信号がいかにうまく流れるかが、脳の勝負。うまくメンテナンスした脳が勝つのである。
自己肯定感は、基本的に、朝日がくれる
網膜に朝の自然光が当たると、その刺激が視神経を伝わって、ホルモンの中枢司令塔に届く。
そして、セロトニンというホルモンを誘発する。
セロトニンは、脳神経信号のアクセル役。脳神経信号をスムーズにしてくれるホルモンである。
セロトニンがしっかり出ると、脳神経信号が、起こるべき時に、起こるべき場所にすばやく起きて、そのスピードが落ちず、情報が劣化しない。
つまり、一日中、脳が目論み通りにすっきり動くことになる。
やる気の信号も萎えない。
脳は、「目論見通りに動く自分」に万能感を覚え、自己肯定感を蓄えることになり、充実した一日を過ごすことになる。
セロトニンが、別名『幸福ホルモン』と呼ばれるゆえんである。
日の出から9時台くらいまでの朝日にその効果があるとされる。
それを知ったら、もったいなくて、朝寝なんてしていられなくない?
セロトニンは、腸で作られて脳に運ばれるので、腸を整えることも、もちろん大事。
朝の便通のためにも、早起きして時間に余裕があるのは重要だよね。
そのほかにも、「脳に信号が行き渡らないうちに(まだ目が覚めきらないうちに)、身体を動かし始める」と、その分泌量が数倍に増えるというデータもある。
してみると、あの夏休みの朝のラジオ体操。
寝起きの、半分寝ているような状態で広場にやってきて、反射的に身体を動かす、あれ。
やる気のない、ぷらんぷらんやるラジオ体操こそ、セロトニン分泌促進の離れ業だったのである(!)。
日常なら、朝いちばんの定番のお手伝いがあるといいと思う。
新聞を取りに行く役、ベランダの植木に水をやる役、スムージーを作る役。
ただし、脳が半分ぼんやりしたまま、だらだらやるのがコツ。
「さっさとやって」なんて言わないであげてね。
脳もガス欠じゃ動かない
さて、セロトニンがアクセルをふかしてくれても、ガス欠じゃ脳は動かない。
車と一緒だ。
脳は電気信号で動いているので、エネルギーが要るのである。
脳のエネルギー源は糖、血糖というかたちで血中に入り込み、脳に届けられる。
血糖は、高いことの弊害ばかりが話題になるが、脳にとっては必要不可欠な栄養素で、最低でも30ほどないと脳は正常に動けない。
80を下回ると、脳はぎくしゃくして、やる気と集中力を失い、ムカついたり、キレたりする。40を下回れば意識混濁となり、それが数時間続けば脳死に至る。
本当は、低血糖の方が恐ろしいのだ。
後に詳しく述べるが、脳は、脳の持ち主が眠っている間に、大活躍している。
知識工場となって知恵やセンスを作りだし、記憶の定着を図っているのだ。
新しい知識をぐんぐん吸収している子どもたちの脳は、夜、大人たちの何倍も働いている。
このため、低血糖状態で目覚めることが多い。
朝ごはんは、その脳に、一日を始めるためのエネルギーを与える重要な行為だ。
朝ごはんに関しては、脳の言うことを聞いちゃダメ
低血糖の脳は、てっとり早く血糖値を上げる糖質の食べ物を欲しがる。
なぜか。
疲れたとき、むしょうに甘いものを食べたくなることがあるでしょう?
特に、精神的な疲れは、脳神経信号を大量に使った結果でもあるので、エネルギーが枯渇してくる。
そのため、甘いものが食べたくなるのだ。
残業帰りに、コンビニを素通りできず、ついスイーツを買ってしまった経験は、多くの人にあると思う。
子どもたちは、起き抜けに低血糖状態なので、同じように甘いものに目がない。
自由に選ばせれば、パンケーキにジュース、カステラにココアのような甘いものをとりたがるが、残念ながらそんな朝ごはんはNGである。
空腹時に、糖質を食べると、いきなり血糖値が跳ね上がり、結果、血糖値を下げるホルモン・インスリンが過剰分泌してしまう。
これが2~3時間後に低血糖状態を作りだす。
脳の適正血糖の下限80より下回ってしまうのだ。
つまり、「いきなり糖質」は、低血糖を誘発するのである。
これでは、脳はぎくしゃくしてうまく動かない。
朝ごはんのツボ
ということで、朝ごはんは、気が抜けない(手は抜いてもいいけど)。
朝ごはんは、タンパク質や繊維質(野菜や大豆製品)と一緒に糖質を摂ること。
セロトニンやドーパミンなど、脳神経信号を制御するホルモンの材料は、トリプトファンと呼ばれる必須アミノ酸だ。
トリプトファンは、だし(かつお、煮干し、アゴ)、たまご、大豆製品などに豊富に含まれている。
だしの利いた味噌汁に納豆、卵焼きなんていう日本の朝ごはんは、脳にとてもよかったのである。
また、たまごは「完全脳食」と言っていいくらい、脳に必要な栄養素が取り揃っている。
たまごが苦手じゃなかったら、ぜひ、朝ごはんのおかずの主役に。
ずいぶん前のことになるけど、脳科学者の間で、朝ごはんの重要性が話題になったことがあった。
脳に必要な栄養素が多岐にわたるので、ある脳科学者は「朝ごはんのおかずの数は成績に比例する」と言い、別の脳科学者は「母親は、旅館の朝ごはんのようなおかずを並べるべきだ」と言った。
どちらも私と同世代の男性脳科学者で、母たちの朝の忙しさを知っちゃいない発言だなと、私はちょっとムカついた。
そのため、少ないおかずの数で、手っ取り早く脳に必要な栄養素を取り揃えるにはどうしたらいいのかを追求してみたら、だしやたまご、味噌や納豆などの大豆製品があったわけ。
これに骨や筋肉の成長を助ける乳製品を足したい。
日々の怒濤のような家事の中で、流されそうになっている母たちに、とりあえず、この綱だけ握っておいてね、というのが、「甘いだけの朝ごはんはダメ」と「だし、たまご、大豆製品、乳製品」という、朝ごはんのツボ。
健康にいい栄養素は言い出したらキリがないけど、これにときどき、魚を添えたり、フルーツ食べたりしていけば、けっこう取り揃ってくる。
野菜が足りないと思ったら、白いご飯は、雑穀やもち麦と交ぜて、繊維質を加えるのも手。
ゴマやわかめを加えるのも○。
わかめや海苔も野菜の一つに数えちゃおう。
朝日が当たっている時間に起きて、朝ごはんに気を抜かなければ、子どもの脳は、脳神経信号がスムーズに動くようにセットされる。
思いやりがあって、キレない一日を過ごしてくれる。
夫も一緒。
いい朝ごはんを食べさせると、思いやりが戻ってくる。
仕事の効率も上がり、機嫌がよくなる。
ほんとです。
私は、離婚相談を受けると、朝ごはんの見直しをアドバイスする。
ほとんどの相談者から「夫の性格が良くなった」と報告を受けている。
株式会社感性リサーチ代表取締役、人工知能研究者(専門領域:ブレイン・サイバネティクス)、感性アナリスト、随筆家。日本ネーミング協会理事、日本文藝家協会会員。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね