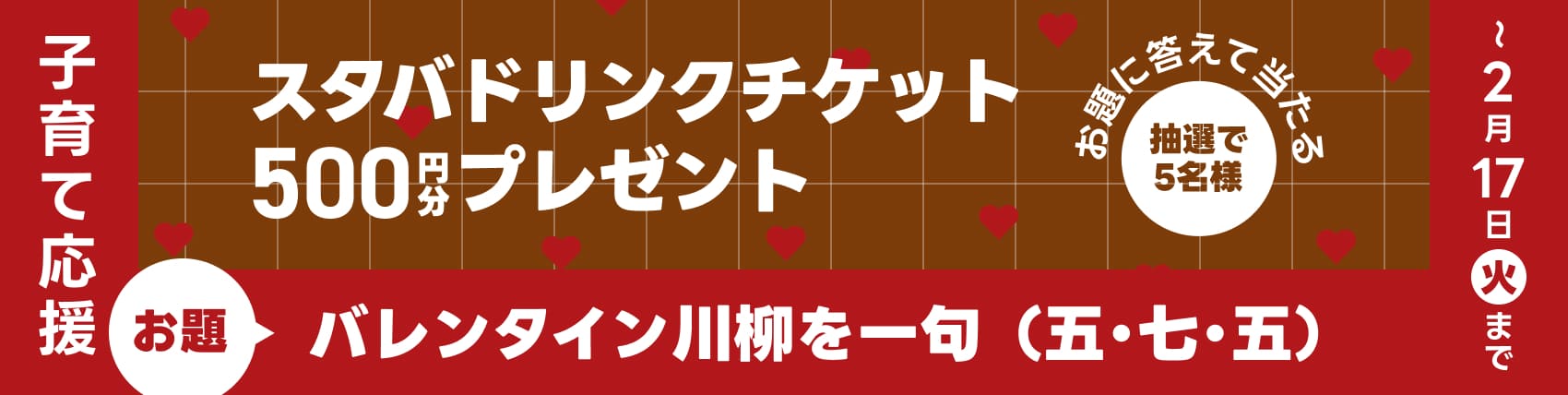敏感な男の子の才能を伸ばす!「子どもをよく観察する」
敏感な男の子の接し方、12歳までに身につけたい感受性を育てる方法と才能を伸ばす勉強法をわかりやすく解説。
発達/発育

子どもをよく観察する
敏感くんを見ていると、不安になる親御さんも多いかもしれません。
新しい環境になじめないのではないか。
友だちができるのか。いじめられないか。
不登校になってしまわないのか。将来はどうなってしまうのか......。
親御さんはみな、同じような不安を口にします。
なぜ不安なのかというと、自分の子どもは「普通」ではないと感じてしまうからです。
わたしは、次々に現れる多様な子どもたちを目にしているうちに、それが少子化社会で兄弟の少なさと関係があること、そして現代の子どもたちは多様化する社会で生きていくために、あえて本能的に敏感に生まれてきているのではないかと思うようになりました。
むしろ、こうした特徴があるのは「普通」に感じるのです。
ところが、世の中で「多様性を大事にしよう」というかけ声は大きくても、異質なものを排除する文化はこの国に深く根づいています。
親御さんが不安になる気持ちもわかりますが、前述したように特殊性は能力です。
普通ではないことは、けっして恥じることではありません。
ただ、育て方に注意が必要なことは確かです。
たとえば、100円均一のお店にずらりと並ぶコップは、安いだけでなく頑丈です。
多少乱暴に扱っても壊れません。
でも、口当たりがいいとは言えず、そのコップでビールを飲んでもイマイチおいしくない。「どうせ壊れるから」と思って買ったのに、頑丈だから何年も使い続けいるなんてことがあります。
一方、高級なグラスはとても繊細です。
乱暴に扱うとすぐにパリンと割れてしまいますが、その口当たりは薄くなめらか。
飲み物の味を引き立ててくれます。
このグラスを長持ちさせたいなら、100円均一のグラスのようにゴシコシ洗ってはいけません。
食洗器に入れるのもNGです。
敏感くんはあきらかに後者です。
敏感くんを観察する2つのポイント
壊れやすい敏感くんをどうやって育てていくのか。
それはわが子を観察して決めていくしかありません。
敏感くんを育てる親には観察眼が不可欠です。
幼ければ幼いほど、子どもは自分の感覚を言葉で説明できません。
親がちゃんと観察して、特に次の2つことを見極めていきましょう。
①子どもが不安・不快なこと
②子どもが心地よいと感じること
わが子にとって心地よいものは与え続け、イヤがることは極力無理強いしないことです。
「甘やかしているのでは?」
「ワガママな子になってしまうのでは」
と思うかもしれませんが、特に幼いうちは敏感くんの行動は本人の意思ではコントロールしにくいものです。
年齢とともに少しずつ慣れてくるので、それまではできるだけ「イヤなもの」を早期発見して遠ざけてあげたいものです。
イヤがることは言語化してあげよう
子どもが何かに不安や不快感を覚えていることに気づいたら、言葉にして本人に伝えることも大切です。
たとえば、「手にお砂がついちゃったね。だからイヤだったんだ。じゃあ、手を洗おうか?」や「さっき読んだ絵本が怖かったのかな?オバケが出てきたものね。でも、お母さんとお父さんがいるから大丈夫だよ」などです。
こうした小さな言葉かけは、敏感くんにとって2つの意味があります。
1つは、「お母さんに理解してもらえた」「お父さんに守ってもらえるんだ」という安心感を得られることです。
それだけで心が落ち着いて、穏やかになれることもあります。
安心感は、年齢とともに親への信頼感に変わってきます。「親はぼくの気持ちをわかってくれているんだ」という絶大な信頼感になるのです。
そしてもう1つは、漠然とした不安や不快感を親に言語化してもらうことで、子ども自身が自分の感情に気づくことができるのです。
「自分は砂を触るのがイヤなんだ」「自分はオバケの話が嫌いなんだ」と気づけば、次から子ども自身で言語化できます。
言語化できれば「砂場では遊びたくない」「怖いお話は聞きたくないよ」と、意思表示できるようになります。
ワンワン泣いたり、「イヤだ」と言う以外の方法を手に入れるのです。
これは幼いころであればあるほど、子どもをラクにします。
幼稚園や保育園、学校などで、気持ちを友だちや先生に伝えることができるようになるからです。
親は間違っても「そんなの平気平気!全然気にしなくていいのよ!」などと言わないことです。
「うちの親はまったくもって100%無理解なのだ」と理解することになってしまいます。
そうやってわが子を観察する目を育てていけば、思春期になったときにも「今は放っておけばいい」「今は相談にのる必要がある」というタイミングがわかってきます。
何でもかんでも声がけするウザい親にならないためにも、早いうちからわが子への観察眼を培ってください。
<松永暢史公式サイト>
https://matsunaganobufumi.edorg.jp/
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね