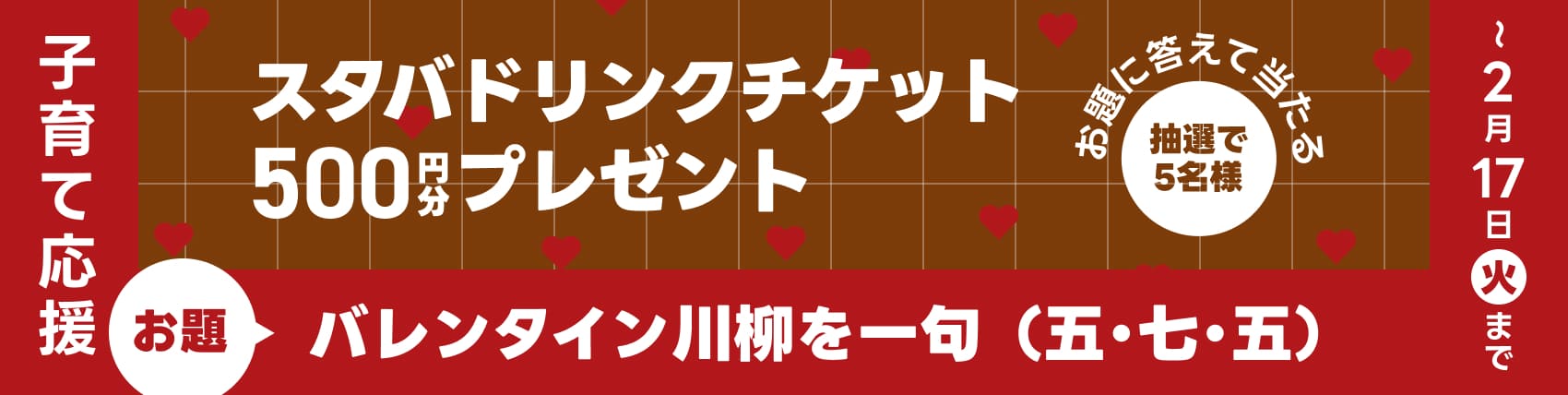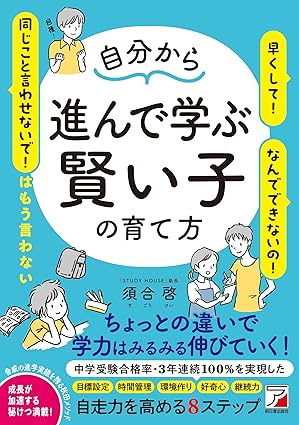教育のプロが伝える!「日常生活の中に学びを」
ちょっとの違いで学力はみるみる伸びていく!中学受験合格率・3年連続100%を実現した目標設定、時間管理、環境作り、好奇心、継続力、自走力を高める8ステップ。脅威の進学実績を誇る秋田メソッド。成長が加速する秘けつ満載!
教育
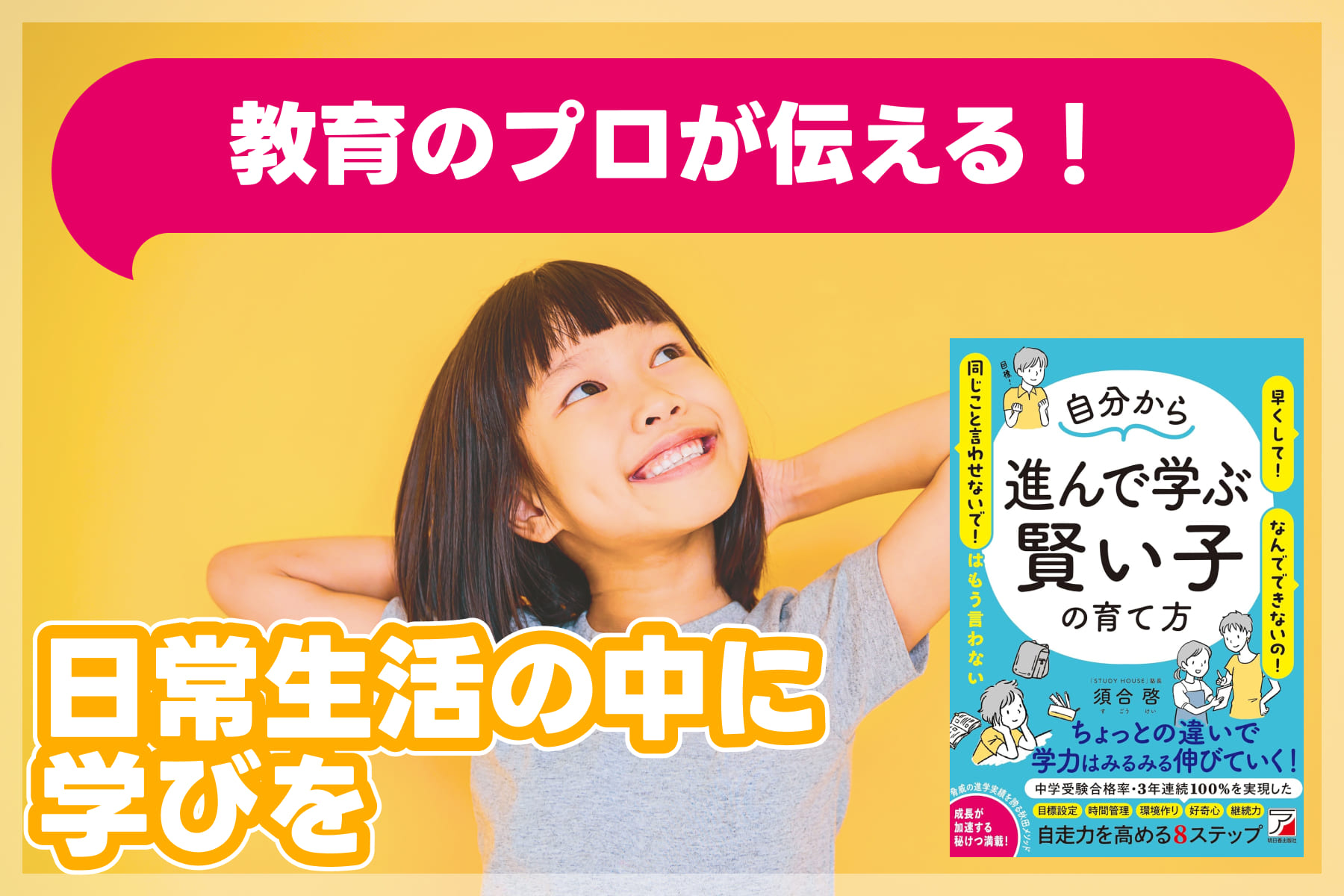
日常生活の中に学びの種をまく
学びは教室や机の上だけで行われるものではありません。
日常生活には、学びの機会が無数に存在しています。
日常生活の中にたくさんある「学びの種」を見いだし、育てることで好奇心は育っていきます。
料理や買い物、旅行
たとえば、料理は学びの宝庫です。
買い物は仮説する力を育て、分量を測ることは数学の実践であり、手順を追うことは論理的思考の訓練になります。
調理過程で起こる変化は小さな科学実験です。
たとえば、ホットケーキを作る際に生地が熱で固まる様子を観察し、「どうしてこうなるの?」と問いかけることで、化学反応への興味を引き出します。
また、買い物も絶好の学びの機会です。
価格の計算や比較は実践的な算数のいい訓練になります。
計算力を養ったり、情報の比較や意思決定の練習になります。
栄養成分表を見比べたり、原産地を確認したりすることで、原産地になる地理的環境はその土地の気候や地形など食育だけではなく、深く社会科の学習にもつながります。
旅行も総合的な学習の場です。
地理、歴史、文化など多岐にわたる学びの機会を提供します。
旅行先の地図を見ながら行程を計画することは地理の学習になります。
訪れた場所の歴史や文化について調べることは社会科の生きた学習となり、地域ごとの方言や食文化の違いを体験することで、言語や文化の多様性への理解も深まります。
日常の散歩や外遊びなども、予定調和が崩されることで、臨機応変に対応する力が育まれます。
たとえば支払いを子どもに任せることだけても、制限のある環境下で修正力を育てるいい機会となります。
また、生き物や植物を育てることも予定調和を崩すきっかけになります。
ペットの世話や植物の世話を通じて、子どもは責任感を持ち、生命の大切さを学びます。
これらの活動は、観察力や問題解決能力を養助けとなります。
学びを生きたものにするために
これらの日常生活における学びの機会を積極的に活用するためには、どうしたらいいでしょうか。
また、「なぜ?」を大切にすることです。
日常の中で起こる現象に対して、「なぜそうなるの?」と問いかける習慣をつけましょう。
料理中に「なぜ水は沸騰すると泡立つの?」といった疑問を投げかけ、一緒に考えたり調べたりすることで、科学的思考を育みます。
次に、五感を使った観察を促すことも大切です。
買い物の際には、商品の色、形、におい、触感などを意識的に観察するよう促します。
これは自然科学の基礎となる観察力を養います。
また、体験を言語化することも重要です。
旅行後には、体験したことを絵日記や作文にまとめる機会を設けます。
これにより、体験を整理し、言語能力を向上させることができます。
家族での対話を大切にすることもポイントです。
日常生活での発見や疑問を家族で共有し話し合う時間を持ちましょう。
これにより、コミュニケーション能力や思考力が育まれます。
さらに、遊びの中に学びを見いだすことも効果的です。
たとえば、積み木遊びを通じて空間認識や物理の基礎を学んだり、カードゲームを通じて戦略的思考を育んだりします。
学びの姿勢を育む
日常生活の中に学びの種をまくことで、子どもたちは「学ぶこと」と「生きること」が密接につながっていることを自然に理解していきます。
これは生涯学習の姿勢を育むうえで非常に重要です。また、学校での学習がより意味のあるものとしても認識できるようになります。
私たちは、子どもたちが日々の生活の中で「あっ、面白い!」「なぜだろう?」と感じる瞬間を大切にし、それを学びにつなげていく支援をしていきたいと考えています。
学ぶことが特別なことではなく、日常の中に自然にとけ込んだ楽しい活動になることを目指しています。
大事
日常生活のあらゆる場面を学びの機会ととらえよう
図書館は学びを深める宝庫
図書館は、子どもたちの好奇心を刺激し、学びを深める宝庫です。
本との出会いは宝探しのような楽しい冒険であり、知的好奇心を大きく育てる機会となります。
豊富なジャンルと静かな環境
図書館の最大の魅力は、豊富なジャンルの本がそろっていることです。
絵本、児童書、小説、科学書、歴史書、美術書など、あらゆる分野の本に触れることができます。
この多様性は、子どもたちの興味の幅を広げ、新たな関心を発見するきっかけとなります。
たとえば、恐竜に興味を持った子どもが、恐竜の本を探しているうちに地球の歴史や進化論に関する本に出会い、さらに興味を広げていくことがよくあります。
司書さんと親子での図書館利用
さらに、図書館には頼もしい味方がいます。それが司書さんです。
司書さんは、本の世界の案内人として、子どもたちの興味や年齢に合わせて適切な本を紹介してくれます。
「こんなことが知りたいんだけど」と相談すれば、思いもよらない本との出会いが得られるでしょう。
図書館の効果的に活用方法を次のように提案します。
まずは、定期的な図書館の訪問です。
週末や放課後を利用して、図書館を訪れる習慣をつけましょう。
たくさんの本と接触する頻度を高め、本を身近に感じることで、読書習慣が自然と身につくようにします。
続いて、テーマ別の本探しです。
その時々の興味や学校の学習内容に合わせて、テーマを決めて本を探すようにします。
親子で話し合い、「今月は昆虫について調べよう」といった具合に、目的を持って本を探す力を育んでいくといいでしょう。
本を読んだら、読書ノートの作成をします
読んだ本の題名、著者、感想などを記録する読書ノートをつけることで、読書の履歴が可視化され、達成感が得られるようになります。
読書傾向の分析にも役立つのでおすすめです。
小学生へおすすめ本!
てつなぎPICKUP
学ぶ力を育む
図書館の活用は、単に読書量を増やすだけでなく、子どもたちの学ぶ力を多面的に育てます。
本を探す過程で情報収集能力が磨かれます。
さらに、図書館という公共の場を利用することで、社会性やマナーも自然と身につきます。
本を大切に扱うこと、返却期限を守ること、他の利用者に配慮することなど、社会生活に必要なスキルを学ぶ機会にもなります。
また、親御さんが子どものときに読んだ本の話をすることで、何を感じ、考えたか、子どもが親を理解するきっかけにもなります。
そうした意見交換を積極的に行う機会にするといいでしょう。
図書館を子どもたちの知的冒険の出発点として位置づけ、そこでの本との出会いが、子どもたちの好奇心を刺激し、学びへの意欲を高め、豊かな人生の基礎となることを願っています。
図書館は、まさに無限の可能性を秘めた宝の山なのです。
大事
図書館を子どもの知的冒険の場として最大限に活用しよう
学習習慣形成プロデューサー(学習塾STUDY HOUSE代表)
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね