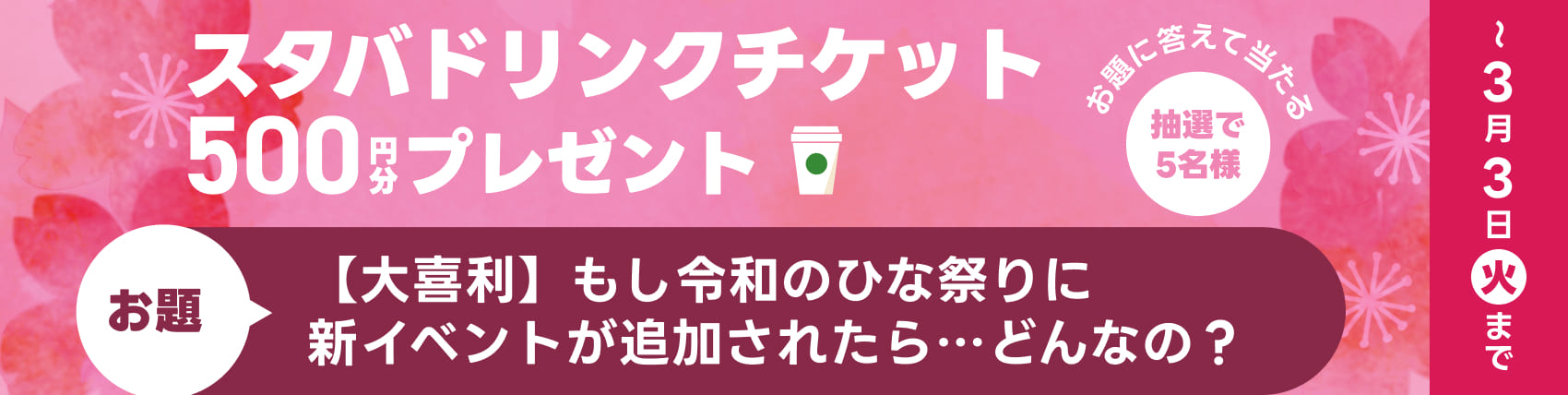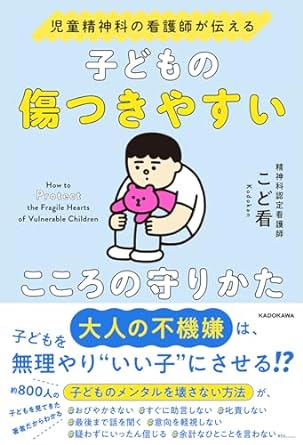子どもがよく使う言葉は「多義語」かもしれない
「話す」より実は大事な「聞く・見守る」
親子関係

子どもがよく使う言葉は「多義語」かもしれない
私が新人だった頃、とある子ども(C君とします)の言動に困っていました。
当時小学生だったC君は毎日病院内の学校に出席していましたが、ある日突然休むようになりました。授業の時間になってもベッドから出てこず、登校の時間であることを告げる看護師に「イヤだ」とだけ言って布団に潜ってしまいます。
さらに困ったことに、「休んでもいいんだよ」と看護師から提案しても、同じようにC君は「イヤだ」と答えるのです。正直な話、C君の「イヤだ」に対して「どっちなのよ!」と苛立ってしまいました。
翌日、何気なく「学校ってめんどくさいよね」とC君に話しかけてみました。
すると、C君は目を見開いて「そうだよ!マジでめんどくさい!」と、こちらが驚くほどの大きな反応を示したのです。
そこから話をさらに聞いていくと、浮かび上がってきたのは、C君が抱えていた宿題に対する不安でした。C君は前日に宿題をするのを忘れてしまい、登校直前になってそれを思い出したそうです。
「先生になんて言われるのか怖い」「どうしたらいいんだろう」「宿題をやれなかった自分にイライラする」こんな気持ちが集約されての「イヤだ」だったのです。
C君が発した「イヤだ」もそうですが、子どもが発する「イヤだ」には、私たち大人が想像するよりももっと多くの意味が含まれています。
子どもからの言葉を言葉通りに捉えるだけでは、子どもが本当は何を感じ、何に困っているのかが見えなくなります。子どもの語彙はまだ少ないですが、大人と同じようにさまざまな感情を持っていることも、またたしかなのです。
実際に子どもから「イヤだ」を連発されたら、聞いたほうはよい気持ちはしないですが、その子はあなたに「イヤだ」と言えていることを忘れてはいけません。
「イヤだ」と言えたことを認めた上で、「イライラしているように見えるんだけど、何か困っていることがあったりする?」と、その子の気持ちを代弁する形で言い換えてみるのもよいと思います。
今の例で出てきた「イヤだ」以外でも、私は子どもから何度も発される言葉は多義(複数の意味を持つ言葉)である可能性が高いと思っています。
当時、左のページには、私が児童精神科の看護師として子どもたちからよく聞いてきた、「イヤだ」「めんどくさい」「もういい」「死にたい」という4つの言葉の裏にある気持ちを表にしてみました。それぞれの言葉の裏には、正反対の気持ちや、SOS、困りごとなどが隠れていることがおわかりいただけると思います。
これらはほんの一例ですので、表に載っていない気持ちを持っていることもあるということを忘れないでもらえたらと思います。
大切なのは、この表の中から子どもの気持ちを探るのではなく、この表の中にあるような気持ちを子どもが抱えているかもしれないという思いを持ちながら、子どもの言葉の裏にある気持ちを一緒に考えることです。
その作業を通して、子どもが自分の感情に気づけるかかわりが大切だと思います。
精神科認定看護師。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね