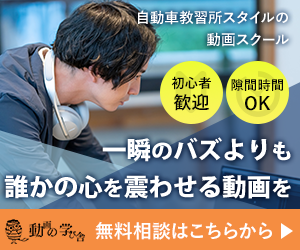精神科医が伝える!発達障害も愛着障害もこじらせない――不登校のこじれと支援のあり方
学校

その生きづらさの背景にはグレーゾーンの発達障害や愛着の問題があるかもしれない――。するする読めて、臨床の解像度が上がる一冊。
村上 伸治の著書『発達障害も愛着障害もこじらせない』から一部転載・編集してお届けいたします。
二次的なこじれ
不登校は不登校自体よりも、二次的にこじれることで難治化しやすい。
ある子が次のように話してくれたことがある。
以下の文章そのままをスラスラと語ったわけではないが、ボソボソと何回かに分けて話したことに言葉を補ってまとめると、次のような内容となる。
「僕は勉強もあまりできないし、部活でもレギュラーになれない。これといって優れたところはない。けど、お母さんは僕の味方だった。学校で嫌なことがあっても、家に帰ればお母さんがいた。僕にとって家は味方がいて安心できる場所だった。けど、不登校になって、お母さんもお父さんも味方でなくなった。学校へ行けない僕をすごい形相で見るようになった。学校に行けないことはとても苦しいけど、それをわかってもらえないのがつらい。『なぜ行けない?』『どうしたら行ける?』といつも言われている感じがする。これまで僕は親に愛されていると思っていた。けど違っていた。僕が言うことを聞くとか、勉強や部活を頑張るとか、要するに親の期待を満たすから愛されていたんだ。僕そのものが愛されていたんじゃない。愛される条件を満たさなくなった僕は要らない子なんだ」と。
彼はこれまで、家族を自分の存在の土台にして、味方にして生きてきた。
だが不登校になった途端、味方である土台は崩れ去った。
だから自分が生きている意味や価値も感じられなくなったのだった。
彼のように自分の気持ちを適切に表現できる子はめったにいない。だが、不登校の子の大半は彼と似たような気持ちなのではないかと思われる。
不登校の子には休める環境が必要であり、それは親が味方である状況で休むことである。
それができると、休むことでエネルギーの充電も始まる。
安心して休めるようになると、しっかりとした充電が始まり、まるで急速充電のように元気になる子もいる。
だが現実の多くの例では、親が味方でなくなってしまうので、充電していても充電電流は微弱であり、逆に放電電流のほうがはるかに大きいので、長期に休んでも充電は進まず、元気は出てこない。
学校の対応
こじれが問題になるのは家庭だけではなく、学校の対応もこじれを生みやすい。
心配した担任が家を訪問する例はよくある。
その気持ちはありがたいのだが、それがプラスに作用する例もある一方、マイナスに作用する例も多い。
担任が訪問する際には自室などに隠れてしまう子は多い。
隠れるだけならまだよい。
訪問をきっかけに暴れるようになる子も少なくない。
その辺のところを本人に尋ねると、「説教される」とまでは思っていなくても、「学校においでと誘われるのがつらい」と述べる子が多い。
その一方、訪問がなくなったあと、「私は見捨てられた」と言って手首を切った子もいる。
「ぜひ訪問すべきである」「行く必要はない」などの画一的な対応は、こじれを生む。
この辺については個人差が大変大きいので、親を通じてでよいから、本人の意向を尋ねながら行う必要がある。
本人の意向を尋ねることは最も重要である。
訪問するかどうかよりも、本人の意向を尋ねること自体のほうが支援として重要なくらいである。
ただ、「じゃあどうしてほしいのよ!」という問い詰める雰囲気になってしまうと、逆効果になるのは言うまでもない。
「周囲の大人からの雑音が静かになり、本人が自分の心と相談して意向や希望を表出できるようになる」過程を育てることが重要な支援であるという意味である。
別室登校なら行ける子もいるが、嫌がる子も多い。
理由を尋ねると、「別室登校がしばらく続くと、どの先生も、自分の教室に行ってみようと言い始める。それが苦しい」と語る子が多い。
クラスへ誘う場となっている別室が実に多く、生徒に罪悪感を植えつける場所になっていたりする。
ある子は「別室って要するにアイスホッケーのペナルティボックスなんだよ」と教えてくれた。
責める雰囲気がない別室であれば、通える子は多い。
責める雰囲気の有無が重要であるのは家と同じである。
別室がただの自習室ではなく、専任の教員がいて「君はここにいていいんだよ」と温かく迎えてもらえる場になってくれたら大変ありがたい。
ゲームやネットについて
不登校に限らず、ゲームやネットは何かと悪者にされやすい。
確かにハマってしまうと抜けにくくなるなど、よくない面があるのは否定しない。
だが、子どもたちを見ていると、ゲームやネットに助けられて何とか生きている子が多いとも感じる。
たとえるなら、海を漂流する子どもが、藁にもすがる思いで丸太にしがみついているようなイメージである。
その丸太を取り上げたところで、溺れる可能性が高まるだけで、解決につながりそうな例は少ない。
ネットゲーム友達との交流が唯一の交友であったり、SNSのつながりに支えられていたりするからである。
それなのに、ゲームやネットを取り上げてしまうと、数少ない人とのつながりを断つことになったり、親との関係の悪化が決定的となり、その子を支援するルートが失われてしまったと感じることもよくある。
子どもたちに尋ねてみると、「ゲームは楽しい」と答える子もいるにはいるが、「あまり面白くない」と言う子のほうが多い。
「何もしてないと気持ちがしんどくなるからする」「ゲーム中は嫌なことを考えなくて済むから」「SNSで死にたいと書き込むと、わかるよとか、死なないでとか書き込んでくれる人がいてくれたりして、自分は一人じゃないと感じる。この感覚は親や先生たちはわかってくれない」と話す子もいる。
メカニズムとしては、(なぜだかわからないが)学校に行けない→親が怒る(悲しむ、失望する)→親の顔を見るのがつらい→昼夜逆転しゲームなどにハマる→親がますます怒る(悲しむ)→子が親を避ける→余計にハマるという負のスパイラルが起きている例が多い。
雑談を
休める環境作りがうまくいっているかどうかの指標の一つは雑談である。
親御さんにも本人にも、「雑談を豊かにしてほしい」とお願いしている。
親がイライラしていたり、不登校を責める雰囲気が家にあると雑談は生じにくい。
不登校の子は自分の気持ちを言葉にするのが苦手なので、言葉にする能力を気長に育てる必要がある。
そのためにも、まずは親との雑談を豊かにしてほしい。
思春期では友達との雑談が重要となるので、親よりも親密に話せる友達がいるのなら、その友達との雑談を自由にさせてあげたい。
だが不登校状態の子の多くは、そういう友達がいなかったり、友達にとても気を遣っていることが多い。
友達との雑談が豊かになるためにも、まずは親との雑談から会話や言語化能力を育てていきたい。
親との雑談が豊かになると、親の対応に問題があれば、本人が気軽に文句を言えるようになる。
なので、親がよかれと思って本人に害を及ぼすことが減る。
外来では、筆者は親を前にして本人に、親への要望と文句はないかを尋ねることを常に行うようにしている。
不登校が受容されてしばらくののち、夜になると親にあれこれ話し相手を求めるようになる子は多い。
親は眠くて困るのだが、この時期はとても重要である。
親が味方に
不登校は、不登校自体が第一の苦しみであり、味方や支えを失うことが第二の苦しみとなる。
本人に「君に味方はいるのかな?」と尋ねると、「いない」と答える子が多い。
「親は味方かな?」と尋ねると、「味方じゃない」と答える子も多い。
「親がどうなれば味方だと感じるかな?」と尋ねると、「軽蔑する目で見ないでほしい」「哀しい目で見ないでほしい」と言う子もいるが、結局は「普通にしてほしい」と言う子が多い。この「普通」とは何を指すのかを考える必要がある。
「普通とは、学校へ行っていた時と同じように接してほしいということ?」と尋ねると、うなずく子が多い。
多くの子は「登校しようがしまいが、同じように接してほしい」と思っている。
これは、「登校しようがしまいが、同じように愛してほしい」という意味である。
親御さんの相談に応じていると、不登校という事実にイラついている親は多い。
「親としてどう対応したらいいですか?」と尋ねられると、筆者は次のように話している。
「親がイライラしたり悲しんだりしているのと、ニコニコしているのと、どっちが本人が元気になるのに助けになると思いますか?」と尋ねる。
時には「素早く学校に復帰する方法を教えろと言われるなら、できないのでお断りします。ただ、不登校を卒業するお手伝いならできます。卒業とは必要単位をすべて修得したら卒業ですよね。不登校も同じです。不登校を十分し尽くしたら、卒業できます。つまり、本人は不登校を満喫して楽しみ、親は不登校児の親を満喫してもらえませんか?」とか「親が不幸を感じていると、子どもは親を不幸にした自分を責めて不幸になり、回復もしません。幸せな不登校児の親になる気はないですか?」と言ったりする。
親がこの路線を受け入れてくれると、こじれた悪循環が止まり、好循環が回り始める。
親子で料理を楽しむとか、親子で遊びに出るなどをしてもらいたい。
母親が有給休暇を取って平日にディズニーランドに行った親子は「平日なので混んでなくてよかったです」と述べた。
不登校を直接なくす努力を熱心にすればするほど、事態は悪化しやすい。
このような状況を、森田療法の創始者の森田正馬は繋驢橛(けろけつ)と呼んだ。
綱で杭につながれたロバが束縛から逃れようとしてグルグル歩き回った結果、綱が杭に巻きついてどんどん短くなり、ついにはまったく身動きができなくなる有様を表している。
必要なのは巻きついた綱、もつれた紐をほどく作業である。
不登校をなくす努力をやめ、不登校をどう豊かにするかを考えるようになると、敵対していた親子が同じ方向に向かって歩み始めることとなる。
充電後
期待に応えたら愛されるという条件つきの愛情ではなく、生きているだけで愛してもらえる環境で十分休めた子にはエネルギーが充電される。
十分に充電された子は、勝手に何かを始める。
しばらくはゲームばかりだったりもするが、もっと楽しいことを始める子が多い。
逆に、ゲーム等から離れられない場合は、本人が周囲から責められる状況がまだ続いていることが多い。
好きなことを始めた子は、どんどんエネルギーが出てくるので、見ていても楽しい。
趣味的なことを始める子もいるが、学校と関係ない勉強を始める子もいる。
好きなことだけ勉強し始めた子に、「それなら学校の勉強をしたら?」と親が言ったら、あっという間にエネルギーがなくなってしまった。
ある母親は、息子が料理に興味を持ったので、褒めておだてて料理を任せるようになった。
そうすると母親としても助かるため、素直な気持ちで子どもに感謝できる。
すると親子の間で好循環が回りだした。
そんな日々が続いたある日、母親は外来で「仕事から帰ってきたら、ご飯ができているんです。とっても助かります。先生、今あの子が学校に行き始めたら、私は困ります」と言って苦笑した。
その後しばらくして、その子は登校を再開した。
実際には、再登校以外の方向で元気になる子のほうが多い。
別の方向で元気になったあとに、通信制などの形で再び学校に行き始め、気がつくとサポート校に毎日楽しく行くようになる子も多い。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね