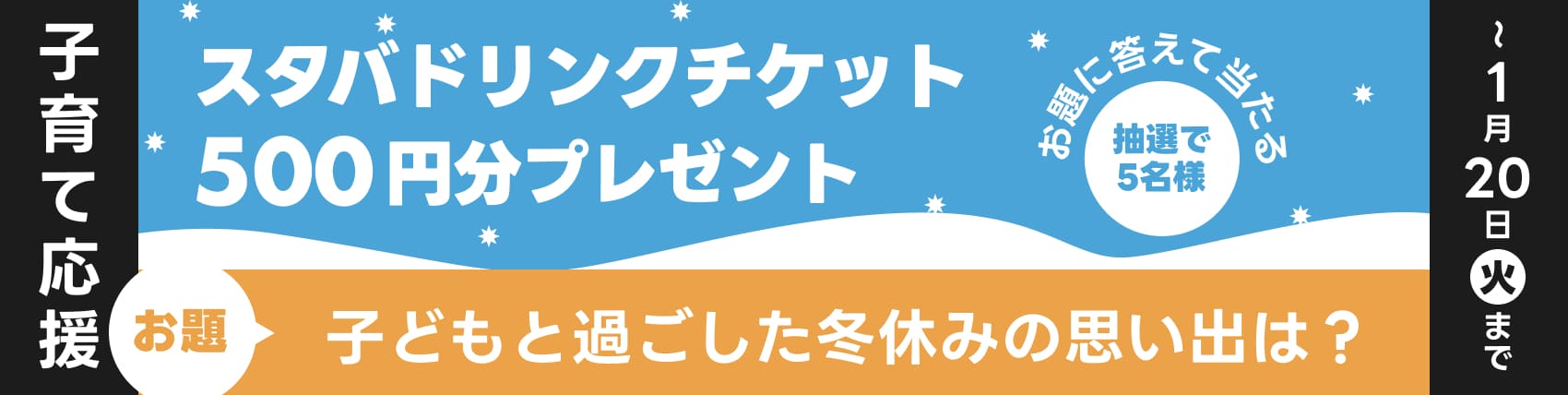親の語彙力③ 慣用表現(わが子に「ヤバい」と言わせない 親の語彙力)
具体的な場面への応用!慣用表現の丸暗記に要注意「慣用表現」
親子関係

これは、中学入試頻出の「慣用句」の問題です。
「慣用句」とは、「二つ以上の単語が必ず同じような結びつきをするもの、また結合して全体が特定の意味を表す言いまわし」のことです。
一例として、「顔が広い」「目が高い」「口 がすべる」「耳が痛い」「胸が痛む」といった身体の部位を用いる表現や、「虻蜂取らず」「馬の耳に念仏」「猫の額」「青菜に塩」「高嶺の花」のように、虫や動物・植物を使った表現、「油を売る」「折り紙を付ける」「焼け石に水」「水に流す」「雲をつかむ」のように、身近な道具や品物、あるいは自然現象を使った表現などがあります。
一般的に塾の国語教材には代表的な慣用句の一覧が掲載されているものです。
この慣用句、どのように学習していけばよいのでしょうか。
これは慣用句に限った話ではありませんが、一番やってはいけないのは、慣用句とその意味をただ丸暗記するということです。
たとえば、手元の教材に次のような慣用句とその意味が記述されていたとしましょう。
例:顔から火が出る・・・大変に恥ずかしく思う。
例:手を打つ・・・話し合い、決着をつける。
例:目が肥える・・・物の良し悪しを見分けられるようになる。
例:気が置けない・・・親しくて気がねなしにつき合える。
例:竹を割ったよう・・・性格がさっぱりしている。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね