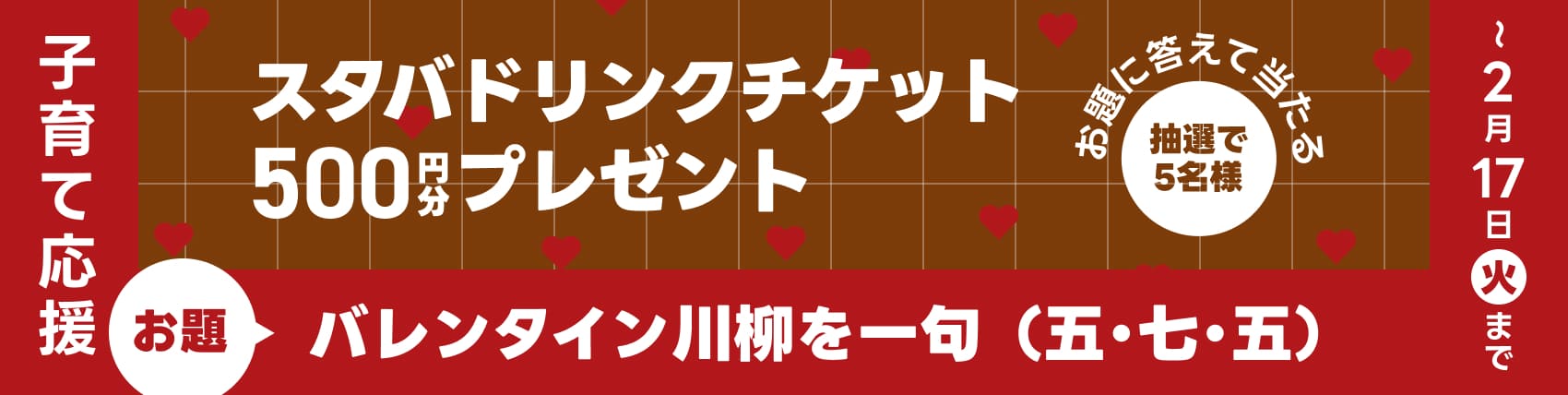世界中の子育てを試してわかった!――学ぶ力を伸ばす
「子どもの才能を伸ばすには、一体なにをしたらいいのか?」--親として、教育者として、子どもの可能性を信じるすべての大人に向けた決定版! 著者自身が世界中のありとあらゆる育児・子育て法を実際に試し、その中から「最も効果的」と実感した「7つの教育アプローチ」に基づく、「子どもの才能を伸ばす方法ベスト100」を厳選して紹介する。
しつけ/育児

著者が世界中の子育てを実際に試してわかった才能を伸ばす最高の方法!厳選したベスト100を紹介する一冊。
相馬れいこ先生著書の『脳科学、モンテッソーリ、レッジョ・エミリア、フレーベル…世界中の方法を試してわかった子どもの才能の伸ばし方ベスト100』から一部転載・編集してお届けいたします。
実験で知識の活用力を高める

STEAM教育では、数量概念を効果的に身につける方法として、「実験を通じた学び」を大切にしています。
単なる答えの暗記ではなく、仮説を立て、実験を行い、観察を通じて答えを見つけるプロセスが、論理的な理解を深め、知識を実践的に活用する力を養います。
たとえば、物理の授業で「加速度」を学ぶ場合、公式や単位を暗記するだけでなく、実際に斜面を転がるボールの速度を測定する実験を行います。
この過程で、重力や摩擦の影響を考慮しながら結果を分析することで、公式の意味を体感的に理解できます。
同様に化学では、化学式を覚えるだけでなく、試薬を混ぜた際の反応を観察。
その結果から化学反応式を導き出すプロセスを経験することで、記憶に定着しやすくしています。
文系的な視点を加えることも重要です。
歴史的な科学者の発見に触れることで、理論がどのように生まれたかを理解します。
ニュートンがリンゴの落下を観察したように、日常の中で疑問を抱く視点を持つことが、科学的思考の基礎となります。
また、実験結果を文章で記録したり、データをもとにグループでディスカッションしたりクラスでプレゼンしたりする過程では、言語力や論理的表現力も高まります。
このように、実験を通じた学びは、単に数式や化学式を暗記するだけでは得られない深い理解をもたらします。
アクションを起こすことでさまざまな感覚器官を使うため、筋肉記憶とも結びつくでしょう。仮説、実験、観察、分析といった一連のプロセスを体験することで、理論の構築過程を身をもって理解できます。
そして、理解したことが記憶に定着することで、応用問題に直面しても、論理的に解答を導き出せるようになるのです。
日本の学校では、大学進学が近くなると文系と理系にクラス分けをし、それぞれの専門性を重視した授業を行います。
授業では教科書や参考書の内容を教師が説明し、生徒はそれを書き写すことが中心となり、生徒自身が疑問に思ったことを皆で探究するやり方はなかなか根づいていないのが現状です。
STEAM教育では文理を融合し、実験や探究を通じて論理的思考や創造性を育む点が大きく異なります。
分野を超えた学びが多様な応用力を養います。これからの時代においては、「特定の大学・学部を目指す」という限定的な考え方ではなく、より可能性を広げる教育に学校自体も発展していくでしょう。
STEAM教育が目指す未来社会は、創造性と論理的思考を兼ね備えた多様性のある社会。
そして、問題解決力や柔軟性を持つ人材が育つことで革新を生み出し、科学技術や文化の発展に貢献する持続可能な社会をつくることにつながるのです。
親子の対話で「本物の教養」を育てる

ESDの特徴は、身近な環境を題材に、学びを日常生活と結びつける点にあります。
たとえば地域のゴミ問題をテーマにしたプロジェクトでは、子どもたちが実際に街を歩いて廃棄物の現状を調査し、「なぜゴミが減らないのか」「どうすれば改善できるのか」という問いを立て、解決策を探ります。
教室の外に出て現実の課題に触れることで、単なる知識習得ではなく、課題解決型の思考力や実践力を養うのです。
農業を題材にする場合は、地域の農家を訪問して地元の農業課題や水の使用状況を学び、食料問題や資源の持続可能な利用について深く考えます。
このように、地球環境の問題を地域での体験から理解することで、子どもたちは自分たちの行動が社会や環境に与える影響を自覚するようになります。
本物の教育とは、課題を見つけるだけでなく、それらを「社会の中でどう解決するか」を考えることです。
企業や行政、地域と連携しながらプロジェクトを進める中で、異なる立場や意見に触れ、コミュニケーション能力や協調性が育まれます。
また、活動を通じて「自分たちにも社会を変える力がある」という自信が芽生え、子どもたちは受け身ではなく、自らの手でアクションを起こす姿勢を身につけていくのです。
では、そうした子どもに向き合う保護者や教育者は、日常的に何をすればいいのでしょうか。
たとえば、新聞やニュースを一緒に見て「これについてどう思う?」と対話する機会をつくることがおすすめです。
あるいは、身近な環境問題(ゴミの分別やエネルギー使用量など)について家庭で話し合い、実際に行動してみることも効果的でしょう。
週末には地域の清掃活動や自然観察会に参加したり、スーパーで買い物をするときに食品の原産地や包装について考えたりする習慣をつけることもできます。
いずれにしても、子どもの「なぜ?」という疑問を大切にし、一緒に調べる姿勢を示すことが重要です。
地域の図書館や博物館を活用して知識を深めたり、地元の専門家や活動家との交流の機会を設けたりすることで、子どもの視野を広げることができます。
日常の小さな実践が、やがて子どもたちの問題解決力や批判的思考力、創造的な発想力を育てます。
そして気候変動や貧困、ジェンダー平等といった複雑な社会課題に対応する力へと成長していくのです。
株式会社Kids Developer 代表取締役
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね