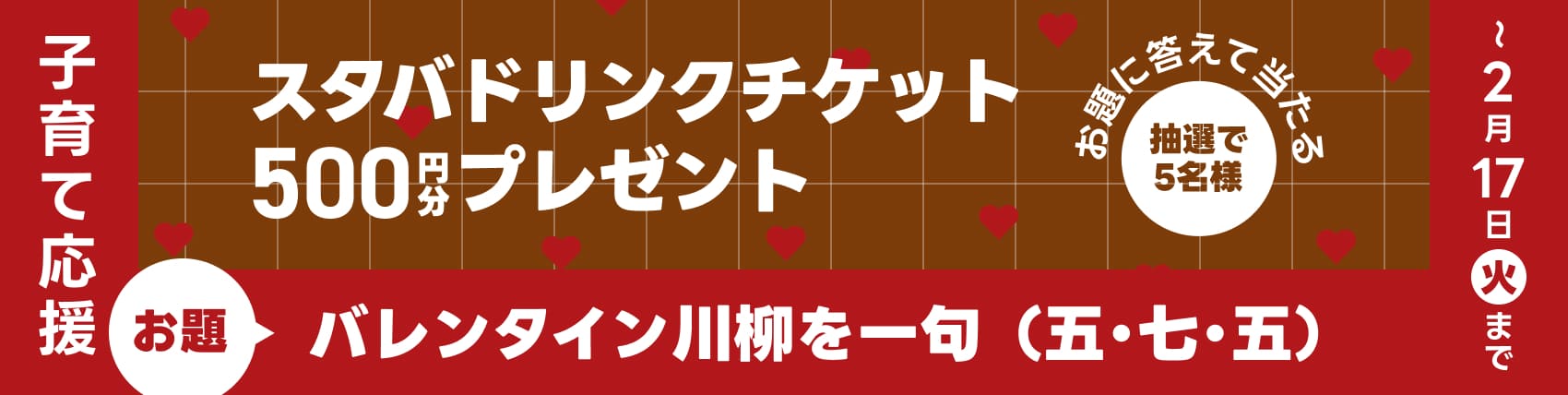世界中の子育てを試してわかった!――社会性を授ける
「子どもの才能を伸ばすには、一体なにをしたらいいのか?」--親として、教育者として、子どもの可能性を信じるすべての大人に向けた決定版! 著者自身が世界中のありとあらゆる育児・子育て法を実際に試し、その中から「最も効果的」と実感した「7つの教育アプローチ」に基づく、「子どもの才能を伸ばす方法ベスト100」を厳選して紹介する。
しつけ/育児

著者が世界中の子育てを実際に試してわかった才能を伸ばす最高の方法!厳選したベスト100を紹介する一冊。
相馬れいこ先生著書の『脳科学、モンテッソーリ、レッジョ・エミリア、フレーベル…世界中の方法を試してわかった子どもの才能の伸ばし方ベスト100』から一部転載・編集してお届けいたします。
理系×文系の学びで、論理的思考力が身につく

AIは、膨大なデータを高速処理し、正確な分析や予測を行える点に大きなメリットがあります。
単純作業の自動化や業務効率の向上だけでなく、医療や教育など多様な分野で活用され、社会の発展に貢献しています。
一方で、AIの進化に伴い、仕事の在り方も変化しています。
たとえば、無人レジやAIチャットボットの普及により、レジ販売員やコールセンターのオペレーターの需要は、近年減少傾向にあります。
銀行の窓口業務もネットバンキングの発展で縮小し、事務職のデータ入力や帳簿管理なども次第にAIが担うようになってきています。
また、自動運転技術の発展により、トラックやタクシードライバーの仕事も減少すると予測されています。
しかし、その一方で新たな職業も生まれています。
AIを開発・最適化するエンジニア、膨大なデータを活用するデータサイエンティスト、AIの倫理やガバナンスを監督する専門家などの需要は年々高まっています。
さらに、仮想空間を設計するバーチャルリアリティデザイナーや、サイバーセキュリティの強化を担う専門家の活躍も注目されてきています。
こうした時代の変化に適応するためには、新しい学びが求められます。
その代表的なものがSTEAM教育です。
STEAM教育では科学・技術・工学・数学に加え、アート的な発想を取り入れることで、単なる知識習得ではなく、創造的思考や問題解決能力を育むことを目的としています。
たとえば、子どもが好きなブロック遊びを取り入れながら、建築やデザインの考え方を学ばせることも、家庭でできるSTEAM教育の一環といえるでしょう。
あるいは、プログラミングを学ぶ際、単にコードを書くのではなく、ゲームをつくる過程でストーリー性やデザインを考えさせることで、文系と理系の垣根を越えた学びにつながります。
また、料理をする体験を通じて科学的な思考を育むこともできます。
たとえば、一緒にパンを焼く際に、発酵の仕組みを説明しながら実験的に温度や時間を変えてみることで、子どもが自然と科学に興味を持つきっかけになります。
現在のSTEAM教育では、アートや哲学といった学問も統合的に取り入れられています。
これにより、単なる技術者ではなく、社会全体を見渡しながら持続可能な未来をつくる人材が育つことが期待されています。
AIが進化しても、人間にしかできない思考力や社会性を発揮できる力こそ、これからの時代に必要なスキルなのではないでしょうか。
環境教育で未来のリーダーを育てる

近年、「グローバルリーダー」という言葉を耳にする機会が増えました。
日本の文化を世界に対して発信し、国際社会に貢献できるような人材を指す言葉として、私自身も以前からよく使っていましたが、時代の変遷とともに「グローバルリーダー」の概念も変化してきています。
近頃は多様性が重視され、「すべての価値観を受け入れなければならない」という風潮が強まりました。
しかし、アメリカでトランプ氏が二度目の大統領になったことで、多様性を否定するような動きも出ています。
このような二極化が進む中で求められるのは、ただ「世界を平和にしよう」と訴えるだけでなく、対立を乗り越えて実際に行動できるリーダーです。
真のグローバルリーダーには、自国だけでなく、世界全体の未来を考える視点が必要です。
そのためには、地球の資源や環境を守る意識が不可欠です。
ESDでは、子どもたちが世界や地球環境について学びますが、それをより身近に感じさせる工夫が求められます。
たとえば、家庭でできる実践のひとつに「宇宙視点」を取り入れることがあります。
子どもと一緒に地球儀を回しながら、「日本の反対側はどこかな?」を問いかけるだけでも、視野を広げるきっかけになります。
また、朝のニュースを一緒に見て、「今日の世界ではどんなことが起きているのか?」を話し合うのも有効です。
こうした日々の積み重ねが、子どもたちの興味の種を育て、将来の学びや社会貢献へとつながるで
しょう。
地球の人口は急速に増加し、2022年には80億人を超えました。
国連の予測によれば、2080年代には約103億人でピークに達し、その後は減少に転じるとされています。
限られた資源の中で持続可能な未来を築くには、一人ひとりが「地球市民」として考えることが重要です。
そのためにも、家庭での環境教育が鍵を握ります。
たとえば、買い物の際に「この食品の産地はどこだろう?」と親子で話し合うだけでも、グローバルな視点が育ちます。
また、不要なものを捨てる前に「ほかに使い道はないかな?」と考える習慣をつけることも、持続可能な社会を目指す第一歩でしょう。
環境問題は今、世界中の学校で重要なテーマとなっています。
しかし、それを実践し、次世代に引き継ぐのは私たち大人の役目。
家庭や地域から始める小さなアクションが、未来のグローバルリーダーを育てる大きな一歩となるのです。
株式会社Kids Developer 代表取締役
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね