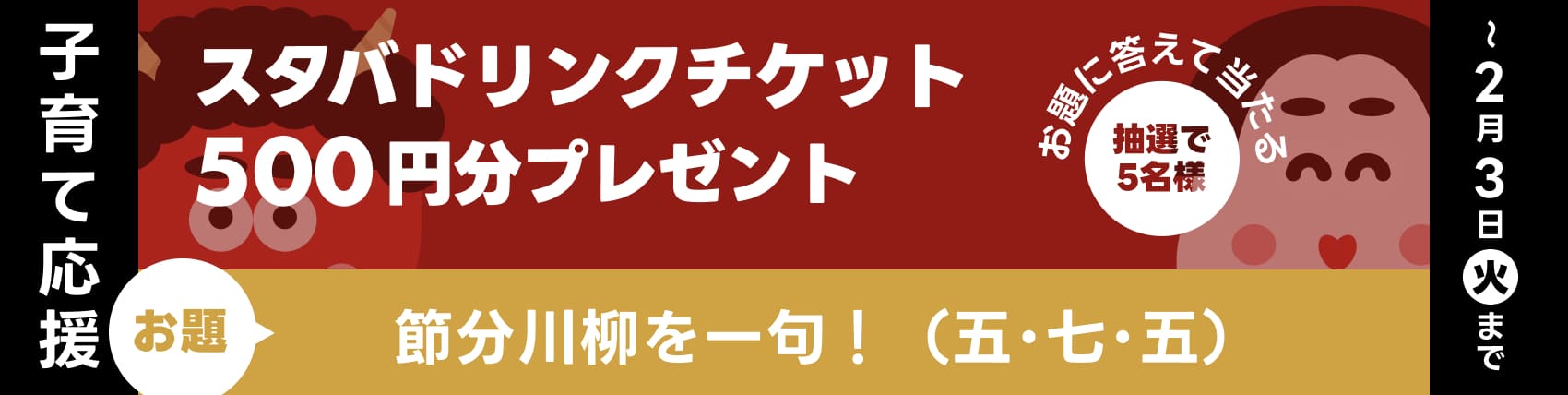「子育ての引き算」――叱ることの代償
『 モンテッソーリ子育てラジオ 』でVoicy子育てジャンル2023年、2024年(上半期)と2年連続で第1位を獲得した著者が話題の新刊『詰め込みすぎの毎日が変わる! 子育ての「引き算」』の中から「自分で考えて行動できる子になるために何を減らし・何を残すか」をお伝えします。
しつけ/育児

叱ることの代償
「賞罰」とは、子どもの行動を褒美や罰で制御しようとする方法です。
たとえば、「すごい!」「天才!」と過度に褒めたり、「鬼が来るよ」「お菓子抜きね」などと脅したり、罰を与えたりすることを指します。
みなさんは、叱られた経験や褒められた経験はありますか?親や先生職場の人などに。
私にも叱られた思い出も褒められた思い出もあります。
自分も経験してきたからこそ、当たり前に「叱ること、褒めることは必要だ」と感じやすいのですが、実は子どもの育ちには「賞罰」は必要ないとモンテッソーリ教育では考えています。
つまりは、叱ったり、罰を与えたり、褒めちぎったりはしなくていいということです。
「賞罰」をすることには、いくつか心配な点があります。
・自分で理由や善悪を考える力が損なわれる
・子どもの内発的動機づけを阻害する
・褒美や罰に依存する可能性がある
これまでの内容でも触れてきましたが、子どもの育ちのゴールは自立・自律です。
そのために必要なことは、子どもが行動の本質を理解して、自分で考えて行動できるようになることです。
これが、自立・自律に直結します。そのため、大人の言動に依存させるのではなく、いかに行動の本質を理解して、自分で理由や善悪を考えられるかが重要になってくるのです。
そのように子どもが自立・自律に向けて、行動の本質を理解して、自分で考えて行動する力を育むために必要なこと、それは「賞罰」の引き算です。
そのために、意識したいポイントが2つあります。
①罰ではなく「理由」を伝える
叱ったり、褒めちぎったりする「賞罰」の裏には、「こうあってほしい」「こういう行動をしてほしい」などの相手を変えたい、コントロールしたいという気持ちが無意識のうちに湧いていることがあります。
そのためにまず、「賞罰」の「罰」を引き算することで、「伝える」かかわりを実現していきます。
叱ったり、罰を与えたり、脅したりするかかわりを引き算することで「伝える」かかわりができるようになります。
子どもは「叱られた」という印象だけが残るのではなく、何がいけないのか、どうしたらいいのかという行動の本質を繰り返し学び、自分で考える力が育まれ、「自律」に向かうことができます。
また、このようなかかわりが、これまでもお伝えしてきた「内発的動機づけ」「外発的動機づけ」にも影響します。
叱られるからやるやらないという行動は、「外発的動機づけ」です。
そうではなく、やはり子どもの内側から湧き出る意欲などから取り組む内発的動機づけをサポートするためにも立ち振舞を意識したいですよね。
②褒めずに「認める」
いつも怒ったり、叱ったり、罰を与えたりして子どもをしつけるのではなく、いけないことはいけないこと、できないことはできないこととして理由とともに「伝える」ことがおすすめです。
さらに、質罰の「賞」として、ご褒美をあげることや褒めちぎることについてもお話ししたいと思います。「賞罰」の「賞」を引き算することで「認める」かかわりができるようになります。
「褒めて伸ばす」などという言葉もあるように、一見褒めることは良いことのように思えるのですが、少し注意が必要です。
一切褒めたらいけないということではありません。
しかし、やはり褒めちぎったり、おだてたりすることの裏にはコントロールしたい気持ちが隠れていることがあります。
「天才!」「すごい!」「才能あるね!」などと言うことで、より子どもの気持ちを盛り上げて、やれるようにしたいという気持ちが意識もしない心の奥底にある場合があるのです。
ここで大切にしたいことは、褒められることやご褒美をもらうことが一番の目的になるのは避けたいということです。
子どもは褒められるためやご褒美をもらうためにやるのではなく、本来自分を自立・自律の方向へと発達させることに全力なのです。
それに、生涯、何かをやったら必ずご褒美がもらえるわけではありません。
そのため、なぜ自分がこの行動をするのか、しないといけないのか、そもそもしたいのかなど、ご褒美の有無ではなく、自分を基準に行動を選択していく力こそが自立・自律のためには必要です。
だからこそ、褒めることやご褒美で子どもの行動をコントロールするのではなく、あくまでも子どもの気持ちや行動、プロセスや努力などをシンプルに「認める」。
そうすることで、子どもが自分で考えて行動する「自律」を助けることにつながります。
このような「伝える」、「認める」かかわりは根気のいることですよね。
すぐに何かの結果として目に見えなくても、チリも積もれば山となるように、日々の積み重ねがお子さんとの信頼関係につながっていきます。
また、この質が必要ないという話は「なんでも子どもの言いなりになりましょう」ということではなく、必ず大人が善悪の線引きをすることも重要です。
このように大人が「貧」を引き算することで、「伝える」「認める」というかかわりができるようになります。
さらに子どもは、行動の本質を理解することができ、自分で考えて行動する力を育むことにつながります。
叱り方や褒め方と一般的に言われる「声かけ」についてもっと知りたい方は、著書『モンテッソーリ流声かけ変換ワークブック』(宝島社)もぜひ参考にしてください。
1日のシチュエーションごとによくある声かけの変換例をたくさんご紹介しています。
「叱る、褒める」をどう変換していくと良いかの「声かけの引き出し」を増やしていただけると思います。
国際モンテッソーリ教師(AMI)、幼稚園教諭、保育士
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね