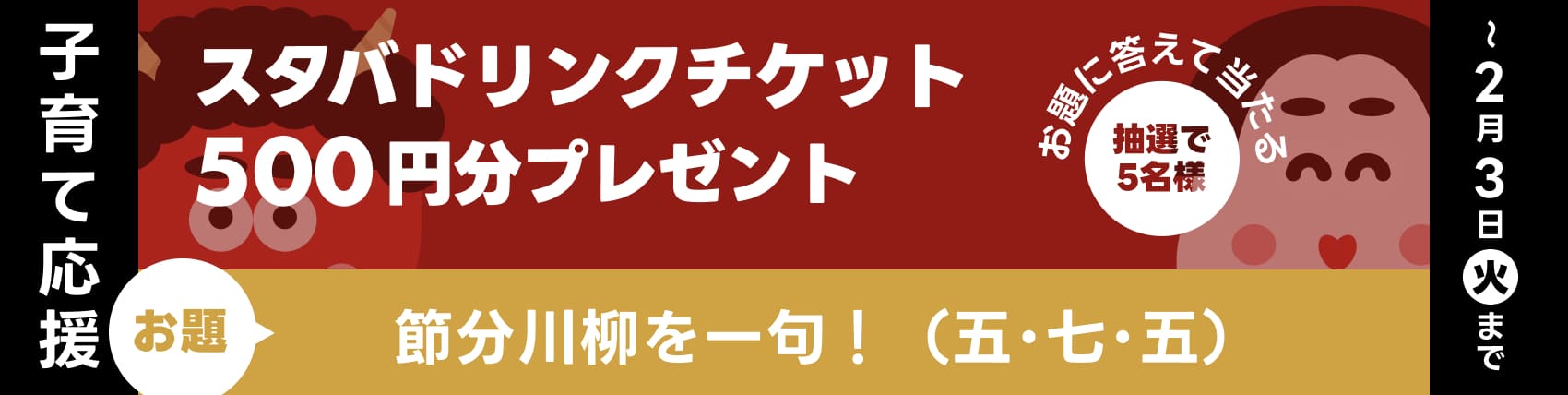「子育ての引き算」――「決めつけ」は先入観や勝手な評価
『 モンテッソーリ子育てラジオ 』でVoicy子育てジャンル2023年、2024年(上半期)と2年連続で第1位を獲得した著者が話題の新刊『詰め込みすぎの毎日が変わる! 子育ての「引き算」』の中から「自分で考えて行動できる子になるために何を減らし・何を残すか」をお伝えします。
しつけ/育児

◆「決めつけ」は先入観や勝手な評価
子育てをしていると、「どうせできないだろう」「この子は本当に何回言ってもわからない子だから」などと、無意識のうちに子どもに対して「決めつけ」をしたくなることはありませんか?
「決めつけ」とは、子どもに対して先入観や固定観念を持ち、その子の可能性や成長を限定的に捉えてしまうことです。
この「決めつけ」には、具体的には「先入観」と「勝手な評価」が含まれます。
「決めつけ」をすることには、いくつか心配な点があります。
・子どもの本当の姿や能力を見逃してしまう
・子どもの自己肯定感や自信の育みを妨げる
・大人が子どもの成長や変化に気づきにくくなる
・一度決めつけると、それに当てはまる姿ばかりが目につくようになり、間違った認識が強化されてしまう
「決めつけ」を引き算することで、子どもはありのままを受け入れてもらうことができ、自己肯定感や自尊感情を育むことができます。
そのために、意識したいポイントが3つあります。
①子どもを「見る」のではなく「観察する」
子どもの育ちを助けるために必要なことは、子どもを“観察する”ことです。
これは、ただ視覚的に見えているという「見る」ではなく、意識的に子どもの姿を「観察する」という意味です。
観察することがなぜ大切かというと、子どもの育ちを助けるためには、目の前にいる“その子”のニーズを知り、それに合ったサポートをしていくことが欠かせないからです。
たとえば、新しいパズルに挑戦しようとする子に、「すぐ諦めるからどうせやれないだろう」という先入観をもっていると、本当に子どもが必要としているサポートができないことがあります。
「本当にやれるの?」「すぐ諦めちゃうからもっと簡単なのにしておいたら?」などと声をかけることもあるかもしれません。
しかし、そのような先入観をもたずに子どもを「観察する」ことをしてみる。
すると、子どもはうまくはまらないピースがあっても、以前よりも長く試行錯誤する姿を見せるかもしれません。
子どもは「自ら育つ力」をもっています。
日々成長しているからこそ、見せる姿も日々少しずつ変化します。
しかし、私たちが先入観をもっていると、その小さな成長や変化にも気づけなかったり、そのチャンスを邪魔するようなかかわりをしてしまったりすることがあります。
②“今”の子どものニーズを掴む
一度決めつけて「先入観」がつくられると、それに当てはまる姿を見るたびに「やっぱり」「また」「ほら」と頭の中でのその認識が強くなっていきます。
たとえば、「できないことがあるとすぐ諦める」という先入観をもっていると、子どもが少しでも諦めるような姿を見せたとき、「やっぱり」「ほら、また諦めた」と感じやすくなってしまうのです。
そして、段々と子どもの直したい部分が目につくようになってしまうということもあるかもしれません。
私たち人間の脳は、使う情報ほど強く記憶されていくため、一度先入観をもつとそのような見方以外では見えにくくなってしまうことがあります。
実際に目に映らないのではなく、見えているけれど気づきにくくなってしまうのです。
しかし、①のように“今”の子どもを先入感をもたずに観察する。
その上で「この子が楽しんでいることは何だろう?」「何を求めているのかな?」もしくは「困っていることはあるかな?」と考えていきます。
このように”今”の子どものニーズを掴むことができるようになると、そのニーズに合ったサポートを実現することができます。
そのようなサポートがあることで子どもはより「自ら育つ力」を発揮できるようになるのです。
さらにそれだけでなく、子どもはありのままの自分を受け止めてもらえているという実感と体験を積み重ねることができます。
その体験が子どもの自尊感情の育みにつながります。
③「子どもがどう感じているか」を大切にする
①や②のように「観察する」、「“今”のニーズを掴む」ことをした上で意識したいことが、子どもを観察した“後”の「勝手な評価」です。
せっかく先入観を引き算して、客観的に子どもを観察しても、その後に勝手な評価をしてしまうと、より「決めつけ」が強くなってしまいます。そのため、子どもを観察する“前と後”でそれぞれの「決めつけ」をしていないかを意識するのがおすすめです。
私たちは、「決めつけや勝手な判断はしたい」なんて思っていないのに、無意識に判断して、評価してしまうものです。
たとえば、公園に行ってわが子と年齢が近い子どもを見たり、保育参観でクラスのみんなの様子を見たりすると、評価したいと思っていなくても、「うちの子の発達って、だいたいこんな感じなんだ」などと思ってしまうということはありませんか?
他にも子どもの姿を見た時に「本当、不器用なんだから」「こういうところがだめなんだよね」と評価したくなるということもあるかもしれません。
そのような評価をすると、私たちの「決めつけ」が強くなり、引き算したはずの子どもを観察する“前”の先入観もさらに強くなってしまいます。
大切なことは、大人がどう評価するかよりも、子どもが何を求めているかです。
だからこそ、観察した“前と後”の「決めつけ」をどちらも引き算するのです。
そうすることで大人にも良い影響があります。
それは、子どもの良い面や成長した姿により気づくことができるということです。
私たちはより子どものありのままを受け入れ、無条件の承認ができるようになります。
それが私たち大人の安心感や楽しさにつながっていきます。
自立・自律に向けて大切なことは周りに評価されることではなく、自分で自分を知っていくことです。
自分の人生を自立的かつ自律的に歩むためには、自分を知っている力=自己認識力が欠かせません。
そのため、大切なことは、「子どもがどう感じているか」に関心を向けることです。
決めつけたくなったら、「子どもは何が楽しいのか」、「何が好きなのか」、「逆に困っていることがあるならどんなことか」、「何を心地悪いと感じるのか」をぜひ考えてみてください。
このように、自分がどう感じているのかに一緒に向き合って大切にしてもらうことで、子どもにとっては自己認識力を育むことにつながります。
国際モンテッソーリ教師(AMI)、幼稚園教諭、保育士
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね