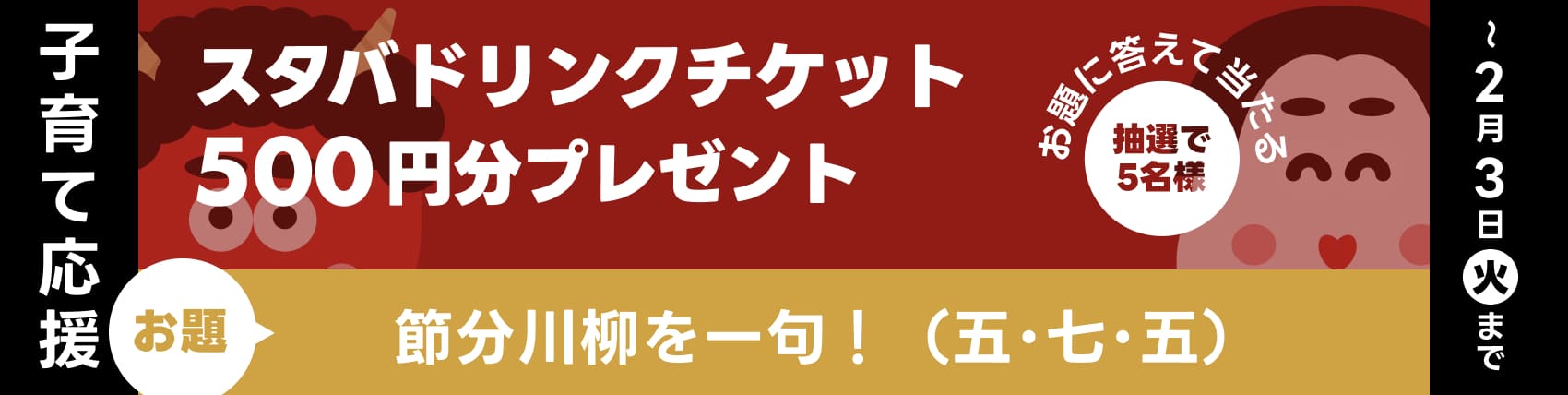「子育ての引き算」――自分で考えて選び取る力を育む
『 モンテッソーリ子育てラジオ 』でVoicy子育てジャンル2023年、2024年(上半期)と2年連続で第1位を獲得した著者が話題の新刊『詰め込みすぎの毎日が変わる! 子育ての「引き算」』の中から「自分で考えて行動できる子になるために何を減らし・何を残すか」をお伝えします。
しつけ/育児

◆自分で考えて選び取る力を育む
子どもに対して、たとえば「女の子だからピアノは習うべき」「来年小学生だから、今のうちにこれができるようになっているべき」「もう4歳なんだから自分でやるべき」などと、「~すべき」と感じることはありませんか?
「べき思考」とは、「~すべきだ」「~でなければならない」という固定的な考え方で子どもを判断することです。
「べき思考」をすることには、いくつか心配な点があります。
・子どもの「意志力」や「経験」を奪ってしまう
・子どもに過度なプレッシャーを与える
・子どもの自由な発想や行動を制限してしまう
この「べき思考」は、普段生活している中ではあまり意識することはないかもしれません。
しかし、「なんでその子どもの姿にイライラしているんだろう?」「どうしてその子どもの姿が許せないんだろう?」「どうしてこんなにモヤモヤしているんだろう?」と深掘りしていくと、実は心の奥深くにこの「べき思考」が隠れていることがよくあります。
子どもが自分の人生を幸せに生きていくために大切にしたいことは、子どもが自己選択を重ねて、自分で考えて選び取る力(自己選択力)を育むことです。
そのために、私たち大人の「べき思考」を引き算することが必要なのです。
そのために、意識したいポイントが2つあります。
①目の前の子どもが求めていることを優先する
ここで大切にしたいことは、“今の子どもに必要なことは何か”を優先することです。
つい私たち大人の「こうあるべき」「こうしないといけない」という思いを優先したくなりますが、ぐっと我慢するのがおすすめです。
なぜなら、子どもの育ちにおいて今、目の前の子どもが求めていることを満たしていくことが欠かせないからです。
目の前で子どもは求めているけど、私たちの「べき思考」がどうしてもそれを受け入れられなくしてしまうことがあります。
そのようなときには、ぜひ心の中でご自分にこう問いかけてみてください。
「その“べき”、今のこの子に本当に必要?」
この基準で判断してみると、より「べき思考」を手放しやすくなっていきます。
それでも、どうしても譲れない、どうしても手放せないときには、一方的に子どもに強制したり、子どもの意見や要求を拒否するのではなく、理由や思いを伝えてお子さんに別の案を提案してみましょう。
②子どもの選ぶものをジャッジしない
1つ目のポイントを合わせて意識したいことは、子どもの選択をジャッジしないということです。
ジャッジせず、失敗も含めて子どもが選ぶ自由を保障していきましょう。
おそらくお子さんと日々過ごしていると、子どもが選んだものやことと私たち大人の「べき」とがぶつかることがあるかと思います。
しかし、人生は選択の連続です。
どの職業を選ぶのか、結婚する/しない、子育てをする/しないなど人生にかかわる大きな選択から、今日の晩ごはんは何を食べるなどの小さな選択も含めると毎日たくさんの選択をしています。
ケンブリッジ大学の研究では、人は1日に平均3.5万回の選択をしていると示されています。
日々、自分で選ぶ経験を繰り返すことで、徐々に自分で選び取ったものに自信をもったり、「これでよかった」という成功体験を積んだりすることができます。
すると少しずつ自分で選択する力「自己選択力」が育まれていくのです。
そのような自己選択力を育んでいくことは、発達のゴールでもある自立・自律するための土台です。
子どもはまだ意志力も未発達で今まさに育んでいる最中で、経験も私たち大人に比べたら圧倒的に少ないです。
そのため、私たち大人のように最適解を1回で導き出すことは難しいのです。
ましてや自己コントロール力も未発達のため、自分の「こうしたい」という欲求をコントロールしてまで常に最適な選択肢を選ぶことはとてもハードルが高いことなのです。
実際に選んでみたけれど、その選択が間違っていた、これにしなければよかったという経験もまた必要なことなのです。
だからこそ、そのような失敗の経験も含め、「自分で選ぶ」経験を積み重ねられるよう、大人の「こうあるべき」「~すべき」という「べき思考」を引き算し、子どもの選択する自由を保障することが必要です。
このように2つのポイントを意識することで、大人は子どもの意見を尊重できるようになり、「べき思考」から解放されることで実は楽になれるのです。
さらに、子どもは自分で選ぶことが叶い、自己選択力の育みに繋がります。
危険がなく、誰かに大きな迷惑をかけていない以上は、まずは子どもの意志を受け入れてみるのがおすすめです。
国際モンテッソーリ教師(AMI)、幼稚園教諭、保育士
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね