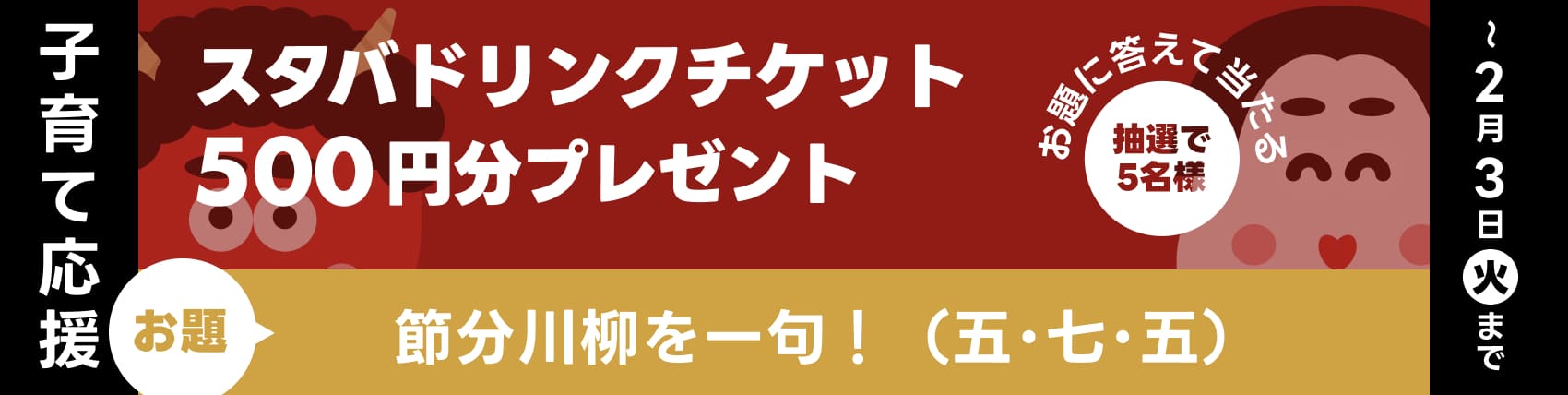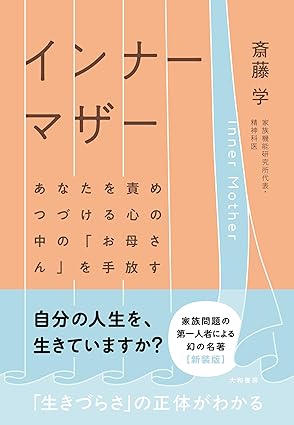「生きづらさ」の正体がわかる:インナーマザー――「安全な場所」を持っていると感じられるか
自分の人生を、生きていますか?「生きづらさ」の正体がわかる。家族問題の第一人者による幻の名著[新装版]
親子関係

「安全な場所」を持っていると感じられるか
家庭は子どもにとって「安全な場所」でなければなりません。
子どもは未成熟なヒトとしてこの世に生まれてきます。
生まれてしばらくは、自分一人では何もできません。
自分の生への欲求を、親(保護者)の愛情と庇護のもとで十二分に満たしてもらう必要のある王子さまであり、お姫さまなのです。
未成熟な赤ん坊は、こうした経験を経て、やがて一人で生きていける成熟した大人へと成長していきます。
赤ん坊は少し大きくなってくると、好奇心のおもむくまま、母親のひざもとから離れ、冒険に出かけるようになります。
そこで不安や危険をわずかでも感じると、声を張り上げて泣き出したりあわてて戻ってきます。
そのとき、「よしよし、もう怖くありませんよ、もう大丈夫ですよ」と抱きしめ、受け止めてくれる母親がそこにいてくれることで、安心してまたもう少し遠くへと出かけられるようになります。
部屋の中の探険から外への探険へと、じょじょに自分の世界を広げていきます。
時には母親に対して腹を立てることもあります。
少し前までは、お腹がすくと泣けばおっぱいがもらえたし、おむつが汚れたら即座に取り替えてもらえました。
ところが、だんだん大きくなってくるとともに、何もかもが自分の思いどおりにはならないということがわかってきます。
そこで癇癪を起こすのです。けれども、どんなに怒りをぶつけても、母親は自分を見捨ててしまわずにやっぱりそこにいて、また自分をかわいがってくれます。
ちょっと怒ったくらいでは母親はビクともしないし、自分との関係も壊れてしまうことはないのです。
腹を立てたときには怒ったり、怖いときには泣いたり、不安なときにはその気持ちを言葉に出して訴えたり、見たり感じたりしたことを話し、受け止めてもらいながら、子どもの心は健康に成長していきます。
こうして育った子どもは、母親が常に目の前にいなくても、離れていても、「お母さん」に抱きとめてもらえる「家庭」という安全な場所があるという感覚を持てます。
心の中に「お母さんと一緒にいる」感覚(基本的信頼感)を持つことで、安心して一人で外の世界に向かっていけるようになるのです。
ところが、こういう基本的な信頼感と安心感を子どもに与えてやれない親もいます。
その場合、子どもは「自己」を発達させることができません。
窒息しそうな息苦しさを感じながらも、家族から離れられません。
なぜなら、どんなときでも抱きとめてもらえる基本的信頼感=安全な場所を心の中に持っていないからです。
正確にいえば与えられなかった。
まだそれを求めている途中なのです。
そのため外の世界になかなか踏み出していけない。
健全に機能していない家庭は、子どもに「安全な場所」を与えてやれず、子どもの心の成長を阻みます。
その子どもたちが大人になり、自らの家庭を持ったときどうなるでしょうか。
与えられなかった体験はなかなか伝えることができません。
次世代でも同様のことが起こりうるわけです。
父親の役割の本質は「区切ること」
この本では母親というものに焦点を当てることにしますが、「母」と対ついになる「父」の役割についても触れておきましょう。
「父なるもの」については私は著書『「家族」はこわい─母性化時代の父の役割』(日本経済新聞社)でかなり詳しく述べましたので、ここでは簡単に説明します。
父の役割の本質は、「区切ること」です。これと対になるという点で母の役割は「つなぐこと」ともいえるでしょう。
父の仕事はまず、「この者たちに私は責任を負う」という家族宣言をすることによって、自分の家族を他の家族から区分します。
このことを指して「社会的父性」の宣言といいます。
この宣言によって、一つの家族が成立するのですから、父の役割を家の塀や壁という区切りにたとえることができるでしょう。
ついでにいえば、妻や子が雨露に濡れることから防ぐ屋根の役割といってもよい。
いずれにしても家族を外界と区切る一つの容器を提供することは父の機能です。
第二に父は、是非善悪を区切ります。
世に掟をしき、ルール(規範)を守ることを家族メンバーに指示するのは父の仕事です。
「父性原理」という言葉がありますが、これは父親のこうした機能を指して用いられるものです。
父の仕事の三番目は、母子の癒着を断つこと、親たちと子どもたちの間を明確に区切ることです。
父を名乗る男は、妻と呼ばれる女を、何よりも、誰よりも大切にするという形で、この仕事を果たします。
子どもは父のこの仕事によって、母親という子宮に回帰する誘惑を断念することができるのです。
スイスの精神分析医カール・ユングが強調したのもこのことで、彼は父の役割を母子の関係を断つナイフにたとえています。
こうした父の仕事は、いずれをとってみても抽象的なものです。
そしてヒトという動物は、周囲の事物を抽象する能力によって人間になったのです。
この抽象の能力を具体的に示すものが言語です。
言葉によって父性を宣言し、規範を定め、親と子の身分差を明確にする存在を得て、ヒトは人間になった、といえると思います。
母と子の二者関係を平面的なものとすると、これに父が入った三者関係は立体的です。
三次元の世界には、光も影もある。
私たちが存在する世界により近い知覚が、これによって私たちにもたらされます。
つまり「父」の存在を認識し、それを父と呼ぶことによって、私たちは人間としての生活に入っていくともいえるわけで、このことを指してフランスの精神分析医ジャック・ラカンは子が人になる入り口として「父の名」を強調したのです。
子どもたちは幼いとき平面的な絵を描きます。
年長になると、それが立体的になってくる。
このような表現様式の発達は、子どもに見える世界、つまり子どもの世界観の発達に対応しているのでしょう。
子どもに影の存在を教え、より現実に近い知覚を与えるもの、それが父の存在の認識です。
父存在(それは神と呼ばれることもあります)の掟に従って生きるほかない自己を認識すること、それによって子どもは人間になるのです。
家族機能研究所代表・精神科医。慶應義塾大学医学部卒業。医学博士。家族機能研究所代表。元・医療法人社団學風会さいとうクリニック理事長。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね